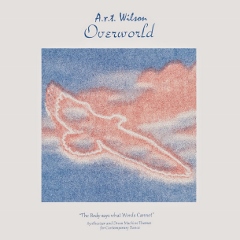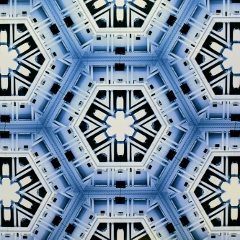MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > A.r.t. Wilson- Overworld
現代音楽やドローンが結果的にアンビエントに(も)聴こえる作品としてリリースされた場合、そこにはやはり本来の目的は違うところにあるという逃げ道が用意されているような感覚を抱きながら接するものにはなりやすい。どうしたってそれは共犯関係の上に成り立つものだし、本来の目的を理解する気はさらさらないというリスナーの主体性がすでに仮構のものであるからである。
しかし、これがポップ・ミュージックであった場合、むしろアンビエント・ミュージックは本格的なものにならざるを得ない。退路はどこにもなく、ストレートに真価や有用性を問われるものになる。80年代の人たちはまだ無自覚だったと思うので、『アンビエント・ディフィニティヴ』で取り上げたエイフェックス・ツインやサン・エレクトリック、ケアテイカーやテイラー・デュプリーはそういった意味で揺ぎない時代性を内包した作品だったと僕は思っている。最近ではディープ・マジックやセヴェレンス(Severence)などがそういったものに近づいているとも。
活気づくメルボルンからアンドラス・フォックス(Andras Fox)の名義でシンセ・ポップを送り出してきたアンドリュー・ウイルソンが〈メキシカン・サマー〉と契約を結んだ一方、新たな名義でリリースした『オーヴァーワールド』は多少のリズム・トラックを含むものの、ポップ・ミュージックがアンビエント・ミュージックに取り組んだ最新の結果を生み出したと僕には感じられる。90年代のようにクラブ・ミュージックとの並走でもなく、ゼロ年代のようにミュージック・コンクレートの方法論を応用したものでもない。なんというか、じつになんでもない。新しいと思える手法は何も用いられていない。非常に簡素で、含みや重層性はなく、最後まで淡々と音が鳴っているとしか言えない。何もないところからは何も生まれないというようなアイロニーもなく、物静かな音楽というような素朴な認識だけがあるというか。これが、しかし、何度聴いても飽きないし、どこか驚きに満ちている。何に驚いているのか自分でもよくわからない。繰り返し部屋のなかに垂れ流すだけ。
しかし、実際にはこれらの音楽はコンテンポラリー・ダンスのためにつくられたものだという。レベッカ・ジェンセンとサラ・エイトキンが「上流階級(=オーヴァーワールド)」をテーマにしたダンス・レパートリーだそうで、ということは、ここにある優雅さは上流階級の身のこなしを表しているということなのだろうか。「言葉では表せないことを身体は物語る」という文句がジャケットには記され、身体性の裏づけがある音楽だということは印象づけられる。あるいは、階級をテーマにしたものだときいてもとくに皮肉げなニュアンスに意識がいくようなものでもなく、なんとなく思い出すのは〈クレプスキュール〉の諸作や細野晴臣といったポップ・ミュージックである。それにしても欧米はダンスと音楽の結びつきが本当に濃い。スージー&ザ・バンシーズのスティーヴン・セヴェリンからクリスチャン・ヴォーゲルまで、どんなジャンルの人でもバレエ音楽を手掛けているからなー。
映像はちょっとヒドいけど、“ジェインズ・テーマ(Janine's Theme)”。
『オーヴァーワールド』を聴いていて、ちょっとだけ思い出すのはエール(フレンチ・バンド)である。いままでアンビエント・アルバムはつくったことがなかったダンケル&ゴダンが、そして、あろうことか、1000枚限定で美術館のためにアンビエント・アルバムをアナログだけでリリース(そのうちCD化されるだろうけど……)。美術館に飾られているさまざまな絵のイメージなのか、ピアノとハミングによるクラシカルなオープニングからどんよりと沈んだムード、あるいは軽く躍動感を感じさせるものまで、意外と表情豊かな曲の数々を聴かせてくれる(“ドリーム・オブ・イー(The Dream Of Yi)”だけは『ラヴ2』(2009)からの採録)。実際にナポレオンの指示で建てられたリール美術館から依頼を受けて製作したものだそうで、ということはフランスまで行けば館内で聴くこともできるということか? これは山田蓉子の感想を待ちたい(紙エレキングで「ハテナ・フランセ」という新連載をはじめてもらいました!)。
2014年もすでに40枚以上の記憶に残るアンビエント・アルバムと10枚近くの奇跡的な再発盤に出会うことができた。機会があればいずれまとめて紹介したいような。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE