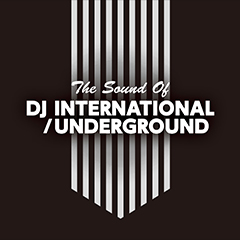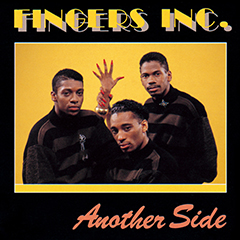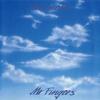MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Old & New > V.A.- The Sound Of DJ International/Un…
ダンスのモードがハウスに回帰していることもあって、ele-kingでは、『ハウス・ディフィニティヴ 1974-2014』を刊行する。「ディフィニティヴ」シリーズは、表向きにはカタログ本で売ってはいるが、実は年表でもある。歴史なのだ。そういう意味で、むしろ1977年と1987年の違いもよくわからない人にこそ呼んで欲しいし、1975年と1985年の違い、章のタイトルの意味するところを面白がっていただきたい。
さて、『ハウス・ディフィニティヴ 1974-2014』の刊行にともなってクラシックと呼べるハウスのアルバム、計3枚がリリースされる。〈DJインターナショナル〉のレーベル・コンピレーション、フィンガーズ・インクの『アナザー・サイド』、ザ・トッド・テリー・プロジェクトの『トゥ・ザ・バットモービル、レッツ・ゴー』の3枚だが、ここではそのうち2枚を紹介しよう。
『ザ・サウンド・オブ・DJインターナショナル-アンダーグラウンド』は、ハウス黎明期における最重要レーベル、〈DJインターナショナル〉(そのプラネット・レーベル〈アンダーグラウンド〉)の編集盤だ。〈DJインターナショナル〉とは……、レゲエにおいて〈トラックス〉が〈スタジオ・ワン〉なら〈DJインターナショナル〉は〈トレジャー・アイル〉だと手っ取り早く説明しているのだが、つまり、ハウスというジャンルの誕生においてそれだけ大きなレーベルということだ。
1985年、〈トラックス〉の後を追って設立した〈DJインターナショナル〉は実に多くのクラシックを残している。たとえばチップ・Eの“ライク・ディス”。DJが2枚がけしたくなるこのトラックのベースラインと「ララ、ララ、ラ、ライクディス」という声ネタは、80年代初頭のディスコ・パンク・バンド、ESGの“ムーディー”からのサンプリングで知られている。これはネタ探しのマニアの話ではない。このようにハウスとは、そもそもシカゴ・ハウスとは、フランキー・ナックルズ、ロン・ハーディらのDJプレイとその熱狂に感化された当時の若い世代が既存の音源をサンプリング(ジャック)して作った音楽だった、ということだ。ファースト・チョイスの有名な“レット・ノー・マン・プット・アサンダー”をジャックしたスティーヴ“シルク”ハーリィの“ジャック・ユア・ボディ”然り、ハウスは他を盗むことからはじまった。
が、ハウスは、盗むだけの音楽に終始しなかった。スターリング・ヴォイドの“イッツ・オールライト”は1989年にペット・ショップ・ボーイズにカヴァーされ、そしてジョー・スムースの“プロミスド・ランド”もまた1989年にスタイル・カウンシルによってカヴァーされている。シカゴ・ハウスは、早々と、ポップ・ソングとしても認められていたのである。
『ザ・サウンド・オブ・DJインターナショナル-アンダーグラウンド』には、1985年の、英国でナショナル・チャートの1位となるほどの大ヒットを記録した歴史的な曲“ジャック・ユア・ボディ”から、先述の“ライク・ディス”、“イッツ・オールライト”や“プロミスド・ランド”、ファーリー・ジャックマスター・ファンクがプロデュースした女王ロリータ・ハロウェイ(ジェシー・ウェアやアルーナ・ジョージの大先輩)の“ソー・スウィート”、再評価が高まっているE.S.P.“イッツ・ユー”、そして1990年のヒップ・ハウス──ファンキーなラップ入りのハウスで、ゲットー・ハウスの青写真とも言える──のミックス・マスターズの“イン・ザ・ミックス”まで、厳選された12曲が収録されている。そのなかには、先日再発されたばかりのフランキー・ナックルズの初期の名曲、美しく切ない“オンリー・ザ・ストロング・サヴァイヴ”も含まれている。
〈トラックス〉レーベルは現在も再発が盛んで、12インチもコンピレーションも入手しやすい状況にある。が、同じくらい重要な〈DJインターナショナル〉の編集盤はいまのところない。音楽的な観点で言えば、解説にも書いてあることだが、オリジナル・シカゴ・ハウスの王道とも言えるレーベルなので、ディスクロージャーで踊っているマサやん世代はもとより、往年のハウス・ファンにも聴いて欲しい。
フィンガーズ・インクの『アナザー・サイド』は、もっとも初期のハウス・アルバムの1枚で、ジャックしながら生まれた、パーティのためのハウスにおいて、最初に音楽的な洗練を目指した作品だった。
学生時代はジャズ/フュージョン・バンドのドラマーとして活動していたラリー・ハードを中心に結成されたフィンガーズ・インクには、天才的なヴォーカリスト、ロバート・オウエンズが在籍していた。1988年にUKの〈ジャック・トラックス〉からリリースされたこの傑作は、いちど海賊盤が出回ったことがあるものの、正規のリイシューはいちどもなかったので、今回は待望の再発と言える。
『アナザー・サイド』には、オリジナルのヴァイナル盤にのみ収録された、当時の大・大・大名曲も収録されている。“ミステリー・オブ・ラヴ”、“キャン・ユー・フィール・イット”、そして“ブリング・ダウン・ザ・ウォール”。これらの曲は、いま聴くとデトロイト・テクノの、ホアン・アトキンス(エレクトロ)とは別の、大きな影響だったとも思える。
1987年以降のハウスには、アシッド・ハウスという実験的なサブジャンルが生まれ、やがてドラッギーな音の響きが強調されていく。ラリー・ハードが探求したのはそうしたドープ・サウンドではなく、ディープ・サウンドだった。のちにディープ・ハウスと呼ばれる音楽の、発火点のひとつである。
とはいえ、『アナザー・サイド』をいま聴くとヨーロッパのニューウェイヴ系シンセ・ポップからの影響の強さをあらためて感じる。両性具有的なオウエンズのヴォーカリゼーションとハードの妖美なシンセサイザーは、題名通り「もうひとつの側」の世界を思わせるには充分で、“アイム・ストロング”や“ディスタント・プラネット”のようなアルバムの代表曲から滲み出る異様なまでの官能的なムードは、いまもリスナーを危うい領域に誘い込む。リル・リスにしてもそうだったが、当初のディープ・ハウスとは、ハウスのセクシャルな特性を掘り下げたものだった。
※同時発売されている、ザ・トッド・テリー・プロジェクトの『トゥ・ザ・バットモービル、レッツ・ゴー』(1988年)は、オリジナル・シカゴ・ハウスを最初に変革した作品である。NYで、ヒップホップを背景に持つ彼は、派手なサンプリング/DJミキシング(そしてラテンの香り)を駆使して、ポスト・シカゴ時代──まさにマスターズ・アット・ワークの登場を準備している。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE