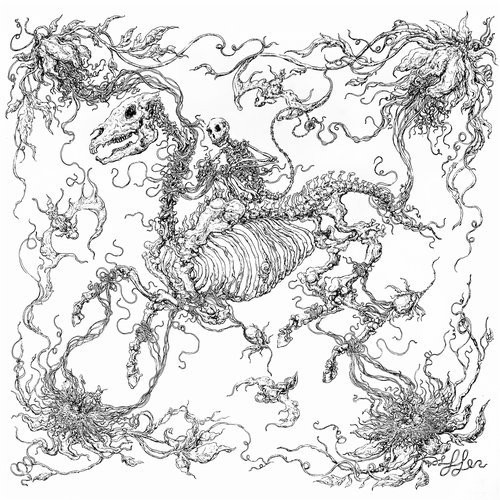MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Call Super- Suzi Ecto
2014年を印象づけるひとつのキーワードが、「IDM/エレクトロニカ」である。ARCAもそうだし、FKAトゥイングスも、AFX人気も、いろいろなところにそれが伺えるだろう。年のはじまりがアクトレスのリリースからだったというのも象徴的だ。
ニッチではない。この現象は実に説明しやすいもので、最初の「IDM/エレクトロニカ」ブームのときと同じく、アンチEDM(反・飼い慣らされたレイヴ)ってことだろう。対立軸がはっきりしているほうがシーンは面白くなる。
とはいえ、『スージー・エクト』がダンス・カルチャーと対立しているわけではない。むしろクラブとベッドルームとの境目を溶解して、両側に通じているというか。ロンドンの〈ハウンズトゥース〉が送り出す、ジョセフ・リッチモンド・シートンによるコール・スーパーのデビュー・アルバムも2014年らしい、聴き応えのあるエレクトロニカ作品だ。
2011年にデビューしばかりのコール・スーパーは、明らかにハウス/テクノのクラブ・ミュージックの側にいた。フィンガーズ・インクをモダンにアップデートしたような……、いや、それをほんとどコピーしたヴォーカル・ハウスである。が、活動の拠点を〈ハウンズトゥース〉に移してからの彼は型を外す方向に向かい、家聴きされることを意識したであろうこのファースト・アルバムでは、OPNとクラブとの溝を埋めるかのようなエレクトロニック・ミュージックを試みているわけだ。
『スージー・エクト』を特徴付けているのは、エイフェックス・ツインの『セレクティッド・アンビエント・ワークス』を彷彿させるほどの、圧倒的なロマンティックさにある。押しつげがましくない程度に、緊張感のあるリズムをキープしながらも、ドリーミーで、なんとも恍惚としたサウンドを展開、曲によってはフルートやオーブエの生音まで入っている。また、そのリズムもテクノ/ハウス一辺倒ではなく、ボンゴの演奏を活かしたパーカッシヴな心地よさ、ダブの陶酔、アンビエント、いろいろある。つまり、工夫はあるが、屈託のない音楽なのである。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE