その端緒をひらいた2014年のソロ作『Ansiktet』の時点では、2010年代後半が映画と音楽の関係の再考に費やされるとは、本人に確証があったかどうかはいささかあやしいが、渡邊琢磨はその1年後の冨永昌敬監督の『ローリング』、2年後には吉田大八監督の『美しい星』などの劇場公開作品の音楽を手がけ、盟友染谷将太監督とは実験的な作風にとりくみ、今年ついにみずからメガフォンをとり、染谷将太と川瀬陽太、佐津川愛美が出演する『ECTO』を完成させるにいたった。同作は今年5月に委嘱元である水戸芸術館で、晩夏には山口県のYCAMの爆音映画祭でも、規模はことなるが弦楽器の伴奏つきの上演を行っている。もうしおくれたが、渡邊琢磨の『ECTO』は映画の上映と生演奏がひとつとなってはじめて作品となる舞台芸術的映画作品で、革新的な方法論もさることながら映画なる形式へのエモーショナルな自己言及によって画期的な作品にしあがった、その完成から間を置かずして、というより余勢を駆ったか、渡邊琢磨はさらに映画に広く深くかかわろうとしている。
そのことは処女作となる映画作品と同名のレーベル〈ECTO Ltd.〉の始動にもうかがえる。またしてももうしおくれましたが、“ECTO”とは超常現象愛好家にはおなじみのあのエクトプラズムのエクトであり、ギリシャ語の「外」を意味するこのことばをレーベル名に冠した渡邊琢磨の胸中には、映画の内にありながら映像に外として付随する音楽の浮動する特異な位置を多角的にとらえんとする野心がうかがえる。とともに、音楽のみならず音をめぐるテクノロジーと価値観すなわち環境の変化が映画にいかに循環するのか、あるいはその逆は? との問いかけをふくみ、そのことはベルが鳴り客電が落ちた劇場の暗がりでおぼえる胸の高鳴りによく似たものを呼びおこす。
サウンドトラック盤『ゴーストマスター』はECTOレーベルの第一弾である。青春群像恋愛SFホラー活劇とでも呼ぶべきヤング・ポール監督の同名作は幾多の形式と手法と記号と技法をDIY風に融合した秀作だが、それゆえに音楽にもとめられる要求にも幅があったという。音楽を担当した渡邊琢磨の苦闘ぶりは本文をご参照いただきたいが、取材の後日仙台から郵送されてきたサントラ盤に耳を傾けながら本編で聴いたのとも印象をことにする音楽のあり方にうたれたとき、私は渡邊琢磨の新たな試みの意義をあらためて認識した。すなわち、映画とは、音楽とは、映画音楽とはなにか、との問いである。

映画がなければ存在しえなかった音楽の傾向はあるかもしれませんね。フィルムスコアリングのあり方が音に反映されている作品は多々あると思うので、映画のなかでしか聴けない音楽は、たとえばそれがオーケストレーションありきの音楽でなくとも電子音楽でもあると思います。
■映画音楽を中心にするレーベル〈ECTO Ltd.〉を発足させたんですよね。
渡邊:染谷(将太)くんが監督した『ブランク』(2017年)という映画があって、そのサントラをリリースするさい、ミックスダウンと部分的に録音もやり直して、アンビエントにつくり変えたんですけど、それが映画音楽の副産物として面白いなと。レコードのセールス的に映画音楽は少々厳しいかもしれませんが、メディアとして再利用するのはおもしろいのではないかと。それがレーベル〈ECTO Ltd.〉をはじめる発端でもあり、今回のサントラのリリースのきっかけでもあります。
野田:『ゴーストマスター』のジャケットをちょっとみせてもらいましたよ。鈴木(聖)くんがデザインしているじゃない。
渡邊:そうですね。じつは〈ECTO Ltd.〉のレーベル・ロゴも聖くんがつくってくれました。
■その〈ECTO Ltd.〉レーベル第一弾が2019年12月に公開した映画『ゴーストマスター』のサントラだと。すでに2作目以降も決まっているんですよね。
渡邊:染谷くんが監督し、菊地凛子さんが脚本を書いた短編作品の音楽を担当したのですが、本編20分弱の間、音楽がずっと鳴り続けていて、モジュラーシンセを使ったりドローンになったり、音楽的にも発見がいろいろあったので、権利的な問題がクリアになれば、同作のサントラを出したいと思っています。
■冨永昌敬監督の『ローリング』(2015年)、吉田大八監督の『美しい星』(2017年)、染谷監督の『ブランク』、今年上演(映)した作品としての『ECTO』もそうですが、琢磨さんはこの数年映画と音楽についてかなり意識的にかかわってきました。サウンドトラックというメディアの現状についてはどう考えていますか。
野田:最近じゃOPNなんかもサントラ(『Good Times』『Uncut Gems』)を手がけているよね。
渡邊:ダニエル・ロパティンのようなアーティストがサントラやるような状況って昔はそんなになかったと思うんですね。歌唱入りのテーマ曲をバンドやミュージシャンが担当するなどはありましたが、劇判をジョニー・グリーンウッドとかトレントレズナーとか、トム・ヨークもそうですし──
■ムームのヒドゥル・グドナドッティルとかね。
渡邊:そうですね。彼女が手がけた『チェルノブイリ』(HBO制作のドラマ)の音楽は素晴らしかったです。最近、音楽好きな映画監督がミュージシャンに直談判するような状況も顕著になってきましたし、映画音楽すなわち職業作家だけの仕事という時代でもない。バジェットいかんにかかわらず、監督や制作部とのコミュニケーションから音楽を着想することも多々ありますし、ミュージシャンが可能性を追求できる現場でもあると思います。
野田:染谷さんと菊地凛子さんは芸術的な野心をすごくもっているじゃない。あれだけメインストリームにいながら彼女もアンダーグラウンドにたいする嗅覚もある。
渡邊:そうですね。凛子さんはこのところ、染谷監督作品の脚本も書いていますが、ご自身の直感と趣向をそれとなく仕事にとりこんでしまう、その才覚がすごいです。海外では女優のマーゴット・ロビーや、ブラッド・ピットなどが独自のプロダクションをたちあげて大作を製作していますが、表方も裏方も手がける人が増えてきました。凛子さんはハリウッドでも仕事をしているし、そういった考え方があってもぜんぜん不思議ではない。
■彼らが制作に関与できる状況があるということですね。
渡邊:ブラッド・ピットが運営する製作会社〈PLAN B〉もそうですが、〈A24〉や〈Oscilloscope〉のような独立系製作会社が2000年以降増えました。最近はポスプロ(ポストプロダクション)なども、映画監督自身が編集ソフトを使って作業することもありますが、以前は分業というか、編集は編集マンにお願いするのが慣例だったと思います。それがいまやラップトップ一台で完結できてしまう。映画は一人で作るものではないので、相対的に考えると良し悪しありますが、テクノロジーの発展とともに映画制作の状況も変わってきましたね。
■職域がゆらいでいる現状がある。
渡邊:私的にシンギュラリティに関心はありませんが、AIの問題なども含まれるかもですね。AIが実装されているツールが出回ることで職域問題のバイアスが多少なりともかわるかもしれない。音楽制作においてもマスタリングやミックスをAIが行うツールがありますし、自己完結できる部分はどんどん増えている。
■映画音楽に特化した、あるいは関連したといってもいいかもしれませんが、そのようなレーベルの構想はいつから?
渡邊:じつはここ最近──なのです(笑)。基本サウンドトラックのリリースは映画の制作会社や委員会の意向に沿って決めるのですが、インディペンデント映画やショートフィルムの場合、サントラがリリースされることがまれだったりするので、監督や制作サイドにサントラの音盤化のご提案をして、話しがまとまればリリースするという感じです。
■いまの予定ではサウンドトラックとその二次利用作品ということなんですか。
渡邊:あるいは映像作家自身がつくる音楽、音響作品ですとか。効果音のスタッフの仕事にフォーカスしたものとか。ECMでも、ゴダールの映画の音だけがパッケージされたアルバムがありましたよね。そういう傾向の作品も含め(映像や映画の)音全般をあつかっていくということです。
■しかしよく考えると、サウンドトラック盤が存在する映画の基準って、音楽のよさ以外になにかあるんですか。いまはサントラはあまり出ませんが、中古市場ではサントラもひとつのジャンルを形成するほどの分量があって、掘っていくとけっこうマイナーな作品のサントラもありますよね。
渡邊:映画音楽の仕事に携わってわかったことですが、音楽コンテンツのとりあつかいが漠然としているケースもありまして、映画の最終行程であるダビング作業の後に、劇伴の出版管理ほか、本編における音楽の使用箇所を記載する「Qシート」を提出するなどの話しになるのですが、映画の公開からだいぶ時間が経って詳細な連絡をいただくことも多々ありまして。映画は制作行程が複雑ですし、音楽以外にも事後クリアしなければならない作業や問題も少なくありません。ただ、映画が公開されてから時間が空いてしまうと、作業内容もあやふやになってくるので、それなら劇伴が出揃った段、もしくはダビング作業直後にプロデューサーもしくは製作会社の担当者に出版の意向などをおうかがいし、所定の管理団体がない場合は、こちらでお預かりすることもできますとご提案しておくのもよいかなと。それから、サウンドトラックをリリースすると、今回の記事のようにパブリシティ効果も期待できるかもしれない。勝手がよいレーベルがあればマーチャンダイズとしてサウンドトラックをつくることも容易ですし。映画作品のPR、掲載メディアも横断的になるというか、音楽の観点から映画をとりあげるのも面白いのではないかと。あわせて、監督からサウンドトラック盤をつくりたいという要望が出る場合もあります。監督は個々の行程に思い入れがありますし、若い世代の監督にはクラブミュージックからサントラまで雑多に音楽好きな方もいます。

映画音楽をメディアとして再利用するのはおもしろいのではないかと。それがレーベル〈ECTO〉をはじめる発端でもあり、今回のサントラのリリースのきっかけでもあります。
■『ゴーストマスター』のヤング・ポール監督は若い世代に入りますよね。これが処女作ですね。拝見しましたが、いい感じで──
渡邊:とっちらかってますよね(笑)。
■(笑)やりたいこといろいろやった感がありますね。
渡邊:初長編作らしい大変、野心的な映画です。
■『ゴーストマスター』の音楽はどのような取り組み方だったんですか。
渡邊:本作は恋愛映画の撮影現場が次第にホラーに転じていくという映画内映画の要素があります。キラキラ恋愛映画を撮っているのだけど、とにかく撮影現場が滞る。キャストもダダをこねるし、監督も投げやりで、プロデューサーもうまくとりもってくれない。三浦貴大くん演じる主人公のダメダメ助監督は、本心ではホラー映画を監督したい野心があります。その思いと現場のストレスがピークに達したとき、恋愛映画の台本がホラー映画にトランスフォームするということなのか、とにかく惨劇の現場と化していくわけです。脚本を担当された、楠野一郎さんは大御所ですが、何とも不可思議でブラックな喜劇性をもあわせもつ恋愛ホラーをお書きになられた。本を読んだ直後は一筋縄ではいかないと思い、じゃっかん身構えました(笑)ホラーとはいえ根底に恋愛映画が通底していて、そこにも監督の演出意図があるので、表層とメタ構造になっている下部の映画の選択肢、要するにホラーなのか恋愛なのかを場面毎に問われる作品でした。
■判断するにあたっての基準や、要素から導き出せる正答みたいなものはあったんですか。
渡邊:それがないんですよ(笑)。正解がみえてこない。ホラーのシーンで恋愛映画のテーマを当てても、そういう演出に思えてきますし。
■形式にたいする批評として成立しますからね。
渡邊:そうなんですよ。しかも映画制作それ自体を扱うという点では、監督のルサンチマンとはいいませんけど(笑)、ポール監督ご自身のいろんな現場の実感にも由来していると思いますので、そういう裏返った自我の面白さも反映したいなと思いまして。
■いつごろからはじまったんですか。
渡邊:去年(2018年)には作業していたはずなので、ポスプロも含め1年はかかったかなと。
■ヤング・ポール監督は琢磨さんの音楽をすでにご存じだったんですね。
渡邊:本作のプロデューサーの1人である、木滝(和幸)さんは、冨永昌敬監督の『ローリング』も手がけていまして、ポール監督も『ローリング』をご覧になっていたらしく、渡邊さんならということで、お話自体はだいぶ前にいただきました。企画の概要的に、最初はホラー映画とうかがっていたので、恋愛映画が作中どういうふうに機能するかわかっていなかったのですが、初稿をいただいた段で映画の構造的に重要なパートだとわかってきました。私的には、ホラーの音楽をやってみたいという思いがかねてよりあったので、音楽作業の開始当初はもっとホラー然とした劇伴をつくっていたのですが、何曲投げても監督が首を縦にふらないので、再度ミーティングしたところ、ホラーと恋愛のどちらかに寄るのではなく、双方の要素を折衷したいということで、ようやくニュアンスがつかめてきました。
■でも音楽の面からいうと微妙ですよね。さきほどもうしましたように、どのようなものでもそのように聞こうとすればそう聞こえる。やりすぎると記号になるし、中庸でいいことでもないような気もする。あるいはジャンル映画風ということなのか。
渡邊:そうですね。だから正解が見えにくいというか、結局、画と音を合わせたときのフィーリングというか、理詰めではないですね。『ゴーストマスター』には、セルフパロディー化しているような登場人物も多々出てきて喜劇的な立ち振る舞いをするのですが、キャラクター自身はマジなので、滑稽でも泣けてくるという(笑)、そういうポール監督の演出の妙と、それを体現してしまうキャストの方々の絶妙さには脱帽しました。そういう異化効果的なバランスにはとてもシンパシーを感じたので、監督と意見が対立するということではなく、もうひと捻りできるかどうかを監督と熟慮しました。
■けっこう音楽ついていますよね。
渡邊:それなりに量はありますね。
■しかも映像でもスローやCGなどの特殊効果場面の音楽もありますよね。これは一概にはいえないかもしれませんが、その場合はホラーと恋愛の二項のほかにも撮影方法や、オマージュしている作品も加味しなければならないのではなかと思いました。
渡邊:トビー・フーパーですとか監督の名前や作品に言及する場面もありますからね。あわせて、旧来の映画音楽的な要素も欲しいという要望が監督からありましたし。それは職能でカヴァーすればよいのですが、音楽が著しく演出に影響してしまうので慎重につくりました。『ゴーストマスター』が面白いのは、意味不明なシーンや謎の伏線が回収されることなく、そのまま放置されるところです(笑)。屋上をみんなで歩いていくシーンとか。突如、ふりつけをしたかのような動きで人々が屋上を歩き出す、一体なんなのと(笑)、監督に演出意図をうかがっても、よくわからないとかおっしゃるし(笑)、そういうナゾのシーンが多々あるのが面白い。
[[SplitPage]] キップ・ハンラハンと仕事をしたときのレコーディングで弦楽四重奏を起用しましたが、なにもかも試してみたくなるんですね(笑)。バルトーク風だったりリゲティ風だったり印象派っぽいのとか、そういうみようみまねのトライアンドエラーの実践を現場でくりかえすうちに、旧来的な分業システムではつくられない、作家性の濃い付随音楽もできたりするわけで、それはそれで面白いなと。
■話は変わりますが、冒頭でも話に出たミュージシャンで映画音楽を手がけるひとたちについて琢磨さんは同じ立場としてどう思われますか。ジョニー・グリーンウッドはもちろん、ダニエル・ロパティンも。彼らはグリーンウッドならPTA(ポール・トーマス・アンダーソン)、ロパティンならサフディ兄弟というふうに監督とのコンビネーションもあります。その点もふくめて、琢磨さんは映画音楽の現状をどうみておられますか。
渡邊:ポール・トーマス・アンダーソンとジョニー・グリーンウッドのコラボレーションについては、なりゆきがわからないので言及できませんが、その点は措いたうえで、グリーンウッドが手がける映画音楽には弦楽が採用されていたり、室内楽的な要素もあったりしますよね。その点を考慮すると、PTAがグリーンウッドを起用したのは別段レディオヘッドのメンバーだからとか、ギターのサウンドが使いたいとか、そういう表面的な事由ではないわけで、逆にいえばグリーンウッドの音楽性、資質をよく理解していたからこそ、弦楽や管楽の劇伴を発注できた、あるいはグリーンウッドのアイディアを採用したということではないかと思います。OPNは、サフディ兄弟との2作目は、ダニエル・ロパティン名義でしたが、初コラボの際は、イギーポップとのコラボを除けば、OPNがそれまで積み上げてきた作風から、さほど逸脱しない音楽を監督も求めている感じでしたね。だから、ジョニー・グリーンウッドの場合は、そもそも弦楽器をフルで使う音楽をつくりたくて、その欲求とポール・トーマス・アンダーソンの映画が邂逅した感じではないかと。音楽家にとっていい実験の場ができたというか。『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2007年)が彼らのはじめてのタッグだったと思いますが、現代音楽のありとあらゆる書法を使っていますよね。僕もキップ・ハンラハンと最初に仕事をしたときのレコーディングで弦楽四重奏を起用しましたが、なにもかも試してみたくなるんですよね(笑)。バルトーク風だったりリゲティ風だったり印象派っぽいのとか、そういった欲張りな感じがどっと出る。でも、そういうある種のアマチュア精神というか、みようみまねのトライアンドエラーの実践を現場でくりかえすうちに、旧来的な作曲は作曲家、編曲は編曲家というような分業システムではつくられない、作家性の濃い付随音楽もできたりするわけで、それはそれで面白いなと。その点、ジョニー・グリーンウッドは音のイメージがちゃんとありますよね。同時に音楽史上の参照点も分かりやすい。
■気軽に生の弦は使えないものね。
渡邊:とくに弦は束になると非日常的な音像になるじゃないですか。それをそれなりの予算で使えるとなったときの欲望ってすごいわけですよ。私的にはそうそうあるわけじゃないですけど。PTAも音楽が好きなひとだからグリーンウッドに弦を書いてもらいというディレクションと、作曲者の状況や意思がうまい具合に化学反応を起こしたんだろうなと思います。それ以来ふたりのコラボレーションはつづいていますよね。最近はジョニー・グリーンウッドがやっている音楽をポール・トーマス・アンダーソンがドキュメントしてたりもするし。
■それだけいい組み合わせだと本人たちも思っているということかもしれないですね。
渡邊:個人的には、PTAはヘイムとかフィオナ・アップルとか女性アーティストのMVなどを手がけているときの方がしっくりきますけどね。好みの女性アーティストばかり撮っているというか(笑)。
■ジョニー・グリーンウッドやダニエル・ロパティンが映画音楽に進出してきているのは象徴的というか、琢磨さんが映画と音楽に関心をもつのもわかります。
渡邊:去年は私的に(映画を)監督し、編集もみようみまねで手がける過程で、映像と音の相対的な発見が多々ありました。過去に仕事をした映画監督、たとえば、冨永監督などは棒つなぎ(仮編集)などは、もしかしたら編集マンがやるのかもしれませんが、その後、冨永くん自身で再度編集や微調をすると、途端に冨永ワールドが立ち現れる。その点では音楽とも似ていますよね。そういう編集のリズム感、グルーヴ感をもっている監督は多々おられます。そういったことも念頭に、私的に映像編集をおこなった際は、完全に音楽的な感覚で切ったり繋いだりしていました。今後、ポストプロダクションを自身で手がける映画監督や映像作家も増えていくでしょうし、逆に、映画監督が音楽にかかわるあり方も変化していくのではないかと思います。サフディ兄弟の映画音楽にしても、タンジェリン・ドリームのようなシンセを駆使した映画音楽を参照しているのは間違いないですし、『神様なんかくそくらえ』(2014年)では冨田勲さんや、それこそタンジェリン・ドリームを使っています。アナログ・シンセサイザーが効果的に使われた70年代後期から80年代全般の映画のムードや質感が好きなんだろうなと思いますし、OPNもその辺の映画に通底する質感は熟知しているでしょう。そうやって1本組んで、前時代的なオマージュだとかリファレンスありきのシネフィル的な趣向を超えて、両者の協働のあり方が新作『Uncut Gems』に結実したのかもしれない。『Good Times』もそうでしたが、ロパティンの映画音楽はかつてのタンジェリン・ドリームやヴァンゲリスのようなエレクトリックワールドな演出とはちがうわけですよ。映像と音の親和性がカメラワークに由来していたり、編集のスピード(これは速い場合もハイスピードのように極端に遅い場合もです)が、現行の電子音楽と相性が良いような気がします。そういう撮影などの技術革新などもあって、映画と音の新たな関係性の土壌ができたのだと思います。ハーモニー・コリンもそうでしたし、『魂のゆくえ』(ポール・シュレイダー監督、2017年公開)でもラストモードが音楽をやっていたりだとか、かつてないような映像と音のインタラクションが増えてきていると思います。過去の仕事の概念からいったらほとんど効果音のような音も劇伴という括りで捉えていますし。ポール・シュレイダーのような巨匠がドローンのような音楽を非常に効果的に使っているというだけでも興奮しますよ。

現代の映画音楽の文脈的に、90年代以降の映画音楽らしさは「低音」なんだと思います。じっさいIMAXやドルビーアトモスなんかの売りもそこですし、それはジョージ・ルーカスがTHXを始動したときからつづいてきたことでもある。そんなことをふまえると、そろそろ反動で高音が流行るんじゃないかと(笑)!
■レーベルの設立文で、〈ECTO Ltd.〉での活動の視野にはサウンドデザイン的な表現も入ってくると述べられていましたが、それはそのような認識からくるものですか。
渡邊:あの文章は自分の仕事に対する戒め的な側面もあるのですが(笑)、じっさいにそうだとは思います。オーディエンスの観点からしても、映画をみているときの体感として、いまやIMAXやドルビーのような典型があるわけじゃないですか。90年代初頭から現在のハリウッドライクなというか、ルーカスのTHXが主導する音響技術が定着していったと思うのですが、つくり手からすると、あの重低音やアタック音は少々食傷気味です。ある特色をもつ技術革新が進むと、最初のうちは物珍しさも手伝って、多くの人が追従する音楽をつくるのですが、二番煎じが昂じると、自分はそれをやらないぞというムーヴメントが反動的に起こります。個人的な見解だと、劇伴における重低音を個性的に推し進めたのが、ヨハン・ヨハンセンが手がけた、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『ボーダーライン』(2015年)のサントラで、あのグリスアップを多用した弦と打楽器の音像は、一頃のアクション映画の代名詞になっていると思います。とにかくコンバスやチェロをひとまとめにしてグリスアップすれば「いま」っぽい(笑)。映画音楽には、そういう流行り廃りの面白さがあるんですよ、映画音楽のなかの音色傾向といいますか。
■ムームのヒドゥル・グドナドッティルはヨハン・ヨハンセンの弟子筋ですよね。
渡邊:そうですね。くりかえしますが、彼女の『チェルノブイリ』の劇伴は、前述の低音演出の総括的な作品としても秀逸です。現代の映画音楽の文脈的に、90年代以降の映画音楽らしさは「低音」なんだと思います。じっさいIMAXやドルビーアトモスなんかの売りもそこですし、それはジョージ・ルーカスがTHXを始動したときからつづいてきたことでもある。そんなことをふまえると、そろそろ反動で高音が流行るんじゃないかと(笑)!
■そんな単純な話なのか(笑)。
渡邊:ハハ、でも音の生理なんて単純なものだと思うんですよ。映画音楽史を意識しながらみていくと、何年かに一度そういった時期、傾向がありますよ。
■高音というのを美学的に言い直すとどうなります。
渡邊:低音というのはアトモスフィアをつくりやすいわけです。体感もあります。低音というのはサウンドトラックだけにかかわらず、地鳴りのような効果音などにも多用されますよね。きわめて映画的なレンジだと思いますが、たとえば、武満(徹)さんのお仕事などは、そこまで低音重視ではないですよね。
■そうですね。
渡邊:世界的にみても映画音楽史の上でも、かなり特異で鮮度のある映画音楽です。もちろん、作曲家=武満の作風というだけではなく、その時代の映画がもちえたトーンに呼応してるようにも思えますが。そういう響きが流行るかはさておき、一方の余白になっているとは思います。
■低音でもグリスアップでもない基準ですね。
渡邊:そうですね。とはいえ、武満さんの映画音楽もある時代の参照点でもあるわけで。映画監督がみてきた映画の音がそのひとのなかに蓄積されているわけですし、それなりに邦画をみていけば、必ずあの独特の武満トーンが記憶に残っているはず。だから音楽に疎いとおっしゃる監督でも、映画における音のマナーやリテラシーはあって、実際、音を当ててみるとなにがしかの映画の記憶が思い起こされたり、具体的な作品名を出して、あの映画の音楽がよかったなどの話しになりますし。
■発見ですよね。それはさきおっしゃっていた映画と音楽、テクノロジーや方法論との親和性と同じで、不可逆的なものでもあると思うんです。
渡邊:ええ、映画がなければ存在しえなかった音楽の傾向はあるかもしれませんね。フィルムスコアリングのあり方が音に反映されている作品は多々あると思うので、映画のなかでしか聴けない音楽は、たとえばそれがオーケストレーションありきの音楽でなくとも電子音楽でもあると思います。
■〈ECTO〉レーベルはそのような映画音楽作品をリリースするレーベルであり、『ゴーストマスター』はその第一弾であると。そう考えると、琢磨さんほど映画音楽に真摯にとりくんでいるミュージシャンはいないかもね。
渡邊:いえいえ! 自重ではありませんが、私はまだまだ試行錯誤の段階ですし、映画音楽の世界もよい意味で魑魅魍魎うごめいていますからね(笑)。最近はノイズやヒップホップ界からもドラマや映画音楽に参入してくるアーティストがいますし。個人的に映画は好きですが、それだけが動機でもないと思いますし。ただ、映画音楽をつくるのも、レーベルをスタートするのも、映画や音楽からの呪いみたいなものであると同時に、つまるところ実験であり、結果的には音楽にフィードバックしてくるなにかだと思います。
■映画情報
映画『ゴーストマスター』
監督:ヤング ポール
脚本:楠野一郎/ヤング ポール
音楽:渡邊琢磨
主題歌:マテリアルクラブ「Fear」
出演:三浦貴大/成海璃子
配給:S・D・P(2019年 日本)
○新宿シネマカリテほか絶賛公開中!全国順次ロードショー
ghostmaster.jp/
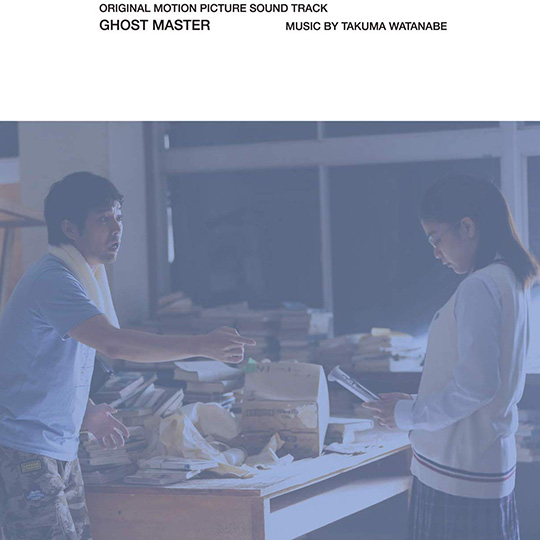




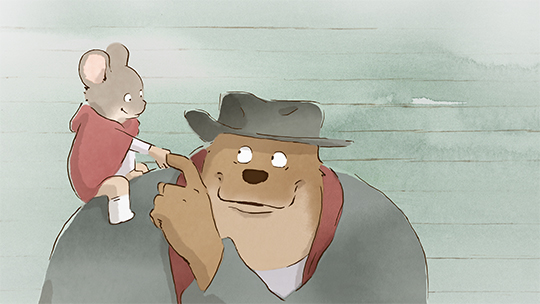





























 ■街のものがたり
■街のものがたり