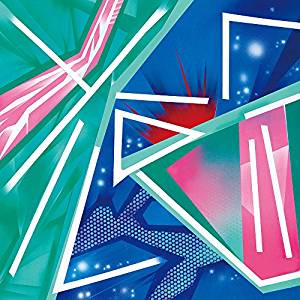MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ryugo Ishida- EverydayIsFlyday
『サタデー・ナイト・フィーバー』は普遍的な青春の物語……だった。かつては。変わりばえしない毎日への鬱憤を毎週末のディスコでのばか騒ぎで発散するジョン・トラボルタ。ナイン・トゥ・ファイヴの退屈な仕事をこなすだけの決まりきった人生のレール。それにあきたらない若者の胸のうずきと、やがて訪れる青春の終わり。そういやアラン・シリトーの『土曜の夜と日曜の朝』ってのもあった。なんにせよそれは、戦後の経済発展を成し遂げた国々に共通の成熟のストーリーだった。
けれど、世界的な規模でミドル・クラスが没落し、ワーキング・クラスがのきなみアンダークラスへと地盤沈下していく現代においては、ナイン・トゥ・ファイヴの安定なんてものはごくごくひと握りの人間にしか享受できない特権になりつつある。落ち着くべき人生のレールはもはや存在しない。朝も夜もなく、曜日の感覚もない。未来っていったってただの言葉にすぎなくて、5年先のことさえまるで現実感がない。……そんな感覚はこの平成日本でも着実に浸透中だ。ポストモダン? 後期近代? そんなめんどうな言葉は必要ない。これはいまこの社会のあちこちで経験されているリアリティだ。
『EverydayIsFlyday』。エヴリデイ・イズ・フライデイ。それが自主流通のみ、いまのところ限定で1000枚しかプレスされていないRYUGO ISHIDAの初フィジカルCDのタイトルだ。手もとにあるCDのジャケットは大友克洋『AKIRA』のパロディで、廃墟の玉座に座るRYUGO ISHIDAがぺろりと舌を出している。現在23歳の彼は茨城県土浦を拠点とするアーティストだ。2014年からDUDE名義で『1993』と題したミックス・テープEP三部作をリリースし、このアルバムでのデビューを機に改名した。このタイトルはもともと、アトランタのトラップ・シーンの現場を追ったVICEのドキュメンタリー『noisey ATLANTA』に登場する「ここじゃ毎日が金曜日だぜ(Everyday is Friday)」というフレーズをサンプリングし、米スラング「FLY」のスペルを組みこんだものだ。全世界に伝播するアメリカ南部産のトラップの熱波が、東京の北方に広がる関東平野のなかほど、霞ヶ浦のほとりに飛び火した結果、この傑作が誕生したことになる。
そう、このアルバムが素晴らしいのだ。まるっきり中学生のようなストレートなリリックと、知性をまったく拒否したジャンクなアティテュード、というラップのスタイル自体は、震災後のトラップの本格流入以降にUSのフロウを意欲的に取り入れたラッパーたちに共通する。しかし目を引くのは、絶妙なバランスで最先端のトラップに落とし込まれた北関東独特の土着の空気感だ。くわえてとくに秀逸なのが、アイラヴマコーネン以降とでも呼ぶべきか、LSDの影響で出現したとされるアトランタのメロディアスな潮流、最近ではリル・ヨッティの『リル・ボート』などに顕著な、サイケデリックな歌声フロウの大胆な導入。サウンドもトラップをベースとしつつも、ダンサブルな4つ打ちやラフなブレイク・ビートが随所に登場し、トベればなんでもありのジャンクな多幸感を盛り上げている。
サタデー・ナイト・フィーバーというよりはエヴリデイ・イズ・フライデイ。それが現在のユースのリアリティ……なのかはわからない。けれどその感覚は、EDM以降の、派手な電子音と中毒性のあるビートで理屈ぬきにハイになりたい、という刹那的な欲望ともどこかで同期しているはずだ。あるいは、危険な脱法ハーブや異常にアルコール度数の高い安価な酒の急速な普及以降の感覚とも。ともかくこれは、ミドル・クラスやワーキング・クラスの墓場で楽しげに踊るゾンビたちのダンス・ミュージックだ。琥珀色のクエルボ・ゴールド、紫のリーン・ドリンク、深紅のピル、チョコレート色のマリファナが混じり合って描く、極彩色のアラビアン・ナイト。まるで悪夢のような世界……だがここには絶望も怒りもない。ぶっ壊れていく社会を嘆き悲しむ連中をよそに、彼らは瓦礫をドラムのように打ち鳴らして笑っている。
*
始まりはフィルターをかけられながらフェードインしてくる“KIDS”。iPhoneのデフォルト着信音っぽいシンセがぐるぐると回り、サンプルされたソウル・シンガーのうめき声がエコーし、マシンのスネアの連打が鳴り響くと、間髪入れずに極太のベースがドロップされる。初っぱなからすでにベロベロのRYUGO ISHIDAはマリファナのブラントに着火しながらひとこと。「幻覚見えるまで吸うぜ、キッズ」。続く“夜が明けるまで”は盟友のLUNV LOYALを客演に迎え、卓越した歌声とスキルフルなラップのコンビネーションを披露する。陶酔を誘うベースライン、快感的なハイハット、ゲームからサンプルしたようなチャチな銃声。序盤はRYUGOのスキャット的な高音フロウとLUNV LOYALのスムースで安定した低音フロウのコントラストを聴かせ、しかし両者のラップはやがて自由自在に交錯しながら見事に溶けあっていく。
リル・ヨッティ的なサイケデリック・フロウ解釈として秀逸なのは、なんといっても3曲目の“FLYDAY”。エヴリデイ・イズ・フライデイ、でも本当の金曜日の夜だけはやはり特別だ、という週末のなんでもない高揚感が、美しいファルセット・ヴォイスで珠玉のポップ・ソングに仕上げられる。トラップ以降のフロウの多様化の流れの中では、ラッパーの歌唱力とメロディ・センスがひとつの試金石となるけれど、その点でRYUGOのポテンシャルは抜きん出ている。その後も、テキーラ・ショットの連発によるオーヴァードーズを描く“ONE SHOT”、墓場でパーティするゾンビのトラップ・ホラー・コア“ZONBIE WALK”、弱冠19歳のフィメール・ラッパーELLE TERESAを迎えた“PARTYGANG2”など、手を替え品を替えのパーティ・チューンの連続だ。赤やピンク、ブルーに染めた髪の毛、顔や首まで刻んだタトゥー、ミラーボールが照らすシャンパンに濡れた肌。自称はPARTY PEOPLEじゃなくPARTY GANG。発音は短くパリギャン。記憶はゲロと一緒にトイレに流して、英語まじりの奇声をあげながら毎夜のパーティに明け暮れる。
パーティ感一色だったアルバムのギアが切り替わるのは、ミーゴスの“YRN(Young Rich Nixxas)”のパロディ的なタイトルの“YRB(Young Rich Boy)”。ヘロヘロのシンセの音色にスカスカなトラップ・ビート。単調なフロウで繰り返されるフレーズは「いま貧乏でもヤング・リッチ・ボーイ/この曲で歌うこと実現する/あと何年後かにはヤング・リッチ・ボーイ」。思わず正気を疑うほどのジャンクさだ。しかしアルバムをここまで聴けば、このぶっ壊れたアティテュードが確信犯的にデザインされたものであることは明白だ。フォトショップで適当にカット・アンド・ペーストしたような素材が飛び交うミュージック・ヴィデオも、iPhoneのエミュレータでリヴァイヴァルされたファミコン感というか、サウス・パーク的なチープさ。グッチのベルトをはずすビッチ、それにバルマンの新作デニムとルブタンの靴。夢はドクター・ドレーと曲を作り、ダウンタウンみたいになること。ラスト近くに鳴らされる最高にラフなブレイク・ビートが疾走感のある4つ打ちに変化すると、チープな夢が壮大なスケールまでドライヴしていく。
この確信犯のスタイルの由来を知るうえで興味深いのが、北関東特有のヤンキー・カルチャーの残滓が炸裂する“FIFTEEN”。これはかなり奇妙な曲だ。言ってしまえばバック・イン・ザ・デイものというか、過去の記憶を辿るストーリー・テリングものなのだけれど、ここにはそうしたナラティヴに必要なはずの「あの頃は……」というようなイントロダクションが存在しない。ほぼ10年前の記憶を語っているはずのリリックが突然「俺はRYUGO/生意気中坊/齢は15/聞かない忠告」と始まるせいで、普通に聴けばまるで15歳の中学生が歌っているように錯覚する。ラップもいわゆるトラップ以降の変声フロウではなく、堅実なライミングによるオーセンティックなスタイルだし、サウンドもトラップ的なハイハットの連打にくわえて、90sのウエスト・コーストを彷彿とさせるラフな感触のドラムが印象的だ。さらには改造学ランの中学生が登場するレトロなヴィデオが、わざとVHSの粗い解像度を再現しているにいたっては……。つまり、リリック、ラップ、サウンド、映像のすべてが渾然一体となって、「過ぎ去ろうとしない過去」というコンセプトを鮮やかに表現しているわけだ。15の夜に始まったRYUGOの悪夢はいまだ終わっていない。小学二年で手紙で知った実父の死の記憶、ママには内緒でのめり込むエリミンにコデイン。いくら泣いても闇夜は明けず、届かない夢を見ている放課後、狂った時計の針が回り出す……。
クライマックスはラストの2曲。吐瀉物まみれのワン・ナイト・スタンドを不思議な爽やかさで歌いあげる“キスはゲロの味”、そしてミックス・テープから再録された“お金持ちになりてえ”。この身も蓋もない2曲のタイトルこそ、USの影響下で形成された日本のトラップのメンタリティを雄弁に物語る。吐瀉物というロマンティシズムとはほど遠いモティーフによって刹那的なラヴ・ストーリーを描くこと。金銭へのストレートな欲望を宗教的なストイシズムさえ漂わせながら口にすること。この点で現在の日本のトラップは、既存のラップのクリシェを破壊する、新たなリアリティ・ラップとして噴出している。くわえて『CONCREET GREEN』に収録された曲の別ヴァージョンである“やりたいことやる REMIX”の、いわゆる自己啓発的なスピリチュアリティ。日本のトラップの画期となったKOHHが、「引き寄せの法則」で有名なロンダ・バーンの『ザ・シークレット』という自己啓発本に強い影響をうけているのはよく知られたことだ。チャンス・ザ・ラッパーとケンドリック・ラマーがそのバックボーンにクリスチャニティを共有しているように、大手古本屋のワゴンセールで数百円でたたき売られているベストセラー由来の自己暗示は、家族の崩壊とコミュニティの空洞化にさらされた日本のユースにとっての、切実なサヴァイヴァルのツールなのかもしれない。まあ、その結果として描かれる希望が、大理石の豪邸で仲間と一緒にマリファナとコカインでハウス・パーティってところには、ああなんてことだ、って思うけれど、絶望感にひざまずいて生きるよりは、きっとずっとマシなんだ。
*
東京の北方の地方都市での南部産トラップの力強い隆盛をうけて、ひとつ指摘しておきたいことがある。それは、ひと昔前まで日本語に翻訳されたアメリカ文学や映画に出てくる南部の黒人は東北地方の方言を喋っていた、ということだ。福島生まれのアメリカ文学者、青山南によれば、それは実在の東北弁ではなく、「THEY DID THESE THINGS」を「DEY DONE DEM THINGS」と喋る呪文的な南部英語のなまりを翻訳するための苦肉の策としての、デタラメな東北弁だったそうだ。しかし、そこには「先進的な東京」と「遅れた地方」というあからさまな文化的ヒエラルキーの構図が凝縮されているのはもちろんのこと、その抑圧的な図式はそのまま、当時のアメリカ南部における白人と黒人という人種的ヒエラルキーへと露骨にスライドされているわけだ。それは程度の差はあれ外国語のなまりの翻訳につきまとう本質的な難題ではあるものの、事実、最近の海外文学の翻訳ではこの架空の東北弁の乱用は改められる傾向にあるらしい。
実は青山は言語学的にいえばアメリカの南部英語のなまりはむしろ九州地方のものに近似しているとの説まで紹介しているのだけれど、たとえ南部作家のウィリアム・フォークナーの小説に登場する黒人が博多弁や鹿児島弁を喋りだしたって、ともすればノーマルな基準から逸脱した存在を表象する記号として地方の方言が使われることに変わりはない。さかのぼれば南北戦争での敗北以降、「遅れた土地」との烙印を押されたダーティ・サウスの叛乱、その最新形が現在のトラップだとすれば、日本の地方都市の不良がサウスの音を鳴らすことには、明確な必然性がある。東京においても、トラップの起爆剤となったのは北区のKOHHや川崎南部のBADHOPなど、都市の周縁である郊外エリアの新勢力だった。それは抑圧された土着の肉体と感性の叛乱だ。
創成期に渋谷や六本木の先鋭的な文化実験によって育まれた日本のヒップホップの主流が当初、暴走族などのヤンキー・カルチャーと意識的に距離をとることでそのアイデンティティを構築してきたことを踏まえるなら、現在急激に隆盛している日本のトラップの一翼は、周縁化されたヤンキー・カルチャーがラップ・ミュージックを飲み込んだ結果の産物だ。それはニューヨークという最先端の文化の坩堝で誕生したヒップホップが、南部アトランタやヒューストンで土着化して生まれたトラップの出自からいって、まったくもって頷けることだ。
もちろんUSトラップの画期にはレックス・ルガーによるワカ・フロッカ・フレイム“ハード・イン・ダ・ペイント”が刻まれているし、爆発的流行後のヒューストンの熱はハーレムに逆流してエイサップ・ロッキーというヒップなアイコンさえ生み出した。崩壊したアメリカのサバービアを撮り続けてきたハーモニー・コリンの『スプリング・ブレイカーズ』において、顔面にアイスクリームのタトゥーを刻んだアトランタのトラップ・キング、グッチ・メインが不気味な存在感を放っていたのも記憶に新しい。サウスの潜勢力はとうの昔に、地理的な南部だけに独占されるものじゃなくなっている。東京でも郊外エリアのトラップ・アーティストの荒々しさに比べ、渋谷を拠点とするkiLLaクルーに漂う不穏でフェミニンなパンキッシュさには目を見張るものがある。思えば、かつてはレコードの不買運動さえ引き起こしたヒップホップは、いまや音楽産業の中で確固たる地位を築いたのだ。サンプリング主体のサウンドに対して「オーセンティック」という本来なら保守的な賛辞が違和感なく投げかけられるようになった現在、荒廃したサウス・ブロンクスで胎動していた型破りなエネルギーは、南部発の新たな潮流のかたちをとって貪欲にフロンティアを探し続けているのかもしれない。
そういえばフォークナーはかつての来日時、「わたしには日本人のことが理解できる。なぜならわたしたちはともにヤンキーに負けたからだ」と発言したそうだ。ここでいう「ヤンキー」とはもちろん南北戦争に勝利した北部諸州のアメリカ人を指していて、その言葉は知っての通り高度成長後の日本で不良の少年少女たちを指す言葉に転用され、それが今ではほぼ地方にしか見られない土着のカルチャーとなっているわけだから、そこにはかなり摩訶不思議な文化的なズレがある。けれどきっと、そんなズレは世界中どこにでもあるのだ。ちょうどちまたで『トレインスポッティング』の続編の映画化が話題になっていたせいか、“キスはゲロの味”のヴィデオの金髪坊主のRYUGO ISHIDAは、あの映画のユアン・マクレガーにだぶって見えた。イギー・ポップとルー・リードをBGMにドラッグに耽るスコットランドの田舎の若者たちの群像。あれはイギリス映画である以上に、スコットランドの映画なんだ。同じように、このアルバムは日本のトラップである以上に、北関東の、土浦のトラップだ。首都の真上に永遠の郊外のように広がる関東平野、その横腹にぱっくりと口を開けた巨大な湖のほとり。どうやらそこでは、こんなにも幻惑的な音が夜ごと鳴り響いているらしい。
*
ミックス・テープではUSのフロウをオリジナルにアレンジするべく試行錯誤していたRYUGO ISHIDAは、このデビュー盤一発で、その音楽的実験の成果を目覚ましいまでに見せつけた。実際、当初はフィジカル限定だったこのアルバムは反響を呼び、今後はiTunesでの配信も予定されている。ひとくせあるトラックを粒ぞろいに用意し、緻密なコンセプトで全曲のプロデュースをてがけたAUTOMATICの手腕も大きいだろう。同じく彼のプロデュースでSoundCloudにアップされた新曲は、チャンス・ザ・ラッパーの新作の“ノー・プロブレム”のビート・ジャックだったことからしても、サウンドのリソースはこのアルバムに現れている以上に豊富のようだ。けれど、やはりこのアルバムの魅力はトラップならではのものだと思う。TR-808のマシン・ビートを基調とするトラップは、かつてトリシア・ローズが「共同体の対抗的記憶装置」と呼んだ過去の音楽的遺産へのアクセス、つまりはサンプリングを、すくなくともビートとしては拒絶している。そのビートのうえで、保守的なマッチョ・カルチャーにはとてもそぐわないヤング・サグの服装倒錯(トランスヴェスティズム)や、リル・ヨッティの突然変異的なサイケデリア、それにキース・エイプやKOHHといったエイジアン・ラッパーの身体と声が力強く躍動しているのには、なにか理由がある気もするのだ。
メジャー/アンダーグラウンド、グローバル/ガラパゴス、東京/地方、肉体/マシン、歌/ラップ、シスヘテロ/クィア……あらゆる二項対立を拒否し、克服するだけじゃ足りない。二項対立を嘲笑し、利用し、勢力図を塗り替えるんだ。口で言うほど簡単なことじゃないけれど、この『EverydayIsFlyday』はその文化的なアクロバットの見事な実践だ。あらゆる周縁に生まれ落ちた人間、既存の文化秩序に牙をむこうとする人間、人知れず野心をたぎらせるすべての人間たちへ。トラップ・イズ・ユアーズ。すこし勇み足ぎみにそう言っておこう。
泉智
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE