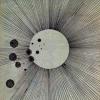MOST READ
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- xiexie - zzz | シエシエ
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング
- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- heykazmaの融解日記 Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑
- world's end girlfriend ──6月に『抵抗と祝福の夜 2026』が開催
- DJRUM - SUSTAIN-RELEASE x PACIFIC MODE - 2026年2月7日@WOMB
- PRIMAL ──1st『眠る男』と2nd『Proletariat』が初アナログ化
- P-VINE × FRICTION ──フリクション公式グッズが、Pヴァイン設立50周年企画として登場
- FRICTION ──フリクションのデビュー7インチ「Crazy Dream」と「I Can Tell」が復刻、『79ライヴ』もCDリイシュー
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Geese - Getting Killed | ギース
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
- 対談 半世紀を経て蘇る静岡ロックンロール組合
Home > Interviews > Flying Lotus - フライング・ロータス最新作『フラマグラ』の魅力とは?
通算6作目、じつに5年ぶりとなる待望のアルバムをリリースし、大いに称賛を浴びているフライング・ロータス。この秋には単独来日公演も決定し、ますます熱は昂まるばかりだけれど、多彩なゲストを迎えさまざまなスタイルを実践した渾身の新作『Flamagra』は、彼のキャリアにおいてどのような位置を占めているのか? そしてそれはいまの音楽シーンにおいてどのような意味を担っているのか? 原雅明と吉田雅史のふたりに語り合ってもらった。
ひとりで作ってきたトラックメイカーがそこからさらに成熟したことをやろうとすると、たいていは生楽器を入れたり、あるいは壮大なコンセプトを練るじゃないですか(笑)。彼は今回の新作でそれにたいする答えを出したんだと思います。 (原)
吉田:まずは、原さんが最初に『Flamagra』を聴いたときどう思われたか教えてください。
原:初めて聴いたときは、『You're Dead!』と比べると地味だなと思った。ゲストはたくさん参加してるけど、ひとりで作っている感じがして、すごくパーソナルな音楽に聞こえたんですよ。『You're Dead!』もいろんな人が参加していて、聴いた箇所によってぜんぜん音が違うという印象を受けたんですが、『Flamagra』は、もちろん各曲で違うんだけど、全体をとおして落ち着いていて、統一感のある作品だなと思ったんです。オフィシャルのインタヴューを読むと、今回は自分で曲を書いてキイボードも弾いて、クラヴィネットの音がポイントになっていると。じっさいに使われている音数もそれほど多くない。要素はたくさんあるけど、決めになる音が『You're Dead!』よりも拡散していない感じで、ずっとある一定のレヴェルでアルバムが進んでいくような印象を受けましたね。
吉田:曲のヴァリエーションは多様だけど、ひとつの原理に沿って聴こえるように「炎」というコンセプトを立てて、作り貯めたものをそこに全部入れたかったんだと思います。そのときひとつの軸になるのがクラヴィネットの音色で。ギター不在の今作では、鍵盤と弦楽器の両方の役割を担っているところがある。ソランジュとの曲(“Land Of Honey”)も4、5年前に作ったって言っていたけど、統一感のためにクラヴィネットの音はあとからオーヴァーダブしたんじゃないかと思うくらいで(笑)。それから今作の新しさを考えるにあたって、サンダーキャットを中心としたミュージシャンと一緒に書いてる曲が多い中で、ひとりで書いている曲がポイントになるのではないか。5曲目の“Capillaries”は、ビートやベースのパターンはこれまでのフライローっぽいんだけど、アンビエントなピアノの旋律が中心になることでピアノ弾きとしての彼の新しいサウンドに聴こえる。それから“All Spies”という曲もひとりで書いていて、これはひとつのリフをさまざまな音色のシンセやベースで繰り返し、その周縁でドラムが装飾的な使われ方をするという、シンプルながらひとつずつ展開を積み重ねる楽曲です。重要なのは、特定のサウンドで演奏されたメロディをサンプリングしてループするのではなくて、あくまでもリフとなる「ラドレファラド~」というひとつのシンセのメロディがあって、それをさまざまな音色がユニゾンしながら繰り返し演奏していく。つまりサンプリングループからアンサンブルへの移行を見てとれる。結果としてこの曲は、YMO的な印象もありますよね。そういう多様な楽曲がひとつの原理で繋がっている。
原:YMOは好きだったみたいな話を実際にしているよね。今回はやっぱり自分で曲を書いて、アンサンブルを活かしているのが大きい。
吉田:これまでは仲間のミュージシャン陣が演奏したラインをサンプリングフレーズのようにして彼が後から編集していた印象だけれど、今回はメインとなるリフや楽曲展開をあらかじめ書いて皆で一緒に弾いているようなところがある。今回ジョージ・クリントンが家にきて一緒に曲作りをしたとき、その場でぱっとセッションをしたらスポンティニアスに曲ができて、それがすごく自信になったと言ってますよね。それは自分で理論を学び直したことなんかもあって、ある程度即興的に楽曲を形にできるようになったからだと思うんです。とくに、『Cosmogoramma』以降は超絶ミュージシャンたちの演奏を編集するエディターの側面も強かったと思うんですが、今回は作曲者兼バンドマスターとしても自信をつけたんじゃないかなと。ちなみに俺は最初に聴いたときはポップなところがすごく印象に残りました。これまでのアルバムより多様性があるなと思ったとき、リトル・ドラゴンとやった“Spontaneous”や“Takashi”辺りが、とくにこれまでにない新しい景色だと。じっさいフライローは「もっと売れなきゃいけない」というようなことを言っていたから、意識的にポップな部分を入れているのかなと。そのあたりはどう思いました?
原:ポップさはあまり感じなかったかな。ポップだと思った曲もあるけど、相変わらず1曲が短いから、感情移入する前にすぐ変わっちゃうんですよね。だから、「この曲をシングルカットするぞ」みたいな感じは受けなくて。
コルトレーン一家という自身の出自へのがっぷり四つでの対峙がようやく終わって、みそぎが終わったというか。「俺が考えるジャズをひとまずはやり切った」みたいな感じがありますよね。 (吉田)
吉田:フライローの曲って、たとえばヒット曲とか代表曲がどれかって思い出しにくいですよね。曲が短くてたくさんあるから、曲単位で「あの曲がシングルでヒットした」というよりもアルバム単位で「あのアルバムはこういう感じだったよね」と記憶されている。だけどあらためて聴くと楽曲をさらに細分化した各パーツの部分、たとえば『Cosmogramma』だったら“Nose Art”のキックとベースの打ち方だったり、“Zodiac Shit”のエレピとストリングスとか“Table Tennis”のピンポン玉の音なんかは、とても印象的なんですよね。曲単位では残ってないんだけど、断片としてはけっこう残っている。
フライローがもともと持っているほかのアーティストと違う点は、アヴァンギャルドやアブストラクトさを追求しつつも、そういったエッジの効いたポップさのあるフレーズを量産しているところだと思うんですね。そういうポップさは昔から持っていた。ただ、全体としてはシリアス・ミュージックだった。扱ってきたテーマも、ジャズとどう向き合うかだったり、死とどう向き合うかという、スピリチュアルですごくシリアスで、その番外編としてキャプテン・マーフィーがあったり『Pattern+Grid World』があったりした。『KUSO』で雑多なイメージをコラージュできたことも活かされていると思うんです。今作も最終的にはアルバム後半に並ぶシリアスな楽曲群に回収されるけれど、そこまで展開はこれまでの雑多な世界観全部をひとつのアルバムにミックスしてもいいという感じになっている気がしますね。たとえばティエラ・ワックとやった“Yellow Belly”のように、『You're Dead!』のときのスヌープ・ドッグとの“Dead Man's Tetris”の奇妙なビート路線もひとつのイディオムになってきていたり、その雑多な世界観の中にクラヴィネットの裏拍のサウンドも含まれている。シリアス一辺倒ではない垢抜け感のようなものが、サウンド面でもリリック面でも楽曲構造面でもさまざまに表れている。リターン・トゥ・フォーエヴァーに『Romantic Warrior』というアルバムがありますよね。〈Polydor〉から〈Columbia〉へ移籍して、チック・コリアが使いはじめたARPの音色が印象的で、そしたらアルバムのサウンド全体も一気に垢抜けて。シリアスから脱皮したというか、ポップな要素もすごく入っている。少し似ているなと思いました。それこそ中世のシリアス・ミュージック=宗教音楽とポップ・ミュージック=世俗音楽の分裂という対置で考えられるかもしれない。ポップ化する以前のフュージョンやフライローのシリアスさにはそれこそスピリチュアルだったり、プレイを崇拝する宗教的な側面がありますし。
原:基本的に今回の作品は、ゲストを自分のところに呼んできたり自分がどこかへ行ったりして録り溜めてきたものが膨大になってしまって、自分でもどうしたらいいか見えなくなっていたところがあったと思うんですよ。時間をかけたというのも、個々の録音を録り溜めていた期間が長きに渡ってということで、そこから実際に曲として仕上げるまでの、手を動かしていない空白の時間も相当長かったんだと思う。それで「炎」というストーリーやクラヴィネットの音を見つけて、ストーリー立てできると思ったんじゃないか。そして、キイボードを習って、アンサンブルや理論を学んだうえで、ようやく見えてきた結果なんだろうなと思いましたね。素材となる録音物はたくさんあったにしても、最終的に完成に導いたのは彼の作曲の能力とか構成力とかそういった部分なんだろうなと。『You're Dead!』はコラボしたものをそのままバッと出したという面もあったと思うけど、コラボして融和的なものができ上がったとして、じゃあその次はどうするかというときに、もう一回、個に戻った表現をしようとすると、ふつうは変にコンセプチュアルな方向に走りがち。でも彼はそうではなくて……『Flamagra』も一応コンセプチュアルなふうにはしてありますが、僕はじつはそんなにコンセプトはないと思う。
吉田:意外とそうですよね。プログレのバンドとかに比べたらワンテーマでガチガチではない。だからこそこれだけ雑多な楽曲群をゆるくつなげてるんだと思います。デンゼル・カリーもジョージ・クリントンも「炎」をテーマにリリックを書いているけど、たとえばラヴ・ソングも「燃える想い(炎のように)」「あなたが好き(炎のように)」みたいな感じで、アンダーソン・パークも「ソウル・パワー(炎のように)」みたいな。もうなんでも炎じゃんみたいなところがある(笑)。
原:「炎」の話も読んだけど、コンセプト的には隙がある。だからやっぱりそれよりも、要となる音、音色を見つけたとか、作曲に関して自信を持てたとか、アンサンブルを作れるようになったとか、そういう手応えの方が大きかったんじゃないかな。
Profile
 原 雅明/Masaaki Hara
原 雅明/Masaaki Hara音楽ジャーナリスト/ライター、レーベルringsのプロデューサー、LAのネットラジオ局の日本ブランチdublab.jpのディレクターも担当。ホテルの選曲やDJも手掛け、都市や街と音楽との新たなマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書『Jazz Thing ジャズという何か』ほか。
Profile
 吉田 雅史/Masashi Yoshida
吉田 雅史/Masashi Yoshida1975年、東京生まれ。異形のヒップホップグループ8th wonderを中心にビートメイカー/MCとして活動。2015年、佐々木敦と東浩紀(ゲンロン)が主催の批評再生塾に参加、第1期総代に選出される。音楽批評を中心に文筆活動を展開中。主著に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之氏、磯部涼氏との共著)。Meiso『轆轤』プロデュース。
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE