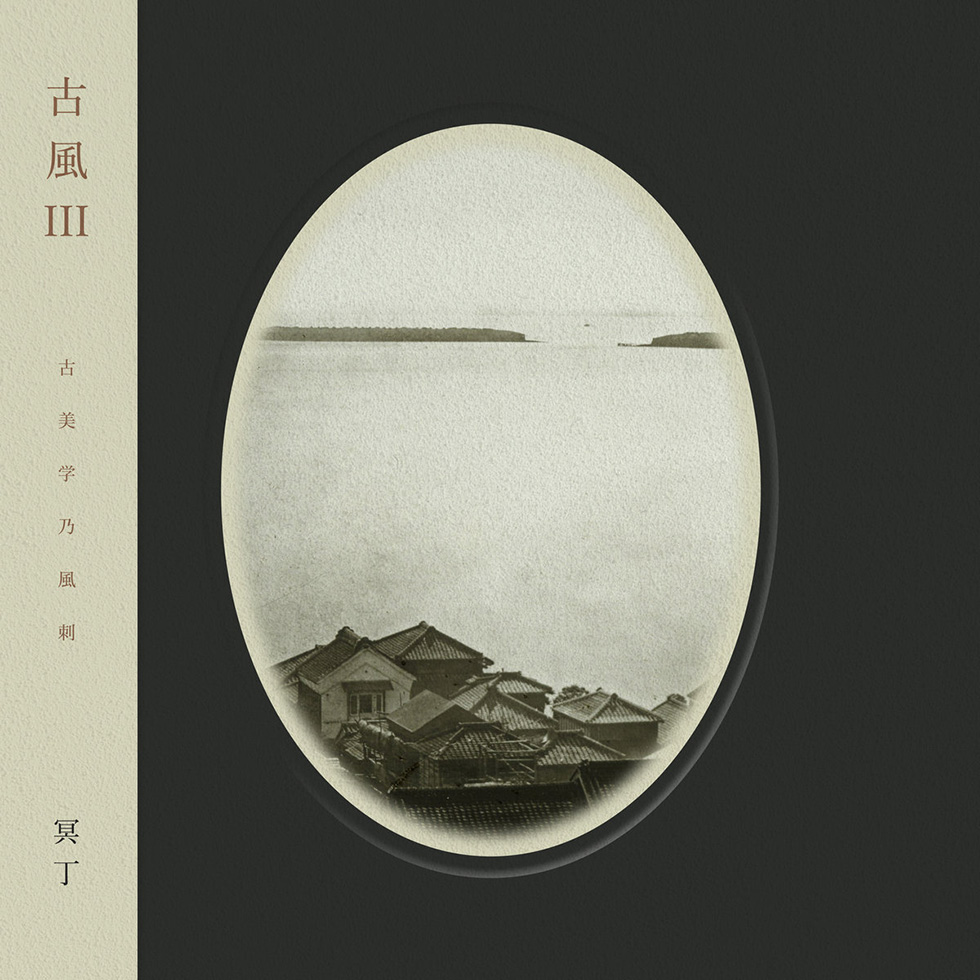MOST READ
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- KMRU - Kin | カマル
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026
- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
Home > Interviews > interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本
彼のコンセプトにおける重要な礎となったのは、服飾の専門学校で出会ったフランス人の教師の言葉だった。彼の作品を見たその教師は、英語の題名と西欧化された彼のデザインに対して、「なぜ日本らしさがないのか」というクリティックを投げた。この言葉は、音楽の世界においても、古くは三島や川端、はたまたきゃりーぱみゅぱみゅへの賞揚さえ抑えきれない、西欧知識人のなかの反白人至上主義から来る常套句のひとつではあるが、現代を生きる日本人にとっては話せば長い、じつに複雑でやっかいなアジェンダなのだ。とにかくまあそんなわけで、以降、「日本らしさ」なる漠然とした問いは、藤田のなかで何度も反芻され、京都での創作にひとつの方向性を与えた。
とはいえ、京都での苦心惨憺たる生活は、いよいよ彼の精神を追い詰め、結果、8年で終わりを迎えた。医師からADHDという診断を下され、カウンセラーからは「音楽をもっと本気でやる方がいい」とも告げられたという。「(ADHDだから)才能を開花できるはずだ」と励まされもしたが、鬱も発症し、それまでの生活でやれていたことがじょじょにできなくなり、彼はすっかり自信を失ってしまった。さらにはパニック障害も併発し、人口の多い都会での生活は困難になり、療養のために一旦広島の実家に身を置くことにした。そして、ここから冥丁がはじまり、『怪談』は、この窮地から生まれたのだった。

そんな風に彷徨っているときに本も読みはじめたんです。図書館に行って、文学や歴史の本を読みましたね。読書をしながら、何のために音楽をやるのかっていうこともずっと考えていて、ただ好きだからっていう理由だけではもたないと思っていたんです。
■『怪談』が完成したのは?
藤田:32歳のときでしたね。人生のなかで、ようやく「これが俺だ」と思うものができたって思えたのは。それで手当たり次第にレーベルに曲を送ったけれど、なんの返事もない。さすがにこのときは挫折を覚えました。もうダメだ。自分はこれだと信じてやってきたけれど、通用しないことが世のなかにあるんだということを初めて、遅いんですけど、32歳の時に知って。もう、すごい惨めな気分になりました。何のために貧乏やっていたのかわからないから、これからは金を稼ぐ仕事をしようとか、真剣に株の勉強をしようと思いました。そうしたら、2017年の年末に近づくにつれて、Soundcloudでだんだんとリアクションが来るようになりました。ならば駄目もとでと、自ら配信サイトで価格を決めて売ってみたほうがいいと思いはじめたんです。
日本は怪談の産地だ。『今昔物語』、ずっと時代を進めて鶴屋南北の『東海道四谷怪談』や上田秋成の『雨月物語』、人間の報われなさや邪悪な内面は物語として語られ、あらゆる階級にとってのダーク・ファンタジーとして享受されてきている。日本趣味を嫌っていた武満徹が雅楽の楽器を取り入れたのは1964年の『怪談』のサウンドトラックだった。そして藤田は、日本の古きポップ・カルチャーの人気ジャンル「怪談」を自由形式のエレクトロニック・ミュージックに変換した。
『怪談』が全曲聴けるようになったのは、冒頭で書いたように2018年1月1日だったが、その翌年冥丁は早くも次作をリリースする。『怪談』の評判をもって連絡をしてきたいくつもレーベルのなかで、もっとも情熱を感じたという、UKの〈Métron〉レーベルから『Komachi』がリリースされたのは2019年3月。このセカンド・アルバムによって彼の自己イメージはある程度固まり、冥丁の折衷的なエレクトロニカはより広く届けられることになった。
スリーヴアートに古い浮世絵をモダンにデザインするというアイデアもまた、「日本らしさ」の表現に思考を巡らせた京都時代に温めていたものだった。浮世絵とは堅苦しいアートではなく、江戸時代に爛熟した庶民文化の象徴だ。藤田は、彼の地で観光客相手に売られている浮世絵をプリントしたTシャツを横目に、「あんな安直な発想ではなく、もっとしっかりデザインしたものがここ日本にあったらいいのに」と思いながら、いつか自作のなかで使いたいと考えていた。「著作権が切れている浮世絵はたくさんあって、ネットを使って、面白いものを探したんです。そのなかで、これ(『Komachi』)の絵を見つけましたね。可愛いし面白いし、これは音楽にも合っているだろうと思いましたね」、と彼は当時を回想する。
■『怪談』と『Komachi』によって冥丁のイメージは固まったという印象ですが。

『怪談』(2018)

『Komachi』(2019)
藤田:時系列的なことで話すと『Komachi』の前に「夜分」というシングルもあるんですが、これもほとんどが京都で作ったもので、『怪談』を出してから、ほかにも曲があることを思い出して、そのなかのいくつかをEPとしてまとめました。
■京都時代に、すでにけっこう作り溜めていたんですね。
藤田:そうですね、(すでに曲は)ありましたね。「夜分」のなかに“宇多野”という曲があるんですが、京都時代に、ぼくはよくそこに夜自転車を漕いで探検しに行っていたんです。そこには、木々の香りや水面の香りが漂っている、ちょっと怪奇的な池があるんです。ひとりでそこにいると、なにか創造的な空気感を感じるんです。まるでこう、日本の昔の民間伝承の雰囲気というか、空気感というか。それを音で捉えられるんじゃないかと思って。
■さっきも話した、場のアトモスフィアみたいなものを表現できないかということですね?
藤田:そうですね。それはやっぱり日本独特のものなんですよね。京都のああいう感じ、あの池の感じとか。これを音楽にしないとダメだろって。
■なるほどね。
藤田:まだ『怪談』を作る前ですけどね。なんか、学びに行っていたというか。「夜分」に入っている“池”とか“提灯”のような曲はそうやってできていきましたね。
■日本にも面白い場所はたくさんありますよね。ぼくも子供の頃は、大きなお寺の裏にある墓地のなかの小さな池で遊んだりしました。そのとき感じた神妙さを思い出しては、いまでも帰省したときそこに行ったりします。
藤田:そういう、何か違う空気感が漂っているような場所が日本にはあるんです。ぼくはその雰囲気や、もっというと世のなかの印象をなんとか音にしたいと思っているんです。
■Burialをはじめ、UKのいろんなアーティストが19世紀のゴシック的な、あのくすんだ英国を表現していますが、日本の文脈でそれをやったのが冥丁ですよね。藤田君はトビラを開けたんだと思います。
藤田:開けたかったと思ってやりました。
■『古風』がやっぱいちばん受けたんですか?

『古風』(2020)
藤田:いや、どのアルバムがいちばん受けたのかはぼくはわからないです。
■だって、これは三部作になったわけだし、とくにリアクションが大きかったのでは。
藤田:いや、当初は三部作にするつもりは毛頭なくて(笑)。最初の『古風』を出して終わる予定だったんです。そもそも最初の『古風』は「l」だと思って作っていないですから。だから、あのアルバムを出して終わるつもりだったのが、出した途端、コロナになってしまった。ぼくもいろいろライヴのスケジュールがあったんですけど、すべてキャンセルになってしまって。だから自分がこれまで作っていて、発表していない曲を整理しようと思ったんです。そのなかで、『古風ll』ができた。『古風』を作ったころに作った曲で未発表がたくさんあったんです。
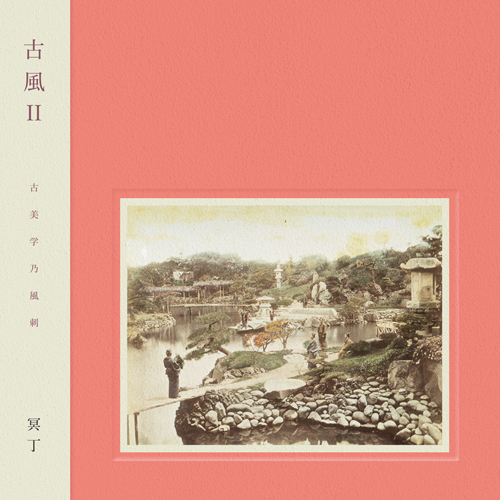
『古風II』(2021)
■なるほど。コロナがあったから生まれたのが続編だったんですね。
藤田:そういうことなんですよ。
■話は変わりますが、初ライヴはいつだったんですか?
藤田:いやー、これもすごい、最近の話で、35歳のときだったと思います。たしか、3年前ぐらいだったんです。和歌山の〈Bagus〉というライヴハウスが呼んでくれたんですけど、そもそも自分にはライヴをやるという発想がなかったから、そのときは、いったいどうしたらいいものかと。
■『怪談』のころですか?
藤田:そうです。洞窟のなかにあるライヴハウスでしたね。突然連絡があって、「冥丁さんライヴやられたことあるんですか?」と言われて「いや、ないです」と。「じゃあちょっとやってみませんか?」っていうので「マジですか!?」って。そんな感じでしたね。
■(笑)
藤田:(笑)むちゃくちゃ緊張して、吐きそうでした。「俺人前に立つタイプじゃないもん」って思っていたんで。
■ライヴを想定して機材も揃えていなかっただろうし。
藤田:いまでもそうなんですけど、ぼくは自分のことをミュージシャンだって思っていないです。たしかに作曲はしていますが、世にいうミュージシャンって、ぼくは音楽と握手をしているようなところがある気がする。ぼくは音楽を握手しているというより、ちょっと野蛮な向き合い方もしているような気がするんですよね。
■アーティストや表現者といったほうがしっくりきますか?
藤田:たとえば、ぼくが興味があるのは、あそこに積んである段ボール(編註:取材場所の窓際に積んであった)の、あの雰囲気を音でどうやったら表現できるのかとか、段ボールのテープの部分のあのカサカサした感じはどうやったら出せるのかとか、そういうことなんですね。ジョン・フルシアンテのインタヴューを読むと、彼はミュージシャンが誰々であれが良かったなんとかなんとか(詳説している)。だから彼はすごいファンなんですよね、音楽の。ミュージシャンの人たちとの横の関係みたいなものもあると思うんです。でも、ぼくはひとりでやっているし、同じ音楽が作っているけどアプローチが全然違いますよね。
■よりコンセプチュアル?
藤田:冥丁はそうですね。
■「Tenka」名義での作品は?
藤田:あれは趣味ですね。何も考えずにただ作っていたっていうだけです。
■「奇舎」の名義でもやっているんですね。こないだ送ってくれた……。
藤田:先日、野田さんに送った「江戸川乱歩 × Jan Svankmajer」ですよね。あれも初期のもので、まだ、作品がまとまっていない頃に作ったものですね。
■江戸川乱歩に関しては、新作の『古風lll』にも“Ranpo”という曲がありますが、どんなところが好きなんでしょう?
藤田:なんだろう、あの怪奇性ですかね。小学校のときに図書室にあった『夜行人間』をよく憶えていて、挿絵の感じも好きだったし。それで『怪談』を作っていたときに、音で怪奇な感じをどうやったら出せるのかを考えていて、その制作の過程で「傑作選」を読みました。「屋根裏の散歩者」みたいな代表作が入っている文庫本です。チェコスロバキアのヤン・シュヴァンクマイエルという人形劇作家がいて、この人の作品もぼくは大好きなんですが、展覧会では、ヤン・シュヴァンクマイエルが表現した江戸川乱歩というのもあって、その解釈(「人間椅子」の挿絵をやっている)がとても面白かったんです。それで、自分も音で江戸川乱歩をやってみようかって思って最初にやったのが奇舎の名義で発表した「江戸川乱歩 × Jan Svankmajer」でした。
取材・文:野田努(2023年12月25日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE