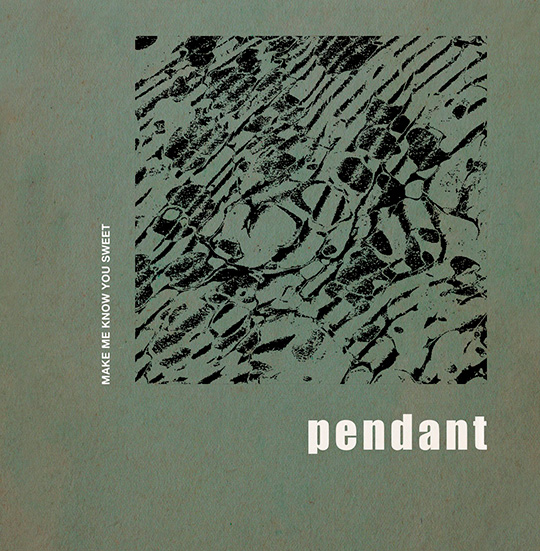1990年代初頭から活躍するデトロイトのDJ/プロデューサー、K-Handことケリー・ハンドの来日が東京、大阪で決定しました。この女性DJは、昨年は、Nina Kravizのレーベル〈трип〉から作品を発表しており、近年はまさに再評価を高めている。いまでこそ女性のDJ/プロデューサーは珍しくないが、ケリー・ハンドが自身のレーベル〈アカシア〉をデトロイトではじめた時代は、右も左もブースでレコードを回すのは野郎ばかりだった。まさに先駆者であり、偉人ではないだろうか。
K-HAND Japan Tour
5/26(土)大阪 @ALZAR
5/28(月)東京 @Contact K-HAND
≪Boiler Room DJ set 2015≫
≪Nina Kravizが選曲したK-HANDの15曲≫
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnZOad80R4noDs94C1e6CsMgydiS_UWuE