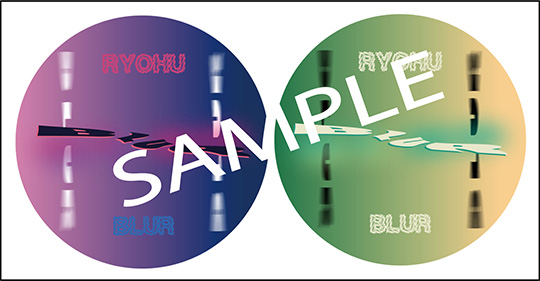勢いが止まらない。メンバー各々が精力的にソロ活動を繰り広げるなか、今度はKANDYTOWN本体が動き出した。去る9月29日、かれらにとって2017年最初のリリースとなる新曲“Few Colors”が配信でリリースされたけれど、この度そのMVが公開された。メンバーたちが一堂に会し、同じブーツを着用している風景はじつに壮観である。今後もかれらの動向から目が離せそうにない。
東京の街を生きる幼馴染たち、総勢16名のヒップホップ・クルー:KANDYTOWN
2017年第1弾リリースとなる新曲“Few Colors”(ティンバーランド 2017年FALL&WINTERタイアップソング)のMUSIC VIDEOを遂に公開!
昨年11月に発売した1stアルバム『KANDYTOWN』がiTunes HIP HOPチャート1位を獲得し、各メンバーのソロ名義でのリリースも活発に行い話題のヒップホップ・クルー:KANDYTOWNが、ティンバーランドの2017年FALL&WINTERタイアップ・ソングとなっていることでも話題の2017年第1弾リリースとなる新曲“Few Colors”のMUSIC VIDEOを公開した!
これまでこの映像は“Few Colors”のiTunes Store限定バンドル特典としてしか見ることができなかったが、新曲“Few Colors”が配信されるや否や、各配信サイトのHIP HOPチャートの上位を賑わせている中での、まさに待望のMUSIC VIDEO公開となった! 今回のMUSIC VIDEOも、KANDYTOWN内のIO、YOUNG JUJUが所属するクリエイティヴ・チーム:TAXi FILMSが手掛けており、映像中では、ティンバーランドのアイコンとも言うべき、シックスインチプレミアムブーツを着用したメンバー全員が出演している。重厚感のある楽曲同様、これまで以上に深く、濃くKANDYTOWNの世界観を味わえる内容となっている。
そんな、KANDYTOWNはティンバーランドとのコラボレーションを記念して、MUSIC VIDEO同様にTAXi FILMSが手掛けたビジュアルを始めとしたスペシャル・コンテンツを擁した特設ウェブサイトもOPENしているので、是非チェックしてみよう!
【“Few Colors”YOUTUBE URL】
https://www.youtube.com/watch?v=pKb2qbY7ccg
【“Few Colors”作品詳細】

配信日:2017年9月29日(金)0:00
タイトル:Few Colors(ティンバーランド 2017 FALL&WINTERタイアップソング)
配信URL: https://lnk.to/KFQE0
備考: iTunes限定で特典にMUSIC VIDEOが付いたバンドル配信も決定。
【KANDYTOWN|Timberland特設ウェブサイト】
https://goo.gl/LFdZSK
【KANDYTOWN オフィシャルHP】
https://kandytownlife.com/
【KANDYTOWN WARNERMUSIC JAPAN HP内ARTIST PAGE】
https://wmg.jp/artist/kandytown/
【KANDYTOWN プロフィール】
東京の街を生きる幼馴染たち、総勢16名のヒップホップ・クルー。
2014年 free mixtape『KOLD TAPE』
2015年 street album『BLAKK MOTEL』『Kruise』
2016年 1st album『KANDYTOWN』
2017年 1st album『KANDYTOWN』(4LP)