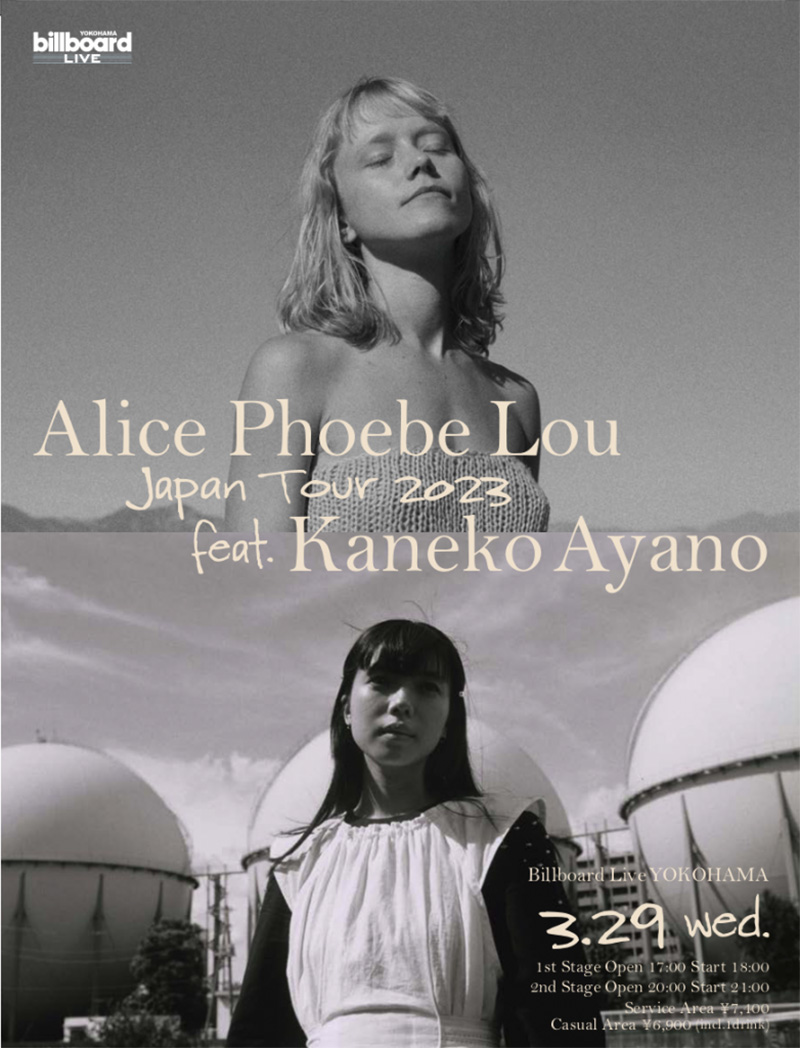ところで皆さん、LPに付属の7インチってどう保存してますか? LP+7インチ盤の有名どころだと、スティーヴィー・ワンダーの『Songs In The Key Of Life』だったり、サディスティック・ミカ・バンドのファーストだったり。そのままスリーヴに入れていると、いつのまにか紛失してしまっている……そんな事情があるからでしょう、中古市場でも付属の7インチを完備しているLPは少なく、完品は高額なことが多いですね。
というわけで朗報。VINYL GOES AROUNDチームが画期的な発明を成し遂げました。といっても複雑なものではありません。12インチ・サイズのボードに、7インチのジャケをパコッとハメる、ちょっとした気の利いたアイテムです。名づけて「ヴァンホルダー(VANHOLDER)」(盤をホールドすることから命名)。ヴァンホルダーに固定された7インチはLPのジャケット内で無駄に動いたり、飛び出したりしないので紛失を防止できます。およそ70年にもおよぶLPと7インチの歴史において、なぜこれまでだれも思いつかなかったのか……。これはLPとセットでなくとも7インチ単独の保管にも適しており、ヴァンホルダーにハメればLPの棚にもそのまま収納できるので、単品での販売も予定しているとか。
これであなたのレコード・コレクティング・ライフの質は格段に向上するでしょう。詳しくは下記動画やリンク先をご覧ください。
株式会社Pヴァインは、アナログ・レコードに関する特許権を取得しました。ヴァンホルダー(VANHOLDER)は、7インチのジャケットを12インチ・サイズに変えるアイテムです。
Pヴァインは2022年12月にアナログ・レコードのパッケージに関わる特許権を取得しました。
本特許は、レコードパッケージにおいて独自の技術を開発したものです。
LPサイズのジャケット内に収まりが悪かった7インチ・シングルやCDがスマートに収納できるプロダクトを作りました。
これは12インチディスクと7インチディスク(または10インチディスク及びCDも含む)をひとつのフォーマットにできるLPの付属具で、専用のボードに7インチディスク(または10インチディスク及びCD)を固定し、12インチディスクのジャケットに収納が可能になります。これによりジャケット内での揺れや、外への飛び出しを防ぐことができます。
特許番号:第7199767号
発明の名称:レコード支持板、レコードジャケット、及びレコード製品
商品名:ヴァンホルダー(VANHOLDER)
特許取得日:2022年12月23日(金)
材質:インバーコート紙 0.6mm(印刷可能)
使用開始日:2023年1月18日(水)
カテゴリ:レコードジャケット、及びレコード製品
詳細はこちらのURLをご参照ください:https://vga.p-vine.jp/vanholder/
※ヴァンホルダーは10インチ・レコードやCDなどにも対応可能です。
その他、製造の事など詳しくは下記までお問い合わせください。
お問合せ先:株式会社Pヴァイン TEL: 03-5784-1250 FAX: 03-5784-1251 vinylgoesaround@p-vine.jp 担当: 山崎