MOST READ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- aus - Eau | アウス
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Regulars > 日本のジャズを彩った音楽家たち > 第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!?
(前半から続く)
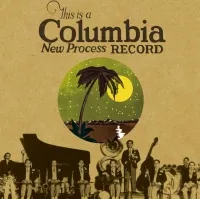
『日本のジャズ・ソング~戦前篇・服部良一和製ジャズ・コーラス傑作集/戦時下の和製ポピュラー南海音楽』(BRIDGE INC.)
服部の曲の特徴である和洋折衷については興味深い話がある。食通としても有名だった映画監督の山本嘉次郎は、著作『日本三大洋食考』の中で、ライスカレー、コロッケ、トンカツを“日本三大洋食”と定義したという。いわば日本が世界に誇る洋食である。
これは音楽評論家の渡辺亨が細野晴臣『泰安洋行』のレビュー(『レコード・コレクターズ00年5月号』)で引き合いにだした逸話だが、戦前の音楽に精通している細野も、どこかで服部を意識していたのではないだろうか。米国のジャズから調達した食材を、日本人なりの調理法でさばいていったという意味で、両者は一脈通じている。そして、先述のピチカート・ファイヴが細野のレーベル“ノン・スタンダード”からデビューしたのも機縁を感じさせるではないか。なお、上田賢一『上海ブギウギ1945 服部良一の冒険』にも音楽を洋食に喩えた記述がある。
「音楽の洋食」——「東京行進曲」「君恋し」を聴くとそんな言葉が思い浮かぶ。ハヤシライスやオムライスといった洋食屋の味。今でも日本料理の多くは、食材、調味料から見ても、完全な西洋料理とはいえない。完全な西洋料理を求めようと思えば、よほどの所に行かなければ不可能で、多くは西洋料理という名の和食だ。
和洋折衷という意味ではこんなエピソードもある。日本では昭和2年、現在のコロムビアやビクターにあたる日本最古の蓄音器商会が、英・米コロムビアと合併の形で設立された。各社は、本国から持ち込んだ洋盤をプレスして発売したが、一方で、民謡、童謡、浪曲、長唄などの邦盤も大量生産している。そのうち、外国の曲に日本語の詞をつけ、日本人の歌手に歌わせることを発案し、このアイディアが成功。一連の舶来流行歌をいつしか“ジャズ・ソング”と称するようになった。これは和製英語で、“ナイト・ゲーム”を“ナイター”と言ったり、“カリー・アンド・ライス”と言うべきところを“ライスカレー”と代用していたのと同じである。命名者は不明だが、音楽レコード会社の文芸部ではないかとの推測が有力らしい。
ハヤシライスやオムライスが庶民の味だったように、服部良一にとって、歌は庶民のものという意識が根柢にあったのではないだろうか。海外からの新鮮な輸入品を日本人なりに加工/変形したものが服部のジャズ・ソングだった。新しい音楽を求めてアメリカのジャズを参照し、庶民が歌える歌を作ることを服部は考えていたように思う。つまり、ジャズのセンスを流行歌の面にも援用しようとしたのだ。
ここであらためて服部の来歴を振り返りたい。ただ、数々の逸話を知らずとも、最近になって服部良一の名前を耳にした人は多いに違いない。ブギの女王と呼ばれた笠置シヅ子の波乱の歌手人生を追ったNHKの連続テレビ小説『ブギウギ』に服部が登場するからだ。笠置を演じる主役は趣里。服部は羽鳥善一という名前に変えられて草彅剛が演じている。
服部良一は、1907年、浪花節を得意とする父と河内音頭の本場・富田林で育った母の間に生まれた。下町育ちで、小唄などが子供の頃から身にまわりにある環境で育ったという。〈当時の日本の庶民の歌に親しんでいて、江戸からつながる日本の娯楽音楽に対する教養があった〉と評論家/音楽家の大谷能生は述べている(瀬川昌久+大谷能生『日本ジャズの誕生』)。服部良一が子どものころに聴いていた曲として「書生節」があり、その影響が彼の作曲にも及んだことが大谷と瀬川の対話からわかる。また、服部がニットー・レコードにいた頃に、小唄芸者だった美ち奴が歌った「〇〇節」「〇〇小唄」といった曲はすべて服部のアレンジによるものだ。
西洋音楽に触れたのは近所の教会での讃美歌、小学校での唱歌やハーモニカだったという。当時の唱歌という言葉には子供の合唱といった意味合いはなく、“シンギング”“ヴォーカル・ミュージック”を意味していたそうだ。やがて学校では、イギリスの民謡を文語体の訳語で歌うようになる。「蛍の光」や「埴生の宿」などがその代表例である。15歳の時出雲屋少年音楽隊に入隊。出雲屋というのは実は鰻屋のことで、今となっては不思議な感じがするが、当時は三越や高島屋や松屋など百貨店が宣伝用に音楽隊をつくって、それが日本のポップスの基礎となったのである。
その第一期の入隊式が行われたのは1923年9月1日だが、この日、おそろしいことに関東大震災が関東圏を襲った。結果、多くのバンドマンが関東から大阪に移動してきて、道頓堀はジャズのメッカとなる。この頃、道頓堀、千日前にダンスホールが初めて竣工。3年後には、20のダンスホールができ、道頓堀川には芸者のジャズ・バンドが乗った屋形船まで出現したという。そんな環境下で、大正15年、服部が19歳の時に大阪フィルハーモニック・オーケストラに入団。これは大阪放送局(JOBK)の専属オーケストラとして発足したもので、服部はオーボエを担当した。
翌年、服部は彼の才能を見抜いたロシア人指揮者のエマヌエル・メッテルに師事し、作曲家リムスキー・コルサコフの和声を学ぶ。メッテルの指導が厳しかったのは服部の自叙伝『ぼくの音楽人生』を読むとよく分かるが、それでも服部は必死で食らいつき、和声学やコルサコフの代名詞である管弦楽法などの音楽理論を習得。メッテルはクラシックが専門だったが、服部が“実はジャズをやりたいんだ”とおそるおそる言いだすと、音楽にジャンルの垣根はないとメッテルに激励されたというエピソードが象徴的だ。
バンドでサックスを吹く一方、服部は同時並行で編曲も手掛けるようになっていた。なお、彼が編曲という名称を覚えたのは井田一郎の仕事を通じてのこと。井田は、1923年に日本初のプロのジャズ・バンドとして名高いラフィング・スターズを結成したキーパーソンだ。当時、編曲という作業を行っていたのが井田くらいしかおらず、二村定一など初期のジャズ・ソングのレコーディングはほとんどが井田の編曲/指揮であった。
なお、編曲に秀でていた才人として、コロムビア所属だった仁木多喜雄の名前も挙げなければならないだろう。夭逝したため服部よりも知名度は低いが、リキー宮川の「マーチャン」は端正で瀟洒、モダンそのものである。アメリカのビッグ・バンド・ジャズ人気を担ったグレン・ミラーやジーン・クルーパのサウンドをうまく翻案/消化した印象もある。その仁木と比較すると、服部の曲は日本的な響きが強い。例えば、コロムビアで制作した和声ジャズ・コーラスもの。昭和14年の「お江戸日本橋」では、ベニー・グッドマンの「シング・シング・シング」を独自に解釈して採り入れ、管楽器のアレンジも完璧だった。
服部は1933年に上京。作曲や編曲の仕事を手掛けるようになり、36年にはコロムビアの専属作曲家となる。コロムビア入社第一回の作品が淡谷のり子の歌う「おしゃれ娘」で、米国で勃興していたスウィング・ジャズの意匠を施した同曲は多くの日本人を驚かせた。同じく、淡谷のり子「別れのブルース」は、黒人のブルースをベースにした作品。服部の意向を汲み、本来得意ではなかったアルトの音域で歌ったという。もちろん、李香蘭(山口淑子)の歌唱による「蘇州夜曲」もヒット。以降、レコード、ステージ、放送、映画音楽など多彩な活動を展開してゆく。戦中は陸軍報道班として中国へ渡り、文化工作に従事。中国の作曲家とも密な関係を築いた。戦後は、ブギウギのリズムを採り入れた「夜来香ラプソディ」の他、「青い山脈」「銀座カンカン娘」とヒットを連発し、人気音楽家として一躍その名を轟かせることになる。
指導者としての服部についても触れないわけにはいかない。戦前、多少なりともジャズの編曲を手掛けた音楽家は、ほとんど全ての人が一度は“響友会”なる服部塾の生徒だったといっても過言ではないからだ。ここで連想されるのが、渡辺貞夫のことである。バークリー音楽大学(筆者註、当時はバークリー音楽院)で学んだ渡辺は帰国したのち、自宅に後輩や同輩を呼び集めて、アメリカで学んだことを若いジャズメンに伝授した。このふたつの私塾は、それぞれ、戦前戦後の一大業績と言えるのではないだろうか。瀬川昌久が監修を手掛けた『日本のジャズ・ソング~戦前篇~シリーズ』の解説などでその重要性を説いている。
また、先述のダンスホールがさかんになってくると、外国だけではなくて日本の流行歌もアレンジして混ぜてゆくことになる。日本で流行っている歌をジャズやタンゴにすると、聴衆が思いのほか喜んだというのだ。ダンス・バンドにはそうした需要が徐々に増え、服部に依頼して「雨のブルース」を(社交ダンスの一種である)フォックス・トロット風にアレンジし、演奏したこともあったとか。
ダンスホールに来場する客では、学生には瀟洒でモダンなアレンジのものがウケる。一方、その他の人はアンサンブルやダンス・リズムには凝っていない歌謡曲を好む。服部はその両方をつなぐような仕事をされている、と瀬川は述べている(『日本のジャズの誕生』)。コロムビアの専属作曲家として業績をあげるには、そういった仕事も必要だったのだろう。服部は意識して古賀政男風のメロディもずいぶん作ったそうだ。
そんな服部が人生最後の音楽会でメインに選んだのはシンフォニック・ジャズだった。コンサートは昭和42年の還暦記念にあわせて開催。クラシックの上海交響楽団と共演し、41分にわたる交響詩を披露した。これは服部の積年の夢であり願望だった。というのも服部は、アメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウィンに強い憧れを抱いていたのだ。ガーシュウィンは1898年NYのブルックリン生まれ。少年時代にピアノを勉強し、1919年、21歳の時に作曲した歌曲「スワニー」で世に出る。
“キング・オブ・ジャズ”を名乗るポール・ホワイトマンがガーシュウィンの才能に目をつけ、ジャズの交響楽的作品を書くことをすすめ、ピアノ独奏と管弦楽のための作品「ラプソディー・イン・ブルー」が完成。初演は1924年(日本では大正13年)で、服部が17才の時だ。服部はかねがね、ガーシュウィンのようにジャズの大交響楽団で演奏することを夢見ていた。大阪にいた頃、服部は「ラプソディ・イン・ブルー」をアメリカ帰りの作編曲家、紙恭輔が東京で舞台にかけたと聞いて、いてもたってもいられなかったという。
服部は、クラシックとポピュラー音楽の間に明確な区別がなく、西洋音楽が一括りにされていた1920年代に音楽家としての訓練を受けた。10代からカフェやダンスホールでジャズを演奏しながら、大阪フィルハーモニック・オーケストラでクラシックを演奏している。そんな風にクラシックもジャズも等価なものとして享受してきた彼が、いま一度自分の音楽人生を総ざらいし、複数のジャンルを統合することを望むのは自然だったはず。服部のスタンスはこの発言に端的に表れている。
音楽にはクラシックとポピュラーといった区別は本質的にないというのがぼくの考え方で、とにかくいい音楽を大衆に親しんでもらいたいという気持ちからだった。この考え方はぼくの一生を通じて変わっていない。音楽に大衆音楽も高級音楽もないと考えるぼくは、当面、学びつつある音楽理論や技法を、ジャズや歌謡曲の世界で生かしたいと苦心していた。(服部良一『ぼくの音楽人生』)
なお、1992年10月20日には大阪で“服部良一音楽祭‘92”が催された。会場は大阪城ホール。歌謡界以外のポップス系の音楽家や歌手が、服部良一作品を積極的にレパートリーに入れているのを受けてのコンサートだった。出演した面々は実に豪華。括弧内に演奏/歌唱した曲を入れると、サンディー(「蘇州夜曲」)、東京スカパラダイスオーケストラ(「ラッパと娘」)、山崎ハコ(「東京ブギウギ」)、アメリカのブレイヴ・コンボ(「青い山脈」)、シンガポールのディック・リー(「ジャジャムボ」)など。上記のコンサートのように『ブギウギ』の放映によって一気に押し寄せたように見える服部良一再評価の波だが、それ以前からその功績は着々と引き継がれている。服部良一と笠置シヅ子と雪村いづみと小西康陽を繫ぐ一本の太い幹は現代の日本の音楽にも確実に影を落としているのである。

ピチカート・ファイヴ
『さ・え・ら・ジャポン』
(日本コロムビア)

荒井由実
『ひこうき雲』
(EXPRESS)

雪村いづみ
『フジヤマ・ママ 雪村いづみ スーパーアンソロジー1953-1962』
(ビクターエンタテインメント)

雪村いづみ
『スーパー・ジェネレイション』
(日本コロムビア)

George Gershwin
『エッセンシャル・ジョージ・ガーシュウィン』
(ソニー)
■参考文献一覧
丸山眞男著『現代政治の思想と行動』(未来社)
梅棹忠雄著『文明の生態史観』(中公文庫)
内田樹著『日本辺境論』(新潮新書)
相倉久人著・松村洋編著『相倉久人にきく昭和歌謡史』(アルテスパブリッシング)
マイケル・ボーダッシュ著・奥田佑士訳『さよならアメリカ、さよならニッポン』(白夜書房)
瀬川昌久+大谷能生『日本ジャズの誕生』(青土社)
服部良一著『ぼくの音楽人生』(日本文芸社)
上田賢一著『上海ブギウギ1945 服部良一の冒険』(アルテスパブリッシング)
『レコード・コレクターズ』00年5月号「特集・細野晴臣」(ミュージック・マガジン)
小沼純一監修『あたらしい教科書 音楽』(プチグラパブリッシング)
末越芳晴著『ラプソディ―・イン・ブルー ガーシュインとジャズ精神の行方』(平凡社)
『ミュージック・マガジン』01年2月号(ミュージック・マガジン)
『ミュージック・マガジン』2024年2月号「特集・『ブギウギ』と笠置シヅ子の時代」(ミュージック・マガジン)
山本嘉次郎著『日本三大洋食考』(昭文社)
内田晃一郎著『日本のジャズ史』(スイングジャーナル)
大谷能生著『20世紀ジャズ名盤100』(イースト・プレス)
井上寿一著『理想だらけの戦時下日本』(ちくま新書)
Profile
 土佐有明/Ariake Tosa
土佐有明/Ariake Tosaライター。音楽評の他、演劇評、書評なども執筆。3月にDU BOOKSから『イカ天とバンドブーム論』を上梓。現在は日本のジャズ史を網羅するディスクガイドを準備中。今年の春から、知見を広めるべく大学の授業にこっそり通ったりしています。
COLUMNS
- Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁


 DOMMUNE
DOMMUNE