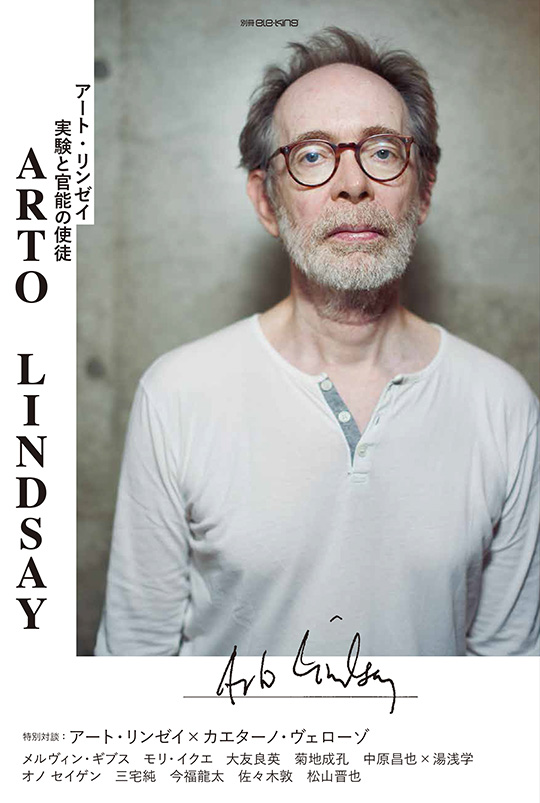作品情報
『サクロモンテの丘~ロマの洞窟フラメンコ』
2017年2月18日(土)より、有楽町スバル座、アップリンク渋谷ほか全国順次公開
監督:チュス・グティエレス
参加アーティスト:クーロ・アルバイシン、ラ・モナ、ライムンド・エレディア、ラ・ポロナ、マノレーテ、ペペ・アビチュエラ、マリキージャ、クキ、ハイメ・エル・パロン、フアン・アンドレス・マジャ、チョンチ・エレディア他多数
日本語字幕:林かんな/字幕監修:小松原庸子/現地取材協力:高橋英子
(2014年/スペイン語/94分/カラー/ドキュメンタリー/16:9/ステレオ/原題:Sacromonte: los sabios de la tribu)
提供:アップリンク、ピカフィルム 配給:アップリンク 宣伝:アップリンク、ピカフィルム
後援:スペイン大使館、セルバンテス文化センター東京、一般社団法人日本フラメンコ協会
エレクトロニックなクラブ系の音楽にとって、フラメンコといえば、チル・アウトの一要素として流麗なギターが使われる程度のことが多い。しかし映画『サクロモンテの丘』のフラメンコの音楽と踊りは、はるかに荒削りで強烈なものだ。歌詞のストレートなあけすけさはラップに負けず、手拍子(パルマ)と踊り手のステップ(サパテアード)と打楽器的なギターによるリズムは、ミニマルなダンス・ミュージックに通じ、ときにトランシーでさえある。
映画が撮られたのは、スペイン南部アンダルシア地方のグラナダ。町の郊外のサクロモンテの丘の洞窟には古くからヒターノ(ジプシー)が暮らし、フラメンコで身を立てている。グラナダ出身の監督チュス・グティエレスは、その丘と住民に焦点を当てた。

チュス監督
「ドキュメンタリー映画を撮ったのはこれがはじめて。テーマに興味があって、身近なものだったので、何かが語れる自信はあったけど、企画の段階では、それが何なのか、まだわからなかった。映画を作るときは、信じるものを追求して撮るだけよ。サクロモンテの人たちにインタビューすることからはじめて、撮りながら作っていったの」
フラメンコ・ダンサー/歌手/研究者のクーロ・アルバイシンを案内役に、映画は少しずつサクロモンテに暮らす人々の中に分け入って行く。世界中を旅して回った人もいれば、踊るために結婚生活を断念した人もいる。ヒターノではないのに踊りを教える人もいれば、大人顔負けのステップを踏む少年もいる。インタビューや歌や踊りに合わせて、登場人物の若いころの姿などの貴重なアーカイヴ映像も挿入される。
「フラメンコは若い人たちの力強い踊りを見るものと思われているけど、わたしが感動したのは、年配の人たちが体力の限界の中で表現している微妙な動き。若い人のような激しさはないけど、抑制された踊りの動きが、かえって新しく見えたりする。その人たちは、みんな見よう見まねでフラメンコを覚えた世代の人たち。マノレーテのように、アントニオ・ガデスの踊りを見て影響を受けた人もいる」

実は1963年の洪水で丘の洞窟住居は大きな被害をこうむり、以後ヒターノたちの生活環境も変化を余儀なくされた。
「この映画の主役はフラメンコだけでなく、昔ここにあった共同体のゆくえでもある。往年のこの丘ではフラメンコが生活と密着していた。それがどうだったのかを知りたかった。いまの子供たちはそんな環境には暮らしていない。学校で先生について学んで、伝統を受け継いでいる」
水害で失われたものは大きかったが、伝統が時代の変化に対応しながら継承されている様子は、映画から伝わってくる。ところでサクロモンテのフラメンコはアンダルシアの他の地域のフラメンコと異なる特徴を持っているのだろうか。
「フラメンコはフラメンコね。本質にちがいはない。ただ、狭い洞窟の店で、舞台の上ではなく、同じ目線の高さで、目と鼻の先にいる客を相手に踊るから、その熱が伝わってくる。床はセメントで、舞台の板のようには響かないから、音を出すためのステップも激しい。ライヴの場面は身内のパーティのような形で撮ったので、みんな親密にリラックスした形で、楽しんで踊ってくれた。奔放に踊るフラメンコになったと思う」

イベリア半島は、8世紀から15世紀までイスラム王国の支配下だった。グラナダは最後の王国が残っていたところだ。グラナダのイスラム建築の精華アルハンブラ(アランブラ)宮殿の姿も、丘の上の踊りの場面で遠望できる。イベリア半島に残ったアラブの音楽家たちが、フラメンコの成立に影響を与えたという説もある。
「イスパニア王国はイスラム王国と戦うとき、鍛冶屋だったヒターノを連れてきて武器を作らせたと言われています。踊りの場面を撮影したタブラオ(フラメンコ酒場)の壁に金属の調理道具が飾ってあるのもその名残。アラブの音楽はフラメンコにもきっと影響を与えたでしょう。いまも北アフリカの弦楽器バンドゥーラを使ってフラメンコを演奏する人がいるし、踊り手が額にアラブの貨幣をつけて踊ったりもする」
両者の古い関係は文献では跡づけられなくて諸説あるが、交流がまったくなかったとは考えにくい。短絡は避けなければならないが、推測する楽しみは尽きない。
海外でのイメージとちがって、「フラメンコはスペインでは外縁的な文化扱いされ、大切にされていない。優れたアーティストは国外に出ていってしまう」と監督は嘆いていた。でもインドに起源を持つヒターノたちがユーラシア大陸の西端でフラメンコの担い手になったように、文化のDNAは国境や民族を越えて繋がっている。「だからこの映画も日本まで来ることができたのだと思う」と語る監督の目はうれしそうだった。
予告編