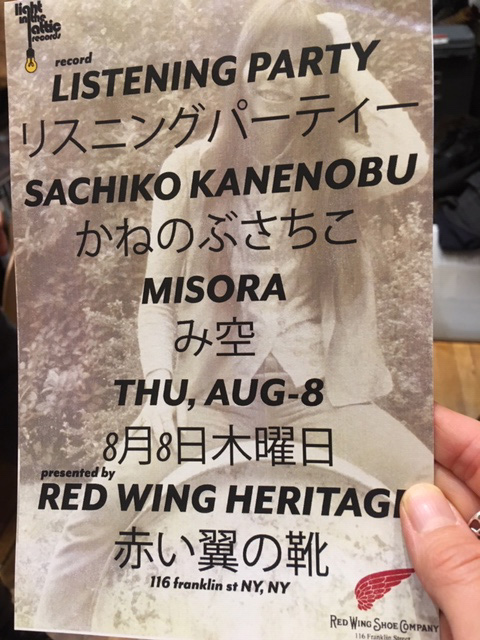沢井陽子さんのコラムを読んでいると、もはや新しいものを生み出せなくなったNYのインディ・ロック・シーンが日本のシティ・ポップに慰めを求めているようで(というのは言い過ぎ?)、なんとも複雑な気持ちになる。ストップ・ターニング・ジャパニーズ、世界が日本化しちゃまずいんだって。それに、音楽は停滞しているように見えて、まだ未開の領域があると言わんばかりの作品も出ているのだ。

シャックルトンの新プロジェクト、 Tunes Of Negation(Shackleton、Heather Leigh、Takumi Motokawa)、「否定の音」を意味する名前のこのプロジェクトのアルバムがヤバい。得体の知れない際どい感覚、ある種の恐ろしさ、そうしたものがここにはまだ生きているような気がする。まだサイケデリックと呼びうる音響があったのかという感じ。ベルリンのレーベル〈Cosmo Rhythmatic〉(キング・ミダス・サウンドの新作を出しているレーベル)から10月18日に現地ではリリースされる。