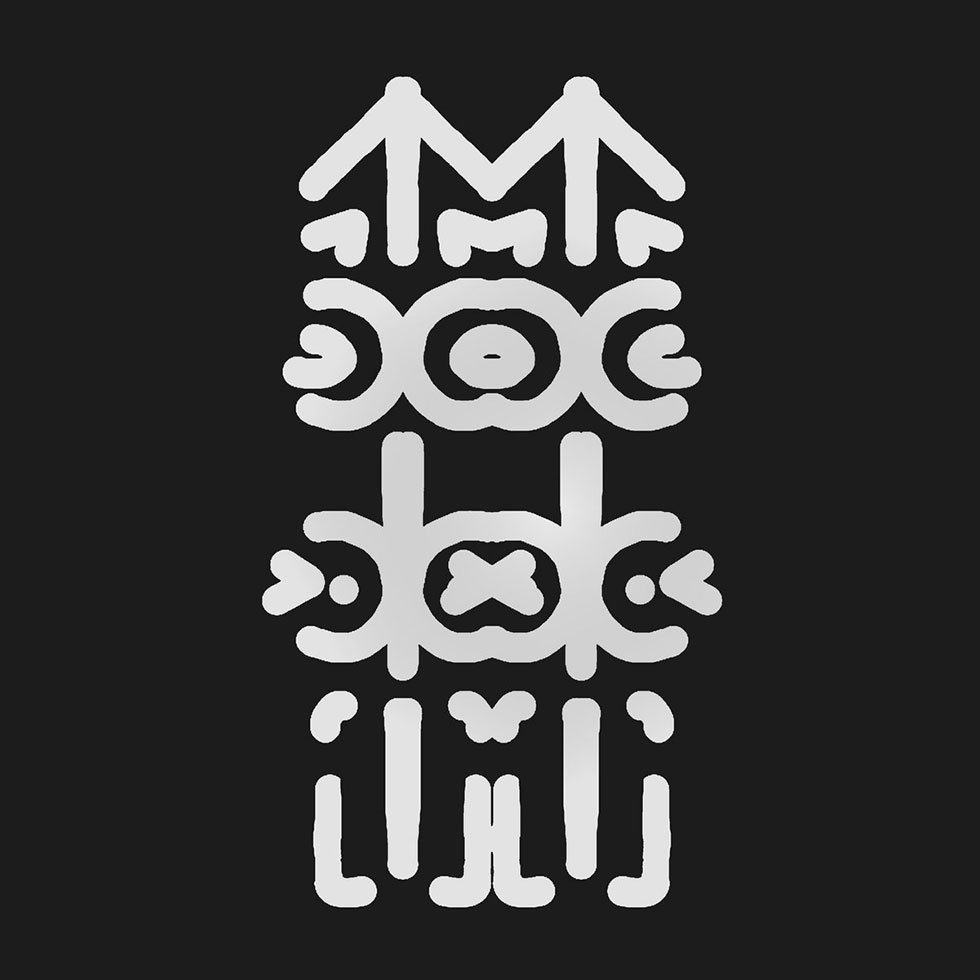最新作『Tranquilizer』が評判のワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティン。彼が映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』(日本公開は3月13日)のサウンドトラックを手がけていることはすでに報じられているが、めでたくもその日本盤がリリースされることとなった。発売は2月27日。映画音楽作家としても着々と地位を固めているロパティン、その最新の成果に注目だ。
MARTY SUPREME
ORIGINAL SOUNDTRACK
BY DANIEL LOPATIN
★ クリティクス・チョイス・アワードでノミネート
★ 英国アカデミー賞でロングリスト入り
★ アカデミー賞でショートリスト入り
注目映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の
サウンドトラック・アルバムが国内盤CDとLPでリリース決定!
購入者特典として先着でオリジナル・ピンポン玉をプレゼント
BEST NEW MUSIC - Pitchfork
緻密かつ雄弁。まるで“第二の脚本”のように機能する - IndieWire
ジョン・ヒューズ作品的な高揚感、宇宙的神秘主義、
そしてジョン・カーペンター的な不穏さが同居するサウンド - Empire
すべてに鮮烈でスリリングなオーラを与えている - Slash Film
ダニエル・ロパティンの予測不能な脈動のスコア。ボリュームは11まで引き上げられている - Variety
本作を語るうえで重要な話題のひとつになるのは、
ダニエル・ロパティンによるきらめくオーケストラルなスコアを中心とした
大胆な音楽の使い方だ
- The Hollywood Reporter
作曲家ダニエル・ロパティンは、マーティの鼓動と、卓球ボールが跳ね返るリズムの両方を、
推進力に満ちたスコアの中で見事に表現している
- AP News
アカデミー賞前哨戦と言われるゴールデングローブ賞にて、主演のティモシー・シャラメがミュージカル・コメディ部門の主演男優賞を受賞し、日本での公開も3月13日に決定している話題映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ (原題:Marty Supreme)』。
現在までに映画賞の213部門にノミネート、うち25部門を受賞し、賞レースのトップランナーに躍り出ている本作のオリジナル・スコアを手がけたのは、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー (以下OPN) ことダニエル・ロパティン。昨年OPN名義で最新アルバム『Tranquilizer』をリリースし、4月には待望の来日ツアーも決定している。
本作『Marty Supreme (Original Soundtrack)』は、Pitchforkにてサウンドトラック作品としては異例となる「BEST NEW MUSIC」に選出され、アカデミー賞でもショートリスト入りするなど、音楽単体としても極めて高い評価を獲得。現在デジタル配信中の本作が、2月27日に国内盤CDおよび2枚組LPでリリースされることが決定した。
ロパティンが手がけた23曲のスコアは、ネオクラシカルなオーケストレーション、広がりのあるシンセサウンド、80年代ハードウェアの有機的な質感を融合し、献身的でありながら陶酔感に満ちた未来的な音世界を描く。ララージの神秘的な演奏、ワイズ・ブラッド の幽玄なボーカルもフィーチャーされ、作品にスピリチュアルな煌めきと揺れ動く感情を一層引き立てている。
本作は現在好評デジタル配信中。
2月27日には、国内盤CDおよび2枚組LP(ブラック&クリア・ヴァイナル)でも発売される。アートワークには映画のビジュアルが採用され、国内盤CDには解説書と両面ポスターを封入。LPはゲートフォールド仕様となり、同じく両面ポスターが付属する。またアルバム購入者は先着で映画にも登場する『マーティ・シュプリーム』オリジナル・ピンポン玉がもらえる。
先着特典:
『マーティ・シュプリーム』
オリジナル・ピンポン玉

封入特典:
両面ポスター

本作は、2025年の年間ベストにも数多く挙げられている、ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー名義の最新作『Tranquilizer』に続くリリースでもある。同作で示された感情表現の透明度と音響テクスチャーの革新性を、映画音楽というフォーマットにおいてさらに拡張。オーケストラのドラマとデジタルの幻影がせめぎ合い、常に変化し続けるロパティンならではの緊張感が全編にわたって描き出されている。
この音楽は、リズムや浮遊感、そして“動き”への強い執着から形になっていった。マーティの変幻自在でスピード感に満ちた、躍動的な性質--まるで卓球のボールそのもののような存在--を表現するために、何百種類ものマレットやベルの音を集めたんだ。このスコアは、伝統と革新のあいだに存在するものにしたかった。ネオクラシカルな要素は、ルールや制約、プレッシャーといった現実の中で彼が生きる現実世界を支え、電子的なテクスチャーは、彼が思い描く未来へと傾いていく。その二つの力が、やがて互いにせめぎ合い始める。
- Daniel Lopatin
ジョシュ・サフディが監督を務め、ティモシー・シャラメが主演。共演には、アカデミー賞受賞俳優グウィネス・パルトローをはじめ、オデッサ・アジオン、ケビン・オレアリー、タイラー・ザ・クリエイターことタイラー・オコンマ、アベル・フェラーラ、フラン・ドレシャーらが名を連ねる。
ロパティンによる音楽は、本作の“神経系”として機能し、ネオンに彩られたマキシマリズムと、結晶のように静謐な瞬間を行き来しながら、サフディが描く野心、崩壊、そして創作への執着を鮮烈に浮かび上がらせている。

label : BEAT RECORDS / A24 Music
artist : Daniel Lopatin
title : Marty Supreme (Original Soundtrack)
release:2026.2.27
商品ページ: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15596
配信: https://a24music.lnk.to/MartySupremeOriginalSoundtrack
TRACKLISTING:
01. The Call
02. Marty’s Dream
03. Endo’s Game
04. The Apple
05. Pure Joy
06. Holocaust Honey
07. The Humbling
08. Motherstone
09. The Scape
10. Tub Falls
11. Fucking Mensch
12. Rockwell Ink
13. Hoff’s
14. Seward Park
15. The Necklace
16. Vampire’s Castle
17. Back to Hoff’s
18. Shootout
19. I Love You, Tokyo
20. The Real Game
21. Endo’s Game (Reprise)
22. Force Of Life
23. End Credits (I Still Love You, Tokyo)
CD

LP

------
ニューアルバム『Tranquilizer』をひっさげ
奇才フリーカ・テットとの最新ライブセットで来日決定!

Oneohtrix Point Never
WITH FREEKA TET
大阪 2026.04.01 (Wed) Gorilla Hall
東京 2026.04.02 (Thu) Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
前売:8,800円(税込 / 別途ドリンク代)※未就学児童入場不可
info:http://www.beatink.com/
E-mail:info@beatink.com
公演詳細:https://linktr.ee/opnjapan2026

label : BEAT RECORDS / Warp Records
artist : Oneohtrix Point Never
title : Tranquilizer
release:2025.11.21
商品ページ: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15439
配信: https://warp.net/opn-tranquilizer
TRACKLISTING:
01. For Residue
02. Bumpy
03. Lifeworld
04. Measuring Ruins
05. Modern Lust
06. Fear of Symmetry
07. Vestigel
08. Cherry Blue
09. Bell Scanner
10. D.I.S.
11. Tranquilizer
12. Storm Show
13. Petro
14. Rodl Glide
15. Waterfalls
16. For Residue (Extended) *Bonus Track
CD+Tシャツセット

LP+Tシャツ

CD

LP

限定LP