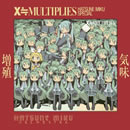禁断の多数決から素敵なプレゼントが届いた。以前よりアナウンスのあったクリスマス・アルバム『禁断のクリスマスBOX』である。ハンドメイド感あふれる箱を開けると、雪を模した綿やらオーナメントやらアートカードの奥から、ディスクが2枚あらわれる。20曲入りのCDと本作用の映像を収めたDVDだ。とても楽しい作りである。しかしこの作品にはもうひとつ重要な要素がある。
前号(ele-king vol.7)で行った〈マルチネ・レコーズ〉主宰トマド氏へのインタヴューでも非常におもしろい話をきくことができたが、本作は話題の「投げ銭システム」、クラウドファンディングを利用し、まさにファンのための仕様を実現している。「メンバー全員、クリスマスが大好きです! 応援してくれた皆さんと完全ハンドメイドのクリスマス作品で一緒にメリークリスマス♪を楽しみたいです」というコンセプトのもと、こうしたシステムを利用し、クリスマス・アルバムというものを「売り物」ではなく「プレゼント」へと、スマートに(またハートフルに)転換してみせた。もちろん定価のついたれっきとした商品だが、制作費をファンがもつというあり方はなんとも直接的で理想的ではないか。投げた金が、プレゼントになって帰ってくるのだ。それはたとえもとからのファンであったとしても、「買わされる」システムとはまったく違うものだ。クラウドファンディングは、うまく利用するならばその過程や手順をスムーズにし、わかりやすく見せてくれる。
曲のほうも、パンダ・ベアをほうふつさせるサイケデリックなトロピカル・ポップや、デイデラス風のラウンジーなカットアップ・スタイルに幕を開け、ベタベタなクリスマス感を避けながらも豊かなフレイヴァーによってこの時期特有のそわそわとした空気を彩る。
購入はバンドの公式サイトから可能だが、明日はメンバーによる手売りが行われるようだ。クリスマス直前でもあることだから、ぜひ行ってみよう。
詳細→ https://kindan.tumblr.com/post/37976471859/12-22-dum-dum-office-box
公式サイト→ https://kindan.tumblr.com/
12/22(土)に高円寺DUM-DUM OFFICEにてメンバーによる『禁断のクリスマスBOX』店頭販売
12/22(土)に高円寺DUM-DUM OFFICEにてメンバーによる『禁断のクリスマスBOX』の店頭販売を行います。12時~17時まで店内におります。先着で、禁断の赤ワイン or チューダー or サイダーを一杯振る舞います。 尚、当HPのショップページからも『禁断のクリスマスBOX』をご購入出来ます。何卒よろしくおねがいいたします。
DUM-DUM OFFICEの地図
https://magazine.dum-dum.tv/archives/901
『禁断のクリスマスBOX』 ショップページ
https://kindan.tumblr.com/shop/