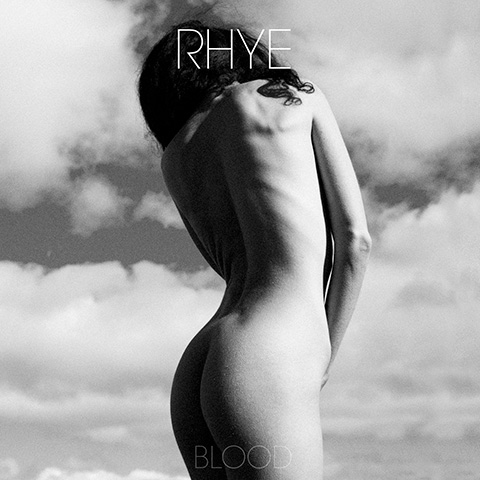2002年9月23日。英国のニューキャッスルにあるバルティック・センター・フォー・コンテンポラリー・アーツにて、ミカ・ヴァイニオ、池田亮司、アルヴァ・ノト(カールステン・ニコライ)らによる最初で最後の競演が行われた。今から16年も前の出来事である。しかし、その音響は明らかに「未来」のサウンドだ。今、『Live 2002』としてアルバムとなったこの3人の競演を聴くと、思わずそう断言してしまいたくもなる。
この『Live 2002』には、音響の強度、運動、構築、逸脱、生成、そのすべてがある。11のトラックに分けられた計45分間に及ぶ3人のパフォーマンスを聴いていると、00年代初頭のグリッチ・ノイズ/パルスを取り入れた電子音響は、この時点である種の到達点に至っていたと理解できる。強靭なサウンドで聴き手の聴覚を支配しつつも、無重力空間へと解放するかのような音響が高密度に放出されているからだ。このアルバムのミニマル・エレクトロニック・サウンドは、00年代初頭の電子音響・グリッチ・ムーヴメントの最良の瞬間である。
2002年といえばカールステン・ニコライはアルヴァ・ノト名義で『Transform』を2001年にリリースし、いわゆる「アルヴァ・ノト的なサウンド」を確立した直後のこと。池田亮司も2001年に『Matrix』をリリースしそれまでのサウンドを総括し、翌2002年には弦楽器を導入した革新的アルバム『op.』を発表した時期だ。ミカ・ヴァイニオも Ø 名義で2001年にアルヴァ・ノトとの競演盤『Wohltemperiert』を、ソロ名義で2002年にフェネスとの競演盤『Invisible Architecture #2』を、パン・ソニックとしてもバリー・アダムソンとの共作『Motorlab #3』、翌2003年にはメルツバウとの共作『V』もリリースしており、コラボレーションを多く重ねていた。
つまり彼らは、これまでの活動の実績を踏まえ、大きく跳躍しようとしていた時代だったのではないか。逆に言えばそのサウンドの強度/個性はすでに完成の域に至っていた。そう考えると『Live 2002』の充実度も分かってくる。3人の最初の絶頂期において、その音が奇跡のように融合したときの記録なのだ。この種の「スーパーグループ」は単なる顔合わせに終わってしまうか、今ひとつ個性がかみ合わないまま終わってしまう場合が多い。しかし本音源・演奏はそうではない。以前から3人が競作していたようなノイズ/サウンドを発しているのだ。
とはいえ3人揃っての競作・競演はないものの、カールステン・ニコライと池田亮司はCyclo.としてファースト・アルバムを2001年にリリースしていたし、ミカもカールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトと共作『Wohltemperiert』を2001年にリリースしているのだから、すでに充実したコラボレーションは(部分的にとはいえ)実現していた。
ゆえに私はこの『Live 2002』の充実は、才能豊かなアーティストである3人がただ揃っただけという理由ではないと考える。そうではなく2002年という時代、つまりはグリッチ以降の電子音響が、もっとも新しく、先端で、音楽の未来を象徴していた時代だからこそ成しえた融合の奇跡だったのではないか、と。
むろん『Live 2002』を聴いてみると、このパルスは池田亮司か、このノイズはミカ・ヴァイニオか、このリズミックな音はアルヴァ・ノトか、それともCyclo.からの流用だろうか、などと3人のうちの誰かと聴き取れる音も鳴ってはいる(M4、M5、M6、M10など、リズミック/ミニマルなトラックにその傾向がある)。
しかし同時にまったく誰の音か分からないノイズも鳴っており(クリスタル・ドローンなM7、強烈な轟音ノイズにして終曲のM11など)、いわばいくつもの電子音の渦が、署名と匿名のあいだに生成しているのである。それは3人が音を合わせたというより、この時代に鳴らされた「新世代サウンド、ノイズ」ゆえの奇跡だったのではないか。グリッチ電子音響時代の結晶としての『Live 2002』。
90年代中期以降に世界中に現れたグリッチ的な電子音響音楽は、グリッチの活用による衝撃というデジタル・パンクといった側面が強かったが(キム・カスコーン「失敗の美学」)、00年代初頭以降は、それを「手法」として取り込みつつ、電子「音楽」をアップデートさせる意志が強くなってきたように思える。つまり電子音響が、大きくアップデートされつつある時期だったのだ。彼ら3人の音もまたそのような時代の熱量(音はクールだが)の影響を十二分に受けていた。先に描いたようにちょうどこの時期の3人のソロ活動からその変化の兆しを聴きとることもできるのだ。
膨大化するハードディスクを内蔵したラップトップ・コンピューターや独自のマシンによって生成された電子音響/音楽/ノイズは、和声や旋律、周期的なリズムなど「音楽」的な要素を持たなくとも、その多層レイヤー・ノイズやクリッキーに刻まれるリズムによって聴き手の聴覚を拡張し、音楽生成・聴取の方法までも拡張した。90年代以降の電子音響は、21世紀最初の「新しい音楽」であったのだ。
そのもっとも充実した時期の記録が本作『Live 2002』なのである。このアルバムは2017年に亡くなったミカ・ヴァイニオへの追悼盤ともいわれているが、〈ラスター・ノートン〉からの「分裂」(という言い方は正しくはないかもしれない)以降、カールステン・ニコライが主宰する新レーベル〈ノートン〉のファースト・リリースでもある以上、単に過去を振り返るモードでもないだろう。「追悼と未来」のふたつを、21世紀の最初の新しい音響/音楽に託して示しているように思える。
じっさい『Live 2002』を聴いていると、そのノイズ音響は明晰で、強靭で、もはや2018年のエクスペリメンタル・ミュージックにしか思えない瞬間が多々ある。2002年という「00年代電子音響の最初の充実期」において、ミカ・ヴァイニオ、池田亮司、カールステン・ニコライの3人は2018年に直結する刺激と破格のノイズを鳴らしていた。16年の月日を感じさせないほどに刺激的な録音である。
2002年、電子音楽には未来のノイズが鳴っていた。そして2018年、その過去との交錯から今、電子音楽/音響の歴史が、また始まるのだ。