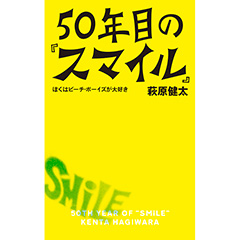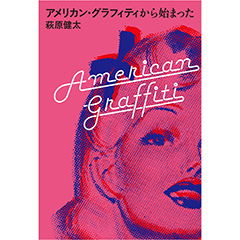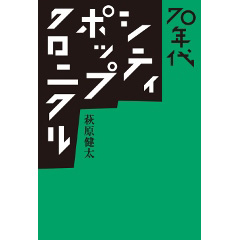MOST READ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 三田 格
- Beyoncé - Renaissance
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場
- Beyoncé - Lemonade
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
Home > News > 70年代シティ・ポップ・クロニクル - ──萩原健太が語る日本のポップ・シーンの濃密な5年
 萩原健太 70年代シティ・ポップ・クロニクル ele-king books |
70年代のシティ・ポップはなぜ古びないのか……いや、それどころか、ここ2〜3年のあいだ、日本の音楽シーンにおいてもっとも人気のあるジャンルとなっている。それが年を追う毎に輝いているのはなぜか?
萩原健太の『70年代シティ・ポップ・クロニクル』は、あまたあるシティ・ポップのなかから、まずは永遠のクラシックと呼びうる最重要作の15枚を選び、時代順に並べ、その15枚から派生する作品を挙げて紹介する(関連ディスクを併せると計100枚のアルバムが紹介されている)。
そして、日本のポップ史上もっとも濃密な5年のあいだにいったい何が起きていたのかを、著者の経験を回想しながら言葉を吟味し、シティ・ポップ・ブームに沸く現代に向けて語る。それは洋楽に多大なる影響を受けながら、しかし、言葉も文化も異なる日本という国でポップ・ミュージックをやることの素晴らしき挑戦の記録でもある。
たとえば、大瀧詠一というアーティストがいる。最近では彼を語るうえで、その情報量の膨大さや分母論ばかりが先行され、ぶっちゃけ、なんだかすごいんだろうけど、よくわからない、というものが目に付く。
また、山下達郎を語る上で、「とにかくすごい」ということになっているが、いったい何がどうすごいことをやってきたのかを明解に語っている文章がどこにあるのだろうか。そう、達郎が「パンク」たる所以とは? そもそも、70年代の日本のポップスにおいて、細野晴臣と大瀧詠一が果たした役割とは何なのか? ユーミンの『ミスリム』がなぜ重要なのか……はっぴいえんどのやったことがなぜ日本語ラップにも繫がるのか……
萩原健太の文章は、そうしたすべての問いに対して明快だ。
名著『はっぴいえんど伝説』の著者が瑞々しい言葉で綴る「僕とシティ・ポップの70年代」。音楽の価値観が揺れている今日だからこそ、読んでいただきたい。健太さんの文章も良い感じで柔らかく、また心地良いです。
彼らは〝場〟を共有していた聞き手たちと微妙な目配せを交わしながら、あの時代ならではの誤解や屈折すら味方につけ、少しずつではあったが、マジカルな名盤をひとつ、またひとつと生み出していったのだった。
ぼくがこれから、つらつらと書き連ねていこうと思っているのは、そんな名盤たちの物語だ。
──萩原健太『70年代シティ・ポップ・クロニクル』
まえがきより
NEWS
- Free Soul──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作
- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート
- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場
- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース
- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート
- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動
- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場
- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加
- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化
- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース
- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売
- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定
- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演
- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演
- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活
- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年
R.I.P.
- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木
- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー
- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー
- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン
- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル
- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート
- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター
- R.I.P. 鮎川誠
- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン
- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏


 DOMMUNE
DOMMUNE