MOST READ
- 別冊ele-king J-PUNK/NEW WAVE-革命の記憶
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ
- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO
- 『90年代ニューヨーク・ダンスフロア』——NYクラブ・カルチャーを駆け抜けた、時代の寵児「クラブ・キッズ」たちの物語が翻訳刊行
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Young Echo - Nexus / Kahn - Kahn EP / Jabu - Move In Circles / You & I (Kahn Remix) | ヤング・エコー
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- KMRU - Kin | カマル
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Jabu - A Soft and Gatherable Star | ジャブー
- LIQUIDROOM 30周年 ──新宿時代の歴史を紐解くアーカイヴ展が開催
Home > Interviews > interview with Yoshinori Sunahara - ミスター・マーヴェリックの帰還
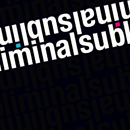 砂原良徳 Subliminal [Limited Edition] Ki/oon |
か、か、か、か、か、か、か、か、と「サブリミナル」は極めて控えめにはじまる。スペイシーな鍵盤の音、ファットなシンセベースが聴こえる。さりげないフィルイン、それからはじまる16ビート......9年ぶりに砂原良徳の新曲を聴く。
砂原良徳は虚構を弄んでいた。亡き"過去"に惑溺し、存在しない"場所"を捏造した。われわれは彼のファンタジーを面白がって、その夢の世界に遊んだ。が、しかし、あるときから彼はそうした楽天主義的な遊びを止めてしまった。2001年に彼が発表した『ラヴビート』は、本人の話を聞いている限りでは、レディオヘッドの『キッドA』やゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラー!の『f#a#∞』、ポーティスヘッドの『サード』やマッシヴ・アタックの『ヘリゴランド』、ゴリラズの『プラスティック・ビーチ』、あるいはコード9&ザ・スペースエイプの『メモリー・オブ・ザ・フューチャー』、こだま和文の『スターズ』、ヘア・スタイリスティックスの『カスタム・コック・コンフューズド・デス』......といった作品と同類ということになる。要するに『ラヴビート』は、時代の暗闇と向き合いながら作られた作品なのだ。
が、しかし、砂原良徳の音楽は、それでもなお、音楽とは快楽であるという論から離れているわけではないように思える。深いメランコリーを有しながら、彼の音楽に逃げ出したくなるような重苦しさはない。実にエレガントで、ときには夢を見てしまいそうなほど甘ったるく、早い話、シリアスだが催眠的なのだ、1970年代に作られたジャマイカのダブがそうであるように。このアンヴィバレンスは彼の音楽の素晴らしい魅力ではないかと思う。
『ラヴビート』から9年ぶりの新作「サブリミナル」もまた、エレクトロニクスのなかに彼の強い気持ち(悲しみ、怒り、慈しみ、優しさ)が込められている。『ラヴビート』のようにメランコリックだ......が、と同時に現実を忘れそうなほどに陶酔的である。
いったい何年ぶりだろうか......本当に久しぶりに砂原"まりん"良徳に会った。
9.11にはじまって、グローバリゼーション、人間がどんどん生きにくい世のなかになっていく......世紀末が終わっても世紀末感はぜんぜん終わらない。そんななかで出すことは悪くはないなと思えてきたことだよね。
■いやー、久しぶり。まりん、ぜんぜん変わらないね。
砂原:そんなことないよ、だいぶ変わったよ。
■しかも9年ぶりじゃないですか。
砂原:アルバムはまだ出ていないからね。
■オリジナル作品としては9年ぶりなんだね。
砂原:そうだね。野田さんの予言通りになったよ。『ラヴビート』を出したときに野田さんが「10年は出さなくてもいいよ」って言ったからね。「ホントにその通りになりました」っていう(笑)。
■ハハハハ。
砂原:「もう10年出さなくてもいい」って言われたとき、「それはありえんだろう」と思ったけど、ホントにそうなっちゃったよ。
■取材で?
砂原:取材が終わってから飲みに行って、そう言ったんだよ。
■オレ、なんて言ったの?
砂原:「当分更新する必要がない」って言ったんだよ。
■そうか......、たしかに『ラヴビート』を聴いたときは感動したからね。本当に素晴らしい音楽だと思ったし......。『テイク・オフ・アンド・ランディング』(1998年)や『ザ・サウンド・オブ・70's』(1998年)のほうがキャッチーなんだけど......。
砂原:ギミックが多すぎるんだよね。
■そう......かもね。『ラヴビート』はテーマ自体は重たい作品だったし。それはともかく、あのさー、なんで9年もかかったの!?
砂原:ハハハハ!
■ホントにもう(笑)。
砂原:スタジオには毎日通っていたんだよね。土日もなく通っていた。
■まりんの〈クリング・クラング・スタジオ〉。
砂原:まあ、そんなもん(笑)。とにかくスタジオに行かない日はないんです。しかも起きてから10分ぐらいで家を出るんですね。で、スタジオで顔洗って歯磨きしたりする。寝たままスタジオに行ってスタジオで起きるって感じなんだけど。
■スタジオはずっと確保しているんだね。
砂原:あるよ。もう10年だね。
■そして毎日スタジオに足を運んでいたと。
砂原:だって何をやるにもスタジオに行かなければならないんだもん。まあたとえば、CMの動画を編集したりとか。
■仕事?
砂原:それは仕事じゃないけどね。趣味、遊びだね。そんなことをずっとやっている。そういうことは作品に影響しているけど。CMなんかは時代の空気みたいなのを反映しているし。CMを観ていると面白いんですよ。
■それだけ聞いていると、道楽的な人生を歩んでいるのね。
砂原:そうかもしれないけどさ。だからってさ、要らないところは要らないのよ。ご飯とかあんまり食べないしさ。コンビニのおにぎりを買ってくるでしょ。それを片手に持ちながら作業していると、いつの間にかおにぎりがカラカラになっている。だから、どんなところにもお金を注ぎ込んでいるような道楽じゃない。好きなことをやっているという意味では道楽的なのかもしれないけど。もちろん、いずれ作品を作るんだという前提でやっているんだけど。
■当然、焦りとかあるわけでしょ。
砂原:ないよ。
■いまは出たからそう言えるよね。
砂原:いやいや、焦りとかないよ。出なかったら出なかったまでだしさ。まあ、そういうつもりはなかったけど。出るだろうなとは思っていたけど。
■コーネリアスだって多作とは言えないけど、自分の音楽を更新しているじゃない。
砂原:そうだね。たしかに更新しているよね。バッファロー・ドーターだって最近更新したよね。
■自分だけおいてきぼりにされるっていう......。
砂原:いやいや(笑)。おいてかれてもいいかなと思っていたし、更新したとしても、中途半端な更新なら意味ないと思うし、やっぱり大きくアップデートしないと出す意味がないよなと思って。いま更新してもマイナーなアップデートにしかならないなと思って。
■それはクラフトワーク主義?
砂原:いや、クラフトワークじゃない。『ラヴビート』のときから新しいジャンルに関する興味がぜんぜんなくなったのね。他人が何をやっているのか気にならなくなった。"新しい"といよりも自分にとって普遍的なもの、モダンなものにウェイトがいった。まわりの人が何をやっているかなんてぜんぜん気にならない。
■だけどやっぱ、職業音楽家としてはさ。
砂原:なんかやらなければならないというのはあるよ。
■でしょ!
砂原:ハハハハ。
■だいたい4年ぶりでも久しぶりだと思うものだよ。9年はないよ。
砂原:いや、だけどさ、逆の考え方もあってさ。レコード会社の人には申し訳ないんだけど、「このゼロ年代をアルバム1枚で乗り切ったのは誰だ!」ってさ。
■ハハハハ!
砂原:そういう考え方もあるんだよ。
■その考え方いいね(笑)。
砂原:いや、野田さんが言ったんだよ、「10年出さなくていい」って!
■ハハハハ。
砂原:唯一、コピー・コントロールCDのあおりを食わなかったんだから。
■あー、それはそうだね。
砂原:コピー・コントロールCDなんか絶対に出しちゃいけない。あのときいろんなアーティストが嫌な思いをしていたのも見ているし、せっかく録音した作品が劣化した商品になっていくって......だいたい万引きするヤツが多いからって......、無銭飲食が多いからレストランの味を落とすって、あり得ないでしょ!
■たしかにね(笑)。
砂原:そんなのレコード会社だけですよ。まあ、言いたいこと言ってますけど(笑)。
■まあ、これは公式のインタヴューだからそういう強気なことを言ってるんだろうけど。
砂原:いや、強気でも弱気でもないんだけど。
■ハハハハ。
砂原:そんなオレの個人的なことなんかよりも、音楽業界というか音楽シーンというか、体力がどんどんなくなってきているなということのほうが頭にあったかな。
■どう思っていた?
砂原:シーンも縮小していったし、経済的にも小さくなっていったし、いままでみたいなやり方では通用しないんだろうなとは思っていますよ。でもね、それが良いことなのか悪いことなのか、それはどっちとも言えない。カルチャーって、無理矢理に保護するものでないと思うし。生活があって、自然に生まれてくるものだと思っているので。だから、「いまこの文化が危ない」とかいって「守ろう」というのも不自然だと思っているんだよね。だから、もし淘汰されたならそれは納得するしかないよねという。
文 : 野田 努(2010年7月21日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE





