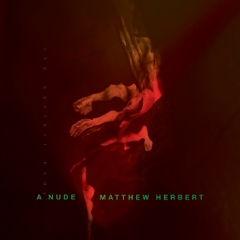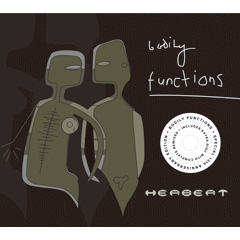MOST READ
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations | テイラー・デュプリー&ジムーン
- Ikonika - SAD | アイコニカ
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎、ニュー・アルバム『ヤッホー』発売決定
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎、先行シングル「あなたの場所はありますか?」のライヴ演奏MV公開!
- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演
- Shintaro Sakamoto ——すでにご存じかと思いますが、大根仁監督による坂本慎太郎のライヴ映像がNetflixにて配信されます
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗
- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー
- Columns 12月のジャズ Jazz in December 2025
- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー
- There are many many alternatives. 道なら腐るほどある 第3回 映画『金子文子と朴烈』が描かなかったこと
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Geese - Getting Killed | ギース
Home > Interviews > interview with Herbert - 音楽は世界を変える
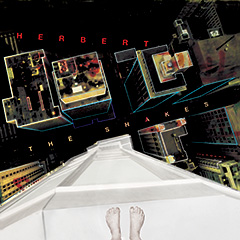 Herbert The Shakes Accidental/ホステス |
音楽で世界は変えられないがひとりひとりの意識は変えられるというのは、いわゆる紋切り型の、いろんな場面で使われる一般論となっている。言葉としては面白くないが、まあ、そんなもんかーと思ったりする。はい、その通り、と言うしかない。
言葉として面白くないのは、シニカルなのか、あるいは未来への期待、音楽への夢を込めたものなのかどうなのか、本気で世界を変えたいと思っているのかどうかが実にアブストラクトな点にあるからだろう(まあ、そのすべてを包含しているのだろうけれど)。ひとつ言えるのは、そして誰も音楽は世界を変えるとは言わなくなったことだ。マシュー・ハーバートを除いては。
ハーバートはUKのハウス/テクノのプロデューサーで、90年代半ばにデビューしている。彼のミニマルで軽快なテック・ハウスは、まだ彼が何者かよくわかっていない最初から人気だった。ポップで、実験的。DJもかけたし、家聴きの人にも誰からも愛されるダンス・トラックだった。
早すぎた初来日時のライヴも楽しかった。鍋やらフライパンやら料理道具をその場で鳴らし、サンプリングし、そしてその場でループさせて曲を作ってくという無邪気なもので、まさかこの人がその数年後、鬼のような左翼ヴィジョンを展開することになるとは、当時はまったく思いも寄らなかった。ただの愉快な人だと思っていた。
欧米のミュージシャンは、思い切り商業的なフォーマットに合わせてデビューして、作品数を重ねる毎に、より非商業的でより実験的な道に進みたがると言われるが(日本はその逆とも)、ハーバートはまさにその通りの歩みを見せているひとりである。
2001年、ライヴ会場で無料配布されたレディオ・ボーイ名義の『The Mechanics Of Destruction』の曲名にはマクドナルドやGAPなどグローバル企業の名前、もしくは実業家、TVや石油など資本主義を象徴するものが付けられている。音はすべてそれら商品の音などから来ている。それがいったい何のためになるのかわからないが、彼はとにかくそれをやり、同じように2003年のビッグ・バンドによる『Goodbye Swingtime』でも、はっきりと彼の政治的な意見を挟み込んだ。(このビッグ・バンドによるライヴも最高に笑えるものだった。たとえば曲のブレイクで演奏者全員がポケットから新聞を出しては破り、そしてまた素知らぬ顔でジャズを演奏しはじめるなど、彼の批評精神は、ほとんどの場合、喜劇的に表出する)
その後も食事文化の側から多国籍企業を批判した『プラット・ドゥ・ジュール』、豚の一生を描いた『ワン・ピッグ』などなど、執拗なまでにグローバリゼーション批判を続けている。たまたまこの1枚は政治的になったけれど、その次はいつものようにハッピーに……なんてことはこの男に限って言えばない。ただ、先述したように、彼の音楽にはコメディタッチがあるので、説教臭くなることはない。要するに、リスナーを硬直化させることがない。『ワン・ピッグ』のときのライヴも面白かったしね。
ハーバートの作曲の方法論として一貫してあるのは、ミュジーク・コンクレートだ。その手法を意識してハウス・ミュージックに活かしたのがまさにハーバートで、『アラウンド・ザ・ハウス』(1998年)と『ボディリー・ファンクションズ』(2001年)は彼のユニークな音作りがもっともポップに展開されたものとして記憶されている。前者はハウス、後者はジャズの響きを打ち出した、より振り幅の広いエレクトロニック・サウンド。どちらもいまだハーバートの代表作として聴かれ続けているが、新作の『ザ・シェイクス』は、洗練された『ボディリー・ファンクションズ』に近い。つまり、ハイブローとはいえ大衆音楽であり、入りやすいのだ。もちろん、そこには以下の取材で語られているような彼の考え方が、確固たる思いがある。そんなわけでぼくは彼の頑なさ,ブレのなさ、その理想に、あらためて触発されたのである。
それでも音楽に世のなかを変える力があるとまだ100%信じているからだよ。でなければ音楽をやめて政治家になっている。「どうして政治家にならないのか」と訊かれることも多い。なぜかというと、政治家は大勢いるけど、政治的なメッセージを訴えるミュージシャンはあまりいない。だから責任を感じるんだ。
■最近の『ガーディアン』に掲載されたあなたの発言のなかの「music’s propensity to noodle inconclusively can seem unhelpful at best(不平等が前例のないほど極端になり、我々が作り出したシステムが育むのではなく破壊するためにあるとき、最善の状況でも音楽は最終的には助けにならないように思える)」という言葉が気になっています。ここにはある種の絶望が込められているのでしょうか?
ハーバート:おそらく絶望ではなく、世のなかを変えたいという欲求を音楽が失ったしまったことへの失望と、いまの多くの音楽、とりわけダンス・ミュージックが退屈に感じることのふたつが込められている。散々ダンス・ミュージックは聴いてきたから、どれも同じようにしか聴こえないんだよ。初めてダンス・ミュージックと出会った人にとっては退屈でないかもしれないけど、30年以上ハウスやテクノを聴いてきた身としては、新しいアイディアや驚きのなさを退屈に感じてしまう。だからあの発言の裏には失望と退屈のふたつが込められているんだと思うな。
■あなたが言うように、現在の行きすぎた資本主義社会で、音楽が政治的な局面において「unhelpful(助けにならない)」であったとしても、あなたは音楽を続け、そこに政治的な主張、左翼的なヴィジョンを織り込み続けるわけですよね?
ハーバート:ああ。
■それはあなたにとってアンビヴァレンツな行為なのでしょうか?
ハーバート:それでも音楽に世のなかを変える力があるとまだ100%信じているからだよ。でなければ音楽をやめて政治家になっている。「どうして政治家にならないのか」と訊かれることも多い。なぜかというと、政治家は大勢いるけど、政治的なメッセージを訴えるミュージシャンはあまりいない。だから責任を感じるんだ。何か社会や政治的な問題について強く感じているものがあったら、それを音楽を通して表現する責任があると感じているんだよ。
ぼくは音楽に物事を変える力があると確信している。実際それをこの目で見てきた。16歳のときにNWAの“Fuck The Police”を聴いたのをいまでも覚えている。「なんで警察をやっつけたいんだ?」って思ったんだ。当時僕は小さな村に住んでいて、その村の警察官が家の向かいに住んでいて、たまに彼が訪ねてきて、紅茶を一杯飲んでいくんだ。彼が友だちだったとは言わないけど、いわゆるご近所さんで、親しみやすい人で優しそうな人だった。だから「なんで彼をやっつけたいなんて思うんだ?」と僕は思った。でもあの曲を通して、アメリカに住む黒人の若者たちの現状がわかった。それまで全く縁のない世界だった。彼らのことをBBCや新聞がわざわざ取り上げるわけじゃない。彼らの声を聞かせるメディアがなかった。音楽を通して知ることができたんだ。そういう力が音楽にはまだあると思っている。
■年々、状況は悪くなっているという感覚があるのですね?
ハーバート:はははは。そうだね。世界の現状に強い失望、憤慨、不信感を抱いている。たとえば女性の権利が自国も含めて世界のいろいろな国で後退していると感じる。宗教と人種の隔たりがさらに広がっている地域もある。世界の多くの地域で状況は悪くなっていると感じる。
もちろん良くなっている場所もあるけど、例えば二酸化炭素の排出量だけを見てみても、1990年に確か京都議定書が締結されたわけだけど、それ以降61%排出量が増えているんだ。我々は狂っているよ。減らすどころか、悪化の一途を辿っている。肉の消費量は増え、遠くへ移動する人も増え、消費も増え、世界は完全に間違った方向に進んでいる。状況は確実に悪くなっている。
■たとえば、“strong”、“battle”とったシンプルで、暗喩的な言葉の曲名を用いて、資本主義の、とくにマッチョなところへの批評性を含んでいると受け止めてよろしいでしょうか?
ハーバート:僕がなぜ音楽を作るかというと……、そもそも自分が満たされて幸せだったら何か作る必要はないよね。僕にとって創造することはすなわち、世のなかで何かが間違っていると思うことだったり、何かを変えたい、解決したいという思いだったり、変化をもたらすきっかけになりたいという思いから生まれるんだ。僕にとって創造することはふたつのことを象徴している。この世のなかがきっと良くなると信じる楽観性と「こうあるべきだ」という世界に対する不満だ。その楽観と不満のふたつの組み合わせが僕を創造へと掻き立てるんだね。
■あなたの音楽では、資本主義への批判は一貫しています。『The Mechanics Of Destruction 』や『Goodbye Swingtime』以降、ずっとあるものです。『The Shakes』は、政治的批評性という観点において、これまでの作品とどこが違うのでしょうか? あるいは同じようなことを、あなたは意識して言い続けているのでしょうか?
ハーバート:僕が伝えようとしていることは一貫していて、それは根本的不公正だ。僕が解せないのは、経済危機はリスクをいとわない経済界の行き過ぎた行為によって巻き起こされたにも関わらず、その尻拭いを庶民がしている。貧しい人たち、社会の弱者である障害者や老人、失業者がその代償を払っている。まるで手品だ。最悪の手品だ。僕はそういう不公正が一貫したテーマになっている。
僕は恵まれた生活ができている。その恩恵には責任がついてくると思っている。その責任のひとつが、その恩恵を疑問視し、それが何によってもたらされているのか理解することだ。例えば自分が日常使っているものを中国の工場で製造してくれている労働者に感謝をしなければいけない。あるいは僕の携帯の部品のためにアフリカで採掘作業を行っている人たちかもしれない。そういう人たちの存在をきちんと把握し、自分の生活が当たり前のものだと思わない責任があると思っている。
■サンプリング・ソースについて、あなたはつねにこだわりを持っていますが、今作の「音」も、それぞれに意味があるんだと思います。しかし、それはあなたの説明を得るまでは、リスナーにはわかりえないことだと思います。それでもあなたは音のソースにこだわるのは、音を資本主義から遠ざけることがいかに重要なのかという話だと思いますが、今作における音のソースについて説明お願いします。
ハーバート:僕としては、なんとなくポンペイをイメージしたんだ。ポンペイには実際行ったことがないんだけど、ポンペイに対する僕のイメージは「時間が止った場所」だ。ある時点から全てが止ったまま、という。僕のとってこのアルバムは自分のスタジオあるいは生活がある時点で止った状態なんだ。つまり、自分の身の回りにあるものだけを使って音を作っている。
例えばゴミ箱や、子供の学校鞄。2014年夏のある一瞬を切り取ったものにしたかった。他のサウンドももちろん取り入れている。“Safty”では、イラクやイスラエルで実際に録られた銃弾や爆弾の音をebayで手に入れて使っている。あの曲は非常に具体的な物語を伝えている。でも他の曲は、身の回りにある無駄なものや消耗品を使っている。例えば食べ物の包装や洋服や家具とか。昨年僕のスタジオと家にあったもののカタログみたいさ。
質問:野田努(2015年6月10日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー
- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー
- interview with caroline - いま、これほどロマンティックに聞こえる音楽はほかにない ——キャロライン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE