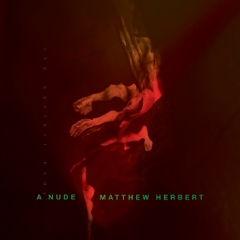MOST READ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
- Fumitake Tamura ──「微塵な音」を集めたアルバム『Mijin』を〈Leaving Records〉より発表
- Stones Taro ──京都のプロデューサーが新作EP『Foglore#1』をリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Visible Cloaks ──ヴィジブル・クロークスがニュー・アルバムをリリース
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- interview with Toru Hashimoto 30周年を迎えたFree Soulシリーズの「ベスト・オブ・ベスト」 | 橋本徹、インタヴュー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Quadeca - Vanisher, Horizon Scraper | クアデカ
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- キングギドラ ──『空からの力:30周年記念エディション』のインスト・ヴァージョンと96年作EP『影』がアナログ盤で同時リリース
- Street Kingdom 日本のパンク・シーンの胎動期を描いた、原作・地引雄一/監督・田口トモロヲ/脚本・宮藤官九郎の『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』が来年3月公開決定
- R.I.P. Tadashi Yabe 追悼:矢部直
- Father John Misty - I Love You, Honeybear | ファーザー・ジョン・ミスティ、J・ティルマン、フリート・フォクシーズ
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
Home > Interviews > interview with Herbert - 音楽は世界を変える
僕が解せないのは、経済危機はリスクをいとわない経済界の行き過ぎた行為によって巻き起こされたにも関わらず、その尻拭いを庶民がしていること。貧しい人たち、社会の弱者である障害者や老人、失業者がその代償を払っている。まるで手品だ。最悪のね。
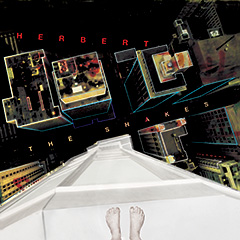 Herbert The Shakes Accidental/ホステス |
■今回はヴォーカリストを起用して、細部において実験的ではありますが、いろんなタイプのポップ・ソングをやっていると言えると思います。たとえば、“stop”で歌われている主語の「僕」は資本主義の奴隷となった「僕」だと思うのですが、これをディスコ調の曲の「ドント・ストップ」というクリシェに結びつけたり、曲調と言葉がコンセプチュアルに結びついていますよね。それは今回のアルバムのコンセプトとどのような関係にあるのでしょうか? それは、『Goodbye Swingtime』のように、政治的であることと同時に娯楽を意識したということとも違うアプローチですよね。より、メタフィジカルにアプローチしているように思いました。
ハーバート:このアルバムはよりエモーショナルな作品だから、例えば“stop”といった曲なんかは、よりパーソナルな視点から見た「誘惑」が枠組みとしてある。我々は常に誘惑に囲まれて生活している。店に入っても、そう。日本ではどうかわからないけど、こっちではちょっとした店に入るとまず目につくところに山のようにチョコレートが並べてある。身体に悪いものを買わせようといちばん目の着くところに置いてある。
広告も至るところにある。最新型の車や魅力的な旅行先といった広告がね。こういった資本主義的構造のなかで我々は常時誘惑に曝されている。ものを買うように、と。我々が消費しなければ経済は成長しないからって。現行の政治体制ではそれが唯一の経済対策だから。消費者に消費を促すだけ。
で、僕からすると、それに対する責任は僕たちの肩に乗っかってくる。チョコレートにしても車にしても「要らない」と言えばいいんだ。ドラッグに対しても、あと一杯のワインに対しても「要らない」と言えばんだ。この曲に限らず今作はそういう政治的な考え、政治的枠組みをより個人の立場で捉えている。
■アンビエント調のトラックの、古めかしいバラード、“bed”は不思議な曲ですよね。この曲で歌われているのは、それこそあなたの失意のようなものですよね? いままで以上に、あなたの感傷的な、エモーションが表現されているようにも思うのですが、いかがでしょう?
ハーバート:たしかに今回はすごエモーショナルな作品だと思う。この前の一連の作品はドキュメンタリーの要素が強かった。特定の状況だったり、事実を物語に構築して伝えようとしていた。でも今回は、同じようなテーマを、感情の面から伝えたかった。ある事象に対する感情的な反応を表現している。腐敗した政権がこの国を治めていることや、大企業が力を持ち過ぎていることやこの国で税金を免除されていることだったり、いまの社会の仕組みを変えない限り地球の破滅に繫がることだったり。扱っているテーマやインスピレーションはこれまでと変わらない。ただ、ただより感情的な表現をしている、という。
■日本では左翼的なものは弱体化していると言われているのですが、UKはいかがでしょう? あなたから見てUKの左翼的な動きは、この時代において、どのような状態にあるとと思われますか?
ハーバート:可能性としては良くなる見通しだ。明後日に選挙が行われるんだけど、政党を跨がって左翼政治家達が新たに連立を組む可能性がある。それはいいことだと思う(※取材は選挙前にやった、実際の選挙ではご存じのように保守党が勝利)。
ただ問題は、この国に住んでいない億万長者がメディアを支配していることで、彼らは商売に有利なように政治を影で動かしている。情報操作が蔓延っている。非常に憂鬱な状況だ。他にも問題はあって、それは「究極の中道主義」と呼べる考えだ。つまり緊縮財政を受け入れ、進歩的な政策を受け入れ、成長は必要だ言い、合理的に考えるべきだと言う。でもそうではない。我々にいま必要なのはまったく新しい社会構造であり、現状からの打破であり、革命が必要なんだ。遠慮がちで柔な代替案ではなく、変化を本当に生む為には強く自信に満ちた代替案が必要なんだ。
■総選挙を前に、スコットランドのSNPが大躍進をしているそうですね。この事態をあなたはどう見ていますか?
ハーバート:非常に難しい問題で、スコットランドにとってはイギリスから独立することが正解だと思うんだけど、イギリス人としてはスコットランドが脱けてしまったら大惨事だ。イギリス人であることを放棄したいくらいだ。僕は隣人よりもイラクにいる人のほうがよほど共感できる。いまの隣人は右翼政党の議員なんだ。そんな隣人よりもブラジルの工場で働いている労働者のほうがよほど気が合うと思っている。国を細かく区切っていくという発想は理解できない。人びとがもっと混ざり合ってしかるべきだと思う。国境なんてそもそも後でとってつけたようなものなんだから。
■“safety”は、あなたのダンス・カルチャーへの期待が感じられる曲だと思いました。階級のないナイトクラブ文化、ハウス・ミュージック、暗に公共圏を主張するレイヴ・カルチャーを政治的抗議運動へと発展させるためには、これまで何が足りていないのでしょうか?
ハーバート:新しいヴィジョンを明確に述べる牽引者がいないんだと思う。例えばクラブに行っても音楽を止めて演説をする人を見たことがないようね。それに「木曜日に選挙があるから絶対に投票に行くように」と促す人もいない。「同性愛者だろうと、白人だろうと黒人だろうと関係ない、それよりも重要なことがある。だからこの人に投票べきだ」ということを語る人がクラブに行ってもいない。ダンス・ミュージックとクラブ・カルチャーの問題は絶え間なく続くことで、音楽が止むことがほとんどない。
僕たちがやらなければいけないことは、行間を読むことなんだ。政治というのはまさに行間で何が行われるかが鍵なんだ。政治家が語る言葉ではなく、その言葉と言葉の行間に本質が隠されている。僕からするとダンス・ミュージックはそういう行間を読むのがあまり得意ではないと感じる。
■“silence”は、いま失われているものとして描かれています。敢えてそれを“silence”はという言葉にしているのは、リスナーに考えて欲しいからですよね?
ハーバート:リスナーは言われなくても考えていると思うし、自分のリスナーの実体も僕にはわからない。誰に向かって音楽を作っているのかって考えはじめたらきりがない。リスナーというひとつの塊があるわけじゃない。なかには取材をしたジャーナリストがいるかもしれないし、自分の祖父かもしれないし、音楽アカデミーの学識者かもしれないし、政治記者かもしれない。その中の誰に向けて音楽を作っているのか、正解なんてないんだ。だからリスナーに何かを求めることは敢えてしたくないんだ。
■これだけ政治的なあなたが、しかし単純なプロテストを好まないのは、なぜでしょうか?
ハーバート:ハハハハ。好まないわけじゃないよ。ただ、同じ問題でも解決策はいくつもなきゃいけないと思っている。問題があまりにも大きい分、解決法もたくさんなければいけない。
■ちなみに、AnonymousとSleaford Modsとでは、あなたはAnonymousのほうに共感するのでしょうか?
ハーバート:はははは。なるほど(笑)。Sleaford Modsついてそこまで知識があるわけじゃないから、これには答えるのが難しい。
■今作においても、曲順は重要ですが、“warm”〜“peak”という流れは、あなたなりに楽天的なエンディングなのでしょうか?
ハーバート:“warm”はすごく切羽詰まっていると思う。「世界が変わり果ててしまったため、君を守りたいんだけど、その術がない」と訴えている。すごく悲しいよね。“Peak”のほうは楽天的かもしれない。いまはSNSがあって、大企業に依存することなく、自分たちなりの生き方ができる。自分たちの想像力を使っていまある問題を解決するのも自分たち次第だ。
僕も根は楽天的な人間だ。世界がどうしようもない状況だっていうのはわかっている。そんななかで、さっきも言ったように音楽を作るという行為は楽天的な思いから来ている。だから楽天的なエンディングにするのは大事だった。とくにこれまでの2作はすごくダークな内容だったから。良い方向に物事を変えていけるだろうという確信を今回最後に持ってくることが大事だった。
■4年前にUKで起きた暴動に関してはいろいろな意見がありますが、あなたはあの暴動をどのように解釈しているのでしょうか?
ハーバート:あの暴動がUK全体に与えた影響はさほど大きいものではなかったものの、暴動に参加した人たちやそのコミュニティーにとっては大きな出来事だった。彼らは経済的に貧しく、社会のなかで蔑ろにされてきた人たちだ。コミュニティーは昔からドラッグで溢れ、選挙法の制約で選挙権も剥奪されている。家賃の高騰で家を追い出されたり、酷い労働条件の仕事を課せられている。政府の対応は酷いものだった。ペットボトルの水を盗んだだけで投獄される人もいた。
その一方で、経済を破綻させた張本人は銀行家たちは何のお咎めもなした。何百万ポンドも盗んでおいてだ。政府からも、年金生活者からも、庶民からも。社会の底辺にいる人たちが立ち上がったときの政府の対応を見ると、そういう社会の仕組みに蔓延る偽善が浮き彫りにされる。暴動に参加した全員が善人だとは言わない。けれども、根深いフラストレーションから起きたことはたしかで、彼らが抱える問題への軽視が生んだものだと思う。
■最後に、あなたがいま読むべきだと思う本は?
ハーバート:ナオミ・クラインの『This Changes Everything(これは全てを変える:資本主義Vs気候)』という本があって、これはいま非常に重要な本だと思う。資本主義と環境問題をひとつの大きな問題として捉えていて、資本主義こそが環境破壊の根本的原因だと指摘している。どちらかの問題を解決することは、もう片方の問題の解決にも繫がると。これは非常に重要な本だ。
もう一冊は音楽本で、『In Search of a Concrete Music(具体音楽の探求について)』というピエール・シェフェールの本で、最近また再版された。サウンドと音楽に関する非常に面白い本だよ。
質問:野田努(2015年6月10日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE