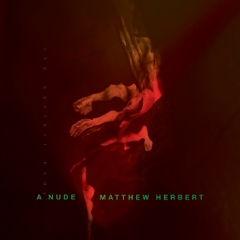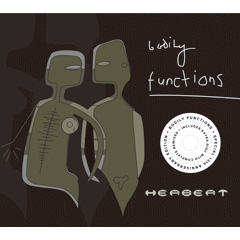MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Reviews > Album Reviews > Matthew Herbert- One
マイク・インクを聴いたことがきっかけでハウスをつくりはじめ、それによって頭角を現したハーバートは、それ以前にドクター・ロキットやウィッシュ・マウンテンの名義でイージー・リスニングからミュージック・コンクレートの応用まで手を広げ、いわば「なにがやりたいのかよくわからないプロデューサー」の代表格だった。ハード・ミニマルやドラムンベースがフロアを最高潮に持ち上げた後で、いまから思えば次にどっちへ行こうかとシーン全体が模索期に入っていたような時期だったから、どんなつまらないこともネクストにつながる何かに感じられ、ハーバートの試みも、そのひとつひとつがそれなりに意味を持っているように感じられたということもあるだろう。ミステリアスでありながら、彼の存在はなぜか信頼できるような気がし、もしかすると必要以上に評価しながら聴いていたような気がしないでもない。「レディ・トゥ・ロキットEP」(95)、「D・フォー・ドクター」(96)、「レイディオ」(96)、「フーシュ」(97)、「ヴィデオ」(97)......いまから思えばヘンな感じである。聴き返したいような、それもまたコワいような。
ハウスやテクノへの没入が一段落して『ボディリー・ファンクションズ』(01)をリリースした辺りから、ハーバートは匿名性が支配するDJカルチャーの住人であることに距離を取りはじめ、それまで福袋のように差し出されていた彼のたたずまいから明確に作家性というものが立ち上がっていく。それと同時にジャズが表現のセンターコートへと躍り出、ビッグ・バンドへの視座やラテンへの目配せなど、まるで菊地成孔とともに時代を併走しているかのようなタイプへと様変わりしていく。90年代を昇華したハーバートと、それを否定した菊地には、もちろん、ハイブリッド感や音楽に持たせる意味がまったく違っていたようだけれど。
「型」をどう演じるか。何度も書いてきたように、これが00年代の課題だった。ハーバートにとってのジャズは、それを狂言回しのように扱っているという印象を与えることでエレクトロクラシュやポスト・クラシックとも一脈で通じるものがあった。裏側に回ればいろいろと小細工は労しているものの、表面的な音のタッチはあくまでもオーソドックスに徹し、実際、ハーバートのそれは「洗練」された商品としての風格を兼ね備えるようになった。『ミュージック・オブ・サウンド』や『レッツオールメイクミステイクス』は遥かに遠い。そして、ビッグ・バンドなど作品を経てリリースされた『ワン』では、ついに、70's風味のなんら変哲のないポップ・サウンドへと歩を進めてしまった。これまでのソロ作に少しは影を落としていたハウスのフォーマットは霧消し、特別な世界でもなければ日常に埋没するでもない「ポップ・サウンド」そのものへと。
曲名はすべて地名になっている。マンチェスター、ミラノ、ライプチッヒ、シンガポール、ダブリン、パーム・スプリング......本人に訊けば、きっと回りくどいコンセプトが饒舌に語られることだろう(そういうところも菊地成孔と寸分違わない)。『ワン』というのはリチャード・バックのような集合無意識のことをいっているのだろうか。それとも単に『ツー』が続くのだろうか。国名ではなく、都市名になっているところはツアー先を意味するのだろうか。どの曲も適度に感傷的で、この世界はそのような気分の積み重ねでできているといわんばかりである。地味なアルバルだけど、その意志は強く、聴く度に存在感を増し、そして、とても落ち着く。そう、ハーバートは相変わらず「なにがやりたいのかよくわからないプロデューサー」の代表格である。こんな作品になるとはまったく予想できなかった。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE