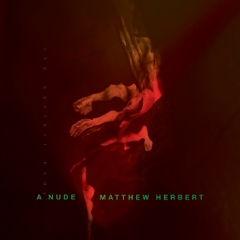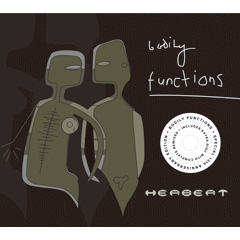MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Live Reviews > Mathew Herbert
ステージの上の数本のマイクには白衣がかかっている。メンバーはステージに登場すると、白衣を着る。中央には四角に張られた数本の赤いストリングスがあって、それをひっぱるとPCから豚の声やらなにやらが聞こえる仕掛けになっている。ステージには豚小屋の藁がおいてある。演奏曲はアルバム『ワン・ピッグ』通りにの曲順で、つまり......なんとも言えない神秘的な力を持った曲""August 2009"、豚の誕生を描いたこの曲からはじまった。

ステージの中央では張り巡らされた赤いストリングスを操作しながら、パントマイムのように演技している男が、時間の経過を知らせるために背中に月の名前(「SEP」「OCT」「NOV」......)が記された白衣を着替えていく。"September"は、豚の成長を表すかのように荒々しい息吹を持った曲で、男の動きも激しくなる。こうしたステージ上での演劇性は、グラム・ロック/ニューウェイヴの時代にはよく見られたものだが、プライマル・スクリームのナルシスティックなライヴや「私のソウル」を主張することが主流となったステージからは排除されていたものである。英国人らしい黒い笑いをもったモンティ・パイソン的な演劇性で曲を展開する『ワン・ピッグ』ライヴは、ライヴの質の変化を象徴するという点でも興味深いものだった。

"December"は豚が親元を離れ、そして兄弟たちと小屋で過ごすようになってからの曲だ。この頃には、ステージ後方に用意されたキッチンでシェフが料理をはじめている。豚肉をジュージューと焼く匂いは扇風機によってフロアへと飛ばされる。生まれて初めて見る、豚肉の匂いの漂うライヴだ。豚肉の匂いのなか、豚の鳴き声、電子音、ドラミングが激しく響く。......それからビートは冷酷にも高まっていく。不気味な高まり、ミニマルなビート......おそらく豚が殺されているのだろう。この残忍なアップテンポの曲のとき、フロアから奇声が発せられていることに違和感を感じていたのは、すぐ近くで聴いていた三田格だった。
シェフはそのあいだもたんたんと料理を進めて、器用な手つきで皿に豚肉料理を盛りはじめる。もうこうなると、最後にその料理をメンバーが食べるかどうかが興味の対象となってくる。キッチンの真横に用意された横長のテーブルには5皿の料理が綺麗に並べられる。演奏を終えたメンバーはテーブルに並び、そのお皿に視線を送る。さあ食べろ。食べたい......三田格が後方で「食べろー」と叫んでいる......。

しかし彼らは食べなかった。マシュー・ハーバートは最後に豚の思い出を歌った。アルバムの最後の曲、"May 2011"である。
ルイス・ブニュエルの映画だったら、最後にくちゃくちゃと音を立てて食べていたかもしれない。その音をサンプリングしてミニマル・テクノを演奏しただろう。マシュー・ハーバートはしかし食べなかった。そこには彼のメッセージが込められていると思っていいはずである。アンコールではマシュー・ハーバートが道化た演技と赤いストリングスを使って、彼のエレクトロニック・ミュージックを演奏し、それまで頑ななまでに笑顔のなかったパフォーマンスにおける唯一の笑顔をもってライヴは終了した。

追記:それにしても残念だったのは、その晩、リキッドルームのすぐ近くのDOMMUNEでは、シカゴ・ハウス/ディープ・ハウスにおけるもっとも重要なDJ/プロデューサー、シェ・ダミエがプレイするというのに、ハーバートのライヴからは誰も人が流れてこなかったことである(しかも7年ぶり2度目の来日)。
文:野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE