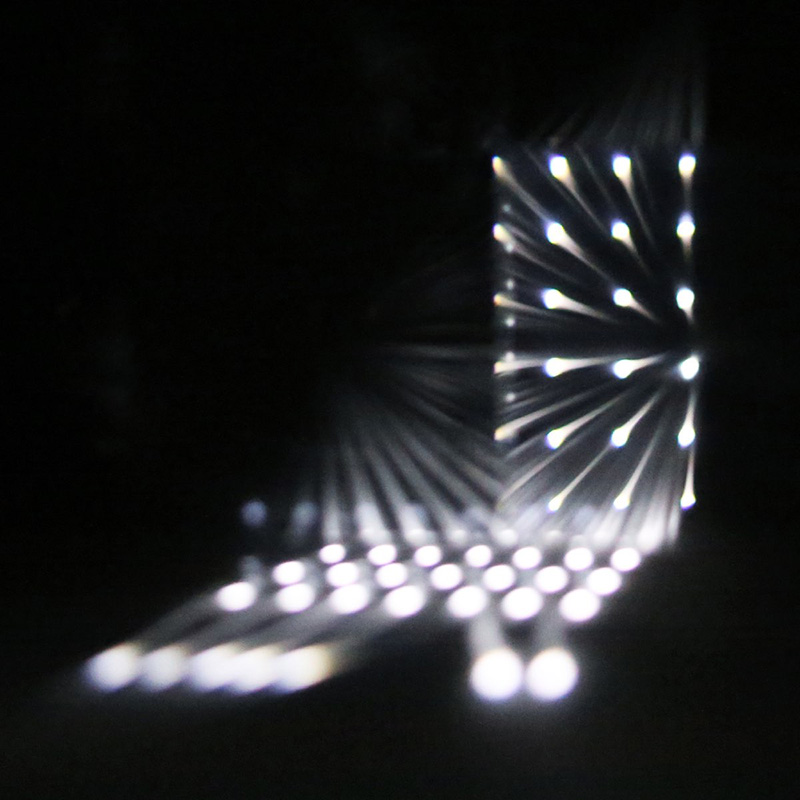MOST READ
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- xiexie - zzz | シエシエ
- Columns 2月のジャズ Jazz in February 2026
- heykazmaの融解日記 Vol.4:如月⊹₊⋆ “15” EPリリースしたよ๋ ࣭ ⭑
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her | アマンダ・ホワイティング
- DJRUM - SUSTAIN-RELEASE x PACIFIC MODE - 2026年2月7日@WOMB
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Geese - Getting Killed | ギース
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
- PRIMAL ──1st『眠る男』と2nd『Proletariat』が初アナログ化
Home > Interviews > interview with Shuhei Kato (SADFRANK) - これで伝わらなかったら嘘
ボサノヴァって当時のことを考えると、めっちゃパンクじゃないですか?
■先ほどドラマーが好きだとおっしゃっていましたが、どんなドラマーが好きなんですか?
加藤:2018年頃にユセフ・デイズにハマって、ゴスペル・チョップス系のドラマーをインスタとかで超見ていたんです。ジャズ・ドラマーじゃなくても「スネアがめっちゃいい感じにポケットに入ってくる」みたいな人とか、無名でもいいドラマーがいっぱいいるんですよ。それを「この感じさ〜」とか言って、NOT WONKのメンバーに聴かせて曲を作ることもしていました。
■SADFRANKには、ユセフ・デイズがやっていたユセフ・カマールのフィーリングを感じました。
加藤:あ〜。ジャズをダンス・ミュージックとして捉えたときの揺らぎ、みたいな……。シャッフル(・ビート)って、そもそも揺らぎじゃないですか。それを、キックを4つにしたり硬くドラムを叩いて人間味を殺したり、そのバランスをうまいことやれる人が好きで。ユセフ・デイズも「最初からサンプリングされたドラム」みたいな感じで叩ける人ですし、そういうフィールがある人が好きですね。ハイエイタス・カイヨーテのドラマー(ペリン・モス)も好きで、ソロ作もいいですよね。
■もうひとつ音楽的な面では、『gel』ではストリングスが重要な役割を果たしていますよね。
加藤:ストリングスは、けっこう必然性を感じましたね。(エルヴィス・)コステロがもともとめちゃくちゃ好きで、バート・バカラックと一緒に作ったアルバム(『Painted from Memory』)がすごく好きなんです。ファースト・アルバムから考えたら、彼って信じられないような音楽的な変遷をたどっていますよね。たとえば、ポール・ウェラーがスタイル・カウンシルをやったのもいい例だと思うんですけど。でも、日本の音楽で考えると、売れたロック・バンドのヴォーカルのやつがソロ活動をはじめたら大層なストリングス・アレンジが入っていて台無しになっている、みたいな歴史ってあるじゃないですか。ストリングスってそういう感じでしか使われてこなくて、しかもクラシックの人がJポップを大味に捉えたものが多いので、よかった試しがあんまりないなと思って。でも、コステロとバカラックのアルバムではすごくうまいことやっていて、ちゃんとかっこよくなっているよなって。それで、自分もトライしてみたくなったんです。
■なるほど。
加藤:“I Warned You” は、わりと最初のほうに作っていた曲ですね。くるりの岸田さんが「NOT WONK、いいね」と言ってくれて、ライヴに招待してくださったことがあって、札幌のライヴを見に行ったあと、音博(京都音楽博覧会)にも遊びに行って、打ち上げの席で岸田さんとふたりで話す機会があったんですよ。それで「SADFRANKっていうのをはじめるんです」と話したら、「ストリングスのアレンジ、俺やるで!」と言ってくださったので、「じゃあ、お願いします!」と頼んだんです。アレンジメントをする人と作曲者が分かれているっていうのはやってみたかったことでもあったので、このアルバムはわりとストリングスありきで最初からイメージしていました。

ロック・バンドをやっていたやつが急にソロをはじめたと思ったら、バンドではやっていなかった私的なことや優しい音楽に手を出したり、ちょっと色気を出してみたり──そういうのは、いままで繰り返されてきた失敗の歴史だろって僕は感じていて。絶対にそういうことをやりたくなかった。
■徳澤青弦さんのカルテットによる演奏もあって、Jポップ的なベタッとしたストリングスとはちがうスリリングで豊穣なものになっていますね。
加藤:そうですね。“Quai” は悠真くんのストリングス・アレンジで、“per se” は基本的に僕がアレンジしました。“per se” のストリングスはNABOWAの山本(啓)さんが入れてくださったんですけど、遠隔で録音していて「思いついたから入れてみたよ」と弾いてくださったのがすごくよかったから、そのまま使っているパートもあります。弦が入っているとはいえ、3曲ともアレンジした人はちがうんですよね。
■一方で “最後” にはフィールド・レコーディングやオブジェクト音、ノイズが入っていて、それがかなりおもしろいです。これは、yoneyuさんが入れたものなのでしょうか?
加藤:基本的には僕が全部やっていて、エディットも僕がやっています。yoneyuは札幌のDJなんですけど、ほとんどすべてのアレンジが終わった段階でyoneyuに聴かせて、「この2ミックスに対して、yoneyuのプレイを録ってみて」と投げて、戻してもらったのを僕が再エディットしました。
■非楽音を入れる発想は、どこから出てきたんですか?
加藤:“最後” は、曲自体はけっこう前からあって、弾き語りでやったりしていたんですけど、レコーディング自体は制作の終盤にやったんですね。だんだんPro Toolsで普通に録ることに飽きてきて、「せっかくみんなで集まっているのに、デモどおりに演奏するのっておもしろくねえな」と思って。それで一発録りすることにして、歌も演奏も「せーの」で録ったテイクを使ったんです。音楽を作るうえで絶対的なパワーを持っている権威的なもの──小節とかグリッドとかトニックとかキーとか、そういうものから離れたい気持ちがあったんですね。だから、自然とメロディがついてない音が入ってきたり、メロディがついているものとついていないものを並列に扱ったり、そのこと自体が自分にとってわりと大事でした。
自分が何かを受け取ったときの気持ちを再現するためには、必ずしもそれとまったく同じものを作る必要がないと思っているんです。何かを再現することと、何かを写実的に綺麗にデッサンするっていうことは、まったくちがうことだと思っているので。
■では今回、ギタリストとしてはどうでしたか? プレイや音色は、ピューマ・ブルーのトーンに近いものを感じました。
加藤:ジャズについてはもう門外漢どころの話じゃないくらい何もわからないし、あまりにも「ジャズ、ジャズ」って言われるのも嫌だな、みたいな感じもありつつ。ただ、録音物としてのロック・バンドの音源があんまりおもしろく感じなくなってきている事実も、自分の中にあるんです。それは、おおよそギターのせいだなって(笑)。というのも、いいギターが録音されている音源って、ギターがはっきり聞こえるんだけど、レンジを食っていないぶん、他の楽器にパワーを割けている側面があるんですね。ビッグ・シーフの新作(『Dragon New Warm Mountain I Believe in You』)なんかもそうで、アコギも入ってるけど、エレキの音色がじつはピューマ・ブルーの質感に近かったりするんです。そういう音の鳴らし方、エレキ・ギターの置き方、音のスペースの作り方を意識したので、ギターがミッド・レンジをガッツリ食っちゃって他の楽器の音の置き場がなくなる、みたいにはしたくなかったんですね。そういうサウンド・デザインのイメージが、先立ってありました。ギターの録音っておおよそいちばん最後なので、自分で作ったスポットにハマるようにギターを弾いていったっていう感じですね。
■あくまでも他の楽器のほうが主役、ということですか?
加藤:う〜ん。とはいえ、最終的にギターが入ってくるよろこびって、かなりデカいんですよ(笑)。だから、重要度ではもしかしたら他の楽器のほうが単純にレヴェルの面で勝っている部分はあるんですけど、画竜点睛として最後に僕のギターを入れておしまい、みたいなところはある。だから、欠かせないパーツではありながらも、あからさまに目立っていたり、大きなレヴェルで入っていたりすることはない。でも今回、ギターは絶対に必要だったと思います。
■“per se” は異色な曲で、ボサノヴァがベースになっているじゃないですか。ブラジル音楽は、加藤さんの音楽的なヴォキャブラリーとして持っていたものなんですか?
加藤:なんとなく好きで聴いている音楽がブラジルの音楽だった、みたいなことがけっこうあったんですね。ケイトラナダがガル・コスタをサンプリングしている曲(“Lite Spots”)があるじゃないですか。それで「これがガル・コスタか」と思って聴きはじめたら、かっこよくてハマっちゃったんです。最初は、そういう「どこをサンプリングできるか」みたいな感じで聴いていたかもしれません。でも、シンプルにどんどんハマっていって、ジョアン・ジルベルトやカエターノ・ヴェローゾを聴いたりして。あと、バッドバッドノットグッドのアルバム(『Talk Memory』)にアルトゥール・ヴェロカイが参加していて、そのへんを聴いたのも自然な流れでしたね。それに、ボサノヴァって当時のことを考えると、めっちゃパンクじゃないですか?
■当時、既存の音楽に対する「新しい潮流(ボサノヴァ)」だったわけですからね。
加藤:あの軽快さとか優しさとか室内楽的に聞こえる感じとかって、何かに抑えつけられていたからこそのものじゃないですか。それで、小さい音しか出ないガット・ギターと小さい音のドラム、小さい声の歌にみんなが耳を傾けているっていう。そういう音楽の強さみたいなものをめっちゃ感じていて、それを自分でやってみたかったんです。
■リリックについてはいかがですか? かなり抽象的に感じましたが、NOT WONKよりも生活感やパーソナルな感覚があると思いました。ラヴ・ソングも印象的で、優しさが通底しているように感じます。
加藤:日本語詞を書いたことがなかったので、どういう詞を書きたいとか、どういう歌を歌いたいとかって、最初はあんまりイメージがなかったんです。でも、“肌色” や “Quai” を作っていたとき、日本語の歌詞とメロディが一緒に出てくることがあって。「この言葉の意味は一体なんなんだろう?」って、出てきたものをあとから考えていきました。嫌な言葉や歌いたくない言葉は、自分から出てこないはずじゃないですか。だから、「なんでこの言葉をいいと思えているんだろう?」と理由を探っていって、「この言葉がいまの自分の考えや気持ちを表現するにあたっていちばん適切な言葉だと思える」という確信をもって歌ったので、個人的にはめちゃくちゃ具体的な歌詞が並んでいると思っています。それが、今回のアルバムの肝でもあるんですよね。ある人が聴いたときに抽象的に思えても、それがすべての人にとって抽象的かどうかは別の話じゃないですか。「ストレートに感じられる」とされる歌詞の意味がわからないっていうことが、むしろ僕はあったりするんです。「メッセージを額面どおりに捉えていいのか、これは?」と思うようなことがあって、言葉とその意味や内容が必ずしもイコールにはならない気がするんです。とはいえ、表現なので、僕が何を伝えたかったかという以上に、聴いた人が受け取った意味のほうが正解だと思う。ただ、僕はこの言葉がいいと思ったし、歌詞を書いたタイミングで思ったことを如実に表すためにはこの言葉が必要だったと感じますね。
■当時の感情やその時々の出来事が直接反映されているのでしょうか?
加藤:そうかもしれないですね。でも、内省的なものでもないし、独り言を書いているつもりもなくて。言いたいこと、歌いたいことは、NOT WONKと変わらないかもしれないですね。
■「NOT WONKもSADFRANKも元のハートが一緒」(https://twitter.com/sadbuttokay/status/1602985525174218752?s=20)とツイートしていましたよね。
加藤:それは、ありがちな話になったら嫌だなっていうのがあって。ストリングスの話にも似ていますが、ロック・バンドをやっていたやつが急にソロをはじめたと思ったら、バンドではやっていなかった私的なことや優しい音楽に手を出したり、ちょっと色気を出してみたり──そういうのは、いままで繰り返されてきた失敗の歴史だろって僕は感じていて。絶対にそういうことをやりたくなかった、っていうのが先立ってあったんです。NOT WONKでやりたいことのひとつに、自分が最初にパンクを好きになった瞬間の気持ちを再現する、みたいなのがあるんです。それは、過去の音楽を再現するとか、「70sの感じを出したいからギターをこういうふうに歪ませる」とか、そういう話じゃなくて。自分が何かを受け取ったときの気持ちを再現するためには、必ずしもそれとまったく同じものを作る必要がないと思っているんです。何かを再現することと何かを写実的に綺麗にデッサンするっていうことは、まったくちがうことだと思っているので。そういう意味では、今回のSADFRANKのアルバムもNOT WONKの作品と同じなんですね。最初にパンクのライヴを見に行ったときの感覚とか、メガ・シティ・フォーの歌詞の意味を調べていたら「これはまちがいなく俺のために歌っている」って確信したときの気持ちとか──そういうことを再現しようと思ったときに僕がいま使いたかったのが、ストリングスだったり日本語詞だったり歌のない曲だったりピアノだったりしたっていう。だから、NOT WONKのファースト・アルバムで表現していることや、NOT WONKの普段のライヴでギターを爆音で鳴らしていることと、ピアノを優しく弾いて歌うことは、本来の意味では同じなんです。まったく同じことをやっていると思いますね。

いままではミックスで「ギターより下にしてください」なんて言っていたんですけど、今回は「歌っているやつの顔をデカくしてください」というオーダーをしたんです。相手の胸ぐらをつかんでいる感じが出ましたね。
■なるほど。では、日本語詞を書くにあたって、何か参考にしたものはありますか?
加藤:それこそele-kingの取材で野田(努)さんにインタヴューしていただいたときに(『ele-king vol.24』)、「加藤くんって好きな日本語の歌詞あるの?」と聞かれたんですけど、答えられなくて(笑)。もちろん、日本語で歌われている曲で好きな曲はいっぱいあるんですよ。当時の所属レーベルだった〈KiliKiliVilla〉の与田(太郎)さんにも「(bloodthirsty)butchersとか札幌のバンドのKIWIROLLとか、なんかあるでしょ」って言われたんですけど、聞かれたときにパッと出てこなかった理由も自分にはそれなりにあるはずだなと思って。なので、butchersやKIWIROLL、あとGEZANも踊って(ばかりの国)もカネコアヤノも中島みゆきも歌詞は大好きだけど、参考にするというより、とにかく彼らと似ないようにしようって気にしていましたね。
■日本語詞で歌うことで、宛先が変わった印象はありますか?
加藤:鋭くなった感じはしますね。「お前に言ってます」って感じがある(笑)。NOT WONKの歌詞はもうちょっとレンジが広いような気がするけど、日本語詞は「これで伝わらなかったら嘘だな」という感じがするので。目の前にどかっと座って歌っているような感じがあるんです。
■SADFRANKの歌詞は、言葉が生々しいですよね。すっと切り出されものが、そのまま差し出されている感じで。
加藤:自分は意外にそういう人間なんだなって思いましたね。大事なことから話していく、みたいな。せっかちなのかもしれない(笑)。
■その意味では、SADFRANKはリスナーにより近くて、加藤さんというひとりの人間の姿が強く表れている感じがします。
加藤:このアルバム、ヴォーカルがデカいじゃないですか。デカくしたいなって思ったんですよ。いままではミックスで「ギターより下にしてください」なんて言っていたんですけど、今回は「歌っているやつの顔をデカくしてください」というオーダーをしたんです。相手の胸ぐらをつかんでいる感じが出ましたね。
■ヴォーカリゼーションの面でもストレートに朗々と歌っているシーンが多くて、それが歌の大きさと近さに寄与していると思いました。
加藤:そもそも、これまでと全然ちがうメロディが出てきたんです。それは、たぶん言葉に引っ張られたんだろうなって。いままでNOT WONKでは絶対にできなかったメロディが急に歌えたりとか、ナシにしてきたことがアリになったりとか、そういう裏返しが起こったので、自分は意外に奥深いんだなって思いましたね(笑)。
■今後もSADFRANKとしての活動は継続していくんですか?
加藤:まだやりたいことが結構ありますね。NOT WONKでも同じくらいやりたいことがありますし。いままで12年間、苫小牧で、ライヴハウスで偶然出会ったやつらとしか音楽をやったことがなかったので、今回、風呂敷を一気に広げて、これだけすごいミュージシャンたちと音楽を一緒に作れたのはすごくよかったんですよ、やっぱり。でも、フジとアキムがSADFRANKに参加してくれた凄腕プレイヤーたちに比べて劣っているとか、そんなことはまったくなくて。最初はSADFRANKでの制作のフィードバックをNOT WONKに持ち帰れるんじゃないかなって考えていたんですけど、レコーディングを進めていったらフジとアキムのめちゃくちゃいいところを改めて再確認して、「あれはあのふたりにしかできないな」って思った瞬間がいっぱいあったんです。だから、フィードバックっていうよりは、単純に……。
■別の表現?
加藤:うん。別の表現として生きているんだってわかりましたね。あと、NOT WONKに対する考え方や捉え方がより鮮明になったというか。3人で10年以上ぼんやりやってきてたけど、NOT WONKにはNOT WONKのよさがかなりあるっぽいぞと(笑)。「もうちょっとやれるはずだ」みたいなことが、もっともっと見えてきたって感じますね。
取材:天野龍太郎 (2023年3月23日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE