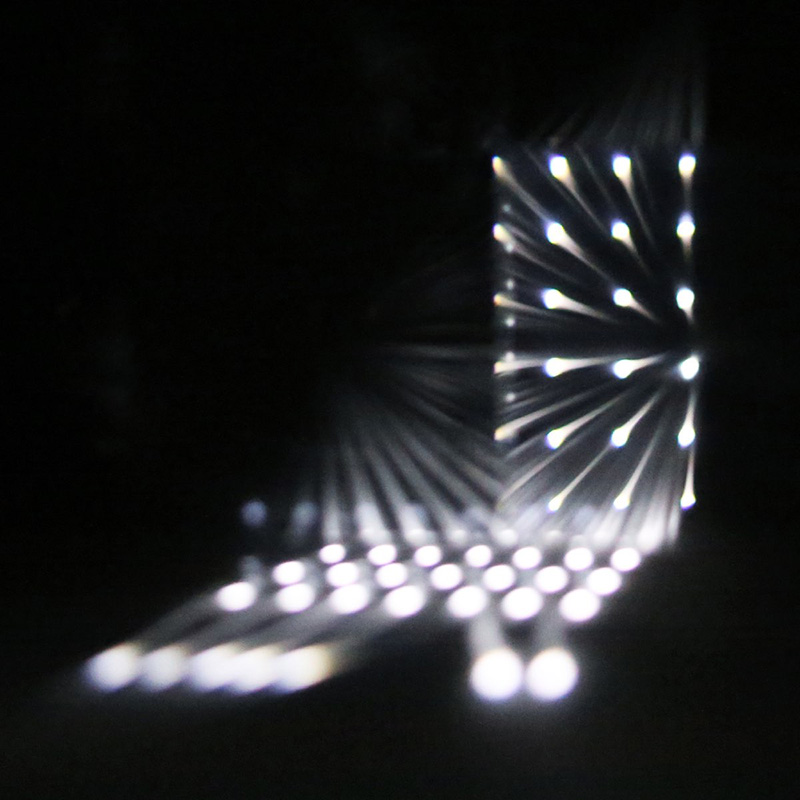MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Shuhei Kato (SADFRANK) - これで伝わらなかったら嘘
成功したバンドのフロントマンがソロでレコードを作るとき、あるいはパンクを出自にするミュージシャンがその表現を深化させ変化させていくとき、どのような道筋が考えられるのか。そんな正解のない難題に対して、NOT WONKの加藤修平は、エルヴィス・コステロやポール・ウェラーの例を引きながら答えてくれた。加藤によるソロ・プロジェクト、SADFRANKのファースト・アルバム『gel』は、2023年におけるその回答として差し出されている。
それにしても、SADFRANKの音楽やここでの加藤の表現は、NOT WONKのそれとはまったく異なっている。いま日本で最も忙しいドラマーの石若駿、ゆうらん船などで活躍するベーシストの本村拓磨、そして映画音楽からファッション・ショー、舞台芸術、インスタレーションなどの領域を横断する音楽家の香田悠真の3人を中心にしたバンドの演奏も、印象的なストリングスのアレンジメントもそうだし、なにより加藤は日本語で歌っている。それでも、NOT WONKがこの数年で遂げてきた変化を踏まえると、突飛なものには思えない自然さと説得力がここにはあって、それはNOT WONKのリスナーをけっして拒絶するようなものではなく、むしろ迎え入れる懐の深さと両者の表現を結びつける確信が感じられる。そして加藤は、SADFRANKとNOT WONKとでやっていることはまったく同じだ、とまで言い切ってみせる。
くるりの岸田繁からthe hatchの宮崎良研、松丸契、んoonのYuko Uesu、NABOWAの山本啓まで、新旧の仲間たちがひとつの点に合流した『gel』は、加藤が新しい海に飛び込んだよろこびが詰められたみずみずしい果実のようでいて、「目の前にどかっと座って歌っている」ような親密な作品でもある。この豊穣な音楽は、どのようにして生まれたのか。加藤にじっくり聞いた。
日本語で歌いてえな、というザックリした欲求があって(笑)。ただ、日本語で歌詞を書いたことは一回もなかったので、どうしたらいいかわからなかったんです。
■SADFRANKというプロジェクトのはじまりはいつなのでしょう? 2020年10月11日にリリースしたエディット・ピアフの “愛の讃歌” のカヴァー “Hymn To Love (Hymne à l'amour CM Version)” ですか?
加藤:その前からSADFRANKという名前で、ひとりでライヴをしたことは何度かあったんです。苫小牧でのライヴだったり、jan and naomiが札幌に来たときのサポート・アクトだったり。カヴァーや、ギターを即興で弾くパフォーマンスを僕ひとりでやるときの名前でしたね。それでLevi’sの広告の音楽を担当することになって、“Hymn To Love” をカヴァーしたんです。でもじつは、石若くんや悠真くんと最初にレコーディングしたのはそれより少し前ですね。
■ドラムに石若駿くん、キーボードに香田悠真さん、ベースに本村拓磨さん、というのが今回の「コアメンバー」とされています。そのメンバーでセッションをはじめたきっかけは?
加藤:日本語で歌いてえな、というザックリした欲求があって(笑)。ただ、日本語で歌詞を書いたことは一回もなかったので、どうしたらいいかわからなかったんです。それを形にしようと思ったときにパッと思い浮かんだ人たちに声をかけた、というシンプルな流れでした。
■NOT WONKで日本語詞を歌うことは考えなかったのでしょうか?
加藤:言われてみたら、NOT WONKでやるイメージは、そのタイミングではまったくなかったですね。そんなわけねえなと。NOT WONKは僕だけのバンドじゃなくて、他のふたり──フジとアキムありきで3人でやっているバンド、というのがまずあって、年々、その気持ちが高まっているんですね。「日本語で歌ってみたい、日本語で表現したい」という気持ちは、もっと私的でプライヴェートな気持ちだという気がしているんです。それをバンドで消化することに、そのときは違和感があって。
■石若くん、香田さん、本村さんとの共演経験はあったんですか?
加藤:本村くんはもともとGateballersというバンドをやっていて、その頃から好きで演奏を見ていました。共演したときにちょっと話す程度でしたね。石若くんと悠真くんとは面識がなくて、石若くんは演奏が好きだったから自分からメールしたんです。悠真くんは、当初一緒に制作する予定だったエンジニアの葛西敏彦さんの紹介で知りました。ピアノを弾ける人や自分のやりたいことを音楽的に汲み取ってくれるような人が僕の周囲のバンドマンでは思い浮かばなくて、スタジオ・ミュージシャンに頼むのも違和感があったので、葛西さんに相談したんです。葛西さんの推薦で初めて悠真くんの作品を聴いて、「もう、この人だろう」って感じて。

「僕がUKジャズのつもりで書いた曲を石若駿が叩いたらどうなるんだろう?」という興味がめっちゃあって。
■『gel』を聴いていると、石若くんや本村さんはもちろんですが、香田さんの役割は大きいのだろうなと感じました。
加藤:ハーモニー担当みたいな感じで関わってくれたんです。悠真くんはアカデミックな道を通ってきてはいるけれど、音楽に対する姿勢は僕とかなり通じるところがあって。僕は和声の理論とかはまったく勉強してこなかったので、そこをふたりで話し合ってアレンジメントや曲のカラーのつけ方を決めていきました。ストリングス・アレンジを岸田さんにやってもらった曲が一曲ありますが(“I Warned You”)、それ以外の楽器のアレンジは悠真くんとふたりで詰めていったんです。僕がいままで「理由や根拠はないけど、これがいいと思う」と感覚的にやっていたことを、悠真くんに根拠づけしてもらいました。悠真くんは、メンター的な感じでいてくれましたね。やっぱピアニストというか、楽譜を書く人にしかわからない音の見え方があるんだなって、彼の仕事を横で見ていて思いました。
■“肌色” や “最後”、“the battler” では、加藤さんがピアノを弾いていますよね。ピアノはもともと弾いていたんですか?
加藤:幼稚園や小学校の頃、教室に通ったことはありましたが、教則本がつまらなくてやめて(笑)。なので、ぜんぜん弾けないんです。SADFRANKをはじめたいと思ったとき、「ピアノを弾けるようになったらいいな」くらいの気持ちで鍵盤を買って、白鍵に「ドレミファソラシド」とマジックで書いて練習をはじめました。ギターを持ちながら和音を探す作業を3年くらい続けましたね。ギターとピアノはそもそも構造的にちがうから、別の考え方をしないといけないんだなって。
■このアルバムの曲は、ピアノで書いているんですか?
加藤:ギターで作った曲は3曲目(“I Warned You”)と4曲目(“per se”)くらいですね。そもそも「ギターと距離を取りたい」みたいなことが今回、裏テーマ的にあったんです。それは「ギターが嫌だ」とか、そういうことじゃなくて。自分自身のキャラクターとして「NOT WONKでギターを弾いて歌っている」というのがあるので、「自分の音楽の表現ってそれだけでいいのかな?」と疑問があったんです。なので、普段使っている方法を手放すとか、あるいは「歌わない」とか、そういうことは自分から離れる手段として選んだって感じですね。
■個人の表現をするにあたって得意なことを全面化せず、そこから離れて新しいところを開拓した、というのはおもしろいですね。
加藤:そもそも自分は何が得意なのかとか、たいしてわかっていないのかもしれなくて。得意なことを活かそうとすると、楽なことを選択しがちじゃないですか。でも、必ずしも得意なことが楽なこととは限らない。それに、ピアノを弾いてみたら、そっちのハーモニーのほうが好きだった、ということも多かったので。「加藤くんは声がいい」とか「NOT WONKはギターがデカくてかっこいい」とか、他人の印象やイメージを自分で自分に貼り付けちゃうのは危険だな、とも思っているんです。自分を定義しないでやっていくほうが、自分を殺さないで済むかなって。
■アルバムの制作に関しては、Bigfish Soundsの柏井日向さんが録音とミキシングを担当していますね。
加藤:NOT WONKの『Down the Valley』を一緒に作ったのも、柏井さんからの「俺にやらせて」という提案がきっかけだったんです。次の『dimen』はイリシット・ツボイさんと主にやったんですけど、一曲(“slow burning”)は柏井さんにミックスしてもらいました。柏井さんは以前から「何かやれることがあったら言ってね」と言ってくださっていたので、その言葉にありがたく甘えさせてもらった感じですね。
■サウンド面の印象や音楽的なトライは、NOT WONKとはだいぶちがっていますよね。パンクやロックからかなり離れていますし、ジャズなどの要素が入っています。
加藤:もともと、「これはNOT WONKではできないな」と感じる曲はいっぱいあったんです。でも、「これは3人でやるおもしろさがあるだろう」っていう曲にトライしていくのがNOT WONKの基本理念でもあって。それでもあぶれちゃったものは、ひとりでも活動するようになってからは「SADFRANKでやったほうがいいだろう」と判断したり。あと、メンバーが固まってからは彼らに当て書きした曲もあって、いろいろですね。NOT WONKと差をつけようという気持ちはなくて、アレンジ次第でどっちでもできると思っています。基本的には一緒ですね。
■現在のUKジャズやコンテンポラリー・ジャズとの繋がりを感じる曲がありますよね。5曲目の“瓊 (nice things floating)”は石若くんのビートを編集したものだそうですが、マカヤ・マクレイヴンやジェフ・パーカーの姿勢に通じるところがあります。
加藤:そうですね。僕、ドラマーがめっちゃ好きなんです。石若くんのプレイって、本人は意識していないでしょうけど、そのへんのドラマーと比べたら圧倒的に勝っちゃうじゃないですか。完全に確立されていて、ああだこうだ言う必要がない。そういうことを考えていたので、「僕がUKジャズのつもりで書いた曲を石若駿が叩いたらどうなるんだろう?」という興味がめっちゃあって。“offshore” は、そういう意図で書いた曲ですね。“瓊” は、そもそも全然ちがう拍子の曲をレコーディングしていて、途中で飽きちゃったので、ちがう曲にしようと思って作った曲です。石若くんのドラムをチョップしたり、キックに音色がついているからキックの音をキーにしたりして作っています。この2曲は、石若駿ありきで作った感じですね。
取材:天野龍太郎 (2023年3月23日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE