ヨーロッパを精力的に駆け回る女性DJ、Cassyのギグが12月30/31日と大阪/東京であるのでお知らせしたい。イングランドで生まれオーストリアで育った彼女は、パリとアムステルダム、ジュネーブとベルリンのアンダーグラウンド・ハウス・シーンにコミットした。ルチアーノやヴィラロヴォスらからの賞賛とともに初期のパノラマ・バーのレジデントDJのひとりでもあった。ここ1~2年は自身のレーベル〈Kwench Records〉を拠点に12インチをリリースしている(DJスニーク、フレッドP、ロン・トレントらも含む)。
12月30日は大阪で開催の〈The star festival 2018 closing〉、12月31日が表参道VENTに出演。間違いなく良いDJなんで、お楽しみね!
■THE STAR FESTIVAL 2018 CLOSING
12/30(sun)

line up :
Peter Van Hoesen(Time to express/Brrlin)
Cassy
Kode 9
yahyel
Metrik(Hospital records/uk)
EYヨ(Boredoms)
AOKI takamasa-live set-
BO NINGEN
Tohji (and Mall Boyz)
環ROY
SEIHO
D.J.Fulltono
YUMY
OPEN AIR BOOTH :
YASUHISA / KUNIMITSU / MONASHEE / KEIBUERGER / AKNL / MITSUYAS / DJ KENZ1 / 81BLEND / RYOTA / GT /SMALL FACE
open 21:00
adv:¥3500 door:¥4000
group ticket(4枚組) : ¥12000
チケットぴあ P-CODE(133-585)
ローソンチケット L-CODE(54171)
イープラス https://eplus.jp
Peatix : https://tsfclosing.peatix.com/
■Cassy at N.Y.E
12/31 (MON)

=ROOM1=
Cassy
Moodman
K.E.G
Koudai × Mamazu
=ROOM2=
Sotaro x EMK
EITA x Knock
Genki Tanaka × Toji Morimoto
SIGNAL × TEPPEI
JUN × UENO
OPEN : 21:00
DOOR : ¥4,000 / FB discount : ¥3,500
ADVANCED TICKET:¥3,000
https://jp.residentadvisor.net/events/1185424
[ FACE BOOKイベント参加 ] で¥500 OFF ディスカウント実施中!
参加ボタンでディスカウントゲスト登録完了です。
※当日エントランスにて参加画面をご提示ください。
Join the event for ¥500 off !! Click " Join " and you are on discount list !! ※You MUST show your mobile phone screen of joined event page at the entrance.
※VENTでは、20歳未満の方や、写真付身分証明書をお持ちでない方のご入場はお断りさせて頂いております。ご来場の際は、必ず写真付身分証明書をお持ち下さいます様、宜しくお願い致します。尚、サンダル類でのご入場はお断りさせていただきます。予めご了承下さい。
※Must be 20 or over with Photo ID to enter. Also, sandals are not accepted in any case. Thank you for your cooperation.
URL : https://vent-tokyo.net/
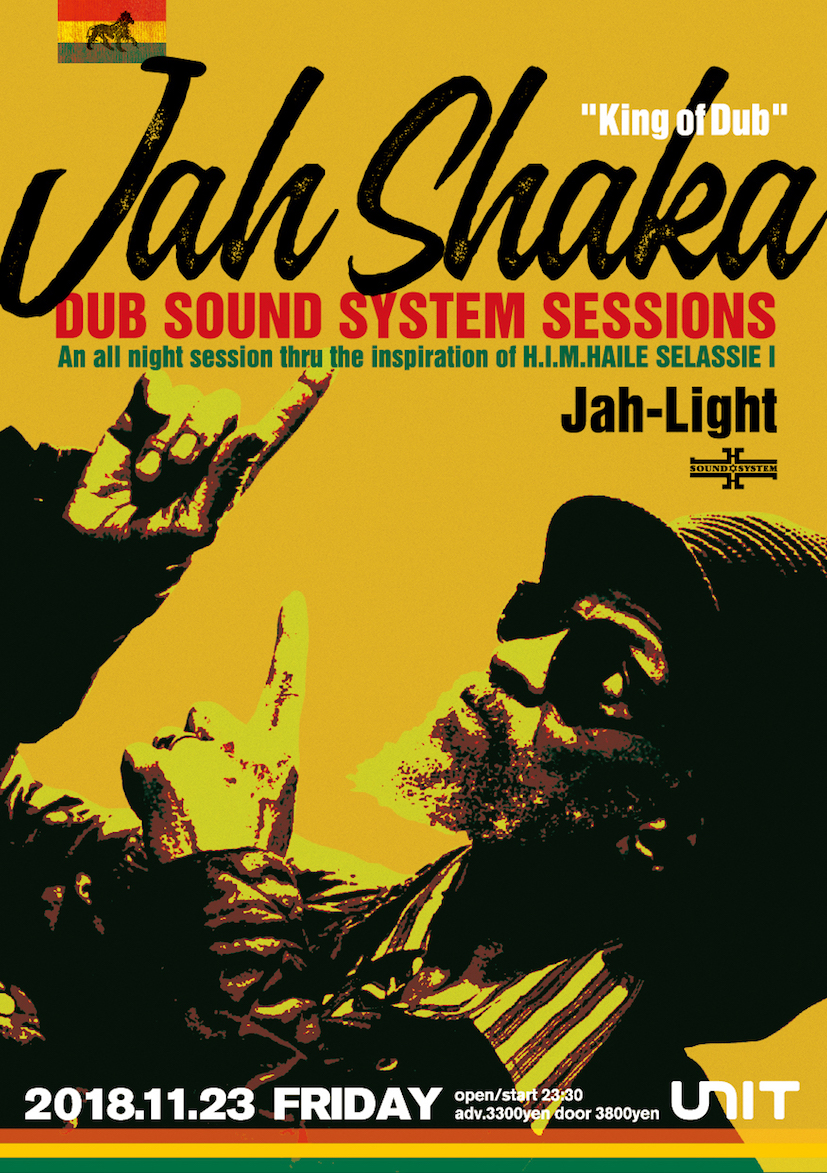







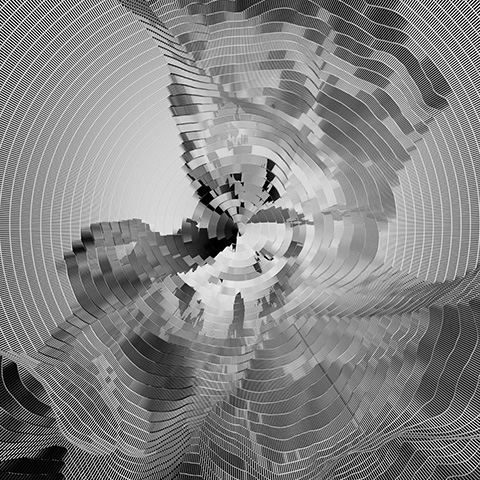























 photo by Tatsuya Hirota
photo by Tatsuya Hirota







