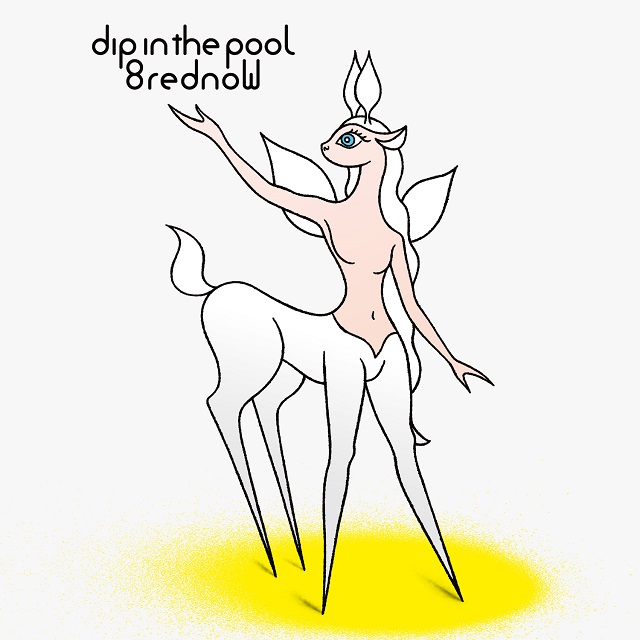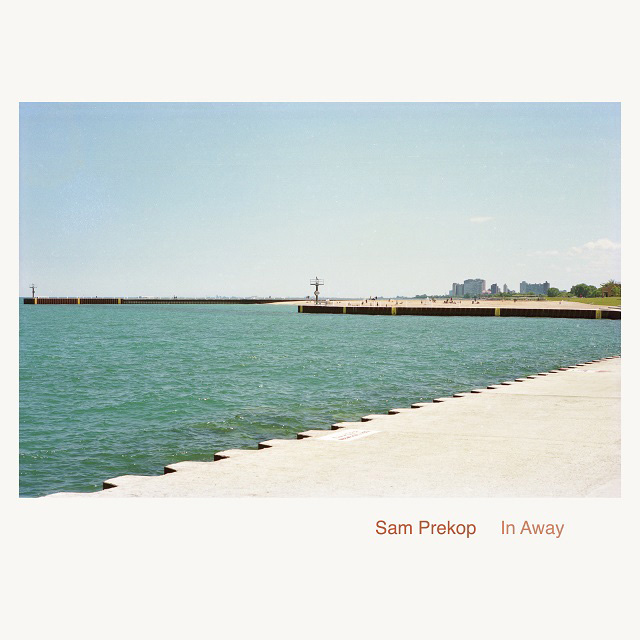これまで多くのイベントを仕掛け、東京の夜に彩りを加えてきたファッション・ブランド〈C.E〉。長きにわたるパンデミックの日々を経て、およそ3年半ぶりパーティが開催されることになった。ラインナップは日本からPowder、ドイツよりPLO Man、そしておなじみのウィル・バンクヘッド。ひさびさのC.Eナイトもまた、春に向け新たな夜の光となるに違いない。3月4日は表参道VENTに集合です。
[3月2日追記]
追加情報です。当日、会場にてTシャツとPLO Manのカセットテープが販売されるとのこと。ぜひなくなる前に。



C.E presents
Powder
PLO Man
Will Bankhead
約3年半ぶりとなるC.Eのパーティが3月4日土曜日にVENTで開催。
洋服ブランドC.E(シーイー)が、2023年3月4日土曜日、表参道に位置するVENTを会場にパーティを開催します。
Skate Thing(スケートシング)がデザイナー、Toby Feltwell(トビー・フェルトウェル)がディレクターを務めるC.Eは、2011年のブランド発足以来、不定期ながら国内外のミュージシャンやDJを招聘しパーティを開催してきました。
本パーティでは、日本からPowder、ドイツよりPLO Man、そしてイギリスからWill Bankheadをゲストに迎えます。
当日、会場ではTシャツとPLO Manのカセットテープを販売します。 ←NEW!!
C.E presents
Powder
PLO Man
Will Bankhead
開催日時:2023年3月4日土曜日11:00 PM
会場:VENT vent-tokyo.net
料金:Door 3,000 Yen / Advance 2,000 Yen
t.livepocket.jp/e/vent_bar_20230304
Over 20's Only. Photo I.D. Required.
20歳未満の方のご入場はお断り致します。年齢確認のため顔写真付きの公的身分証明書をご持参願います。
■Powder
曲がり角の向こうが目に映らないからといって、そこに何も無いわけではない。道中にパッと現れた景色のように、Powderは「突然」その場に居合わせた様に見えるが、少し先の曲がり角にいただけのような存在だ。未だに、わざわざ曲がりくねった道中を選んでいるのか、チラっと見えてはいなくなってしまい、なかなか全部を掴める事は少ないのだが、手がかりもなく行方をくらますわけでもなく、意地悪な道で興味を持つものをふるいにかけたりするわけでもなく、存在と印象を残して、一定の距離を保持しながら少し離れた所を走っている。
2015年ストックホルム “Born Free Records” から楽曲 “Spray” を含むEPのファーストリリースや、ESP Institure “Highly EP” でのデビュー以降、日本をベースにしつつも、積極的に自己更新されない情報の少なさも手伝い、全ての動きを掴みきれていないリスナーの憶測とは平行線に、かと思えば時に期待に答えながら、落ち着きが無いようで一貫した(彼女の楽曲のように)、ジャンルマップに左右されない存在感を保ち、楽曲リリースを重ねる。
PowderのトラックやDJプレイを説明するために、“ミニマルな、浮遊感のある、ファニーな…” と、トラックの印象を表すキーワードを探してしまうと、目新しい言葉が特に思い浮かばないが、連想が尽きる事もない。突き詰めていくと、レフトフィールドなトラックである以外の何物でもないことに気づかされるが、それと同時に奇妙さが突き抜ける事なく、普遍的なダンストラックとしてのバランスを保った、オーセンティックなレフトフィールドさ、とでも形容できる脱構築的な世界感を持っている。時代を即座に感じさせるような記号を含むわけでは無く、散りばめられた仕掛けの組み合わせが綿密ながらシンプルに整理され、新しさ、という事よりも、既聴感の無さ、を追求している様にも思える。
Powderのブッキングは非常にドメスティックで、予測できない。
ハイプロフィールなフェスティバルから、小さな町の特別なギグまですべてのブッキングを自身でこなすが、どこであっても「ダンスフロア」をコントロールするような場に居合わせる一貫性を保っている。…といっても、器用なフロアマスターという印象とも異なり、フロアの集合知とでも呼べる古き良きグルーブを放棄しない、実はストレートなDJでもある。
快楽的なトラックとしての機能をストイックに追求した上で、長い夜の後でのみ訪れるシンプルな感情を喚起する。メッセージや刺激はその空気感の中にのみ漂い、感覚的なものとして各々に必要なだけのパワーを与える。
規模の大小に問わず、Powderの行動を決定づけているのは、
自然さだったり、私的な視点のようだが、拡大を続けるパーソナルなアウトプットが違和感無くフィットするためのギグ以上の受け皿として、自身のレーベル “Thinner Groove”も2019年より始動した。“友人のグルーブを紹介する”このレーベルでは、自身が一番大切にしている小さな、しかし全幅の信頼を置く知られざるコミュニティが少しずつ明かされていく。
TGの最近のリリースとして、5AMによる “Pre Zz” がリリースされた。5AMは長年の友人である5ive, AndryとMoko(=5AM)によるバンドでありグループエフォート、PowderはMokoとして参加し、プロデューサーとしての新しい側面を覗かせている。
text by Franc Rare
http://powd.jp
■PLO Man
PLO manはCC NotやGlobex、INTe*raのメンバーであり、インディペンデント パブリッシング プロジェクトであるACTING PRESS(アクティングプレス)主宰。2015年からACTING PRESSはグローバル化したアンダーグラウンドな音楽の世界において、レコードやテープ、イベントなどを丹念に矛盾なくプロデュースしています。
AP22. we have the technology.
https://youtu.be/KW_8E-3Kvew.
■Will Bankhead
イングランドの音楽レーベル、The Trilogy Tapes(ザ トリロジー テープス)主宰。Mo Waxでメイン ヴィジュアル ディレクターを務めたのち、洋服レーベルであるPARK WALKやANSWERを経て、The Trilogy Tapesを立ち上げる。Honest Jon's Recordsをはじめとする音楽レーベル、Palace Skateboardsなどの洋服ブランドのグラフィックデザインを手がける。
http://www.thetrilogytapes.com



 by Ben Rayner
by Ben Rayner