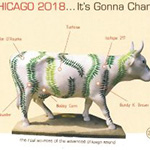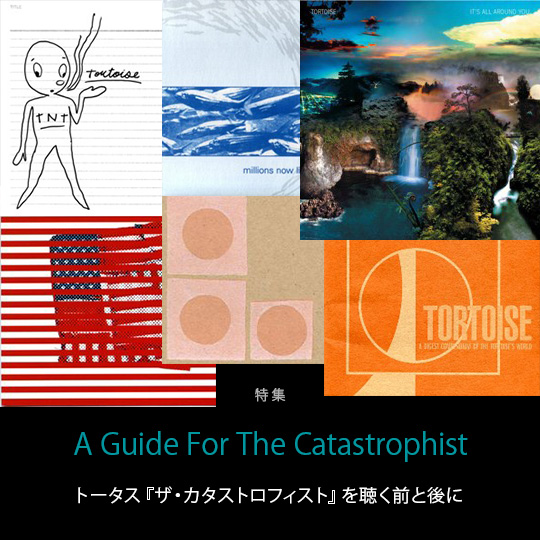MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Tortoise - 亀たちの成熟の年齢
彼らが新作を録り終えた情報はつかまえていた。「別冊ele-king」のポストロック号をやっていたときだったので数ヶ月前になるが、おあつらえむきの特集なのにリリースの都合でとりあげられなかったのはいかにも口惜しい。爾来このアルバムは何度も聴いた。冒頭の表題曲のニュース番組を思わせるジングルめいたイントロにつづくトータス節ともいえるリズムの提示、アンサンブルは複雑さよりスペースを求め、打鍵楽器の記名性はこれまでより鳴りをひそめシンセサイザーがムードを演出するこのアルバムは『イッツ・オール・アラウンド・ユー』『ビーコンズ・オブ・アンセスターシップ』の、つまり『TNT』以後の傾向雄の延長線上にあるのはあきらかだが、前作から7年の時間の経過は彼らの、リロイ・ジョーンズいうところの「変わりゆく──」いや、よそう。それより『ザ・カタストロフィスト』にはミシェル・レリスの書名「成熟の年齢」をかぶせたくなるやわらかさとかすかな官能をおぼえる。90年代、私たちはそれをまさにテクノロジーの、つまりポストロックのかもすものとして聴いたが、20年を経て、それがトータスの唯名性だったことにおそまきながら気づきつつある。
ジョン・マッケンタイア、ジョン・ヘーンドン、ダン・ビットニー、ダグラス・マッカム、ジェフ・パーカー──5人を代表してギタリスト、ジェフ・パーカーにお答えいただいた。
■トータス・Tortoise
1990年に結成されたシカゴのバンド。ダン・ビットニー、ジョン・ハーンドン、ダグラス・マッコームズ、ジョン・マッケンタイア、ジェフ・パーカーの5人からなる、音響的なアプローチを持ったインストゥルメンタル・バンドであり、「シカゴ音響派」等の呼称によって、当時の前衛音楽シーンを象徴・牽引した。のちに「ポストロック」という言葉の誕生、発展、拡散とともにさらに認知度を上げ、多彩な試みをつづけている。今年1月リリースの『ザ・カタストロフィスト』で7作めのアルバムを数えることとなった。
シカゴ市のための組曲に入れるべく、メンバーそれぞれが1曲ずつ作曲したんだ。
 TORTOISE The Catastrophist Thrill Jockey / Pヴァイン |
■『ザ・カタストロフィスト』はおよそ7年ぶり7枚めのアルバムですが、これまでのどのアルバムより、作品の間隔が空いた理由について教えてください。
作品の間隔が通常より空いてしまったのにはいくつか理由があるんだ。ひとつはメンバーのうち2人がLAに住んでいて、みんながいっしょに集まることのできる機会を見つけるのが難しくなったこと。もうひとつはそれぞれ別のプロジェクトが忙しかったこと。自分はフリーのジャズ・ミュージシャンとして、ジョン・マッケンタイアはエンジニアやプロデューサー業、マッコームズはブロークバックやイレヴンス・ドリーム・デイで、等々。
■『ザ・カタストロフィスト』に着手したきかっけについて教えてください。またいつごろはじまり、終わったのはいつですか。
新しい楽曲には『ビーコンズ・オブ・アンセスターシップ(Beacons Of Ancestorship)』のツアーが終わってからすぐ取り掛かりはじめていたんだ。シカゴ市から新しい作品を依頼されて、シカゴの即興音楽コミュニティのアーティストとコラボレートして組曲を制作した。そのときの楽曲が今作に収録されている曲の元になっているんだ。
■本作の制作上のプロセスでいままでと変化したところはありますか。各自がアイデアをもちより、編集的に構築したのか、セッションでつくっていったのか、あえていうならどちらの比重が高かったですか。
今回はあなたの言う両方のプロセスを組み合わせたものだった。メンバーがそれぞれアイディアを持ってきて、それからグループとしてそれを新しいものへと発展させていったんだ。『ザ・カタストロフィスト』は『イッツ・オール・アラウンド・ユー(It’s All Around You)』のスタジオをベースにした制作プロセスにより近いものなんだ。『ビーコンズ~』はライヴや実際の演奏をもとにしたものだよ。
■先行シングル“Gesceap”はメロディとリズムを効果的に交錯させた、長さを感じさせないすぐれた楽曲だと思いました。たとえばこの曲を例にとり、完成にいたるまでのプロセスを教えてください
前の質問で言った、シカゴ市のための組曲に入れるべく、メンバーそれぞれが1曲ずつ作曲したんだ。“Gesceap”はジョン・マッケンタイアが作った曲で、彼はテリー・ライリーの“In C”のような感覚をよりトータス的な文脈で表現しようとしていた。アルバムに収録されたバージョンになるまでにかなり多くの回数作り直している。曲の構造はできるだけ単純化して、録音にはたくさんの楽器が重ねられているんだ。
自分たちはまだ「アルバム」を作っているんだ。
■『ザ・カタストロフィスト』は多様性に富んだ、しかしとてもまとまりのあるアルバムだと思いました。断片的なアイデアの折衷というより、曲ごとの自律性を重視したつくりになっていると感じました。この意見についてどう思われますか
自分たちはまだ「アルバム」を作っているんだ。偉大な作品というのはリスナーがさまざまなムードや感情を経験することができるものだと思う。同時にグループとしての自分たちの広範な音楽的な興味を反映したものでもあるよ。
■サウンド面では、『ザ・カタストロフィスト』は『イッツ・オール・アラウンド・ユー』、『ビーコンズ・オブ・アンセスターシップ』よりエアー感が強いと思いました。今回のアルバムではトータルな音をどのようなイメージに仕上げようと意図したのですか。
今作に関して自分たちは絶対にオープン・サウンドを取り入れようと考えていた。それぞれの楽器のまわりにたくさんのスペースがあるようなサウンドだよ。
■音づくりの面で、スタジオの機材およびメンバーの使用機材で、これまでと本作とで顕著なちがいがあれば教えてください。
知っているかもしれないけど、ジョン・マッケンタイアは彼のSoma EMSを15年あった場所から別の場所へと引っ越したんだ。『ザ・カタストロフィスト』はほとんど、もともとあった場所で録音されたんだけど、いくつかは新しい場所でも録音して、ミックスもそこで行われた。
■『スタンダーズ(Standards)』以降、初期トータスの代名詞でもあったヴィブラフォン、マリンバの代わりにシンセがアンサンブルを牽引するようになりました。この変化は意図的なものでしたか?
そうだね。自分たちの音楽をより拡張する必要を感じて、シンセサイザーでの実験をよりたくさんするようになったんだ。
■“ホット・コーヒー”は『イッツ・オール・アラウンド・ユー』時のアイデアをリサイクルした楽曲だということですが、収録を見送った楽曲を次作以降でとりあげることはままあることなのでしょうか? もしかしたら、トータスの楽曲のためのアイデアのストックはかなりの数にのぼるのでしょうか。
アルバムをリリースするごとにたくさんの「残り物」が出るんだけど、それらはしばしばシングルやコンピレーションとしてリリースしている。時折、それらに立ち返って何か新しいものを作るインスピレーションをもらったりすることもあるんだ。
“ロック・オン”は素晴らしい曲だしメンバーみんなが聴いて育ったんだ。当時としてはとてもユニークな曲だった。
■デイヴィッド・エセックスの“ロック・オン”をカヴァーした理由を教えてください。またこの曲にトッド・リットマンを起用したのはなぜですか。
“ロック・オン”は素晴らしい曲だしメンバーみんなが聴いて育ったんだ。当時としてはとてもユニークな曲だった。かなりおもしろいミニマル・サウンドが加えられていたり、ロックンロールについての歌なのにギターが使われていなかったりね。自分たちはみんな長い間トッド・リットマンのファンであり友人で、彼の起用は自然な選択だった。
■『ザ・カタストロフィスト』には“ロック・オン”以外にもヨ・ラ・テンゴのジョージア・ハブリーの歌う“ヨンダー・ブルー”を収録しています。なぜヴォーカル曲を2曲も収録したのですか? またこの曲はアシッド・サイケともいいたくなる曲調ですが、この曲の生まれた背景を教えてください
次回作にはヴォーカル曲をいくつか入れようと事前に考えていて、しかも自分たちはトッドと同じように、ヨ・ラ・テンゴのジョージアの曲を敬愛している。“ヨンダー・ブルー”は、曲は先にできていて、ジョージアに興味があるか音源を送ったんだ。そうしたら彼女のヴォーカルと歌詞が付いて戻ってきたんだけど、それを聴いてまったく吹き飛ばされてしまったよ。
■ポストロックなることばについては、語ることもあまりないかもしれませんが、日本ではこの20年前にとりざたされたことばに今年復権の兆しがありました。こと日本だけの現象かもしれませんが、かつてトータスの代名詞ともなったこの言葉をもう一度もちだすのだすとしたら、どこに可能性を見出せばよいと思いますか。
新しい可能性というのは僕たちのイマジネーションのなかにあるんだ。可能性に限界はないよ。
■今回〈Pヴァイン〉から、過去作品がすべて紙ジャケットで再発されます(それも先の質問と無関係ではありません)が、旧作のなかで現在、もっとも気に入っている作品を一枚あげてください。
すべてのアルバムが好きだけど、今日の1枚を選ぶとすれば『イッツ・オール・アラウンド・ユー』かな。
■新作をライヴセットにかけるとしたら、ヴォーカル曲含め、ライヴ用のアレンジが必要になると思いますが、どのようにするおつもりですか。ライヴとスタジオワーク、トータスにとって比重が高いのはどちらですか。
どちらのケースもたくさんの作業を必要とする。よくスタジオで曲を作ってアルバムを完成させてから、ライヴでそれをどう演奏するか考えなければならないこともあるよ。それにもたくさんの時間とクリエイティヴィティを要する。
自分のやることはすべてトータスに反映されるし、トータスとしてやることはその他すべてのことへと還元されるんだ。
■それにしても、私は『ザ・カタストロフィスト』はトータスの新局面をあらわす野心的な作品だと思ったのですが、なぜ「Catastrophe」を文字ったタイトルなのでしょう
アルバムのタイトルはジョン・ハーンドンが彼の読んでいた本から思いついたんだ。自分はその本を読んでないんだけど、いまの政治状況や環境のことを含めた日々の生活のことを考えると、興味深いし良いタイトルだと思った。
■カヴァーアートには90年代のエイフェックス・ツインのような露悪的な意図をこめていますか? ちがうのであれば、その真意を教えてください
このジャケットは何年か前に撮った写真を使ってメンバーの顔を合成したものなんだ。自分たちの顔をジャケ写にするならこの方法しかないだろうと話していて、ご覧の通りになった。
■90年代から2000年代初頭にかけて、トータスはシカゴおよび、インディ・ミュージックのある種の結節点と、すくなくともリスナーである私たちは見なしていました。現在のUSインディおよびシカゴのシーンでトータスはどこに位置づけられると自己評価なさいますか。
トータスはある特定の時代にシカゴのインディ・ミュージック・シーンを代表する存在だったと思う。メンバーはそれぞれさまざまな形でそのシーンに参加していて、それが自分たちの生み出す音楽に反映されていた。いまでは違ったシーンがあるし、自分たちの前の時代もまたそうであったように、すべてはつねに変化していくんだ。
■トータスが、現在の5人、不動のメンバーになってから短くない時間が経ちました。ほかのプロジェクトでの活動も多いみなさんにとってトータスというバンドはどのような意味をもちますか。
僕たちは偶然にも同じ時に同じ場所にいた良き友人であり、気の合う仲間なんだ。自分にとってトータスはいつもアイディアを試す場所であり、アーティストとして成長する場所でもある。自分のやることはすべてトータスに反映されるし、トータスとしてやることはその他すべてのことへと還元されるんだ。
トータス約7年ぶりの新譜を祝し、本インタヴューにつづき、第2弾となる特集をお届けいたします!
質問作成・文:松村正人(2016年1月08日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE