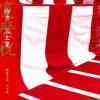MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Kan Mikami - もうひとりの、“日本のパンク”のゴッドファーザー
漁師と海の歌っていう。たとえばリバプールなんかもね、ほんとに漁師町ですよ。海どころって感覚の音楽が生まれるじゃないですか。アメリカ西海岸でも、東海岸でも。わたしは北の海だったり、働く海っていうんですか。漁師が好きな好きな音楽ばっかり聴いてましたからね。
■三上さんにはあまりにも訊きたいことがたくさんあって、演歌(怨歌)というのもそのうちのひとつなんですが、ほんとどこから話を切り出せばいいのか、すごく迷ってたんですけれども(笑)。
三上:それで、もうひとつ付け加えたいのがね、漁師の連中から話を聞くとね、いまみたいにネットとかもないので、彼らは3ヶ月同じ曲を聴かないといけないんですよ、1回陸(おか)で買ったら。だから相当チョイスするらしいんだよな。そういうものも、意外に自分のなかにあるのかもしれないですね。1曲の完成度と言うとちょっとおこがましいけれども、暮らしと本質的に結びついているっていうのは無意識にあるのかもしれない。すいません、挟んじゃって。
■いえいえいえ。あの、すごくざっくりした質問なんですけれども、三上さんが青森から出てきて、で、板前やられて、そして板前の寮を抜け出してギターを抱えて、そこからデビューして活動はじめられて、およそ40年くらい経ってると思うんですね。この40年っていうのは日本は、世界は、とにかくまあ、破壊的なまでに変化しましたよね。この40年の日本の変化というものに三上さんはどういう思いを持ってらっしゃるんでしょう?
三上:そうですね、まずひとつが若い世代がですね――若い世代っていうのはわたしたちの世代を言ってるわけです、いわゆる世に言う団塊の世代ってわけですけども。そういう日本の若いひとたちが戦争以外で――まあ戦争はちょっと違うかもしれないけれど、まさにざっくり言ってしまうと、最初に挫折したところからはじまってますよね。若者が挫折するってところから。学生運動におさらばして、髪を切って会社に勤めなきゃいけないってところから日本の文化ってはじまってますよね。戦後のというか、いまに繋がるものが。
だから彼らの失敗からはじまっている、失敗というか挫折ですよね。わたしもデビューしたときは、このままいけるんじゃないかと思いましたもんね。つまり中津川(注)で歌ったときに、このまま世のなかにばっと広がっていくんじゃないかと思いましたよ。で、3年ぐらいその気でいたら、まわりを見たら誰もいなかったっていうのが(笑)、まあ現実でしたね。それはものすごくショックだったですね。
■たとえば、60年代を生きた方々の本なんかを読みますと、やっぱり岡林信康さんという方がいかに影響力が大きかったか、ということを言われてるんですね。喩えの言葉はともかくとして、「神様」とまで呼ばれた方が、どうして失速――という言葉が合ってるのかわからないですけれども――居場所を失っていってしまったんでしょうか?
三上:それはね、個人的な情報というか、彼を大変知っている人間ですから、わたしの立場で言えるならば、やっぱり彼個人の考え方っていうのが結局あったんだと思います。彼はほら、牧師のせがれでしょう? わりとそのほら、平等意識というか、日本の風土に似合わないと言いますか、それほどアクの強い男じゃなかったんだよね。日本的なある種のミュージック・シーンのトップになっても、ある種育ちがいいというか。
しかし当時(60年代)は日本中から百姓の子どもたちが集まったわけですよね。それまでは東京に来るってことはないわけですから。たとえば地元で家業を継いで百姓をするとか。それが、「いやこれからは学問だ」つうんで、みんな田畑を売って、いままで学問を身につけたことのない人間が日本中から集まってくるわけですからね。元々は百姓ですからね、まあ言い方はそれでいいと思うんですけどね。その波で岡林みたいな、ある種西洋の教養を受けた流れがあって。それはやっぱり分離していくでしょうねえ。わたしの個人的な見方ですけれどもね。もっとアクの強いやつじゃないとだめだったんじゃないですかね。だから親分がこけたからみんなこけちゃったわけですよね。そのなかで親分が唯一生き残っていたのがね、内田裕也ですよ(笑)。彼はやっぱりちゃんと親分してたんですよ。だからここまでロックっていうのはこれたわけで。だから不思議なもんですよ、ひとりの力っていうのは。
■なるほど。
三上:だから求心力を失ったわけですよ、我々もね。〈URC〉も、なくはならないけれど、まあ終わっていってしまう。で、彼自身はそんな意識はあんまりなかったんじゃないかな、自分がトップだ、とかっていう。
■なんかこう、もっと時代的な風向きが変わってきたみたいな......。
三上:そうですね、いまの話は音楽ってことに限定して言ってるわけで、もっと大きいことで言うならば、なんて言うんでしょうかねえ、あの当時我々が影響を受けた波というんですか、1969年から世界的な流れでしたよね。まさにビートルズが来たりとか、まあ「革命」という言葉が合言葉のようになってた時代ですよ。すべてのことにおいて。音楽を変えよう、演劇を変えよう、映画、もちろん政治っていう。とくにやっぱりアメリカの――というか世界的な大きいうねりのなかでね、取り残されたと思うんですよね。つまりその、まだ機が熟してないと言おうか、まあいまだに熟してないんだろうけど日本の場合は(笑)。
つまりそういう、日本中から集まった百姓のせがれたちの感覚じゃあ、無理だったんじゃないでしょうかねえ、うん。つまり世界の動きっていうのは、ある種まあインテリ指導と言いますかね、そこそこ毒を持ってた連中ですよね、ヨーロッパでもアメリカでも。そういう連中が起こしたムーヴメントに、やっぱり格好だけじゃついていけなかったっていう。スタイルだけじゃだめだったんじゃないかな。ほんとにやる気があったらそりゃね、大学終わったぐらいでやめませんよ。社会に対するアプローチとか。やっぱり親から「いつまでそんなことしてんだ」とね、「田畑売ってお前を大学に入れさせて、せっかく公務員にしようと思ってたのに」とか、「いまだにヘルメットかぶって三上寛とだなんて、やめなさい」ですよ(笑)。
だからあっという間に消えたと思いますよ。あと下地がなかったんだと思いますね。これは明治維新とかああいうひとつのムーヴメントにはなり得ない。明治維新とかその辺はもっと切羽詰った想いがあったでしょ。流行とかそういうことだけじゃなくて。スタイルなんかじゃ全然相手にならなかったぐらい、まさにあの頃は似たような激動でしたよね。それにやっぱり耐えられなかった、つまりその、ひとが好すぎた、村社会に戻っちゃったんですよね。だから一瞬垣間見た世界ですよ、おそらくいま思うと、きっとね。70年代というのはね、きっと。
■たとえば、田川律さんなんかの日本の音楽の歴史を書かれている本を読みますと、フォークの時代からニュー・ミュージックの時代っていう言い方をされるじゃないですか。荒井由美とか吉田拓郎みたいなひとたちが出てくることによって、文化がどんどん変わっていったという。ああいうのはご自身現場にいらして、ある種価値観が揺らいでるような感覚っていうのはあったんですか?
三上:もちろんありましたよ。つまり過激なことはもうやめようっていうものですよね。それはやっぱり浅間山荘が大きいですよね。つまり最終的には、お互い殺し合うんだっていうとろこまで追い詰められるという。
だからいま思うと戦略も何もないよね。いま思うとですよ、精一杯だったとも思うから。お上っていうものに対する、なんて言うんでしょう、やり方が結局同士討ちなんだっていうことがショックで。それでもう誰もがやめようと思った、「あんなことになるんだったら」っていうね。それはやっぱりそこまで追い詰められたんだと思いますけどね。それもやっぱりある意味で、格好だけでいった部分も大きいんじゃないかな。本気でやろうと思ったら違ったんじゃないかなと思いますね、いま思うとね。
■だからそのやっぱり、60年代的なものを忘れたかったっていうような世のなかの風向きみたいなものがあったんですか?
三上:そうですね、それは「もういやだ」って言おうか、脈々と続いてきたお上に対する奴隷根性と言いますかね。ずっと虐げられてきたでしょ、日本人って。百姓も、侍もそうだと思うんですよね、実はね(笑)。そういうことに対する1000年にいちどあるかないかのチャンスにビビったっていうのがほんとのとこじゃないかなー。そこそこだったらいけるけれども、変えようと思ったらほんとに変わっちゃったんだから。しかも世界一のレヴェルでね。
■って言いますよね。すごかったってね、当時の日本の学生運動っていうのは。
三上:ええ、ええ。マイク・モラスキーっていうジャズ評論家のアメリカ人で、サントリーの賞もらったぐらい日本語の文章が上手いひとがいて。そのひとが書いた本の一節で引用がありましてね、オランダのある学者によると日本の70年代はルネッサンスよりもすごかったっていうことを言ってますね。あの当時アングラから発生した文化っていうのはルネッサンス以上だって外国の学者が言ってるぐらい、まあチャンスだったんですな。それを逃してしまった脱力感というのは非常に大きいと思いますよ。
■たしかにそうですよね。寺山修司さんや唐十郎さんの演劇もあったし、若松孝二さんがやっていたような前衛映画もありましたし。
三上:前衛もありましたし、フリー・ジャズもそうだし、それから舞踏なんかそうですよね、
■土方巽さんをはじめとする。
三上:彼らはまさに生き残った、生き残ったっていうのはおかしいけれども、立派に外で花咲かせてるわけですよね。舞踏なんて、あんなもの世界を見渡したってなかったわけですからね。
■すさまじいエネルギーがあった時代なんですね。
三上:だから面白いじゃないですか。津軽から出てきたですよ、漁師の末裔の、まあ勤め人の人間がですよ、ぽっと東京に出てきてその中心にいれるっていうかね、みんなをとらえたって言いますかね。それはやっぱり、それだけでもすごい話ですよね。
■それがね......三上さんは、1978年に『負ける時もあるだろう』というアルバムを出されてますけれども、あの「負ける時もあるだろう」という言葉はどういうようなところから出てきたものなんですか?
三上:あれはね、種明かしをしますとね、これはふたりしか知らないですけれども。あるとき新聞を見ましたらね、東映のヤクザ映画のね、たしか77年ぐらいかなあ......わたしがちょうど東映に出入りしていたときに、鶴田浩二のね、何ていう作品だったかな、最後のほうの作品だったと思うんだけどもね、それのキャッチだったんですよ。「負ける時もあるだろう、わたしは」って、「あ、これいただき」っていうね。それであの曲ができて。そしてね、実はあのキャッチを作ったのが深作欣二なんですよ。夜中に電話来ましてね、「三上、お前も売人だな」って。つまりあの「商売人だな」って(笑)。
■はははは。
三上:「見ただろう」、「はい、いただきました」っつって(笑)。「じゃあいちどどういう内容か教えてくれ」と言われて。それは曲を作った直後でしてね、30分ぐらい監督がチェックしましてね、それで向こうは何も言いませんでしたけどね。あのキャッチはわたしと彼しか知らないですね(笑)。
■でもその『負ける時もあるだろう』という言葉がピンときたっていうのはやはり時代のにおいのようなものを嗅いだっていうか......。
三上:だと思います。それはもうある種の世のなか全体を覆っていた、我々のようにいろいろなことをやっていた人間の、敗北感と言おうか、「もうダメだな」感ですよね。
■あの歌のなかで、「夢にまで見た不幸の数々が今目の前で行われ様としている」っていうね。あれは心に刺さる言葉なんですけれども。あの「夢にまで見た不幸」というようなフレーズは、当時の三上さんの気持ちとしては何を指していたんですか?
三上:それはまず、具体的に何だっていうのはないと思うんですよね。それは、いわゆる芸術家と言いますか、歌い手、ものを作る人間の予感ですよ。予感のないアートはダメですよ。
それは分析するとこういうことになるんじゃないかと思うけど、つまり、それで新しいアルバム(『閂』)でわたしは「みんなこのことを知ってた」って歌ってるんですよね、実はね。要するにね、ひとびとの無意識っていうのはね、迫りくる危機っていうものに対してね、直観ってものがあるはずなんですよ。それは著名な文学者であるとか占い師だけじゃなくてね、普通に生きているひともまるで獣のごとく来たるべき危機に対しても備えてるわけですよ、いまこうやってる時点でもね。
ミュージシャンはやっぱりそこに反応すると思うんです。そうしないとわたしはダメだと思っているんだけども。それでほとんど無意識の状態で、そこそこの詞を書くテクニックがあって、その当時ある種のこだわりっていうのかな、自分のスタンスっていいますかね、それを考えて見つめてあの歌は自然にできたんだと思うんですよ。きっとそうなんだと思いますよ。アートはね、後付けじゃダメ。政治とかジャーナルは後付けだけどね、アートは先に行ってそこで「まさか」って言われるんだけども(笑)。誰でもみんなそうですよね。
■たぶん、おっしゃる通りだと思います。でも、またその言葉を繰り返し歌わなければならないっていうのも、宿命的とはいえ非常に重たいものを感じます。
三上:そうですよね。だから「ミュージシャンって何なんだろうな?」っていうことになりますよね、私なんかは。あれだといまから30年前に作ってるわけでしょ。それでいま......何て言うんでしょう、現実が追いついてきてるわけじゃないですか。自分が作った曲にね。極論するとね、三島(由起夫)はこういうこと言ってるんですよね。「自然は芸術を模擬する」。つまり芸術のほうが先だっていう。「地震が来る」って言ったら地震が来るっていうのはこれはもうね......。
■三上さんはあるインタヴューのなかで「三陸のひとたちはDNAのレヴェルで津波が来ることをわかっていた」っておっしゃってます。三上さんにとっての三陸は『怨歌に生きる』という著書のなかでも書かれていますけれども、長年ツアーで行かれていた場所でもありますよね。
三上:行きましたねえ。しらみつぶしに、なぜかね、それもね。ほかの県でも良かったはずなのに。きっかり10年やりましたね。80年代ね。
だから振り返って、80年代、わたしは曲も1曲もできなくてね、東芝に行ったり大手に行くのもダメになったりして、それで世のなかデジタルになったりして......っていうようなことで、あの頃は自分の音楽の経験のなかでもどん底だったんじゃないかとしばらく思い込んでたんだけれども、「えっ、俺、そう言えば80年代ってオール三陸だったよな」っていうね。ええ。それは東京にいなかっただけで、まあいなかったって言うとおかしいけれども。だから静岡で「JanJanサタデー」やって、それで1年に2週間のツアーをやって、それは大変なツアーでしたよね。10年間やり続けました。
それでねえ、岩手っていうのはですね、四国より面積が大きいんだから。移動が大変だったり、あの狭い道だったり(笑)。あるときなんて洞窟でまでやったことあるんだな、なんかやるとこなくなっちゃって。自然に開いてる洞窟がありましてね、みんなロウソク持ってやったり。まあつまりね、ありとあらゆることをしたんですよね、三陸で。わたしの答が出るまでやってみたいっていうことを、受け入れてくれたひとたちもすごいと思うし。
■それは三上さんがご自身で企画されて?
三上:企画して。もちろん受け入れるひともいるわけですよね。三陸のひとたちも受け入れるわけですから。で、あんまり知られてないんだけれどもね、三陸岩手っていうのは大変な音楽王国でしてね、ジャズ王国ですよ。そこのジャズ喫茶の連中は、ちょっとずつ金出して、カウント・ベイシーを直接呼んで直接返すってことをやってるようなひとたちなんですよ。だからものすごく音楽が好きなひとたち。音楽もわかる、まあわかるって言ったらあれですけれども。ただ意外とフォーク・シンガーが生まれてないんですよ。ロック・シンガーも生まれてない。聞き手のプロって言いますかね。
■それこそ宮沢賢治なんかは、生前、仙台までレコードを買いに行ってるんですよね。盛岡から汽車に乗って。
三上:だから賢治っていうパブリシストがいるっていうことで安心してそういうことにハマれるっていうのもあるかもしれない。宮沢賢治ってものすごく大きいですからね、岩手のひとたちにとっては。
■我々にとってもでかいひとですからね。で、『怨歌に生きる』には、はからずとも陸前高田の写真が見開きで載ってらっしゃる。写真を見ていても、物凄い盛り上がりを見せていますよね。
三上:要するに三陸に行くきっかけっていうかね、『おんなの細道』っていう日活ロマンポルノの最後のオールロケ作品で、その後日活が潰れるんですけど、たまたまわたしも準主役でやって。それが物凄い厳しい撮影でね、神経が参りそうになった瞬間っていうのがあったんだな。あまりにも寒くて。あの寒い冬のロケで、ロマンポルノですから8割裸になってないといけなくて(笑)。いちいち着てたら余裕ないですしね。まあ裸ってわけじゃないですけども、何か羽織って待ってるという状態で。この年ではとてもできないけれども、20代でまだ丈夫だったからできたんですね。
で、神経しかないなっていうときに、人間ってああいう状態だと何か見るんですよ、幻ですわな。三陸っていうのは景色がいいんですよ。それが津波だったんでしょうね、いま思うと。それが後で"大感情"って曲になるんだけども。その縁で行くようになったんですよ。「何だろう? これ見たことのない景色だな」っていう。「感じたことのない予感だな」という。それでこだわっちゃったんでしょうね、いま思うとね。それがこの前の津波に繋がるんだと思いますね。きっとね。30年前に「えっ、何これ」というような感情があったんじゃないでしょうかね。
これは意外とわたしのなかでは繋がってることでね、そしてその去年の3月の16日にメキシコシティでアンダーグラウンドのアート・フェスティヴァルがあったんですよ。まあアンダーグラウンドだけじゃなくて、メキシコシティ挙げての祭で、ハービー・ハンコックも出てたぐらいの祭だから。1ヶ月ぐらい、ロンドンからパリから、世界中からミュージシャンが来て。それが3月の16日だった。それでわたしは、予感というかいんでしょうか......ヨーロッパでもアメリカでもなくてメキシコか、どんなところだろうなっていう、ある種の期待と不安のなかでどーんと来ちゃったんですよね。行く4日前に。
だから去年のいまごろはずっとメキシコ行くこと考えてましたよ。津波とか関係なくね。ところがメキシコっていうまだ見知らぬところに行くっていうある種の期待と不安が、それとも繋がってた気がする、予感で言えばね。だから物語がすっきり終わっちゃったような感じがあるよね、そういう意味では。だから車も全部止まってて、必死で羽田まで行って。なんか自分のなかでね、物語っていうか......だからあのとき見た「これは何だ」っていう景色はもしかしたら遠くメキシコを見てたのかもしれないし。だから初めてこう裏側から見たわけだよな。メキシコ行ってね。それでメキシコにもちょうど10年前に大きい地震があって15000人ぐらい死んだらしくて。物凄かったらしいんですよ、10年前ね、ちょうどね。そういう縁で行ったのかなと思ったりしましたけれども。だから、三陸、津波、いまの音楽、自分の立場っていうのはきれいには整理されてないけれども、きっと何かあるんだと思いますね。
(注)中津川
ウッドストックに触発された日本で最初の音楽フェスティヴァル「全日本フォークジャンボリー」。1969年8月、3千人規模ではじまったそれは1971年には2万を超える規模へと発展した。1回目には遠藤賢司、岡林信康、ジャックス、高田渡、田楽座、中川五郎など出演。三上寛は3回目に出演している。
取材:野田 努(2012年3月09日)
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE