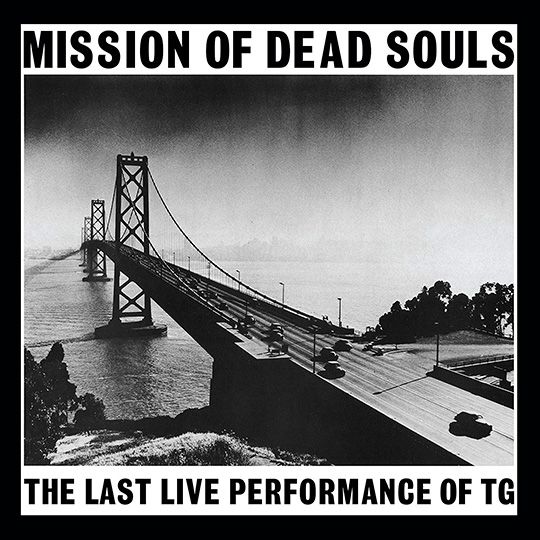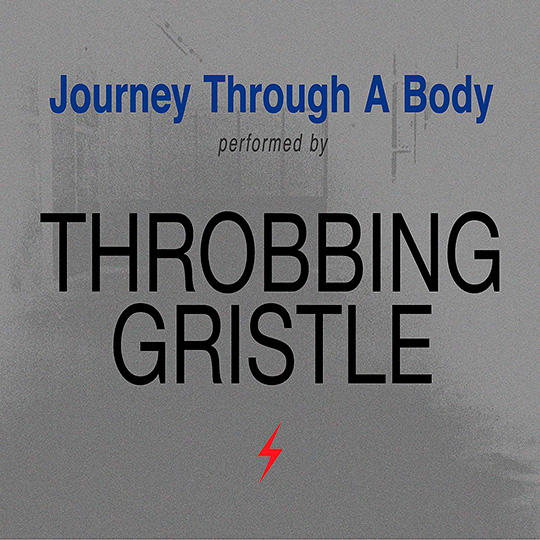MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - コージー、『アート セックス ミュージック』を語る
9月12日、(それはおそらくこの記事のアップ日)に、スロッビング・グリッスルの再発第二弾として、『Heathen Earth』(1980/一般的には最終作とし知られる)、『Mission Of Dead Souls』(1981/最後のライヴを収録)、『Journey Through A Body』(1982/イタリアのラジオ局のために制作された)の3枚がリリースされる。
また同時に、創設メンバーのひとり、コージー・ファニ・トゥッティの自伝『アート セックス ミュージック』の日本版も刊行される。
現在、日本で〈ミュート〉と契約しているトラフィック・レーベルの好意によって、今回ふたたびコージーのインタヴューを取ることができた。質問のいくつかはぼくが作成し、それを『アート セックス ミュージック』の訳者でもある坂本麻里子さんが、いつものように臨機応変にアレンジなりアドリブなどを交えて取材はおこなわれている。
『アート セックス ミュージック』は、COUMトランスミッションズ〜TG〜クリス&コージーというノイズ/インダストリアルの話であると同時にエロ本のモデルおよびストリッパーの物語だが、それ以上に、ひとりの女性のサヴァイヴァルとその人生哲学をめぐるかなり勇敢な回顧録と言える。原書が500ページ、日本版は二段組にしておよそ500ページ、平均的な単行本の3冊分というなかなかの大著だ。
以下、これもまた、ひじょうに長いインタヴューになるが、これでもかなり削ったです。どうか最後までお付き合い下さい。
だからなのよね、あなたがさっきも言っていたように、人びとがスロッビング・グリッスルに対する「神話」を抱くことになったのは。でも、わたしたちはすでにあの頃ですら、ギグのおしまいにマーティン・デニーを流すことでその神話を反故にしていたわけで。わたしから言わせれば、じゃあ彼らはいったいどんな神話に執着しているんだろう? みたいな。
■まずはあなたの『アート・セックス・ミュージック』の日本版を刊行できることをたいへん誇りに思います。しかしものすごい分量ですね。
コージー:ええ。
■この労作を執筆しようとした動機のひとつに、TGの成り立ちやその実態について歪んだ情報が流布しているということがあったということですが、よくぞ書いてくれたと思います。日本には昔から熱心なTGファンがいることはご存じでしょうか?
コージー:ええ、彼らの存在はずっと知っていたわ。ただ、わたしはこれまで日本に行ったことがなかったから……。そうは言ってもファンが存在することはずっと前から気づいていたし、かなり初期の頃から日本のレーベルがTGのアルバムをリリースしてくれていたわけで。だからわたしたちも、そうね、70年代後半〜80年代初期あたりから、日本にファンがいることは認知していたわ。それに、日本にはクリス&コージーのファンだっているし。というわけで……日本にファンがいるのはわたしも知っているし──だから、本が日本で出版されることになって本当にわくわくさせられている。うん、とてもハッピーだわ。
■最後の日記が2014年4月30日になりますが、刊行までおよそ3年かかっています。じっさいものすごい文字量の大著になりますが、執筆に当たってもっとも苦労されたところはなんでしょうか?
コージー:だからあの本はまるまる、わたしの人生についての本なわけよね。そして、わたしの人生で何が起きたか、ということについてであって。わたし以外の人間にとっての「こうすべきだった、こうするべきではなかった」という内容ではないし、だからわたしはああいう書き方であの本を書いた。というのも、あれがわたしの身の上に起きたことだった。あれらが(コージーにとっての)事実だった、と。で、あそこに書かれたことを信じずに、彼らが信じることを選んだなんらかの「神話」みたいなものについていきたいのであれば、それは読んだ人びとの自由、彼ら次第だわ。
わたしは別に、あの本から人びとがなにを得るのか、そこを指図するつもりは一切ないから。あれはわたしのストーリーであって、他の誰の物語でもない、という。というわけで……あの本の執筆中に、自分が知っていた以上のさらなる「嘘」が明るみになったのよね(苦笑)。あの点が、わたしにとってはもっとも難しかった。というのも、自分がその場に居合わせなかった状況では、知らないところでいったい何が起きていたかまったく知らなかったから。たとえば、わたしとジェネシスとの関係のなかでのいくつかの場面だったり。そこがもっとも苦労したところね。だから、わたしと彼の関係において、様々な事柄がどれだけ間違った形で伝わっていたのか、その度合いをわたし自身はまったく知らなかった、という。そんなわけで、その点を知ったときは……執筆中に何週間か足止めを食らわされた。自分の思いをしばらくの間どこか別の場所に持っていかなくてはならなかったし、その上で(気持ちを落ち着かせた上で)再び自分の物語に立ち返った、という。だから、あの部分はとても難しかったわ。一方で、あれを体験してとても良かった、というところもあってね。というのも、(苦笑)あのおかげでいまや、わたしも自分の過去を正しく理解できるようになったわけだから。
■ひとりの人間の人生が描かれているわけですが、ヒッピー・コミューンからセックス産業など、それ以上のものすごくたくさんのことがこの本には詰め込まれています。おそらく音楽ファンにとっては、COUMトランスミッションズ〜TG〜クリス&コージーの話がより知りたい部分なので、まずはそこから訊きたいと思います。
コージー:なるほど。
■ある意味では、COUMやTGというのは神話化されていると思いますし、サイモン・フォードの『Wreckers of Civilization』はその神話をより強固なものにしているかもしれません。
コージー:ええ。
■長いあいだ、それこそ1998年からその神話やストーリーが続いてきた、と。その意味で、あなたの本は偶像破壊的でもあると思うんです。そうした神話化されたTGの信者たちをある意味では裏切るというか、その神話をいちど破壊するというか、本当にリアルなTGの姿が明かされたわけですよね。もちろん、いわゆる「暴露本」だ、というつもりはないのですが、一部の読者にとってはこの本はショックだったんじゃないか? と。昔ながらのTGファンからの、そのへんに関する反応はありましたか? あなたの本はTG「神話」を売りつけられてきたファンたちを動揺させたと思いますか?
コージー:ええ、たぶんそうだったんでしょうね。けれども大事な点は、では、その「神話」を支えるために、COUMトランスミッションズおよびスロッビング・グリッスルのメンバーだったひとりの人間がこれまでプロモートしてきた「神話」を支えるために、わたしは自分自身の人生体験の数々を犠牲にするだろうか? ということであって。それが正しい行為とはわたしには思えない。この星の上で共に生きている人間同士として、わたしたちはお互いになにかを負い合っているわけよね。ということは、ただお互いに対して親切に振る舞うだけではなく、敬意も抱き合って生きるものだ、と。ところがそのリスペクトの念は消えてしまったわけ。だから、ここでジェンダーの問題を持ち出させてもらうけれども──COUMトランスミッションズとスロッビング・グリッスル唯一の女性メンバーだった身として、わたしにはいっさい発言権がない、ということになる。あれらのグループの実際がどうだったか、それを声に出すことはわたしにはできない、わたしが黙らされるという犠牲を払うことでそれが成り立っている、と。となると、それはやはりどこか間違っているわよね、人びとのなかにあっという間に事実とは違うヴァージョンの話が流布してしまうわけで。
で……それはなにも、スロッビング・グリッスルそのものを破壊しよう、ということではないのよ。というのも、わたしはどんな風に、スロッビング・グリッスルがどんな風にはじまったか、それをありのままに本のなかで説明したし、その背後にあった興奮もちゃんと書いた。それに、わたしたち全員がTGに送り込んだ突きの勢いについても描写したしね。あれは単にひとりの人間のやったことではなかったし、ひとりの人間のアイディアから生まれたものでもなかった。もちろんCOUMトランスミッションズは、ジェネシスがあのグループを命名したことで始まったものだった。けれどもそれ以降、COUMは参加者みんなのものになっていったわけ。「COUMは誰もに属するもの」という、それはそもそもあのグループの気風の一部だったんだしね。ということは、ではどうしてわたしが自分自身のストーリーを本に書く行為が、(苦笑)スロッビング・グリッスルのそういう気風を破壊するということになるのか? という。それはつじつまの合わない話よね。
それに、誰かが神話を信じようとすること、それだっておかしな話であって。というのも、COUM/TGは神話以上にもっと興味深いものだから。だから、あの当時実際になにが起きていたのか、そこをまず理解しなくてはいけないし、それらを知った上で、いままで知ってきたことをまだ信じ続けていきたいか、その判断を自分で下してもらわないと。というのも、あそこで起きていたのはかなり害をもたらすものだったし、そこでわたしたちもツケを払わされて……とは言っても実際のところわたしたち3人(コージー、クリス・カーター、スリージー)は、スロッビング・グリッスルをなんとか軌道に乗せ続けたのよね。3人以外のメンバーとの間で起きた様々な難関にも関わらず、わたしたちはスロッビング・グリッスルをあるべき形で具体化させることができた、という。その点は、人びとも「すごい、よくやった」と考えるべきだと思う。いろんな困難が生じたにも関わらず、スロッビング・グリッスルは人びとが「そうあるべきだ」と考えた、そういう形でちゃんと存在していた。というのも、なにが起きてもTGはTGで変わらない、かつてあったそれそのものの強さ、そしてパワーをいまだに備えているわけで。ただ、いまや人びとは、その内面に関するもっと深い洞察を得ることになった、という。どんな風に物事がはじまっていったのか、人びとがその点を知るのは大事なことだとわたしは思っていて。それを知ったからと言って、別になにかが損なわれることはないだろう、そう思っているし。
■ええ、それはないです。たとえば、『RE/SEARCH』マガジンの4&5号(1982年)に掲載されたスロッビング・グリッスルの取材を読むと、「スロッビング・グリッスルのインタヴュー」と銘打たれている割りにテキストのほぼ90%はジェネシスが発言しているんですよね。
コージー:フム。
■彼に焦点が当たり過ぎだ、という。いまの自分からすればスロッビング・グリッスルはリーダー格不在の真の意味で民主的なバンドだったのに、当時のメディアでは誤ったバンドの提示の仕方がおこなわれていたんだな、と感じます。あれじゃ、まるで「ジェネシスのグループ」という印象ですし。
コージー:ああ。でも、その点に関しては、本でも触れたと思うのよね。だから、わたしたち3人は自分の声を大きく張り上げるとか、自分自身を宣伝することに興味がなかったわけ。そういうことにわたしたちは入れ込んでいなかったけれども、ただ、ジェネシスは自己宣伝を楽しんでいたし、人びとから注目を浴びるのをエンジョイしていた、と。でも我々残る3人はそれよりももっと、音楽を形にすることやテクノロジーetcに関する色んなリサーチにもっと力を注いでいたのよね。それにまあ、ああした取材のいくつかは、わたしたち自身が知らない間におこなわれてもいたんだしね!
■はっはっはっ!
コージー:──だから……(苦笑)バンドの一員にも関わらずそのなかで個人的な自己プロモーションをおこなっていた人間がいた、ということだし、ずっと後になるまでそういう行為がおこなわれていたのをこちらも知らずにいたわけ。それは良くないことよね。それによって問題が引き起こされ、バンドにひびが入りはじめてしまった。というのも、あのバンドは個人云々の存在ではなかったわけだから。ところが、バンドがいったん終わったところで、また他の誰かがバンドを宣伝するようになったわけだけれども、彼らはそこでバンドの名前を傷つけていった、という。そんなわけで、わたしたち3人はまったく関与していないところで、とても奇妙な、心理的なあれこれが起きていた、ということになるわね。それは他の誰かが勝手にやっていたことだった、という。
■でも、あなたの本のおかげでわたしたち読者にもスロッビング・グリッスルの真の姿がクリアに掴めるようになりました。4人が平等な民主的な、しかもまったくDIYのバンドとしてのTGを描いたということは大きいと思います。
コージー:ええ。
■にしても本当に、可能な限りご自分たちでなにもかもやっていたんですよね。DEATH FACTORYのTシャツもあなたの手製だったわけで。で、このDIYの気風、Tシャツからプロモ写真はもちろん音楽まで、制作/生産面に関して可能な限り直接関わるという、このTGの気風はどこから生まれたんですか?
コージー:それはもともとは……取材の最初の方で、あなたも本に書かれたヒッピー文化について触れていたわよね? で、あの頃、1968年、69年頃から、わたしはもう(ヒッピー系の)Tシャツだのズボンだのを作って売っていたわけだし。単純な話、当時自分たちの身の回りには買いたくてもああいうものは売られていなかったし、それを作ってくれる場も存在しなかった。だから当時のわたしたちのDIYの気風というのは、自分たちの求めていたものは通常の商業ルートでは手に入らなかったし、したがって自分たちで作るほかなかった、と。ところがそれをやった結果として、DIYなら実際、自分のやりたいことを完全にコントロールできるじゃないか、という点に気づかされるのよね。なにもかも、完全に掌握できる。というわけで、その点はスロッビング・グリッスルにとって非常に重要だったし、またクリスとわたしにとっても、クリス&コージーのはじまりからいま現在に至るまで、いまだに重要な点であり続けている。
■ロバート・ワイアット、AMM、ジョン・ダンカンといった名前がわりと重要な場面で出てきますが、こういうところからもいままであまり語られなかったTGの音楽的背景を伺い知ることができました。それはたぶん、TGやあなたたちのことを「インダストリアル・ミュージック」という括りでわたしが捉えていたからだと思います。あれら3組の名前は必ずしもその括りには入らないわけで、その意味で驚きだった、ということでしょうが。
コージー:思うに、いまあなたが例にあげた名前を考えてみれば……というか、それら以外の影響のいくつか、それこそもっとポップ音楽系な人たちのことを考えてみてもいいと思うけれど、彼らのことをじっくり考えてみれば、実は彼らのアプローチもわたしたちのそれととても似通ったものであるのがわかるはずだわ。非常にパーソナルで、心のなから、お腹の底からから出て来たものであり、そして自分のやることに対する自分自身を信じるパワーを持っている、という意味でね。だからなのよ、繫がりが存在するのは。それは必ずしも音楽的な意味での繫がりではなくて、その人物そのものとのコネクションかもしれない。ただ、彼らには、彼ら自身の、そして彼らの作品の背後に、そういう打ち込みぶり、そして意志の強さとが備わっている、という。
■ジェネシス・P・オリッジの素顔について書くことはやはり神経を使われたことと思います。彼はあなたたち3人に続々と困難や苦情のタネを持ち込んだわけですが、それでもはやりフェアに書かなければならなかったわけだし、かつ本として客観性も維持しなくてはいけなかったわけで。かつての恋人であり、コラボレーション相手であり、しかしいつしか破壊的な存在になっていった、そういう人物を描くのは難しかったのではないかと思うのですが。
コージー:まあ、わたしがこの本を書きはじめた頃──いつになるかしらね、2015年には書き終えていたわけだから……
■ああ、そうだったんですか(※英オリジナル版の出版は2017年)。
コージー:ええ。だから、さっき話に出た「日記からの最後の引用が2014年」というのも、もっと意味がわかりやすくなると思う。というのも、あの時期からわたしは本の執筆をはじめていたし、そこから出版社のフェイバーがこちらにアプローチをかけてきて。と同時にその頃、わたしは「ハル・シティ・オブ・カルチャー 2017」企画にも取り組んでもいて(※シティ・オブ・カルチャーは4年に一度選ばれる「イギリス文化都市」で文化やアート振興を目指し長期にわたって多彩なイヴェントが組まれる。コージーの生まれ故郷ハルは2017年にその座を射止め、ハルが初期の拠点だったCOUMトランスミッションズの大々的な回顧展も開催された)。
というわけである意味なにもかもが、わたしにとってきちんとこぎれいなパッケージとしてまとまっていった、みたいな。フフフッ! 自分の本の執筆、そしてCOUM回顧、という形でね。わたしがCOUM展のためにやっていたリサーチ、それがまた本向けのリサーチにも流れ込んでいた、という。そんなわけで、エモーショナルなアプローチと共に、わたしはある種客観的なアプローチも用いることになった、と。この、パラレルを描くふたつのアプローチの仕方、これが実際、わたしには上手く機能したのよね。というのも、それならわたしは客観的であると同時にまた、主観的にもなれるわけで。で、わたしは自分の本を、なんというか……なにも「積年の恨みを晴らす」めいたものにしたくはなかったから。そういう本ではないんだしね。
■(苦笑)はい、もちろん。
コージー:そうではなくて、これはわたしの人生についての、わたしの物語を書いた本だ、と。で、とある誰かがわたしに対して、あるいは他の面々に対して本当にひどい仕打ちをしてきたこと──それは彼らの側の、その人間の問題であって、わたし自身の問題ではないわけ。そういう連中は、わたしのストーリーのなかに登場するキャラクターに過ぎない。彼らがあまりにひどい振る舞いをしたことについても、(苦笑)それが彼らの人なり/実像なんだから仕方ない、と。その事実を変えることは、わたしにはできなかったしね。それと同じで、逆に誰かがわたしに本当に良くしてくれたら、その事実を書き換えるつもりはないわ。それに実際の話、わたしの物語にしても、他の誰かがしでかした悪質な行為のいくつかに負っていたんだし。というのも彼らのそうした行為のせいで、わたしが立ち向かい対処しなくてはならないシチュエーションも生じたわけで。で、それらの行為はわたしの人生に本当に大きなインパクトを与えた、と。
というわけで……当時なにが起きていたか回想する意味では、それが困難だった、ということは一切なかったわ。というのも、いろいろな状況をくぐり抜けていた時点で、その都度それらに対処し乗り越えていったから。ただ、さっきも言ったように、本当に困難を感じた点というのは、本を書いていくなかでわたしはある意味欺瞞の程度の深さを明るみにすることになった、その根深さを初めて知った、そこだった。だから、自分というのは本当に、彼が敵対していたものの縮図的な存在だったんだ、その事実に気づかされたことは難しかったわね。悲しいことに、彼はそれらすべてを否定しているけれども──彼がいつも使う手口、それは「敵対」なわけだし。あの点は、だから厄介だった。
■ある意味、本を書くことで嘘を発見し、あなたは再び傷つけられた、ということになりますね。
コージー:そうね。
■もちろん、そのつもりで執筆したわけではないけれど、結果的に更なる嘘がばれていった、と。
コージー:そうそう、結果的に、自分が気づいていた以上の嘘があったことが明るみになった、という。
■(苦笑)ひどいですね。
コージー:ほんと、まったくよね。
■やぶへびになってしまった、と。
コージー:ええ、そういうこと(苦笑)。まったくもう、キリがないっていうね(苦笑)。クックックッ……。
■とくに後半の6章ぐらい、TG再集合のくだりでジェネシスのやったとんでもない仕打ち等々、書いていて決して楽しくはないことにも触れていますよね。普通の人だったら伏せておきそうなところも、あなたは本に収めています。ありのままを伝えよう、あなたの経験をできるだけ忠実に書き記そう、ということだと思うのですが。
コージー:それはそうよ。だから、あれらすべての事情がまた、わたしのストレスを大きくしてもいたわけで……それ以前に、わたしとクリスは息子を病気で失いかけた、そんな大きな心的負担もこうむっていた。ところがあの時点で、わたしは他の誰かから余計なストレスまでもらう羽目になった。しかもその人間には明らかに、わたしとクリスが当時どんな状況をくぐっていたか、そこに対する同情心が一切欠けていたわけで。とにかく、心労の上にさらなる心労が重なっていって。それで遂には、わたしは疱疹で倒れることになったし、体調も相当悪くなって。自分たちの上に山積みにされていったすべてのストレスの結果がそれだったわけよね。
で……と同時に、わたしたちにはスロッビング・グリッスルのファンたちに対する責任もあったわけで。だから、あれはもう──「これがわたしの人生。こんなにつらいのに、どうやったらこの人生を好きになれる?」みたいな(苦笑)。あれはわたしの人生のなかでも大きなポイントだったし、人びともスロッビング・グリッスル再結集劇については読みたがるだろう、と。ただ、あの背後で起きていたのは、わたしたちが味わった数々の困難の物語だったのよね。
けれども大事な点は、では、その「神話」を支えるために、COUMトランスミッションズおよびスロッビング・グリッスルのメンバーだったひとりの人間がこれまでプロモートしてきた「神話」を支えるために、自分自身の人生体験の数々を犠牲にするだろうか? ということであって。それが正しい行為とはわたしには思えない。
■『アート セックス ミュージック』にはユーモアもありますよね? クリスが何気に感電して、部屋の隅にまで飛ばされたり──
コージー:(苦笑)ああ。
■それとか、彼がドリルで指に穴を開けてしまい、その数日後に今度は別の指を折った場面とか。
コージー:(笑)そうね、あれは可笑しい。
■よく考えたらすごいことをさらっと書いていますよね。クリスの健康面で言えば冗談じゃなかったでしょうが、あなたの淡々とした書き方が逆に笑いを誘うところがあって。
コージー:でも、あれが……(笑)だから、ユーモアはわたしの人生のなかで大きな役割を果たしてきた、ということ。それから、「笑い」ね。っていうのも、わたしはべつにダークで陰気な、鬱でふさぎ込んだ人間ではないんだし。人生を愛しているし、楽しんでいる。で、わたしは他の人たちには見つけられないような場所にも、ユーモアを見出してしまうのよね。だから……そうねぇ、人生の大半を自分は笑顔を浮かべながら過ごしてきたんじゃないか、自分ではそう思ってる。もしかしたらそのせいで、わたしのかいくぐってきた色んな問題が逆にもっと際立つことになっているんじゃないか? とも思うし。
でもほんと、ああいう「手榴弾」(※本文中に出てくるジェンからの報復/嫌がらせの比喩)にはなんとか対応しなくちゃいけないのよね。それにユーモアで応じてやろう、と。ユーモアはわたしの人生のとても大きな部分を占めてきたし、とても、とても大事なことだわ。
■そういうユーモアというか茶目っ気は、スロッビング・グリッスルのメンバーも共有していましたよね。
コージー:そうね。
■たとえば、『20ジャズ・ファンク』のプロモ写真で──
コージー:(苦笑)ああ。
■ジェネシスがYMOのシャツを着てかっこつけていたり、TGのライヴの最後をマーティン・デニーで締めるっていうことにも通じているように思います。
コージー:ええ、だからアイロニーもあったわけよね。で、あれはちょっとこう、「ミューザック」というコンセプトで遊んでみた、というところもあったし。だから、スロッビング・グリッスルを通じてはらわたに響くとてもフィジカルななにかを体験した後で、聴き手を軽く落ち着かせてあげよう、と。あの経験の後には最高に素晴らしいマーティン・デニーのミューザックが待ち構えている、というね。彼はレズ・バクスターなんかと共にひとつの新たなジャンルをはじめたんだから、それってすごいことだと思う。
■他愛のないユーモア、いたずらっ子めいた側面があったわけですね。
コージー:そう。だから、スロッビング・グリッスルとは真逆なことよね。
■そのふたつは、TGのコインの裏表だったんですね。
コージー:だからなのよね、あなたがさっきも言っていたように、人びとがスロッビング・グリッスルに対する「神話」を抱くことになったのは。でも、わたしたちは既にあの頃ですら、ギグのおしまいにマーティン・デニーを流すことでその神話を反故にしていたわけで。わたしから言わせれば、じゃあ彼らはいったいどんな神話に執着しているんだろう? みたいな。
■(笑)。
コージー:それにその神話は、当時のスロッビング・グリッスルすら喧伝していないものだったんだしね。わたしたちはそういう神話を絶えず自分たちで破壊してきたし、TGを終結させたのもそれだった。そうすれば、神話もなくなるわけだし。その点を人びとは誤解していたのよね。TGというのは、人びとがTGにインスパイアされて彼らがそれぞれ自ら作品を生んでいく/仕事していくための、その媒体を提供する存在だった。だから、わたしたちは人びとのために色んなドアを開けていった、ということ。せっかく開けたそのドアを人びとが閉ざしてしまい、わたしたちの実際の姿とは異なる「TGとはなんだったか」を彼らに定義してもらうことは、こちらは望んでいなかった。
取材:坂本麻里子+野田努(2018年9月12日)
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE