MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Interviews > interview with BORIS - 往復するノイズ
バンドの中での三角形と、バンドとプロデュース、エンジニアの三角形がバランスよく進行しましたね。(Atsuo)
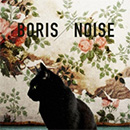 BORIS - NOISE Tearbridge |
|
■アナログ盤 BORIS - NOISE Daymare |
A:それで今回『NOISE』ではバンドに立ち返って演奏に集中して。表層的なテクスチャーとか肌触りみたいなポスト・プロダクション部分を成田さんに。サウンド・エンジニアの中村さんが音楽としての骨格の強さを構築してくれました。バンドの中での三角形と、バンドとプロデュース、エンジニアの三角形がバランスよく進行しましたね。
■ボリスは過去作品をかえりみても、外に仕事を振らずにすべて自分たちで完結していた時期もあると思うのですが、現在そこを外に振ってゆくということは、そこに新たな可能性を見い出しているということでしょうか?
A:そうですね。いや、できるんですけどもうボロボロになるんですよ。
■どういうことですか?
A:全作業を受け持つと……。曲とバンドの関係性が猛獣ショウみたいな、猛獣使いみたいな……。
(一同笑)
A:……猛獣っていうよりはキメラだよね?
T:なんか見たことがない想像上の生き物みたいな。
A:お互いがこう鞭でバシッ! ガブッ! って噛まれたり、いつも戦っている感じがあった。その暴れているイメージをどうにか焼き付けるのにかなりの労力、集中力を使う。それは自分たちで暴れさせているんですけどね(笑)。曲とつくり手がお互い暴走し合ってボロボロになってゆく。けっこう疲れるんですよね。
■なるほど(全然わかっていません)。ただ、先ほどのお話にあったみたいに、作っている段階では大文字BORISなのか小文字borisなのか、はたまたBorisなのかということは考えていないとおっしゃっていましたが、それでも小文字borisは大文字BORISやBorisに比べるとジャム色は強いように感じていました。しかし、要はすべて同じようにジャムから生まれて、それに対しての外の方々の作業の中で聴こえ方が変わってゆくということなんですかね。
A:ここ何年かはTakeshiがデモをつくって、それをバンド・アレンジしていくっていう手法も取り入れていますけど、基本はジャムですね。今回のリード曲、“Quicksilver”も、ジャムって「あ、できた」みたいな感じでした。ジャムだから、基本的に繰り返しとかサビみたいな構造的な作曲をしていない──日本の音楽の方法論的な部分でいうサビってところがなかったり、リフレインがホント少ないんですよ。どんどんどんどん展開していっちゃう。
■個人的な好奇心でお訊きして申し訳ないのですが、生活の中のどれぐらいの時間を制作に割いていますか? ボリスは3人での活動歴がとても長いと思うのですが、普段どのくらい3人で制作に臨んでいるのか、いち音楽家の僕としては単純に気になります。
A:平日は仕事しよう! というふうに決めていますよ。
■平日はガッツリですか?
A:うん。昼から。やることがなかったら「ちょっと録ろうか?」みたいな感じ。
T:リハーサルスタジオに入って、レコーダー回して。
A:一応、皆さまのおかげでこうして生活させていただけているので、ちゃんと仕事として捉えています。
■スッゴイっすねー……(溜息)。
A:このやり方がいいのか悪いのかはわからないですけどね。ツアー中に刺激を受けることが多いので、帰ってきたら直ぐ「スタジオ入ろうか?」ってなりますね。
自然の現象と音楽が生まれる現象って同じことじゃないですか。音楽って空気が振動している現象であるし、水が降っていることとか、火が燃えていることとか。そういう自然の現象に匹敵する情報量がないと、人の目とか耳って楽しめないんじゃないかな? (Atsuo)
■話が飛んでしまいますが、名作『flood』以降、現在まで僕にとってボリスは水のイメージがまとわりついています。それはリリックであったり、タイトルであったりさまざまな形ではあるのですが。しかし同時にボリスはデザート・ロックにはじまるようなカラッカラのドライヴ・チューンが根底にあるとも捉えられますし、そういった意味では相反するふたつの要素が混在しているようにも思います。そのあたりは意識的なのかなと。
A:いや……、僕が「雨男」ってくらいですよ。
(一同笑)
A:そういった自然の現象と音楽が生まれる現象って同じことじゃないですか。音楽って空気が振動している現象であるし、水が降っていることとか、火が燃えていることとか。そういう自然の現象に匹敵する情報量がないと、人の目とか耳って楽しめないんじゃないかな? なんかグリッドに沿ってやる音楽とか、均一なループとか、規則的なことは僕らにはできないし(笑)。
グダグダなズレとか、オーガニックな感じでしか演奏ができない。そういった意味では今回『NOISE』はかなりそっちの方に寄っていったかな……。
T:構築するってことより、自分の内面から自然にグワァーって流れ出てきてしまうような、そういう意味でのオーガニック感。
A:単純に一点でアタックを「ダン!」って合わせるアレンジにしても「ダワァン」とハミ出ちゃうみたいに合わない。合わないときの情報量っていうか、そういう表情が出ちゃうことが僕ららしさなのかなって、ここは「良さ」として再認識しています。
■僕はそのあたりをすごく深読みしていて、ボリスはメルヴィンズの同名曲に由来するように、アメリカの乾いた音楽の影響で生まれていながらも、たとえば日本の文化や民族性において、湿度──という表現を僕はしばしば用いますが──そういった部分を意識的に落とし込んでいるというふうに捉えるのは考え過ぎでしょうか?
A:影響受けてやっても同じにはならないですよね。体の大きさも違うし、楽器の鳴りも違うし。
■電圧とかも違うッスよね。
T:湿った空気を震わせているのか、乾いた空気を震わせているのか、とかもね。
A:あんな大きな体の人たちと、こんな細い華奢な女の人(Wata)が同じ条件でギターを弾いてもやっぱりぜんぜん違う音になる。そういったことを思う機会もたくさんあったけど、逆に日本人らしいグラデーションというか、階調の多さみたいなものも売りになると思っています。
取材:倉本諒、野田努 写真:小原泰広(2014年6月20日)
Profile
 倉本 諒/Ryo Kuramoto
倉本 諒/Ryo Kuramotocrooked tapes代表、イラストレーター兼スクリーン・プリンター。
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE