MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with BORIS - 往復するノイズ
■CD(ALBUM+SINGLE)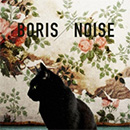 BORIS - NOISE Tearbridge |
|
■アナログ盤 BORIS - NOISE Daymare |
海外のアーティストとの交流の中で、お互いの国のアーティストやシーンに関する意見交換は必至であり、筆者の経験においてはその中でボリスの名が挙がらないことはまずない。名義の表記にはそのときどきの音楽性の差によって使い分けがあり、ロックの中心へと向かう大文字のBORIS、ロックの外側へ向かう小文字のboris、たとえばそうした二項の往復の中に、90年代から誰よりもワールドワイドに活動をおこなってきた彼らだからこそのジャパニーズ・ヘヴィ・ロックがある。2011年発表の『New Album』からはメジャー・リリースとなり、彼らは日本のロック史における新たなる地平線を提示した。
そして、このたび最新作『Noise』が発表される。ボリスにおけるインターナショナルとは、ボリスにおけるフィジカル・リリースとは、ボリスにおけるノイズとは、ロックとは? アルバム・タイトルとは裏腹に、近年でもっとも音楽的な作品となったともいえる『Noise』の深淵にダイヴする! ……ということでインタヴューに向かいましたが、なにぶん過去の思い入れも深いバンドなのでおそろしいほど緊張してしまい筆者はほとんどホワイトアウト状態でありました。(倉本)
■BORIS / ボリス
1992年に結成され、現在はAtsuo、Takeshi、Wataの3人体制で世界的な活動を続けるロック・バンド。これまでにおびただしいリリースがあるが、2000年代には『Amplifier Worship』『あくまのうた』『PINK』などの成功によって海外からも絶大な支持を集めるようになる。2011年に初のメジャー・リリースを行い、活動をさらに多元化させた。最新作は本年リリースの『NOISE』。
A:Atsuo
T:Takeshi
W:Wata
N:野田
当初はすごくブルータルでノイジーなアルバムになりそうな予感だった。それで、そのタイトルが降りてきて、終わってみたら逆にいちばん音楽的なアルバムになっていたんです。(Atsuo)
■はじめに、今作『NOISE』は、ロックの中心へ向かうもの=大文字BORISとしての作品、という認識で間違いないでしょうか?
A:う~ん……。なんか、完成したら今までの中で一番音楽的なアルバムができたなと思って。だから今回は大文字BORISでいいかなーと。
■毎回、最初に小文字borisか大文字BORISかというコンセプトを決めているわけではないのですか?
A:そうじゃないですね。
■完成していく段階で振り分けるんでしょうか?
A:まぁ、だいたいそうかな……。作っている段階では何も考えてないことが多いので、できあがったら「こっちだね」みたいに。
■アルバム・タイトルが『NOISE』とのことですが、ボリスは過去作も含めて象徴的なアルバム・タイトルが多いように見受けられます。先ほどおっしゃった、いままででいちばん音楽的であるアルバム『NOISE』に込められた意味は何でしょうか。
A:プリプロが全体的にでき上がった頃ですかね、タイトルとしてフッと「Noise」って言葉が降りてきて……。去年の春ぐらいですかね、「あぁ、もうこの感じでいこう」と。当初はすごくブルータルでノイジーなアルバムになりそうな予感だった。それで、そのタイトルが降りてきて、終わってみたら逆にいちばん音楽的なアルバムになっていたんです。
■前作『Heavy Rocks』ですが、なぜ再びかつてと同じタイトルを冠したのでしょうか? BORISにとっての「Heavy Rock」に対する再定義ともとらえられるのですが。
A:あの時は、『Attention Please』と『Heavy Rocks』を同時にリリースしたんですが、その兼ね合いの中で、Wataのヴォーカル曲だけの『Attention Please』に対して、その当時の「Heavy」感を詰め込むという感じで、アルバム相互のキャラが別れていった。それで『Heavy Rocks』と同じタイトルでもいいかな? ってなりました。
■ジャケットのデザインも同一で色ちがいということだったので、ボリスとしてのへヴィ・ロックの再定義があったのかなと思いまして。
A:そうですね。ただ、非常に感覚的なものですよ。言葉でこう定義するって感じでもなく、いまはこんな感じかなと。僕らのフィーリングとしての「Heavy Rock」が、あのときはあんな感じだった。
■ロックのヘヴィ性に対する感覚の変化であると。
A:そうですね。やっぱり僕らの意識の中だけではなく、周りの状況、認識も変わっているじゃないですか。それってすごく大きいことですよね。
買ってくださるお客さんが手に持って、開封して、聴くという、フォーマットそれぞれのシチュエーション、流れまで含めてデザインしています。リスナーが作品に触れている、見ている時間も音楽の重要な要素です。(Atsuo)
■なるほど。逆に僕にとってボリスの変わらない部分ということで、ひとつお訊ねさせてください。
ゼロ年代半ばからヴァイナルの需要がグンと伸びた理由のひとつに、プロダクトとしてのフェティッシュなマーケットの拡大があげられると考えています。時期的に捉えてもボリスのフィジカル・リリースの方法論はそれらのパイオニアとも言えると思います。また音質の点でもCDとヴァイナルのマスタリングを明確に差別化してきたと思います。ボリスのフィジカルへの異常ともいえるそのこだわりとは何なのでしょうか。
A:CDとLPでもフォーマットが結構違うじゃないですか。サイズであったり、収録面が分かれていたり。買ってくださるお客さんが手に持って、開封して、聴くという、フォーマットそれぞれのシチュエーション、流れまで含めてデザインしています。リスナーが作品に触れている、見ている時間も音楽の重要な要素です。
■出会いってことでしょうか?
A:はい。経験していく過程というか。それもイメージして。やっぱり音だけの世界観じゃなくて、聴いていただける人がいて、手に取ってもらうっていう経験があって、参加してもらうところまで含めて作品ですね。
■まだ僕の手元に届いていない、来る『NOISE』2xCDと2xLPのフィジカルへのこだわりがあれば教えて下さい。
A:国内盤は友だちのReginaっていうデザイン・チームのリョウ君にやってもらいました。ジャケットはもう公開されていますけど、彼なりの「Noise」をこちらに提示してくれています。
■印刷とか毎回異常にこだわっているじゃないですか。今回はどうなんですか?
A:国内盤に関してはそういったところ、ギミックではなくてもっとこう……見えない空気感とか、そういうところをつくり込んでいる感じかな。海外盤の方は僕がデザインを担当していて、そっちはまあ特色とか光沢感とかのギミック有り。Web上では絶対再現できないような。僕はそういうデザインしかできないんで(笑)。
■でもそこはやっぱりすごく大事じゃないですか。僕は音源を買う要素としてそこがなければはじまらないみたいな部分もあったりするので。
取材:倉本諒、野田努 写真:小原泰広(2014年6月20日)
Profile
 倉本 諒/Ryo Kuramoto
倉本 諒/Ryo Kuramotocrooked tapes代表、イラストレーター兼スクリーン・プリンター。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE