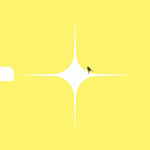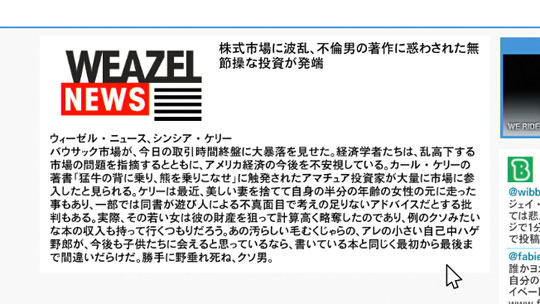恐るべきインターネット時代のならず者集団、デス・グリップスは高速で休みなく走り続けている。彼らの話題は尽きることがない。自身のレーベル、〈サード・ワールズ〉のサイトを閉鎖したり(その後復活)、傑作“陰茎”アルバム『ノー・ラヴ・ディープ・ウェブ』を〈エピック〉に無断でフリーでリークしてメジャー契約を解除されたり(のちになぜかフィジカル・リリース)――突然ライヴを中止したことも1度や2度ではない(昨年の来日公演は無事に開催されて本当に良かった……)。
いや、もちろんネガティヴな話題ばかりではない。ライヴをキャンセルしようとも、彼らは新曲やヴィデオをコンスタントにリリースし続けている。そのなかにはプロディジーのクラシック、“ファイアスターター”のリミックスもあった。ドラマーのザック・ヒル(ちなみに『ノー・ラヴ・ディープ・ウェブ』のジャケットに写っているものは彼の身体の一部だ)は自身が脚本・監督・音楽を務める短編映画を作っているという噂もある(「そんなもの作ってはいない」と否定する声明も出しているが……)。
ひょっとしたら、彼らにとっては停滞こそが忌避すべき死なのかもしれない。その一方で、デス・グリップスは死を欲するかのように生き急いでいるようにも見える。最初のミックステープ『エクスミリタリー』から数えて4作目にあたるこのフリー・アルバム、『ガヴァメント・プレイツ』(ダウンロード・イット!)においてもまたデス・グリップスの態度や表現は過激化と先鋭化の一途をたどっており、MCライドは再びギリギリの縁に立って両手の中指を突き立てている。露悪的なまでにタナトスを剥き出しにして、死へとひた走ることによって駆動するかのような音楽――ピッチフォークは「過去もなく、未来もない現在の音楽」と評している。現在時制によってのみ構成されたデス・グリップスを聴いていると、死の欲動を攻撃性という点に特化して21世紀的な表現方法で音楽化するとどうなるのか、という実験に巻き込まれているかのような気分にもなる。
タイニー・ミックス・テープスはなぜかポール・ヴィリリオを引き合いに出しているが、絶対的な光の速度が現実空間や社会を解体させていることを分析したヴィリリオの仕事を思い出してみれば、デス・グリップスの態度や音楽はまさに速度と情報の暴力だと言えるだろう。
ともあれ。カニエ・ウェストの『イーザス』よりもずっと暴力的で恐ろしいインダストリアル・ノイズにまみれたラップ・ロックのアルバムであるこの『ガヴァメント・プレイツ』は、これまでの作品のなかでももっとも騒々しく、耳を痛めつける音で溢れかえっている。おそらく、デス・グリップスもまた怒っている。怒りを増幅させて、それを吐き出している。
しかし、MCライドのラップはますますシンプルになり、曲によってはほとんど素材のような扱いとなっている。もはやラップというよりも叫びやフレーズの反復に終始し、曲によっては激しくチョップされてしている。
冒頭の“ユー・マイト・シンク・ヒー・ラヴズ・ユー・フォー・ユア・マネー・バット・アイ・ノウ・ワット・ヒー・リアリー・ラヴズ・ユー・フォー・イッツ・ユア・ブランニュー・レオパード・スキン・ピルボックス・ハット”(ボブ・ディランの曲名のパロディか)は、ガラスの割れる音とサイレンのような電子音、左右のチャンネルから耳を圧迫する壊れたワブルベース、ジョーカーのような笑い声、そしてザック・ヒルの重たいドラミングで聞き手を圧倒する。“ディス・イズ・ヴァイオレンス・ナウ(ドント・ゲット・ミー・ロング)”や“フィールズ・ライク・ア・ウィール”、“アイム・オーヴァーフロウ”の性急でジャングルめいたビートは、悪夢をプレゼンするダンス・ミュージックとして提示されている。もともとデス・グリップスのビートは複雑で展開が多いが、“ビッグ・ハウス”や“ガヴァメント・プレイツ”のそれはジュークを思わせるせわしない動きを見せつけている。
6分にも渡る“ワットエヴァー・アイ・ウォント(ファック・フーズ・ウォッチング)”は、デス・グリップスらしくいくつかのパートで構成されている。時折挿入されるダウンテンポのノイズ・パートはレイムやそういった類のインダストリアル・ビートとほぼ同じ次元で鳴っている一方、性急なダンス・パートは焼けただれた、あるいは壊死したEDMの残骸のような暴力的な臭みを放っている。
アルバム中もっとも重要な曲はおそらく先行曲の“バーズ”で、ここではまたザックのドラミングとアンディ・モリンakaフラットランダーのプログラミングが組み合わされており、ビートの緩急がどんどん激しく変化していく。MCライドの声は奇妙に歪んでいるが、じつに重たくパラノイアックな“Fuck you”を吐き出している。
デス・グリップスにはメランコリーはない――もちろん『ガヴァメント・プレイツ』もその例外ではない。あるのは直接的な攻撃性、凶暴性、速度、ノイズ、アナーキズムであり、インターネット時代の破壊者としての態度である。パンクではあるがしかし、理想やアティチュードを掲げてそれに反するものへ「ノー」を突きつけるよりも速く、あらゆるものに中指を立てている。