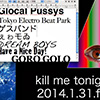MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with GORO GOLO - 音が鳴れば、肉は揺れる
ツイッターのタイムラインに江戸アケミbotのツイートが流れてくる。いわく、「内から出てくる踊りってことね。その人が我を忘れて動き出す時の。それが本物の踊りじゃん?」
(https://twitter.com/akemiedo/status/414420578909421568)。
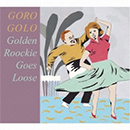 GORO GOLO - Golden Rookie, Goes Loose Pヴァイン |
江戸アケミ的な意味ではGORO GOLOの音楽は純度の高いダンス・ミュージックだ。GORO GOLOのフロントマン、スガナミユウは自分の踊りについて「音が肉にぶつかって、肉が揺れているだけ」と語っているから。でもGORO GOLOはじゃがたらみたいにコワいバンドじゃない(じゃがたらがコワかったのかどうか、実際のところを僕は知らないけれど)。ポップで、ユーモラスで、ダンサブルで、観客をあたたかく歓迎するソウルフルなバンドだ。だからGORO GOLOのショーをぜひ覗いてみてほしい。観客たちは思い思いに身体を揺らし、そしてその場にいる誰よりもスガナミユウがマイク片手にめちゃくちゃに踊りまくっている(叫び散らし、ハンド・クラップしながら)。
バンドの演奏も踊っている。つまり、ロールしている。ラグタイムからモダン・ジャズへと至る約40年にあったであろう熱狂と、その後にやってきたリズム・アンド・ブルースやロックンロール、そのまた後にやってきたソウルやファンクを全部混ぜ込んで、パンクの態度でロールしたのがGORO GOLOの音楽だ。
12年ぶりのリリースとなるGORO GOLOの2ndアルバム『Golden Rookie, Goes Loose』は、オープンリールで録音された抜けの良い超高速のダンス・ミュージックが約22分収められている。笑いあり、涙あり、そしてもちろん怒りもあるアルバムだ。
音楽前夜社というクルーを主宰し、〈ロフト飲み会〉や〈ステゴロ〉といったイベントでライヴ・ハウスの未知の可能性を拡張せんとするスガナミの言葉と態度には、気持ちいいくらいに一本の筋が通っている――そしてそれはGORO GOLOの音楽に間違いなく直結しているのだ。ここに取りまとめた対話を読んでいただければ、きっとそれがわかっていただけると思う。
GORO GOLO “MONKEY SHOW”
もともとは「GORO GOLO」ってバンド名もないようなゆるい、ただ「集まって鳴らしてみよう」みたいなもので。
■スガナミさんには昨年、何度もライヴにお誘いいただいてとてもお世話になりました。そこで僕はGORO GOLOのライヴを何度か観ているんですけど、GORO GOLOの歴史については全然知らないんですね。1月19日の〈音楽前夜社本公演〉でもHi,how are you?とかあらべぇくんとか、すごく若い子たちを巻き込んでいます。なので、そういうGORO GOLOをよく知らない世代にバンドの歴史を説明していただけますか?
スガナミ:結成はですね、1999年なんです。当時、高円寺で友だち8人で共同生活をしていて、そのコミュニティの仲間たちで結成しました。もともとは「GORO GOLO」ってバンド名もないようなゆるい、ただ「集まって鳴らしてみよう」みたいなもので。
■共同体みたいな?
スガナミ:うん。それで、この音楽性でGORO GOLOとして活動をはじめた最初のきっかけが、NHKで放送したスペシャルズの1979年か1980年の日本公演のブートのライヴ・ヴィデオをみんなで観たことで。それがすげーカッコよくて。白人も黒人もいるんだけど、みんな自由に動きまわって演奏していて、すごく楽しそうで。「この感じ、やろう!」と。でもそれでべつにツートーンをやろうっていうことにはならなかったんだけど。俺ら結構ひねくれてたから「スカはなし」、みたいな(笑)。
だけど「この楽しい感じでやろう」と。そういう共通認識でちゃんとまとまって、曲作りもはじめて、GORO GOLOでライヴするようになりました。そうしたなかで、角張(渉)さんと安孫子(真哉/銀杏BOYZ)さんがやっている〈STIFFEEN RECORDS〉から「アルバムを出さないか?」っていう話が来て、2002年にファースト(『Times new roman』)を出すことになるんだけど。この頃は6人組で。
■ヴォーカルの方がもう1人いたんですよね。
スガナミ:そうそう。『Times new roman』は10月頃に出たんだけど、これ、その翌年の1月に実家の事情があって、もう1人のヴォーカルが帰省しなきゃいけなくなっちゃって。そこで「じゃあ、いっそやめちゃおう」ってことで一回解散して。
■じゃあ、アルバムを出してすぐに。
スガナミ:すぐです。それでずーっとやってなくて。6年後か5年後に、ドラマーのmatの結婚式があって、「その二次会でGORO GOLOで演奏しよう」って話になって。それでやってみたら楽しくて、ちょくちょくライヴとかも誘われるようになったんです。「ちょっと継続してやってみようか」みたいな感じでゆるくはじめたんだけど。曲も結構溜まってきていたので、2012年に何か音源を出そうって思ったんです。それがちょうど風営法、いわゆる「ダンス規制法」が話題になっていた頃で、DJユースの7インチ作ろうっていう話になって。どこからリリースしようかって話をしていたときに、やっぱり古巣の〈STIFFEEN RECORDS〉から出すのがすごく面白いんじゃないかって思って。それで、角張さんに相談させていただいて、お忙しいなか手伝ってもらいました。
■なるほど。それが去年の8月に出た『GOD SAVE THE DAINCING QUEEN EP』ですね。GORO GOLOの曲って、スガナミさん以外にもみなさんで書いてるんですか?
スガナミ:うん。ドラマー以外はみんな曲を書いています。今回の2ndだと、俺の曲の他にしいねはるか(キーボード)の曲とベースのきむらかずみの曲なんだけど。
■どういう感じで曲を書いているんですか?
スガナミ:歌ものは俺がほとんど書いてて、インスト曲を他のメンバー2人が書いてます。歌ものはざっくりとしたものを俺が持ってきて、あとはドラマーのmatに「やりたいリズムで叩いて」って言って。この“GOD SAVE THE DAINCING QUEEN”は、ありえないほど16(ビート)が早くて。
■ははは。
スガナミ:「これ、すげーウケるね! これやろう!」って言って作った曲ですね。だから、リズムありきでメロディーを乗せたりもします。いまはそのやり方が結構多いですね。インストだったら、誰かが持ってきた1つのリフから広げるとか。はるかの曲だったらまるっとピアノで作っちゃって、それに肉付けするみたいな感じ。
ソウルとかジャズとかを自分たちの音楽に変換したときに、スピードを上げるとすごく新鮮になるというのがアイディアとしてあって(笑)。
■そうなんですね。“GOD SAVE THE DAINCING QUEEN”もそうですけど、GORO GOLOには「速さ」という要素があるじゃないですか。
スガナミ:速さね(笑)。
■GORO GOLOはすごく速いです。さっき取材前に野田努さんが「ポーグスみたいだね」っておっしゃってたんですけど、GORO GOLOの速さというのは、スペシャルズとか、やっぱりそういうパンキッシュな面からきているんでしょうか? 僕は全然知らないところですけど、もともとは〈西荻WATTS〉とかのパンク・シーンに出自があるというのも関係しているんですか?
スガナミ:あるね。
■なぜGORO GOLOはあんなに速いんですか?
スガナミ:退屈なのが耐えられなくて(笑)。
■ははは。
スガナミ:スピードに逃げるというか(笑)。あはは! やっぱりスピードがあるとさ、聴きづらくなったりもするじゃん? それでも……突破したい、みたいな(笑)。何かをこう駆け抜けたいときに、スピードができるだけ速い方が……気持ち良いんだよね。はっはっはっはっ!
■ははは! 曲もすごく短くて駆け抜けて、アルバム自体もすごく短くてすぐに終わりますよね。
スガナミ:あと、ソウルとかジャズとかを自分たちの音楽に変換したときに、スピードを上げるとすごく新鮮になるというのがアイディアとしてあって(笑)。それは昔からそうなんだけど。考え方としてはパンクに近いかもね。レコードを間違って回転数上げて再生したらすごくイケてるな、みたいな。逆もあると思うんだけど。すごく遅くて良いのもあると思うし。その感覚に近いかな。
■GORO GOLOの音楽って、リズム・アンド・ブルースなどのブラック・ミュージックやロックンロールとかを詰め込んだガンボ・ミュージックだと思うんですけど、それはスガナミさんの趣味なんですか? メンバーのみなさん、そういうのが好きなんですか?
スガナミ:鍵盤のはるかはもともとラグタイムとかが好きで。ソウルやファンクが好きなのはベースのきむらと俺なんだけど。GORO GOLOをやるようになってからいろいろディグりだしたんです。ファーストの頃って、そこまでまだマッチングしてないというか、まだ音楽自体に魂を入れきれてないというか。表面的にファンク的なものでやっていた面もあったんだけど。でもいまはそれがわりと血肉化できるようになったと思う。それはたぶん、音楽をたくさん聴いてきたということもあるし、あとは年食ったってのもあると思うんだけど(笑)。
■味が出たんですね。
スガナミ:味が! 自分たちのニオイみたいなものが出るようになった。
取材:天野龍太郎(2014年1月08日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE