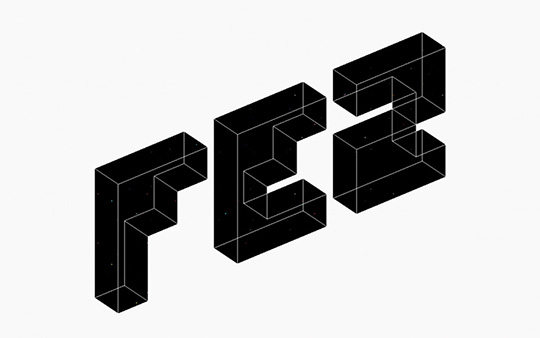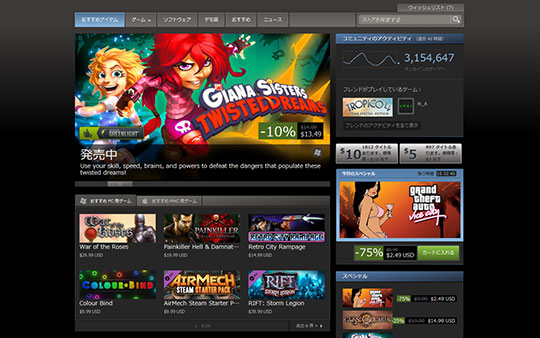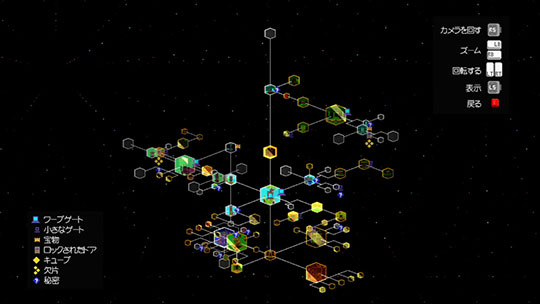空気公団 - 夜はそのまなざしの先に流れる BounDEE by SSNW |
新しいことをやっていると思っていたら、「70年代が帰ってきた」と言われた......山崎ゆかりと空気公団は、はじめからある種のズレを抱えて年を重ねてきたようだ。今年で第一期結成から15年になるが、ベテランという風格も古びた様子も感じられない。特定の世代から支持を受けているというふうでもなく、どちらかといえば考え方やライフ・スタイルを同じくする人々から愛されるバンドであるように見える。実際のところ、彼らの音楽はとくに新しいわけでも古いわけでもない。そうした価値観の外で、自分たちが大事にしているものに正直に、忠実に制作しているという印象がある。自分を表現することから一歩引くこと、引いた部分に人を引き入れること。そのような音楽のあり方を空気公団は大切にする。おそらくそのために新しいものからも古いものからも少しずつズレるのだろう。彼らは、そのズレさえも大切に思っている。
今月、空気公団は新作となるフル・アルバム『夜はそのまなざしの先に流れる』をリリースする。先を読んでいただければわかるように、本作は独特の録音スタイルとコンセプトによって組みげられた意欲作だ。筆者のようにこれまで彼らの音をそれほど耳にしてこなかった人も、この冒頭1曲ばかりは足を止め、手を止めて集中せざるを得ないだろう。なにも難しいものではない。むしろ人が自然に耳をひらくことをうながすべく録られた音である。詞があり曲があり、そこに人がすっと入っていけるように隙間(=ズレ=空気)がつくられている。むしろこの「隙間」をどうつくっていくかということに思念をこらした作品であるとさえ思われる。
一種の公共空間を設計することが、ポップスの役割かもしれない。たくさんの人間の思いや気持ちをのせられる無限容量の共用スペースを、そのときどきに様々に生み出してきたのがポップスではないのか。......一方では「初期ユーミン」などと形容され、また一方でクラムボンやキセルに比較され、筆者自身は美術館で演奏したりするアート寄りなバンドだと思っていた空気公団は、そのどれからもズレながら、あくまで自分たちのやりかたでポップスの限界を押し広げている。
- 1. 天空橋から
- 2. ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
- 3. 4層の物語
- 4. 「空気」というキー概念――結成を振り返る
- 5. アニメ『青い花』と
- 6. 山崎ゆかりとラヴ・ソング
- 7. 30を越えること
- 8. 空気公団、新しいコミットメントの可能性
- 9. 明日とはきみのこと
天空橋から
どうやって録音しようかと話していたときに、じゃあ空気を録音するっていうのをもっとメインに考えていこうってなって。それでライヴをそのまま録るというところにたどりつきました。
■今作『夜はそのまなざしの先に流れる』の1曲目なんですが、これはすごく長い導入部を持ってますよね。
山崎:そうですね、はい。
■この長さ、このパート自体が、アルバムというものの時間性ではないなというふうに思ったんです。この奇妙な感触や尺はなんなんだろう、っていう。そのとき、この作品が演劇とともに演奏されたライヴ録音であるということの意味が立ち上がってくるように感じました。
山崎:ああ。
■おそらくそれって、この「天空橋」っていう場所を舞台に立ち上げるために必要な時間だったんじゃないか。あのパートはきっと、なにかパフォーマンスが行われていた部分なんですよね?(※1)
山崎:あれは、もともとセリフを入れてた部分なんですよ。あとでセリフをカットしたんです。
■ああ、そうなんですね。
山崎:そこは津軽弁で物語の筋書きをしゃべってたんですが、カットしたといういきさつです。
■全体の録音から、声だけきれいにトリミングしたということですか?
山崎:いいえ。あのオケははじめに録ってあったもので、それに合わせてしゃべってるんですよ。だからあとから声だけ取っ払ったかたちになります。物語の説明なんてべつにいいか、ということになりました。
■なるほど。すごく不思議な感触がありました。生演奏でも編集作業でもなくて、もっとべつの力の作用によって成り立った空間だっていう感じがすごくしました。ナレーションがあったということは、アルバムにはなにか設定があったということなんですか?
山崎:いつもまずコンセプトを考えてからアルバムを作るんです。今回は、「人に穴があいている」っていうことを発見して、その穴が何なのかっていうことを探しに行くところからはじまっていて(※2)、それを導入で説明しているんですね。演劇が入ってくるっていうことも念頭にあったので、そうなると歌以外の部分も大切になるな、とは思っていました。それで最初の部分は長く取っています。あれを1曲めにするっていうのはみんなに反対されるかなと思ったんですけど、意外にアリになりましたね。
■演奏自体もプログラムの冒頭だったんですか?
山崎:そうですね。曲順通りに演奏してます。
■あ、そうなんですね。なんというか......フィールド・レコーディングっていう言葉は、自然の音とか、音楽という意図で編まれていない音を録音することを指しますけども、この冒頭の演奏は、この日のステージをフィールド・レコーディングしたもの、という感じがしました。ちゃんと音楽として組織された音なんだけれど、それが鳴っている場所自体を、ひとつの自然として記録したというか。
山崎:もともとあの部分って、コードしかなかったんですよ。コードだけをひたすらみんなに聴かせる。演奏する人たちとは、「ひとりフレーズをやったら、それにつながるフレーズをまたべつの人がやるというふうにしよう」ってそれだけ決めてました。なので、最後のほうになるとワン・フレーズみたいになって楽器が3つ分重なる部分があると思うんですけど、最初はそれをわからないように演奏しています。パーカッションはその場のノリです。まあ、みんなその場のノリでやってるんですけど......基本的には「天空橋」っていうキー・ワードしかないっていう状態です。あとは、パフォーマーがいるんだ、歌詞はこれだ、これは録音されてるんだ、っていう情報だけは共有されていて、みんなそこから想像してやっています。
■「天空橋」っていうキー・ワードはどこからきたものなんですか? あえてそこは明示しない感じでしょうか?
山崎:「天空橋」って言ってますけど、天空橋って行ったことないんですよ。
■あれ? 実在する場所なんですか?
山崎:羽田空港の近くですよ。
■あー! あるかもです。
山崎:曲を作っているときに、ふと「天空橋に」って言葉が口から出てきて、あれ、天空橋って何なんだ? って思って、自分で調べたら、なんか駅があるらしい。特に場所の設定として天空橋がいいって最初から決めてたわけではないんです。
■明確な設定もないし、イメージもとくに統一しないし、天空橋が実在すると知らない人もいるかもしれないくらいのあいまいなキー・ワードだったんですね。
山崎:そうですね。
ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
ライヴ盤......っていうかライヴのときのテンションがあまり好きではないんですよね。なんか、作品を作るっていうよりはその場のお客さんを楽しませるという感じとか。そのちょっとした余裕が生まれている感じがあんまり好きじゃないなって思うんです。
■はあ、なるほど。そういういろんな偶然性をはらむような、ライヴ録音というスタイルでこの作品を録ろうとされた意図はどんなところにあるんでしょう?
山崎:いつも空気公団って、録音をメインにしているんですよ。で、手紙みたいに1年に一回はぜったいアルバム出したいなって思ってるんです。次はどうやって録音しようかと話していたときに、じゃあ空気を録音するっていうのをもっとメインに考えていこうとなり、それでライヴをそのまま録るというところにたどりつきました。
■でも「ライヴ盤」ではないわけじゃないですか、これは。
山崎:ライヴ盤......ライヴのときのテンションがあまり好きではないんですよね。知ってる曲を演奏するから楽しいし、やり慣れているっていう、そのちょっとした余裕が生まれている感じがあんまり好きじゃないなって思うんです。それで、もうちょっと作品を作っている感じにするために、新曲を演奏しようと考えました。といって、ステージでやるわけだから、録音してる様だけを見せるというのもどうなんだって気もました。音楽をもうちょっと立体的にみせられる方法を思い浮かべたときに、演劇かなと。
■へえー。どういうふうにポスト・プロダクションを加えていったんでしょう。8割9割そのままだってことはないんですよね?
山崎:8割9割......そうですよ。ベーシックは全部そのままで、ほとんど差し替えはしていないです。全部録ったあとで、間違えた音を録り直さなきゃね、とは言っていたんですけど、スタッフも「べつにやり直さなくてもいいかもね」とのことだったので、じゃあこれにしようかと。
■劇の人たちのズシン、バタン、みたいのは聴こえないですね。
山崎:そこはカットしました。
■あ、そこもライヴ盤とはちがう性格のものだって感じがします。スタジオ録音ではないんだけど、スタジオ録音的な作品として完成させようとされている。それは、その場にあったことをそのまま記録しようというライヴ盤とはちがいますよね。そのあたりの差がしっかり考えられて作られていると思いました。
山崎:生(ナマ)なんだけど「生」感を消してるんですよ。だけど、演奏してる人の気合い自体は生というか。歩き回ったりしてますしね。ドラムは囲いで録っていて、スネアなんかも曲によっては替えたかったんだけど、それはできなかった。
■前作にあたりますかね、『春愁秋思』のライヴ盤があるじゃないですか。あれとかはヴィデオ・カメラの粗悪な音も積極的に活かすかたちですよね。要は、そこにそういう場所があった、そういう音楽が鳴っていたということのリアルな記録や証拠みたいな性格のものだと思うんです。そういう、ライヴ盤らしいライヴ盤である前作の方法から得たこととか、今作につながった要素があればうかがいたいんですが。
山崎:やり方はいろいろあるってことですね。スタジオでひとりずつ、ドラム録って、ベース録って、っていうやり方じゃなくても録れるし、そういう機械も増えてる。もっとクリアに録って......みたいな欲求も生まれてくるのかもしれないですけど、あんまりそういうのないんですよ。あんまり分離のいい音すぎるのもどうかと思うし。言い方が難しいですよね、「ライヴ録音」っていうのが適当なのか......
■ライヴの緊張感をうまくスタジオ・アルバムの単位に落とし込んだような、新鮮な方法ですよね。
山崎:お客さんも緊張してて。1曲めの後なんかも、ふつう曲の終わりとかに拍手があったりするじゃないですか。曲の終わりがわからないというのもあるけれど。でもこれの場合は誰かがパチって叩いて終わった、みたいな。
■なるほど。そういう、仕組まれた音が鳴ってるのに環境として録っちゃうというような、コンセプチュアルな仕掛けがあるような気がしておもしろかったです。資料には、山崎さんのことをシンガーとかソング・ライターとかじゃなくて「アルバム・コマンダー」って書いてあったんですけど......
(一同笑)
■(笑)そういうコンセプト込みでの指示を出すシンガー・ソング・ライターをうまく呼び表す言葉がなくて、そう表現したのかなあと思いました。言いたいことはすごくわかります。
山崎:3人は空気公団なんですけど、3人だけが空気公団じゃない。そういうところから来てますかね。
■山崎さんは、すごく若いときに朝の音を毎日ひたすら録音してたんだという記事を読んだんですよ。
山崎:(笑)
■そういうときに音に映り込むものってなんだろうなと考えると、ちょうどこのアルバムの全体の音が、それを人工的に再現した感じに近いのかなと思いました。
山崎:ああー。
※1...2012年7月6日、日本橋公会堂にて『夜はそのまなざしの先に流れる』が開催された。舞台上では演劇ユニット「バストリオ」による演劇が繰り広げられ、アルバム収録曲すべてが初演奏された。新作『夜はそのまなざしの先に流れる』はこの公演の録音をもとに制作されている。
※2...
いつもの帰りの電車で
ふとあることに気がついた
それは「穴」であり
わたしはそれが何なのか
ぼんやりとわかるが説明できない
これは何であるのか
人々に「穴」があいている
そこからいつもとは全く違うルートで
目的地を目指す
その道すがら思考する
この「穴」は何であってどこに続いているのか
目的地には知らなかったわたしがいた
(『夜はそのまなざしの先に流れる』プレス資料より)
- 1. 天空橋から
- 2. ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
- 3. 4層の物語
- 4. 「空気」というキー概念――結成を振り返る
- 5. アニメ『青い花』と
- 6. 山崎ゆかりとラヴ・ソング
- 7. 30を越えること
- 8. 空気公団、新しいコミットメントの可能性
- 9. 明日とはきみのこと
4層の物語
昔は30テイクとか40テイクとか録って、そこでいいものができれば「ああ、よかった~、録れたよ」って感覚もあったんですよ。けど、重ねていけば重ねていくほど、自分だけが深くなって、まわりとの距離がどんどん広がっていくんですよね。
 空気公団 - 夜はそのまなざしの先に流れる BounDEE by SSNW |
音響的なものに対する感性や感度の一方で、詞も気になるところです。1曲めばかりで恐縮ですけど、「いつもの通りを抜けてみたら/知らないふたりに/会える気がする」の「知らないふたり」ってなんだろう、ってちょっとびっくりしましたね。「知らない人」とか「知らないあなた」なら予想の範疇なんですけど、「知らないふたり」って単位は何なんだろうと。
山崎:はは(笑)、そうですか。
■発話主体からみて、「知らないふたり」ってどんな存在なんだっていう。
山崎:ヴォーカルはナレーションになればいいと思っていて。歌っている人がいるとその人が主人公みたいに見えますけど、じつはその人じゃないんだっていう感じがいちばん好きですね。だからかなあ。
■人と人との関係をみていきたいっていうようなことですか?
山崎:どうなんでしょうね......。書いてるときは、その「ふたり」っていうのは、自分とこれから会いにいく人っていうイメージだったんですけどね。いままでの自分と君じゃない、まったく新しいふたり、っていうような。
■ああ、なるほど。すごく俯瞰の視点ですねえ。この詞の前には「誰かを待つ人/探して見つけた人/抱き合う別れる人/会えなくなる人」っていう、いろんなカップリングを暗示する描写があるので、そういう関係性自体をみつけようとしているのかとも思ったんですが。「あなた」じゃなくて、関係に自分の気持ちが向かうのはポップ・ソングとして変わってますよね。
山崎:そうやって言われるとなんか、書いてよかったなあって(笑)。えーと、手前にドラムがいて、奥にベースがいて、向かって反対側に、前から順にギター、キーボード、わたし、と......まあ、横に3列になっているんですが、その3列のあいだを4本の帯として、それぞれの帯でバラバラの物語が展開されているんですよ。
■あ、へえー。
山崎:4つの線のそれぞれにパフォーマーがいて、異なる線の人同士はたがいに挨拶することもあるんだけど、基本的にはそれぞれの線の上で世界が完結している、っていうのがバストリオの今野さんが考えていた。今野さんに「ここはこういうことを言っているから、こんなふうにやってくれる?」みたいな指示は全然してないんです。音楽って顔がないから、その顔になり得るような何かがほしい......音楽の世界を立体に見せてほしい、みたいなことは言いましたけど。
■音はみなさんあらかじめ聴いてるんですよね? 脚本ではなくて、音を聴いておのおのの解釈で動くって感じですか?
山崎:一度、稽古を見に行ったんですよ。そしたら男女でペアを組んで、それぞれにお題が与えられて、そのお題をどう表現するかということを話し合っていたんですね。歌詞の意味ではなくて、歌詞に出てくる単語をお題? として。たとえば「角部屋」のチーム。「角部屋」って歌詞に出てくる言葉なんですけど("あなたはわたし")、それをどう表現するかというのをペアで表現し、そこで出てきたものを今野さんが「これはいいね、これは使おう」って決めてました。
■なるほど。それで、その4組は舞台は同じだけど、それぞれに違う次元のストーリーを同時進行していると。
山崎:歌詞もそうなんですけど、全部を言い切っていないんですよね。間(あいだ)が抜けてるって言われたことがあって。それぞれの行をレイヤーとして見ると、今回の4つの線も同じで、4面の層になっている。今野さんがやろうとしていたのは、その4枚が重なったときに見える色があるっていうことなんですよね。たとえば。
■へえー。実際すごくコンセプチュアルに組み立てられたステージだったんですね。ステージの上から見ててどうでした? 音との絡みとか。
山崎:あんまり見てる余裕がなかったですね。曲間とかクリックもあるし、どこから誰が入ってきてというのもヘッドホンで確認しながらだったので......ほぼ録音と同じでしたね。リハーサルは当日だし、通しの稽古もあったんですけど音は出してないんです。音だけの最終リハーサル時の録音を流しながらバストリオの8人が踊っていました。本当に、初めてのものを作る、という感じでしたね。
■緊張感はみなぎってますよ。
山崎:あんまりにも緊張感のあるアルバムってどうなんですかね? 演奏している側には踊っている人の動きが見えてるものだから、やっぱり自分のなかに入り込むというよりは、出すって感じが強く働いてて、すごく音が太いんです。だから差し替えられなかったんですよね。
■あ、後から録り直したものとテンション的に違ってて、差し替えられなかったと。
山崎:そうそう、同じにはならなかったですね。

「空気」というキー概念――結成を振り返る
ライヴハウスとかもみんな大体壁が黒いですけど、ここで絶対やらなきゃいけないのか? というようなことも、観ていくうちに考えるようになって。ライヴをして、お客さんを増やしていって......っていうのではないやり方があるんじゃないかなあ、と。
■へえー。ライヴ盤の話ももうちょっと聴きたいんですよ。ヴィデオ・カメラの録音も採用するというのは、演奏された音をいかに精緻に録るかというのとはまたべつの意図があるからですよね。音自体ではない、あるなにかを録ろうとしているわけで。
山崎:いい空気かどうか、ということを基本に考えてますね。もちろんいい機材があればそれで録りますけど、毎回揃えられるわけじゃないし。やっぱりあるんですよ、すごく空気が濃いときが。澄んでるというか。あと、一気に丸くなるとき。お客さんとか自分たちとか場所の空気がうまく噛み合うと、すごく大きい、丸みたいになるんですよ。どんな録音のときでも、それはアルバムに入れたいなと思います。
■そのときその場所でしか生まれなかったというような、体験の一回性みたいなものを記録したいということですよね。でも、そこで聴いていたファンだけが買えばいいというものでもないわけじゃないですか。
山崎:そうですね。昔は30テイクとか40テイクとか録って、そこでいいものができれば「ああ、よかった~、録れたよ」って感覚もあったんですよ。けど、重ねていけば重ねていくほど、自分だけが深くなって、まわりとの距離がどんどん広がっていくんですよね。そうじゃなくて、一気に録ろうと。いいものを出そう、出そうとするのではなくて、自分がいま思ったこと、感じたこと、それがうまい具合に空気になっていくのを録れるといいなって思います。それに、ヴィデオ・カメラについてるふつうのマイクの音って古い、昔っぽい音がしませんか.....なんか、削られてるんだけど、なんかいい音......。
■空気っていうのは、ほんとにキー概念ですよね。その朝の音の録音にしてもそうですし、空気公団という名前にもなってますし。とすると、空気公団って名前は......「公団」っていうと戦後スキームの歪みとか矛盾みたいなものを象徴するみたいな響きがありますけれども(笑)、空気を仕切っていい塩梅に配分するっていうようなイメージでしょうか。アイロニーがあったりはするんですか?
山崎:(笑)漢字がよくて、どうしても。あと、ふたつの単語に分かれるのがいい。ただそれだけでした。みんななんか、わりと横文字だった。横文字だとカッコいい。けど、そんな感じじゃないしな、と。それで、そのときのメンバーに「じゃ、今日から空気公団ってことで」って言ったんですけど、そしたらみんなに「やだよ」「恥ずかしいよ」って言われました(笑)。
■ははは!
山崎:みんなもっとカッコいいのに、なんか収まってる、って。
■(笑)でも、漢字がいいからって、「空気」と「公団」をもってくる理由にはならないですよね?
山崎:なんでか思いついちゃったんですよね。最初はパンク・バンドに間違えられたりしました。
(一同笑)
■ありえますねー。
山崎:そのころ「団」とかなかったし......。空気公団を名乗りはじめたあと、ある人がライヴをやったほうがいいよ、ホームページを持ったほうがいいよって言ってくれて、「ああ、ライヴか」と思ったんです。それでライヴ・ハウスを探してたら、面接なしでうちですぐやれるよっていうところがあったんです。で、そこに行ったら、骸骨から血が出てるみたいなポスターが貼ってあったりとかして。
■あははは。
野田:僕、当時初めて名前をきいたころのことを覚えてるんですよ。当時は『ele-king』っていうテクノの雑誌をやっていて(旧『ele-king』)。コーネリアスとかを表紙にしてたんですけれども、ちょうどそういうものに対するアンチテーゼみたいなかたちでサニーデイ・サービスとかが出てきたんだよね。曾我部くんとかははっきりと僕なんかがプッシュしていた音楽に対して反対の立場で意思表明をしてたんです。彼とはそのころ知り合ったんだけど、あのときのサニーデイのはっぴいえんどというコンセプトは、ある意味では1990年代後半だからこそあえてやったというようなところがあって。やっぱり彼の上の世代、フリッパーズ・ギターとかへの違和感が彼にはっぴいえんどという選択肢を与えているんだと思うんですけど、そのへんはどうだったんですか?
山崎:結成したときは、いろんなところに声をかけたけどべつに誰が何をするでもなくという状態で、自分たちで売るしかないなって、自分たちで店を開拓して売ってたんですよ。それがきっかけでCDを出すことになるんですけど、そしたらいろんな雑誌とかが取り上げて、レヴューしてくれるようになったんです。で、それを見たら「70年代の音楽が帰ってきた」みたいに書かれてて、「あれ? 70年代なんだ」ってそのとき思いました。
■ああー。意識してたわけじゃなかったんですね。
山崎:新しいことをやってると思ってたのに、あれ? そういうことだったんだ? って(笑)。大貫さんがやってきたこと、と。
野田:さすがにユーミンではないだろうというのは僕も思いましたけどね。
■うん。いまとなっては活動全体からもまったくそういうイメージが結びつかないですね。学校の先生に「きみはバンドをやったほうがいい」って言われた、というインタヴューも読みましたけれど、その先生の言葉の意図ってどういうところにあったんでしょう。何を聴かせたんです?
山崎:いや、ただ手に負えないと思ったんだと思います。
■ああ(笑)、え? 悪い生徒だったんですか。
山崎:悪い生徒ではないんですけど、あんまり言うことをきかなかった。曲を先生のところに持っていくと、「歌詞を黒板に書け」って言われて、書いたら「この歌詞に出てくる男の人は何歳の設定なんだ」とかきかれたりして、そういうことをやっているうちに、何を教わりたいのか疑問に思いました。
■いちばん初めのメンバーは女性ばっかりなんですよね。
山崎:女3人と男1人なんですけど、よく女性4人グループって書かれてましたね。
(一同笑)
山崎:男だけど髪が長かったんで、そのせいもありますかね。で、またその髪が長いっていうのも70年代的ってところになんとなく重ねられたのかもしれないです。
■ほんとに、全然そういうバンドのコンセプトはなかったんですか?
山崎:全然ないですね。その当時はすごくたくさんのライヴを観に行ったんです。そのなかで、空気公団が何をやったらいいのか考えましたね。なんか疑問がいろいろありました。伝統や習わしめいたやり方の中で何を守っていくのがいいのか。ライヴハウスは大体壁が黒いですけど、わたしたちの音楽もここに合うのか? って観ていくうちに考えるようになって。それと、ライヴをして、お客さんを増やしていって......っていう以外にやり方があるんじゃないか、というようなことですね。
■なるほど。
山崎:2度めにライヴをやったのはスパイラル・ホールなんですけど、そのときは「空間」というタイトルをつけました。スクリーンをステージの前に降ろし、その後ろで演奏して、それをカメラで撮ったものをスクリーンに映してるっていうステージです。
■絵本とのコラボがあったり、いろんな不定形を試みているのも、基本的には同じ疑問から生まれたものだということになりますか?
山崎:そうですね。聴き方は自由であっていいと思うし、聴かれ方も自由であっていいと思うので。いろんなところで音楽が鳴っていてほしいとも思うし。
■空気の創造というか、画一的なもののなかに押し込められるのではなくて、鳴っている場所ごと作るっていう、それが「空気公団」ということなんですかね。
山崎:音楽が主役でいいと思うんですよね。音楽がまず目の前にあって、演奏してる人はスクリーンの後ろでもいいじゃないかって。なんというか、自分たちがバンドだというふうにはあまり思ってないですね。音楽があって、それを演奏しているだけというか。メジャーでデビューしたときの録音で、ギターがほんの3音しか入らないアレンジを考えて、「ここにギターを3音入れたい」って言ったら、「ライヴしたときのことを考えてごらん」と返されまして、ライヴすることを考えるものなんだなってそのとき思いました。ギターが3音だけだったらその人はそこまで何にもしてないことになるんですよね。
■(笑)
山崎:そういう考え方もあるんだ、って思いましたね。
■あらゆる型を窮屈に思ったんですね。けど業界とはソリが合わなかったという。
[[SplitPage]]- 1. 天空橋から
- 2. ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
- 3. 4層の物語
- 4. 「空気」というキー概念――結成を振り返る
- 5. アニメ『青い花』と
- 6. 山崎ゆかりとラヴ・ソング
- 7. 30を越えること
- 8. 空気公団、新しいコミットメントの可能性
- 9. 明日とはきみのこと
アニメ『青い花』と
いちばん最初にメジャーでデビューしたときの録音で、あたしはギターがほんの3音しか入らないアレンジを考えて、「ここにギターを3音入れたい」って言ったら、「ライヴしたときのことを考えてごらん」って返されたんですよ。ライヴすることを考えるものなんだなってそのとき思いました。
 空気公団 - 夜はそのまなざしの先に流れる BounDEE by SSNW |
■ところで、話は変わるんですが、2009年にアニメ『青い花』のオープニング・テーマを担当されてますよね。この曲("青い花")はライヴ盤にも入っていますけど、お好きな曲なんですか?
山崎:あれはリクエストが多いっていうのもあって。
■そうなんですか。アニメのOPって、もうエモーションを盛りに盛って、疾走感を出しまくってという、かなりはっきりとした感情表現が求められるのかなという印象がありますけれども、あの曲はピアノのシンプルなイントロが逆に強烈なインパクトを持ってますよね。
山崎:依頼をされて、出した案のひとつですね。こんな感じですかね? って。1曲めはちょっと違うかなってことになったんですけど。歌詞はほとんど添削なしでそのままでした。思ったとおりに書いていいですよって言われて書いたものです。
■初めにある程度の指定を受けて作られるわけですよね。ストーリーや内容の説明を受けるんですか?
山崎:マンガ本をもらいました。それを見て好きに書いていいですよって。録音も好きにしていいよということでした。
■あ、かなり自由なんですね。では依頼されたかたは、もしかするともともと空気公団のイメージでオープニングを考えていらっしゃったのかもしれないですね。
山崎:いつか(空気公団に)お願いしたいと思ってくださってたというお話をききました。
■ああ。ちゃんと狙いが定まっていたような、すごく腑に落ちる引き合わせだと思いました。あれは女性同士の恋愛、しかもうら若い女子高生同士の恋愛が描かれた作品で、それが鎌倉の明媚な風景のなかで展開されるじゃないですか。淡い光と繊細な関係性、みたいなモチーフが大切にされてますよね。実際、そういう部分に対するひとつのアンサーとして曲が書かれているんでしょうか。
山崎:思ったとおりにやっただけ、という感じではあって......あんまり、オーダーに対して「わかりました」って応えられるタイプではないので。読んでみて印象的だったコマ、そこからふくらませた話を書こうと。そのときはまだ結末がなかったんですよ。
■ああ、いちばん最初ですもんね。ちなみに印象的だったコマってどんな部分だったんですか?
山崎:女の人の横顔で、うしろに、その人の気持ちを表す吹き出しみたいなのがある......まだそれが言葉になっていない、そういうコマですね。言葉にしてないんだけど、なんだかわかるというか、奥行があるというか。そういうのが印象的だったかな......。
■世間一般としてストレートな恋愛ではないわけなんですが、そういうテーマ性への意識などはありましたか?
山崎:いや、なんの抵抗もなかったですけどね。
■先ほども触れた、山崎さんの歌詞のなかの「ふたり」問題もそうなんですけど、山崎さんの「ふたり」とか「あなた」というのは、恋愛関係があるようでいて、ベタな恋愛とか相聞歌に回収されないような種類のものだと感じるんですね。なんというか、届きようもない「あなた」というか。どこかで性別も年齢も関係ないような点に行き着く「あなた」というか......。2人称をどんなふうに使っていらっしゃるんですか?
山崎:見えてるものだけが正確なものじゃないから......人のなかにもう一個あるわけで。なんというか、心みたいなものが。だから「あなた」とか「きみ」とか言ってるけど、目の前に現れてる人っていうよりは、もうちょっともやもやした記憶のなかの人のことだったりするかもしれないです。これから出会う人とか。
■つねに微妙な関係性に焦点があって、『青い花』の音楽を依頼されたかたも、山崎さんの音や詞のそういう部分を必要とされたんじゃないでしょうか。
山崎:さっき言ったことと重なりますけど、ヴォーカルがナレーションみたいだったらいいですね。男女でも、何でも、物語が繰り広げられているのを隙間からのぞいて、その様子を書いてるってふうにしてるんです。だから「あなた」とか「きみ」とか「ぼく」とかがちょっと遠く感じるのかもしれない。でも、それを見つつ、そのなかに入っていく自分という視点もある。あんまり深く考えてないかもしれない(笑)。
■あまり激しい感情表現をされませんよね。「嫌い」とか「憎い」とか、どぎつくて直接的な表現を避けながら作っておられるのかなというふうにも見えます。
山崎:言葉が簡単だと、安いというか。直接的な言葉......たとえば「嫌い」って言うときの「嫌い」の範囲ってすごく大きい気がしませんか。言葉だけで何でも完結させる必要はないし、音楽だけで何かを理解させなくてもいいかなあとは思います。音楽と言葉が同時に鳴って、言葉の消えかける瞬間、和音、そんなところからいろいろなものを感じとってもらえるはずだから。みんなそこに潜んでいるものをおのおの見つけて、ああこれが空気公団かって思ってくれているという感じがしてますね。なんか空気公団のお客さんって、ひとりで聴いてくださっているかたが多いようなんです。
■ああー。
山崎:みんなで聴いてほしいんですけど(笑)。
(一同笑)
■いや、わかりますよ。それ重要な観察じゃないでしょうか。だから......その音楽が自分との間で成立してほしい、1:1で向かい合いたいという感じになる構造を持ってるってことかもしれないですね。あんまり人と聴くものじゃないかも。

山崎ゆかりとラヴ・ソング
言葉が簡単だと、安いというか。直接的な言葉......たとえば「嫌い」って言うときの「嫌い」の範囲ってすごく大きい気がしませんか。言葉だけで何でも完結させる必要はないし、音楽だけで何かを理解させなくてもいいかなあとは思います。
■ちなみに、せっかくなので恋愛とかラヴ・ソングについておうかがいしたいんですが、音楽を作る上で恋愛というテーマを意識したことはありますか?
山崎:うーん、ないかな......。むしろ意識してできるようになりたいですよね。
■でもほとんどラヴ・ソングに聴こえるって話もあると思うんですよ。
山崎:その相手の人がひたすら好きっていうよりは、その人を活力にしてるというか、その人がいるおかげで自分が生きていけるんだというような......結局、自分で完結してる。その人が死んじゃったらどうしようとか、そういうラヴ・ソングじゃないんですよね。誰かがいて自分が生きているという、そういう感じかもしれない。
■「きみ」もたくさん出てきます。
山崎:まず、「ぼく」が主人公の曲が多いんですよね。ヴォーカルが女の人で、曲中で「わたし」って言ってたら、ズレがないというか。そこにズレが欲しいですね。歌ってる人が曲のなかの一人称と同一人物じゃなければ、聴いている人もそこに入っていけるじゃないですか。それで「ぼく」が歌うとなると、相手は「きみ」になるっていうことなんです。
■ああー。べつに少年に仮託してるってわけじゃないんですね。
山崎:聴いてる人がもっと自由になったらいい。
■主体がつねに歌い手とイコールじゃないっていうのは、ロックとかポップスのなかでは異端的ですよね。「I(アイ)」を中心にして表現をする、歌う言葉がすなわちその人の揺るぎない実存を表す、みたいな定式があるわけじゃないですか。そこを避けていくのはなぜなんですか?
山崎:音楽ってもっと自由だったらいいのにって思ってたことですかね。バンって言い当てられちゃって、考える隙がないというのはもったいないって。
■それが一種、引いたカメラみたいな構図を引き出すんですかね?
山崎:空気公団の音楽って、毎日のなかになんとなく流れてて、ふと気づいたらそこにある、みたいになればいいと思ってたんですよ。真正面から流れてるというよりは。ひとりのときにだけ流れていることがわかって、背中をポンと押すようなものであればいいなっていう。
■むき出しの主語で実体験を書いたことはないですか?
山崎:嘘は書いてないですね。誰かの話を聞くのが好きで、その人の話してる表情が強く印象に残るし、そういう風景を写真で撮っている感じです。言葉で「これだ」ってひと言で表現してしまうと、みんな同じものしか見えなくなる。ズレてズレてズレて、空気公団というものができあがっているんじゃないかと思います。
■なるほどなあ。空気公団とズレ......。"日寂"って曲は、詞がアナグラムみたいになっていますよね。ええと、「るいへくおの/ろここてせよに(/もととひにかず/しはみなんばざ/とつづく)」......
山崎:ああ、それは後ろから読んだだけなんですよ。後ろからよむとちゃんと歌詞になってるんです。リハーサルのときに違う歌詞を逆さにして歌ってたら、「それでいいんじゃない?」って感じになって。
べつに、ふだんから歌詞がどう読まれてもいいって思ってるわけじゃないんですけど、そういうズレってすごくいいもので、しかもみんなが空気公団になれる。その音楽に入れる。それに、それぞれの思う空気公団の音楽もみんな違っていたりして、それがいいと思うんです。
■これ、ニコ動(ニコニコ動画)だったか、逆回転させたものが上がってましたよ。
山崎:ええー、すごい(笑)。
■楽しいですよね。ズラす人がいたら戻す人がいて、ちゃんと戻るわけじゃない......っていうかむしろもっとズレてるんだけど、そのときちょっとだけ世界の厚みは増している、みたいな。
山崎:いいんじゃないですか。かっこいいと思いますよ!
■ズラしという仕掛けがあったからこそ、思いがけないコミュニケーションが生まれて、思いがけない作品の表情をえぐり出したというか。
山崎:中心はあるんですよ。どう読まれてもいい、どう思われてもどうズレていってもおもしろいんじゃないかって思う反面、やっぱり自分たちのなかに中心はあるわけなんです。それを明かさないというだけで。
■詞ではなくてヴォーカルのほうはどうですか? 山崎さんの歌い方にも、空間にズレを生むようなものを感じます。
山崎:ほんとですか?
■それこそ"青い花"の「きみがいて」の「て」とか。極端な話、その「て」の歌い方があるから、「あ、ここに出てくるきみって量産的なラヴ・ソングのきみじゃないんだな」みたいに感じるというか。「きみ」のニュアンスとかイメージも多層的になるんですよね。
山崎:歌詞のなかにもっと入っていってもらうためには、ヴォーカルにクセがないほうがいいというか、そこは気にしてます。登場人物を歌うためっていうよりは、景色を見せるために、って思ってますね。ライヴでも真ん中に行かないんですよね。いつも端にいるんです。空気公団を「町」だと考えると、ヴォーカルが中央にいる必要はないかなと。
[[SplitPage]]- 1. 天空橋から
- 2. ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
- 3. 4層の物語
- 4. 「空気」というキー概念――結成を振り返る
- 5. アニメ『青い花』と
- 6. 山崎ゆかりとラヴ・ソング
- 7. 30を越えること
- 8. 空気公団、新しいコミットメントの可能性
- 9. 明日とはきみのこと
30を越えること
わたしは、空気公団の音楽って、毎日のなかになんとなく流れてて、ふと気づいたらそこにある、みたいになればいいと思ってたんですよ。真正面から流れてるというよりは。
 空気公団 - 夜はそのまなざしの先に流れる BounDEE by SSNW |
■なるほど。芸能の世界だと、女性ってなんだかんだと若さとか容姿の追い風を受けたりする部分もあるじゃないですか。そうじゃなくて、ミュージシャンとして20代を越え30代を越えていくときに、大事になるものとか感じることとかはないですか?
山崎:うーん、あんまり考えたことないかなあ......
■もちろんそういう魅力を消費されるようなバンドではないと思うんですけど。
山崎:最初から古くならないような気がしていたし、いつまでもやっていけるかもしれないというふうに思えましたけどね。そういうことをよくメンバーと飲みながら話してました。
でもだからといっていまも昔と変わらない気持ちかといえば、そんなこともないけど、貫くのがいちばんだって思いますかね。昔言ってたんです。自分たちを砂山だと思って、その砂山を、光が差しているところへ崩れながらでも少しずつ移動させていこうって。移動させるたびにそれはボロボロ崩れていっちゃうんですけどね。自分たちが変化していくっていうんですかね。でもあるとき、もう砂山を移動させる必要はない、「ここに砂山がありますよ」って言いに行けばいいんだって思いました。自分たちが出ていこうというふうに考え方を変えたんです。(移動できる砂山ではなくて)一定の場所にもっとしっかりと作ってしまおう。そういうふうに考えはじめたのは、20代の終わりだったかもしれないですね。
■ああ、へえー。
山崎:やっぱり、揺るがされる瞬間ってあるんですよね。でも、もう揺るがないなと思ったんでしょうね。そこから、はじめに言ったような、何十テイクも録っていいものを作ろうっていう考え方じゃなくなったように思います。もっと自由でじゃないかってなってった。
■なるほど。揺るがないことで、むしろ自由になるんですね。
山崎:自分を表現したいって思ってるわけではないんですよね。気持ちがあるのってもっと奥なんです。自分をアピールしたいというよりは、自分のなかで見えてるものをもっと外に、って思ってました。
■音楽と年齢との関係になにか変化があったりはしないですか?
山崎:べつにないかな。曲を書くぞって思ったときに、歌詞のなかに出てくる男の人の像がふわっと見えてきたりするんですよ。でもその人がいっしょに年をとってるかどうかもよくわからないですね。とってるかもしれないですけど。

空気公団、新しいコミットメントの可能性
昔言ってたんです。自分たちを砂山だと思って、その砂山を、光が差しているところへ崩れながらでも少しずつ移動させていこうって。でもあるとき、もう砂山を移動させる必要はないと思って。「ここに砂山がありますよ」って言いに行けばいいんだって。
■ではもうひとつ。山崎さんはソロとしてではなくて、バンドというかたちで活動しているわけじゃないですか。いまって、たとえば家族ですら、とても偶然的な集団として考えられてたりして、人と人がいっしょに集まっていることの意味が昔ほど自明ではないと思うんですね。この10年、ソロやデュオで音楽やる人もとても増えましたし、バンドってものの意味も空洞化してると思うんです。そんななかで、人と関わって音楽をつくっていくことにどんなことを見出していらっしゃるんでしょう?
山崎:自分ひとりが考えてることってほんとに大したことがないんですね。とくに自分で曲を書いて詞を書いてると、アレンジも想像できたりして。自分は人が好きなので、がっちり合わなくても、ちょっとでも交わっている部分の色を大切にしようって思います。
わたしの場合、自分ひとりで突き詰めたものって、自分の思ってるものじゃなくなる気がする。逆に。
■人と人が交差するかもしれないプラットフォームを準備することのほうに意識があったりするんでしょうか。
山崎:人数が多いといろんなところに点が置けるので。
■ライヴ盤もお客さんふくめたくさんの人が参加してるし、今回のも劇の方々が入ったりと多くの人で構成されてますよね。そうやって人を集めていくというか、同じ意志を持ってるわけでもない、いろんな人の集まる場所を作っていこうという考え方の根本には、何があるんだろうって思うんです。
山崎:うーん、なんでしょうね。
■べつに互いがベタベタしてる関係でもないし。
山崎:3人だけでも欠けているので。3人でやれることは限られてる。だけど、そこのなかには思いが強くあるので、それをわかってくれる人を巻き込んで、もっとおもしろいことができればいいのに、とは思ってますね。上手い下手じゃないですね。窓をいっぱい持たせて、どこの窓から入ってきてもいいよってふうにさせたい。
■人が集まると軋轢が生まれると思うんですよ。まあ、必ずしもそうじゃないかもしれませんけど、人が多いほどストレスも生まれるし、やっぱりそのリスクを避けたくて、多くの人はそこからなるべく隔たって自分の自由なスペースを確保したいって思ってると思うんですよね。いまはそれである程度不自由なく暮らせる条件が揃っているんで。でもそうではないところでつくっているのはなぜなのか......
山崎:でもそれなら空気公団の音楽はちょうどいいですよ。ひとりで聴く人が多いから。
■ははは。それもそうですね。なんで矛盾するんだろ。そうそう、そうやって多くの人が交わりながらもベタつかずにひとりでうまくやってけるんなら、うちらもそうしたいんですよ。......っていう気持ちがすごいあるんですけど。
野田:さっきからうかがってると、共同体とかコミュニティに対する山崎さんなりの視点っていうのがはっきりあるよね。ヴィジョンとして旧来的でない共同体のかたちが頭に描かれているようにも見えますけど。
■そうそう。そんなものがあるのなら社会としても知恵を拝借すべきじゃないですか(笑)。
山崎:「主張したいのは自分だ」っていうのを後ろに置けばいいんじゃないですかね。わかんないけど。CD作りたてのころに、ミックスのエンジニアの人とかによく言われたのが、「『もっと上げてほしい』じゃなくて『もっと下げてほしい』みたいな要望が多いねー」ってことだったんです。「もっと自分の楽器を落としてほしい」とか、下げる方向のことばかりお願いしてたんだけど、「ふつうは上げてくれって言うもんだよ」って。不思議がってましたね。
■それは一種、共存を可能にするスタイルだってことなんですかねー。
山崎:うーん、町を表現するというか、そういうときに重要になるのは、そこに流れているメロディをどうやって伝えるか、だと思うんですよね。
[[SplitPage]]- 1. 天空橋から
- 2. ライヴ盤とライヴ録音のコンセプチュアルな違い
- 3. 4層の物語
- 4. 「空気」というキー概念――結成を振り返る
- 5. アニメ『青い花』と
- 6. 山崎ゆかりとラヴ・ソング
- 7. 30を越えること
- 8. 空気公団、新しいコミットメントの可能性
- 9. 明日とはきみのこと
明日とはきみのこと
流れると、止まるじゃないですか。レコードって。でもまたすぐ明日も来るというか。「明日」っていうのが「きみ」なんですよ。「朝」も「きみ」です。自分はやっぱりひとりでは生きていけない、というか。音楽にはもっと力があるというか。
■まとめのようになりますけれども、"夜と明日のレコード"の「明日」とか「レコード」のイメージってどういうものなんですか?
山崎:これは自分たちのことを言っているような気がして、メンバーもいちばん好きな曲なんです。ここにでてくる彼は、最初に夜に似たものを見せてくれる。彼女に対して。でもそれは「秘密」だと思う。自分なかの。音楽ってどういうものか、ということでもあるし。コミュニケーションに似たものだと思うんですよね。ひとりでは成り立たないものというか。夜と朝があるみたいに、自分と相手もいて。
■アルバム後半は、どんどんテンポ・アップしていきますよね。夜のイメージのなかから、光とか朝とか希望みたいなものがなんとなく暗示されて、この曲が現れてくる。そこで「レコード」にどんなイメージを見ていらっしゃるのかなと思ったんです。
山崎:レコードにこだわっているというわけではないんですけど、音楽ってもっと人を支える力があるということは書きたかったです。スケート・リンクみたいなところに――それがレコードなんですけど――、男女が、ひとり立ち止まって、ひとりぐるぐる回ってて、という絵を想像してました。流れると、止まるじゃないですか。レコードって。でもまたすぐ明日も来るというか。「明日」っていうのが「君」なんですよ。「朝」も「君」です。
■アルバムのことが立体的に見えてきてよかったです。今日はありがとうございました! ちなみに、「人に穴があいている」感覚についてもおうかがいしたいですね。ふつう、人のなかには心臓とか魂とかカタマリを見るものじゃないですか。その逆ですよね、穴は。
山崎:それは電車に乗っているときだったんですけど、ホームには楽しそうにしてたり、携帯をいじってたり、抱き合っている人だったり、いろんな人たちがいて、でもそのみんなに穴が空いているように見えた......すごく言いにくいというか、どう説明していいかわからないんですよね。
■うーん。そこもこじつけになるかもしれないですけど、中心が空洞として捉えられることで、人びとに交通のためのスペースを敷いているようにも思えますね。足すじゃなくて引く、盛るじゃなくて減らす、カタマリではなくて空洞、そこもほんとに一貫してますね。
山崎:もう、演奏者やパフォーマンス、デザインの方すべてにその穴の話をしているんですけど、みんな「なるほど、ああ、そうなんですか......」って......(笑)。
■(笑)。うーん、とか思いながら、なんだろう穴って、とか思いながら、めいめいに穴のイメージを浮かべつつ制作していると。
山崎:1曲めで花束を持っていた男の人は、10曲めの明け方ではもうその穴が何なのかを探す旅に出てしまったので、花束はしおれてしまった。扉を開けると明日があった。それが、穴。そのふたつの曲には山本精一さんを、と思って。
■あ、やはりこのふたつの声が山本精一さんですか。なるほどー。すごく大事な部分をそっと歌ってらっしゃいました。謎がいろいろ解けましたよ。
 空気公団『夜はそのまなざしの先に流れる』
空気公団『夜はそのまなざしの先に流れる』
(DDCZ-1840)
発売日:2012年11月21日
価格:3,000円(税込)
【収録楽曲】
1.天空橋に
2.きれいだ
3. 暗闇に鬼はいない
4. 街路樹と風
5. つむじ風のふくろう
6. 元気ですさよなら
7. にじんで
8. 夜と明日のレコード
9. あなたはわたし
10. これきりのいま
【参加ミュージシャン】
奥田健介(NONA REEVES)
山口とも
tico moon
山本精一
■ライブ情報
空気公団 LIVE TOUR 音・街・巡・旅 2013
――夜はそのまなざしの先に流れる 2013.2.11ー2013.6.15
2013年2月11日(月・祝日) @渋谷WWW
演奏:空気公団 / ゲスト:山本精一
Info: https://www.kukikodan.com
https://www-shibuya.jp/schedule/1302/003174.html
空気公団オフィシャル・サイト:https://www.kukikodan.com/