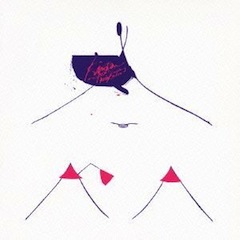MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 禁断の多数決- はじめにアイがあった
面白い。くだらない。そして、素晴らしい(田中宗一郎なら「ははは」と書くところだ)。てんぷらちゃん、尾苗愛、ローラーガール、シノザキサトシ、はましたまさし、ほうのきかずなり、処女ブラジルを名乗る、まったく名乗る気のない7人組=禁断の多数決のデビュー・フルレンス『はじめにアイがあった』は、最初からリミックス・アルバムとしてレコーディングされたような、奇妙な位相差を含んだ作品である。
半年ほど前になるだろうか、編集部から送られた『禁断の予告編』なるプレ・デビュー作は、はっきり言ってパロディとしか思えなかったが、本作がそこから遥かに飛躍しているのは、すべての行為がパロディ/引用として振る舞ってしまうポストモダンの辛さを、前向きな貪欲さで迎撃しているからだろう。TSUTAYAで面陳されたJ-POPと、親の書棚から拝借したオールディーズと、YouTubeで聴き漁ったアニコレ以降のUSインディを片っ端からメガ・ミックスしたあと、派手なエディットでぶっ飛ばしたような......そうした音楽がここにある。
あらゆる表現においてメモリがほぼ食い尽くされた同時代への意識がそうさせるのだろうか、そうした編集者目線は彼らのポップに奇妙な分裂性(リミックス感)をもたらすことになる。驚いたことに、もしかすると本人らは意識していないかもしれないが、"The Beach"や"Night Safari"は完全にヴェイパーウェイヴ・ポップで、人工度の高いオフィス・ミュージック(のフリをしたサイケデリック・ミュージック)の上に、メンバーの声が無表情に浮かんでいる(これがけっこう、コワい)。
また、壊れたロックンロール、ないしブルックリンのフリーク・フォークを思い出させる"World's End"、ノイジーなハウス・ビートにクリーン・ギターが浮つくシンセ・ポップ"アナザーワールド"、フレーミング・リップスを思わせるハッピー・サッドなドリーム・ポップ"チェンジ・ザ・ワールド"と、目まぐるしいエディットのなかで世界というタームがクリシェのような使い方をされ、問題を提起する前にさらっと消費されているあたり、このバンドの身軽さを象徴するようだ。
まんまオールディーズ・パロディな"Sweet Angel"もいい。けれども、教養主義的な名盤ガイドで仕込んだようなポップ音楽の記憶は、もしかしたらもう邪魔なだけなのかもしれない。昨今のポップ・ミュージックをめぐる膨大な情報量(http://www.ele-king.net/columns/002373/)は、これまでの常識からすれば、すでに一人の人間が体系的に俯瞰できる量を物理的に超えている。だから、極論すれば、iTunes/Soundcloud/Bandcampなどのネイティブ・ユーザーにとって、録音音楽の一義的な差異は、もはやURLやタグの違いでしかないわけだ。
『はじめにアイがあった』は、あるいは音楽をそのように扱っている。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとパフュームのどちらが偉いかなんて、まるで考えたこともない。そう、禁断の多数決は、例えばそのような狭量さの先へとずんずんカット・インしていく。批評性を失効させることで立ち上がる何か。正史が定められたかに見えるポップ音楽の記憶を、彼らはリズミックに改ざんしている。「ポップ(多数)」なき時代のポップはどこにある? 一見、軽薄に見える態度とは裏腹に、彼らの問いかけは切実である。
もっとも、『はじめにアイがあった』に一票を投じるなら、村社会内での終わらない相互孫引き(=近親相姦)がこの国のポップ・ミュージックを疲弊させている事実にも目を向けなければならないだろう。ぐるぐると無限に再流通する音楽群を前にして、「俺たちは音楽を知らない」とシャウトすること。無限に可視化されてしまった情報を前に、目を閉じて叫び散らすこと。批評性と呼ぶのが大げさなら、神聖かまってちゃんが体現したそれは、何かしらのSOSとも言えただろうか。
とするならば、禁断の多数決から感じるのは、この広い海を引用にまみれながらも泳ぎ切ってやろうとする前向きさである。どう聴いてみても、器用さやシニカルな愛情だけでなせる業ではない。彼らはここで、どこにも行けないその場所で、楽しんでやると決めたのだ、おそらくは満場一致の多数決で。みんなで寝そべって、ポップ音楽のアーカイブをフラットなトランプにして、ババ抜きでもして遊んでいるようじゃないか。副題を付けるなら「さらば相対性理論」。J-POPの退屈さを呪ったJ-POPによる逆襲である。
竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE