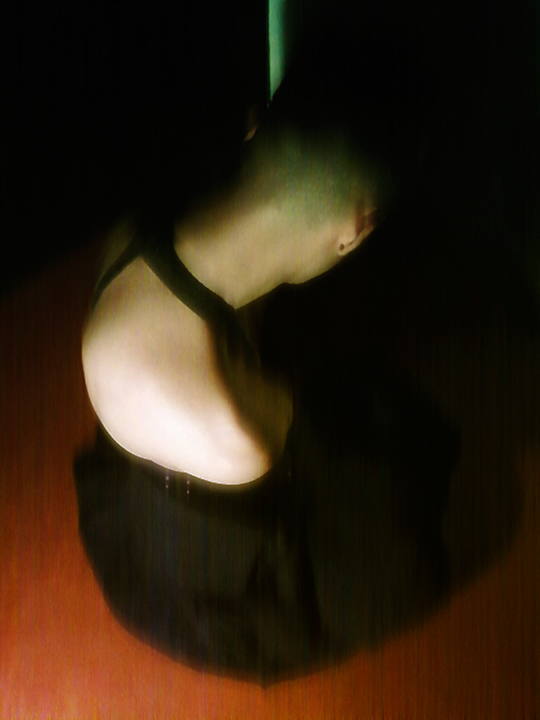MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース
- 『成功したオタク』 -
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙
Home > Interviews > interview with Arca - ベネズエラ、性、ゼンとの出会い
たとえ愛の意味がわからなくってもね。あのころの僕は性的にまったく満たされていなかった。じつは、僕ってとーってもクローゼットだったんだ。自分がゲイだっていうことはかなり昔からわかっていた。でもね、ベネズエラの社会ではそれに気づくことすら許されないんだ
  Arca Xen Mute / トラフィック |
ゲルシは1年とちょっと前にニューヨークからロンドンへと居を移し、彼いわく、この引っ越しはボーイ・フレンドである写真家/マルチメディア・アーティストのダニエル・サンウォールドの近くにいたいという気持ちがいちばんだったと語る。またカンダともっと仕事をやりやすくする手段でもあった。彼はカナダで育ったのだが、ここ10年以上、ゲルシの親友でもっとも近しいアーティスト・コラボレーターである(彼自身は7年前にカナダからロンドンに移住している)。彼らが住居を構えて以降、ゲルシは単独の共作者として、またひとつ世間から渇望されているポップ・アルバムであるビョークとの作業を終えた。彼女の2000年代初期から続く変幻自在のシンセポップ、その力強いバラッドは、奇しくもゲルシの音への硬派な方法論を予見していたかのように感じられる。「ゼン」という、彼の空想上のもうひとつの人格がタイトルとコンセプトとなっているゲルシ自身のニュー・アルバムも、ビョーク作品と同様の仕上がりだ。カンダが手がけたアルバムのブックレットには、ダンスや犬の散歩から自慰行為にいたるまで、彼女(ゼン)のさまざまな表情や年齢、日常のストーリーのイメージが収められたポートレートが描かれている。それらはゲルシ自身の写真をもとに作られており、その表現のなかで身体は原型をとどめていない(ゲルシはゼンのことを「ハー(彼女)」と表現するが、その彼女は男性でも女性でもないという)。ゲルシがレコーディング・スタジオで、カンダが2階のベッド・ルームでゼンに魂を吹き込む。その過程についての説明から、ふたりにとって仕事と遊びの境界線が曖昧になっているのは明らかである。
「僕らは多くのことに閃めいた。それは共同生活によって起こりえたことなんじゃないかな」とゲルシは言う。「ふたりで2階に駆け上って問題を解決したら、1階に舞い戻って僕がヴォーカルとストリングスなどのふたつのサウンドを組み合わせる」。表面上、ふたりの間柄は親友関係とは真逆である。カンダは力強い眉を持ち身長もゲルシより高い。静かでシニカルなところもゲルシのおしゃべりな気質とはちがう。けれどもカンダにゼンのキャラクターをどのように描写するのかを尋ねてみると、彼らがなん人も持ち得ないお互いの一部を共有しているのだと確信する。「アレハンドロにはいくつもの人格がある」とカンダは語る。「それに彼はたまに、冗談で僕らがゼンと呼ぶものにだってなれる。それは生意気で自身に満ちあふれた、彼のすごく女性的な部分だね。そしたら『おー、彼女(ゼン)が出てきたぞ』って僕らは言うんだ。大抵は僕らがウィードを吸ってふざけてるときだけどね。『ゼンが現れる』。するとゲルシは上着を着替えたり、いろいろやらかしたりでクレージーになる。彼のなかのゼンの仕業だよ。一種の幽霊みたいなものかな。もしくはアレハンドロの精霊だね」
今日にいたるまで、ゲルシはたくさんの家で暮らしてきた。ある場所はゼンにとって居心地がよく、そうでない場所もあった。投資銀行の銀行員だった彼の父がニューヨークへ転勤となり、家族もいっしょに故郷のカラカスを離れノース・メトロ鉄道郊外の街コネチカット州のデリエンに引っ越した。ゲルシが3歳のときのことだ。その当時のことを彼はそんなには思い出せない。思い出の大部分は「森のなかには大きな家があって、地下の部屋にはスーパーファミコン」というものである。だが、9歳で家族とともにカラカスに戻ってきたときには、英語もペラペラでアメリカの漫画もすらすら読めた。つまり、彼が故郷に帰ってきたときには少し場違いな感じを覚えるのには十分な時間が流れていた。そのように彼が感じた理由のひとつには、カラカスが政情不安、オイル・マネーの加速や貧困によって揺れ動いていたことも関係している。子どもが安全に外で走ったり遊んだりできる場所ではなかった。
「僕がそこに住んでいた時期は、マジでクソみたいな出来事ばっかり起きていた」と彼は言う。「国の名前もベネズエラ共和国からベネズエラ・ボリバリアーナ共和国に変わって、通貨の名前も少し変更された。僕は私立の学校へ通っていたんだけど、友だちはボディガードやドライバー付きで防弾仕様の車に乗っていたね。一軒家は簡単に侵入されるから、みんな綺麗なアパートへ越していった。玄関にセキュリティがいるからね」(※)
(※編集部注)
1999年、大統領に就任した軍人のウーゴ・チャベスは、社会主義的な理念と反米、反新自由主義を掲げながら、国名もベネズエラ・ボリバル共和国に変更。しかしながら、貧困や格差問題はさらに深刻化して、治安の悪化は加速した。アルカの場合は、記事を読めばわかるように貧困層ではないが、なかば暴力的なプレッシャーを受けていたことがうかがえる。独裁政権でもあったチャベスに対する評価については他にゆずる。
ゲルシの両親は彼に良い学校に通わせ、門扉に囲まれた環境や音楽レッスンの機会などを与えた。比較的快適で教育熱心な両親だったが、若き日のゲルシは、いかなる国の経済的背景に育った子どもにもひとしく影響を与えうるものを経験した。彼が16歳になったとき、両親が夫婦関係の障害に直面し、長い期間にわたって別れたり復縁したりするようになる。彼はこの期間が「自分を大いに成長させてくれた」と語る。彼の家庭がますます惨憺たる状況になるにつれて、彼も自分が他の男子たちとはちがうことに気づいていった。「僕は13歳のときに、スパイス・ガールズの映画『スパイス・ガールズ』を見て、すごく気に入った、みたいなことをよく日記に書いていた。ときどき、その日記にゼンという名前でサインしていたよ。自分がリヴィングで毛布にくるまって遊んでいて、その場に母親がいると、僕は毛布をマントみたいにしていた。でも、ママがいなくなったらすぐにそれをドレスみたいにしていたよ。その瞬間の僕が本当の自分だと感じた。わかるでしょ?」
彼は7歳から16歳になるまで、クラシック・ピアノを学んでいた。ゲルシにとってはミュージシャンとしての準備期間だったわけだが、ピアノはときとして自身の開放というよりも義務的なものとして働いていたと彼は言う。兄のCDコレクションに助けを借りながら、90年代に育ったキッズが夢中になる一連の典型的なミュージシャン(アリーヤ、オウテカ、ナイン・インチ・ネイルズ、マリリン・マンソンなど)にゲルシは入れこみ、インターネットに使う時間も増えていった。最終的にデジタル・グラフィックへの尽きない興味から、彼は、ユーザーが自作の画像やそれに対するコメントをアップできる初期のSNSのデヴィアントアートへとたどり着く。当時、4000マイルも遠くに住んでいたカンダとゲルシが初めて出会った場所はこのサイトだった。フルーティ・ループスでの基本的なIDMの制作を通し、ゲルシが音楽に没頭する時間が増えていくいつれて、カンダは単なるフレンド・リストのアイコンであることから、ゲルシの最初のクリエイティヴなパートナーへと変わった。「彼はいつも僕の第二の目みたいだったよ。もしくは第二の耳だね。僕たちにとってあのサイトは本当に意義深いものだった。デヴィアンアートを使っている連中のほとんどは似たようなことばっかり繰り返している。現実逃避みたいなものだよ」
プレスはまったく触れていないかもしれないが、ゲルシの高校時代のプロジェクトであるニューロはまだネットで聴くことができる。初期の音源の大半はグリッチやエイフェックス・ツインに感化されたビート構築だが、それらに合わせて彼は自らの歌声を披露したりもする。そのため、仕上がりはほのかに野心的なサウンドで、スペイン語版のザ・ポスタル・サービスのようだ。
「理由はいくつかあるんだけど、僕はラヴ・ソングをよく書いていたんだよ」と彼は回想する。「たとえ愛の意味がわからなくってもね。あのころの僕は性的にまったく満たされていなかった。じつは、僕ってとーってもクローゼットだったんだ。自分がゲイだっていうことはかなり昔からわかっていた。でもね、ベネズエラの社会ではそれに気づくことすら許されないんだ」
ニューロの曲が初期のMP3ブログに掲載されると、最終的にはライヴの依頼が舞い込み、メキシコのインディ・レーベル〈サウンドシスター〉と契約を結ぶにいたる。プロジェクトがオンラインで勢いづいてくると、彼は高校の同級生から注目を浴びた。ゲルシは生まれて初めてオフラインの世界で、自分が人気を得ていることを同世代と分かち合あうようになったのだ。彼はパーティに通うようになり、高校の女の子とデートをし、女性の一人称でラヴ・ソングを歌いはじめた。自分自身が「認められる」ことを願いつつ。ゲイであることをオープンにするとストリートで暴力を受けるような街において、他に選択肢はなかったのかもしれない。
「一生カミングアウトしないつもりでいたね。結婚して自分が夫としての役割を果たす姿をずっと思い描いていたかな。思い返せば、ゲイをやめたいって祈ってた。自分がどうかストレートになれますようにってね」
17歳のときに彼はニューヨーク大学の教養学部の入学許可を得たが、最終的にはティッシュ芸術大学のクライヴ・デイヴィス録音音楽科で学位を取るつもりだった。そして、それはニューヨークへ引っ越したらニューロを終らせて、音楽を共有することから身を引くということも意味していた。「2、3年くらい化石なっちゃったみたいだった。振り返ってみると、自分と結んだ神聖な契約みたいなものを破ったからだと思う。偽るのではなく、みんなのためにただ音楽を作るっていうね」
それと同時に、ひとりで暮らすことは、彼がいままで負ったことのないリスクを冒すために必要な一押しとなった。故郷から遠く離れた巨大な都市では、生まれた場所で自分自身をアウトサイダーだと感じてきた何千もの人びとがうごめいていた。
霧が立ちこめるとある夏の夜。大学に入って2年めのこと。ゲルシはチャイナタウンに住んでいた。そのころ彼が夢中になっていたのはダウンタウンのミュージカルに革命をもたらした、ティム・ローレンスの伝記にあるカウンター・カルチャーのロマンス。そしてゲイ・アイコンであるアーサー・ラッセルだった。
「人生のあの夜まで、自分のことを知られないように僕はかなり徹底して他人の視線を拒否していた」と彼は言う。「その晩、ユニオン・スクエアの地下鉄駅である男を見つめていたのを覚えている。駅はとても暑くてうるさかったな。彼はプラットフォームの階段の側に立っていて、彼はこっちを向いて、僕も彼を見ていた。それより前の僕だったら、すぐに目をそらしていただろうね。でもアーサー・ラッセルの話と音楽に勇気をもらったこともあって、『今日がそのときだ』って決心した。その男のほうに歩いていき、『今度、コーヒーでも飲みにいかない?』って文字通り言葉が僕から出てきたんだよ」
次の日ゲルシはその見知らぬハンサムな男とシンク・コーヒーで落ち合った。会話からキスへ、キスから相手の家で夜を過ごすことへ発展した。
翌朝、ゲルシは自分のアパートまでわざわざ歩いて帰ることにした。家に着くと、笑みを浮かべながら当時のルームメイトだったジェイコブに、ちょっとそのへんでも散歩しないかともちかけた。親しい友人に初めてカミングアウトした体験を思い出すと、ゲルシはわたしがロンドンにいるときに何回か耳にしたメタファーに戻る。それは、人生を変えてしまうような決断の崖っぷちに立たされた彼の、そのキャリアの一幕に触れるときに必ず出てくるものだ。
「断崖絶壁から飛び込むようなものだね。生存本能がそれを止めさせるんだけど、自分のなかの何かが僕を前に進める。なんで崖から飛び降りるかと言えば、地面に落ちる時間や、たくさんのレゴみたいにバラバラになってしまうことがわかるからだよ。そしてかつて自分だったかけらを拾い集めるんだ。でも都合がいいようにかけらを組み立てることはできないし、そのピースの集合体は元の自分のようには感じられない。飛び降りるたびに、本当に美しくて豊かで、そして不愉快なチャンスが訪れる。かけらを組み立てた体は完全じゃないんだけど、インスピレーションを与えてくれるものや、人生のすべてだと思えるものを自分自身の本質が教えてくれるんだよ。それが僕の身に起こったことだね」
農場にある軋む床の家屋の部屋のように、ゲルシのスタジオは森のにおいがする。庭にある長方形の独立した小屋は、かつては温室だったにちがいない。ゲルシはコンピュータの前に座って作業をし、休憩中にハンギングプラントに水をあげたり、引き出しにしまわれたマイクをときおり取り出していた。そのようにしてデビュー・アルバムの大半の制作とミックスがここで行なわれたのだ。
とある日の午後、音楽ジャーナリストにとって夢のような話だが、自分の作曲過程を生で披露するために彼はパソコンの電源を入れてくれた。アイゾトープ社のアイリスと呼ばれるべつのプログラムを使って、彼は芝刈り機の音を取り出して、その周波数グラフのランダムで幾何学的な形を切り刻み、ネズミの鳴き声のコーラスのような音を作り出す。一方でエイブルトンを起動させ、小さな球状の波形データをタイムラインに配置し、コピー&ペースト繰り返しながら手作業でビートを構築していく。作業は素早く行なわれ、目では追いきれない早さで作曲は拡大し、画像的には数分ごとに都市の地図が広がっていくような光景がスクリーンには広がっていった。庭で猫のトゥルーが悲しそうに鳴きはじめると、「彼女もピッチベンドしてるんだね!」とゲルシは大声を出した。そして、わたしはあることに気づいた。彼は音を聴きながら曲を作っていないのだ。頭のなかで、どのよう何の音が鳴っているかわかっているのだろう。
文:エミリー・フライドランダー(2014年10月31日)
Profile
 髙橋勇人(たかはし はやと)
髙橋勇人(たかはし はやと)1990年、静岡県浜松市生まれ。ロンドン在住。音楽ライター。電子音楽や思想について『ele-king』や『現代思想』などに寄稿。
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE