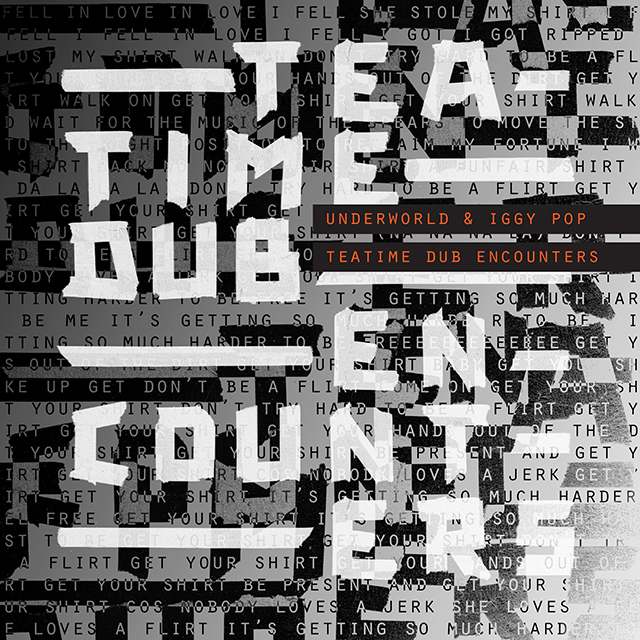たしかいまから3ヶ月ほど前、OLD DAYS TAILORのレコーディングのために大分から東京に出てきていた増村君とひょんなことから吉祥寺で飲むことになった。その時、GONNO×MASUMURAのレコ発の話になって、さらには、対バンは誰が良いかな~というような話になったのだった。安い焼酎が数杯入って無責任な精神になっていた私は、単純に自分が観たいだけという理由で、トリプルファイヤーが良いよ! と提案したのだった。まあ全然ファン層も違うし却下されるだろうな、と思っていたら本当に決まってしまっていた(告知で知った)。
アルバム『In Circles』のレヴューでも書いたが、GONNO×MASUMURAのリズムへの意識の鋭敏さは、改めて言うまでもなくすごい。生ドラムと打ち込みという相互関係が表出する揺らめきまでも含め、国内で今ここまで自覚的にリズムへ対して取り組むアーティストは稀有であると思っていた。そして、トリプルファイヤーも(その特異な立ち姿や「面白い」歌詞世界に幻惑されてしまいがちであるが)同じくリズムに対して鋭敏な視点を持っている稀有なバンドである。アフロビートや変拍子を取り入れながらも極めて沈着、しかし、そこに内在する熱は、ずっと触れ続けていると知らぬうちに低温火傷を起こしそうなほどに豊か。一見ミスマッチな組み合わせに思えるかも知れないけれど、だからこそこの両者が相まみえる面白さは格別だ。
はじめに登場したトリプルファイヤーは、パーカッション担当のシマダボーイをサポートに迎えた4人体制。このところの演奏の充実ぶりを伺わせる盤石のライヴで、トリッキーだが統御の行き届いた硬質(なのに靭やかな)グルーヴ。おそらくGONNNOのファンと思われるお客さんがその演奏にじわじわ魅入られていくのを横目で見ながら、ビールを一杯、二杯。途中ボーカルの吉田がMC(僕はいつもライヴ演奏と同じくらいこれを楽しみにしている)で「今日は呼んでもらってありがとうございます……今日は音楽的な現場で……なんかすごく……(突然大声で)今日は音楽的に凄い人たちとやってまーす!」と言い、私は爆笑してしまったのだけど、あまり他に笑っている人がいなく少し気まずい思いで回りを見渡していたら、微笑を浮かべるGONNO×MASUMURAの二人がいた。
この日のトリプルファイヤーは新曲を織り交ぜたセットリスト。私は体を揺らしながらも、リズムやリフなどそれぞれの曲の構造を把握すべく頭の中を整理しようとするのだけど、そこへ歌声が次々と鮮烈な意味を注入してくるので、忙しく、そして楽しい。あっという間に終わってしまったような感覚。搬入バイトを終えて現地解散する人たちのように楽屋に戻っていくメンバーの様が格好良い。
ステージ上、ごっそりとセットチェンジが行われる間、主役目当てのお客さん達も徐々に増えてきたようで、自然とフロアにも熱気が篭ってくる。
いつの間に会場へ到着したのか野田編集長が客席下手スピーカー前の柵に寄りかかって近距離から増村のセッティングを凝視している。「いやあ、二人とも緊張しているね」そう、実はGONNO×MASUMURAとしてライヴを行うのは今回がたった二度目のことなのだという。だからこそ、今ライヴを観ることに価値がある。
ラップトップやミキサー卓などの機材の山を前にしたGONNOが徐々に電子音を響き渡らせ始め、それに呼応するように増村のドラムが静かに交わっていく。時折アイコンタクトを織り交ぜながら繰り広げられていく演奏は、決まり事があるようでいて無いようでもある、インプロヴィゼーションと非インプロヴィゼーションの境界を内部から溶かしていくようなスリルを帯びる。GONNNOのDJイングは精密でありながら大胆で、増村もそれに煽られるように即妙のフレーズを叩き込んでいく。
ポップ・ミュージックにおける一般的なドラミングでは、リズムキープとフィルという要素が繰り返させることにより、曲自体の構造が釘打ちされ建築物としての楽曲構成が立ち上がってくるものだが、ここではそういったプレイ上の境界も溶かされ、電子音と相克しながらまるでパルス的鼓動の如く空間をリズムで満たしていく。GONNOのプレイも、テクノ・ミュージック一般におけるマシーン的反復性の快楽を携えながらも、生ドラムが叩き出すリズムのしなりに焚き付けられるように、変幻していく。
最初のうちは緊張感の漂っていたフロアも、気づけば思い思いに体を躍動している。体感音量はどんどんと上がっていき、ステージ上のふたりもプレイ前のこわばりが嘘のように自らの奏でる音楽に身を委ねる。アルバム終曲を飾る「Ineffable」でライヴはついにクライマックスに達し、その天上的アフロ・バレアリックとでも呼ぶべき世界が昂まりと静けさを同時に召喚する。
ダブル・アンコールを欲するオーディエンスの前に三度現れたGONNOと増村が、「もっと演りたいんですけど、演れる曲がありません(笑)」と口下手に言ってみせると、空間に充満した音楽がフッと発散されるように辺りに笑みが広がり、幕は穏やかに閉じられた。
それにしてもこの日、トリプルファイヤーとGONNO×MASUMURAの二組の創出した空間の差異、それこそがライヴイベントの醍醐味というべきものだった。二組は、個的なリズムフォルムへの拘り・固執という点では志を共有しつつも、そのリズムを楽曲構成の中でどう位置づけ、そしてライヴ演奏の場でどのように実践するかという方法論においては全く違った行き方を取っている。本来そういった方法論が演奏集団によって十者十様であるという(自明すぎてむしろあまり顧みられることの少ない)音楽を楽しむにあたっての重要な視点が、これほどまでに鮮烈に提供された空間は稀だったかもしれない。
音楽は共通言語として(観客含め)いかようにも共有されうるが、コンテクストの差異を味わうことは、その共有と理解に更なるダイナミズムを与えることが出来る。いわゆる「客層」判断上のマーケティング的視点からの躊躇や、一定ファンへの「配慮」などから、なかなかそうしたキャスティングが難しい状況もあるだろうが、こういったイベントがどんどん増えて欲しいと思う。