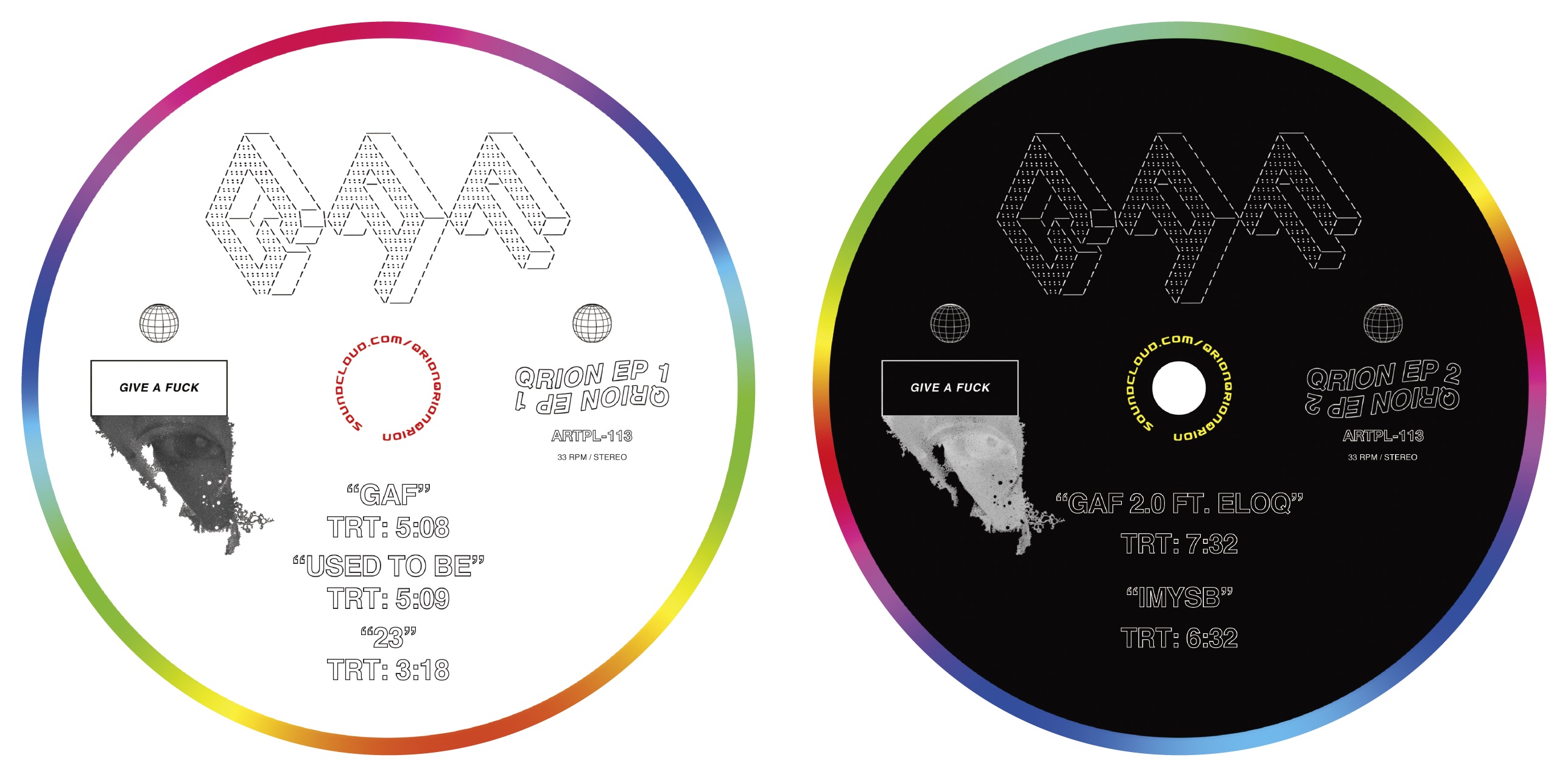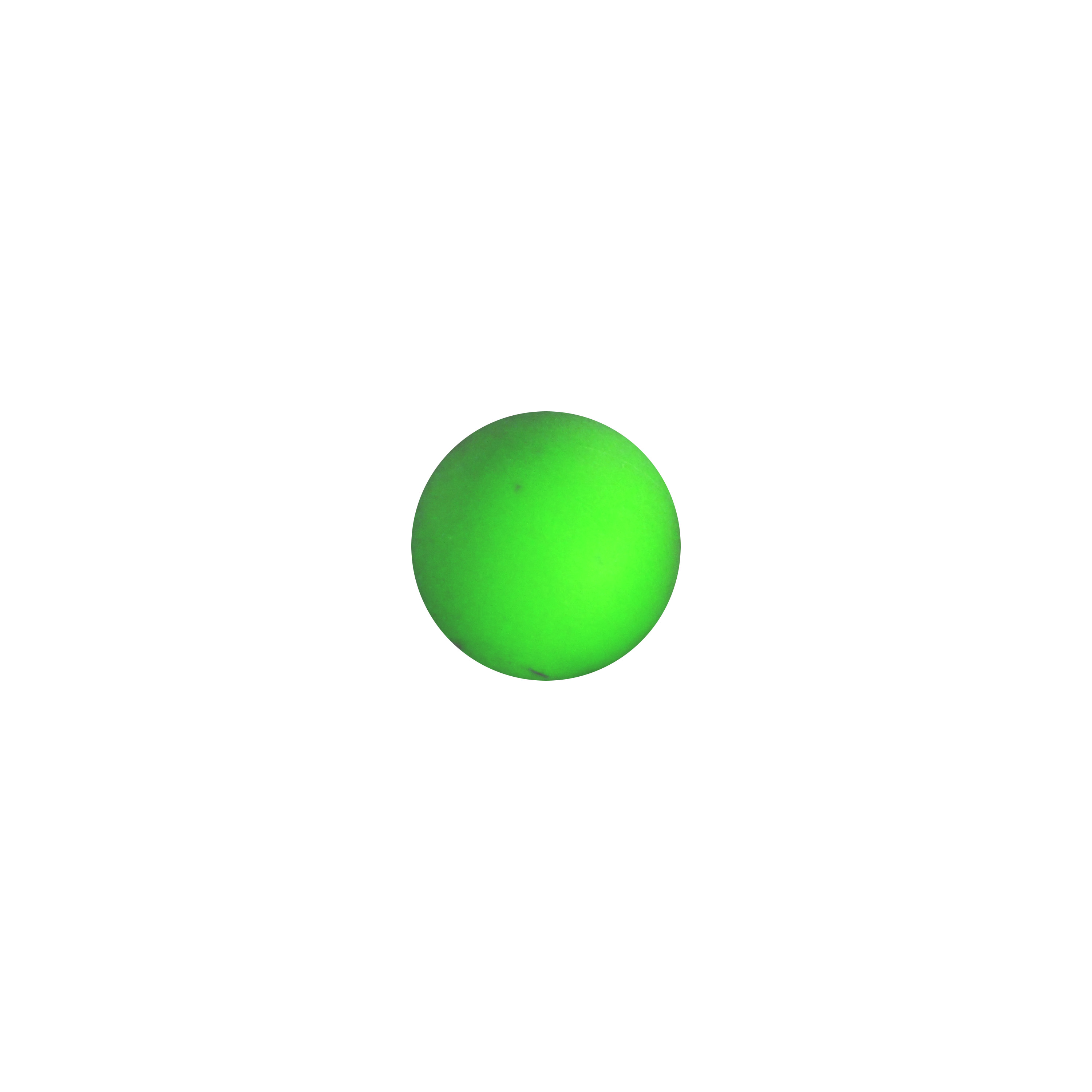年明けに「日本」をテーマにした作品『Heritage』を発表したマーク・ド・クライヴ=ロウが、新たなプロジェクトを開始する。WONK や CRO-MAGNON、KYOTO JAZZ SEXTET や SLEEP WALKER などのメンバーたちと組んだ「浪人アーケストラ」がそれだ。『Heritage』に続いて彼のルーツである「日本」がテーマになっている模様。アルバム『Sonkei』は9月25日に発売。なお、明日7月27日にはマーク・ド・クライヴ=ロウ個人の来日公演も開催されるので、そちらもチェック。
マーク・ド・クライヴ=ロウ来日情報:
https://wallwall.tokyo/schedule/mark-de-clive-lowe-melanie-charles/
RONIN ARKESTRA(浪人アーケストラ)
Sonkei
MARK DE CLIVE-LOWE の呼びかけで、ジャズを中心に日本の精鋭プレイヤーが集結したニュー・バンド RONIN ARKESTRA (浪人アーケストラ)!!
WONK、CRO-MAGNON、KYOTO JAZZ SEXTET 等のメンバーが参加、待望のデビュー・アルバム完成!!

Official HP: https://www.ringstokyo.com/roninarkestra
マーク・ド・クライヴ・ロウが『Heritage』に続いて、自身のルーツである「日本」にフォーカスしたプロジェクトが、浪人アーケストラです。LAから東京へと場所を移し、日本人のプレイヤーたちと作り上げたアルバムは、日本のジャズの歴史に新しいページを刻む作品となりました。 (原 雅明 ringsプロデューサー)

アーティスト : RONIN ARKESTRA (浪人アーケストラ)
タイトル : Sonkei (ソンケイ)
発売日 : 2019/9/25
価格 : 2,800円 + 税
レーベル/品番 : rings (RINC56)
フォーマット : CD
Tracklist :
1. Lullabies of the Lost
2. Onkochishin
3. Elegy of Entrapment
4. The Art of Altercation
5. Cosmic Collisions
6. Circle of Transmigration
7. Fallen Angel
8. Tempestuous Temperaments
& Bonus Track 2曲収録決定!!
参加ミュージシャン:
MARK DE CLIVE-LOWE
荒田洸 (WONK)
コスガツヨシ (CRO-MAGNON)
藤井伸昭 (Sleep Walker)
類家心平 (RS5pb)
安藤康平 (MELRAW)
池田憲一 (ROOT SOUL)
浜崎 航
石若 駿
Sauce81