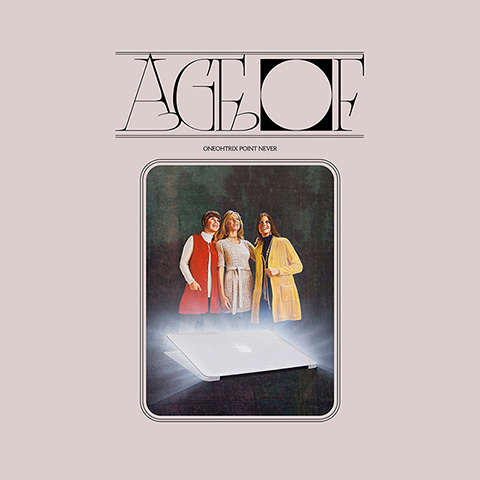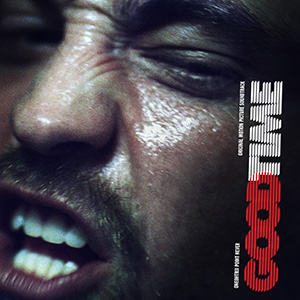MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Oneohtrix Point Never- Age Of
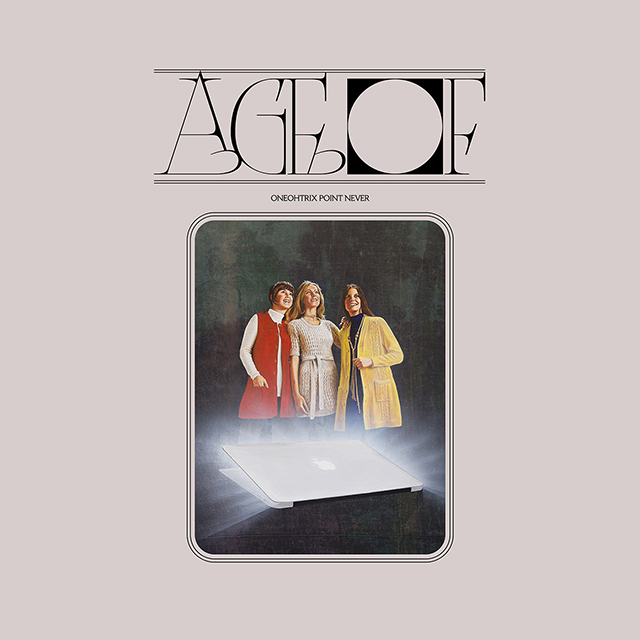
作者が死んだのはちょうど50年前のことである。テクストは作者の考えていることを表したものではないし、ましてや作者の人間としての内面を吐露したものなどでは断じてない。テクストは引用の織物であり、内面なんてものはそれが言語によってしか説明されえない以上、すべて事後的に構成されるものである。
もちろん、そのように人間を縮減していく試みは、19世紀の終わりから20世紀半ばにかけて何度も試みられてきた。詩人は言葉に主導権を譲らねばならないと主張した詩人、書物は日常生活を営む自我とはべつの自我によって生み出されると考えた小説家、ゲームや無意識など主体のコントロール外にある偶然的要素を創作に活かそうとした文学・美術グループ、あるいは「この女」と言うためにはその女から実態を剥奪し殺戮してしまわなければならないと説いた批評家。けれど、よりわかりやすい形で人間としての作者に死が与えられたのは、やはり1968年ということになるだろう。ようするにそれは、なんらかの対象について語るとき、それを生産した人間に着目するのはいい加減やめませんか、という提案である。そのような反人間的な発想が現れてから、もう半世紀ものときが流れたのだ。
どうやらワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンもまたこの問題について考えを巡らせることがあったようで、先日公開された最新インタヴューにおいて彼は、われわれはついつい「この人間そのものの表現だ」と思えるような「苛烈なまでにパーソナルな表現」を賞賛しがちだけれども、自分は「演奏する人間が排除されている」ような「音楽機械」にこそ心惹かれる、と語っている。つまり、いままさにここでおこなわれているように、彼という人間をとおして彼の鳴らす音を説明しようとするのはもうやめませんか、ということである。たいせつなのは人間じゃなくてそこで鳴っている音でしょうよ、というわけだ。アンチ・ヒューマニズムである。
とはいえOPNは、その発言によって自らの作品をパフォーマティヴに変容させていくタイプのアーティストでもある(同じインタヴューで彼が録音物ですら変化しうると言っているのは、そういう外在的な効果を念頭に置いてのことだろう)。その作品の強度と発言をつうじて、いまや10年代でもっとも重要な電子音楽家と言っても過言ではないほどの存在にまでのぼり詰めたOPN、あまりに大きな期待を背負って発表されたその8枚目のアルバムは、われわれの予想をはるかに超えるアイディアとサウンドをもって、いまふたたび彼のキャリアを更新している。
どきどきしながら再生ボタンを押すと、すぐさまチェンバロの音が耳に飛び込んでくる。その響きと音階はバロック音楽の雰囲気を醸し出しているが、そのムードは幾度か差し挟まれる叫びとノイズ、そして中盤で30秒ほど挿入されるインスト・ポップ・バラードとでも呼ぶべき謎めいたパートによって破壊されてもいる。異なる時代を強制的に接合するコラージュ。冒頭のこの表題曲の時点ですでにロパティンの勝利は確定したも同然だが、続けざまに「バビロ~ン♪」という加工された音声が流れてくるのを耳にした瞬間、われわれはさらなる驚異と遭遇することになる。歌である。それも、ダニエル・ロパティン本人による歌だ。
その旋律はポップ・ソングによくある「いかにも」な進行を見せる。押韻もわかりやすい。途中でプルーリエントによるスクリームが挿入されるものの、それでも曲はクリシェであることを全うしようともがき続ける。「ヘルプ・ミー」という高い声が乱入する。クレジットを確認して初めてそれがアノーニによるものであることがわかる。助けて。しかしロパティンは歌うことをやめない。「わかったよ/なんで君が僕らがバビロンにいると思うのかを」。助けて。「わかったんだ/なぜ君がこのバビロンから離れられないのかを」。そしてトラックは解決らしい解決を見ないまま唐突に終わりを迎える。バビロン。それはいったいなんの比喩だろう。インターネットか。資本主義か。それとも、常世すべてか。
OPNらしい鍵盤とシンセが横溢する3曲目へと至ってようやく、われわれはこれがあのOPNの新作であることを思い出す。アッシャーのために書かれながらもアッシャーには使ってもらえなかったという“The Station”は、前半のロパティンによる歌を否定するかのようなミニマルなギター音の反復をもってリスナーに先を急がせる。ミュージシャンがよく口にする「架空のサウンドトラック」というクリシェを試したという“Toys 2”は、卓球のような具体音と『アール・プラス・セヴン』で展開されていた賛美歌風音声ドローンの断片、『ガーデン・オブ・ディリート』のような強烈なノイズと東洋風の旋律によるかき乱しを経て、初期のOPNを思わせる穏やかなシンセ・ミュージックを響かせる。そしてアルバムは先行公開された問題曲“Black Snow”へ到達する。吐息とフィンガースナップに誘導され、「盲目のヴィジョン/盲目の信念」と、ロパティンは静かに歌いはじめる。リリックはニック・ランドが設立に関わったCCRUの論集からインスパイアされている。バッキングに徹するアノーニ。東洋的なモティーフとノイズの手前で、ダクソフォンが不気味な唸りを上げる。
アルバムはふたたびチェンバロを呼び込み、大規模なアート・プロジェクトを成功させるためには金融業者と仲良くならなければならないことを諷刺した小品“myriad.Industries”をもって、その後半を開始する。『R+7』の延長線上にあるトラックのうえでプルーリエントが雄叫びをあげる“Warning”や、ミュジーク・コンクレートとインダストリアルを同時に試みたかつてない作風の“We'll Take It”、ようやくアノーニがそれらしい歌声を披露する“Same”など、最後まで聴き手を飽きさせないトラックが続く。『R+7』から目立ちはじめ、『GOD』において突き詰められた、ポップ・ミュージックのメタ的な解体作業。『エイジ・オブ』ではそれがより尖鋭的な手法をもって実践されている。あるいは逆の見方をすればそれは、いわゆる大きな物語が機能しなくなり、幾千の島宇宙がそれぞれに閉じたサークルを形成するポストモダン以降の情況にあって、電子音楽の冒険を電子音楽ファンのなかでのみ完結するものにはしないという強い意志と捉えることもできる。
ともあれ本作の肝をなす自身の歌唱と、アノーニやプルーリエントといったゲストの参加、あるいはダクソフォンの活用は、前作でチップスピーチを導入していたロパティンにおける声への志向性が、いま、ますます高まっていることを示している。けれどもそれらの声は著しく加工され変調され切り刻まれ、歌い手のキャラクターを尊重しない。声そのものへのアプローチを突き詰めつつもロパティンは、けっしてその人間性には依拠しようとしないのである。それはたとえばジェイムス・ブレイクの起用法にも表れていて、あくまでも彼はキイボーディストおよびミックス・エンジニアとして参加しているにすぎない。
ロパティンはこれまでも本名名義での作品やプロデュース作品、あるいはサウンドトラックやリミックスなどでじつにさまざまな相手とコラボを繰り広げてきたわけだけれど、他方で自身のメイン・プロジェクトであるOPN名義のソロ・アルバムにゲストを招くことだけは頑なに拒み続けてきた。多くの客人を招待した『エイジ・オブ』はだから、彼のディスコグラフィのなかで大きな転機となるはずで、であるならばいっそ大々的にアノーニやジェイムス・ブレイクの歌声をフィーチャーしたポップ・ソングを作ってもよかったはずである。だがロパティンはそうしなかった。それにはおそらく、現在の彼が人間に対して抱いている二律背反的な、複雑な思いが関与しているのだろう。
アノーニとの口喧嘩を経て、自分はニヒリストなのかと問いはじめたところからすべてがスタートしたという本作は、他方でわざわざクレジットにCCRUの名を掲げてもいる。ロパティンは揺れている。半分は無意識的に、そしておそらく半分はきわめて意識的に。思い出そう、先に引いたインタヴューにおいて彼が、人間が排除されたような「音楽機械」もまた「とても人間的なものに感じられる」と述べていたことを。「ハートから生み出された感じがする、そういう音楽」こそが好きなんだと、それこそクリシェのような発言をしていたことを。そしていままさにわれわれは、彼という人間をとおして『エイジ・オブ』を理解しようと試みている。
いまさら人間に全幅の信頼を寄せるようなかつての発想には戻れないし、戻るべきでもない。かといって人間の縮減ないし抹消によってもたらされる種々のほころびをそのまま歓迎することもできない。急速にテクノロジーが変容し、人工知能や人新世といったタームが脚光を浴びる今日、人間と反人間とのあいだで揺れ動く現代、ポストモダンという言葉さえレトロスペクティヴに響き「ポスト・ポスト」という言い回しでしか名指すことのできないこの時代、それこそが『エイジ・オブ』の切り取ろうとしている生々しいバビロンの姿だろう。「オブ」以下が言葉を欠き、大いなる余白を残すゆえんである。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE