MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with TOKiMONSTA - ウサギおばけの帰還
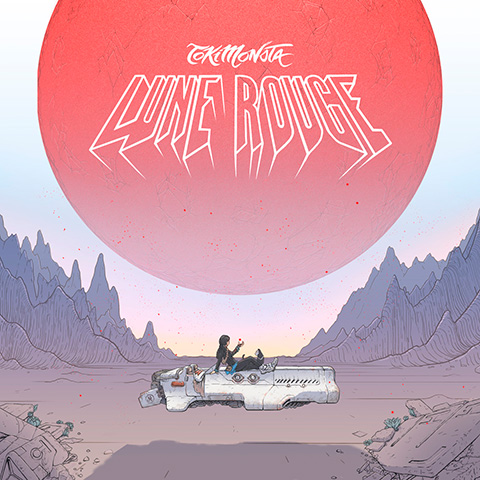 TOKiMONSTA Lune Rouge Young Art / PLANCHA |
トキモンスタが帰ってきた。2年前に重大な脳の障害を患った彼女は、二度にわたる手術の影響により音楽はもちろんのこと、動くことも話すこともできない状況にあったのだという。リハビリを終えた彼女はすぐにこのアルバムの制作に取り掛かったそうで、そのような闘病体験が霊感を与えたのか、新作『Lune Rouge』はこれまでの彼女のサウンドとは異なる優美さを湛えている。LAのビート・シーンから登場し、〈Brainfeeder〉からのリリースで一気に重要なプロデューサーの地位へとのぼり詰めた彼女だが、このニュー・アルバムは、フライング・ロータスの影響下にあったかつてのビートとも、EDMに寄ったセカンド・アルバムとも異なるポップネスを獲得している。ビートはより躍動的に、メロディはより叙情的に、ヴォーカルはよりソウルフルになった。そしてそこに、あるときはひっそりと、またあるときは大胆に、韓国や中国のトラディショナルな要素が落とし込まれている。この『Lune Rouge』における新たな試みは、めでたく復帰を遂げたトキモンスタの今後の道程を照らす、輝かしい燈火となることだろう。そんな彼女のこれまでの歩みを振り返りながら、4年ぶりとなる新作についてメールで伺った。
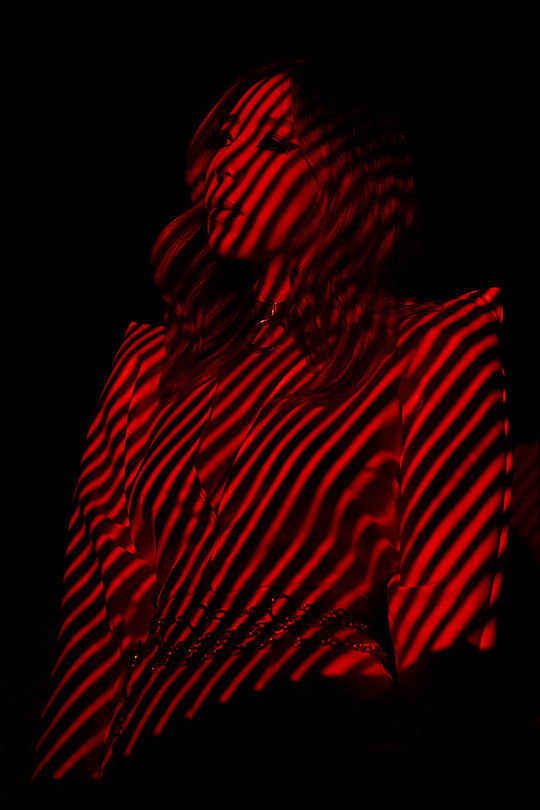
私の目標は、これらの伝統的なサウンドを、フェティシズムやアジア文化のエキゾチックな感覚ではない方法でシェアすること。この問題にどうやってアプローチするかはとても気をつけているわ。
■あなたは幼少よりピアノなどを習い、クラシック音楽を学んでいたそうですが、そこからヒップホップに興味を抱くようになったのはなぜなのでしょう?
トキモンスタ(以下、T):じつはもともとピアノは弾いていなくて、両親の影響でクラシック音楽を学んでいたの。つまりクラシックが私の音楽の最初の入り口。それから私が他の音楽に触れることができる年齢になったとき、次に好きになったのがヒップホップだったわ。
■ヒップホップやエレクトロニック・ミュージックを制作する際に、クラシックの素養はどのような助けになっていますか? あるいは逆に、その素養が足枷になることもあるのでしょうか? たとえば、プレイヤーとしてのスキルが作曲の可能性を狭めてしまうことはあると思いますか?
T:私は自分の音楽にクラシックのポジティヴと感じる側面のみを取り入れ、好きではないところは取り入れない。たとえば、私はクラシック作品の物語性は好きだけど、ルールや制約は好きではないの。
■あなたは2010年にファースト・アルバム『Midnight Menu』を発表し、翌2011年に〈Brainfeeder〉からEP「Creature Dreams」をリリースして脚光を浴びました。あなたの出自はLAのビート・シーンにあると思うのですが、いまでもLAのシーンに属しているという意識はお持ちでしょうか?
T:私はいつもビート・シーンの一部であると思ってる。私たちはみんなLAでスタートして、いつもルーツはそのサウンドにあると感じているけど、私たちはそこから旅立ち、皆それぞれ異なる個性を持つミュージシャンへと進化しているわ。
■カマシ・ワシントンやルイス・コール、ミゲル・アトウッド・ファーガソンらに代表されるようなLAのジャズ・シーンとは交流がありますか? また、彼らのようなプレイヤーと楽曲制作をしてみたいと思いますか?
T:私は現代のLAのジャズ・シーンが大好きで、すべてのアーティストを深く尊敬しいるわ。
■同じ年にあなたはディプロやスクリレックスとツアーを回っていますね。そして翌2013年にはEDMのレーベルからセカンド・アルバムとなる『Half Shadow』をリリースしています。ファースト・アルバムとは異なる作風へシフトしましたが、そのときはどのような心境の変化があったのでしょう? EDMに関心があったのですか?
T:ディプロやスクリレックスとツアーを回ったけど、私の音楽は何も変わってないわ。「EDM」は作っていないし、いまだにアグレッシヴなダンス・ミュージックを作ったことはない。でも一方で、私はそれをひとつの芸術形態として尊重し、とても楽しいものだと思っているわ。私は〈Ultra〉から作品を出したけど、〈Ultra〉は私が作る音楽を制作してほしがっていたわけではないし、レーベルのアーティストがすでに作ってきた多くのものと同じものを作りたくはないと思っていたの。『Half Shadow』はもしかしたら〈Brainfeeder〉や他のレーベルでリリースされていたかもしれないけど、私はただ、より大きなレーベルでビート・シーンのサウンドが受け入れられるかどうかを見たいと思ったのよ。

■昨年デュラン・デュランをリミックスしていましたよね。それはどういう経緯で?
T:デュラン・デュランのリミックスは、彼らから依頼が来たの。まさか彼らが私の音楽に興味があるとは思ってなかったので、依頼が来たときはとても驚いたわ。私は彼らとツアーもしたの。ツアーはシック・フィーチャリング・ナイル・ロジャースも一緒だった。私のようなエレクトロニック・アーティストにとって非常にユニークで、信じられない体験だったわ。
■今回のニュー・アルバムはファーストともセカンドとも異なる作品に仕上がっています。本作の制作を始めた直後、難病を患ったとお聞きしていますが、病中の体験は本作に影響を与えましたか?
T:私はもやもや病という脳の病を患い、それを手術しなければならなかった。手術の副作用により、話すことも、言語を理解することも、身体をうまく動かすこともできず、さらには音楽を理解することもできなくなってしまった。もう一度音楽を理解できるようになるかどうかわからなかったときはとても恐ろしかったけど、最終的にはすべてが回復し、正常に戻った。精神的な能力を取り戻すとすぐに、私はこのアルバムの制作に取りかかったわ。
■『Lune Rouge』ではヴォーカルがフィーチャーされたトラックがアルバムの半数以上を占めていますが、自身の楽曲に歌やラップといった言葉を乗せることにはどのような意味がありますか? ご自身で作詞されている曲はあるのでしょうか?
T:このアルバムでヴォーカルが配された曲は、それが適切だと思ったの。私はヴォーカルを別のひとつの楽器としてとらえることが好きだから。私はアルバムの2曲めの“Rouge”を自分で作詞して歌っているわ。
■本作は1曲め“Lune”から2曲め“Rouge”までの流れや、ピアノが耳に残る4曲め“I Wish I Could”など、メロディアスな印象を抱きました。そういったメロディの部分と、ヒップホップのビートとを共存させるうえでもっとも注意を払っていることはなんですか?
T:私はつねに自分の音楽に感情だけでなく躍動感が欲しいと思っている。メロディは感情を作り、打楽器とドラムは躍動感を作る。両者の間には良いバランスがあるから、私はいつもそれを見つけようと努力しているわ。
■先行公開された8曲めの“Don't Call Me”では、マレーシアのYuna Zaraiをフィーチャーしています。彼女とはどういう経緯で一緒にやることになったのでしょう?
T:Yunaとはマネージャーを通じて会ったのだけど、私たちはもともと互いの作品の大ファンだったのね。彼女は素晴らしいアーティストであると同時に素晴らしい人物でもある。この曲は本当に理解のある人によって生み出されたから特別なの。
■あなたは過去に何度かアンダーソン・パクと共作していますが、近年の彼の活躍についてどう思っていますか?
T:私はアンダーソンがスターになっていくのを見るたびにハッピーな気持ちになってエキサイトしてる。彼は弟のような存在だし、私はただ彼がもっともっと輝く様子を見ていたい。
■ご自身のルーツのひとつである韓国では、近年ヒップホップやR&Bを中心に、インディ・ロックやダンス・ミュージックなど幅広いジャンルで質の高い音楽が生まれていますが、現在の韓国の音楽で注目しているものはありますか?
T:私はいつも、変化している韓国の音楽にいつも興味を持っているわ。いまのところは、ビートや電子音楽を作る現地のプロデューサーについて学んでいるところね。
■6曲め“Bibimbap(ビビンバ)”で使われているのは伽倻琴(カヤグム、Gayageum、가야금)でしょうか?
T:うん、そうよ!
■最終曲“Estrange”でも伝統的な弦楽器が用いられていますが、これはなんという楽器でしょう? また、このアルバムには他にも韓国の音楽の要素が含まれていますか?
T:“Estrange”で使っている楽器は中国の弦楽器なの。アルバム全体にほのかに韓国の要素を通底させているわ。特に目立つのは“Bibimbap”だけどね。
■積極的にそういった音を取り入れるのは、ご自身のルーツを打ち出したいという思いが強いからなのでしょうか?
T:私は多くの文化の中から伝統音楽に触れるのが好きなの。自分が韓国人である以上、当然韓国のカルチャーから生まれた音楽にもっとも親しみがあるわ。多くの人びとはモダンな音楽や、もしくはたぶん「オールディーズ」のような音楽に焦点を当てがちだけど、何世紀にもわたって存在してきた伝統音楽にはとても豊富な音楽があるの。
■そういった要素を打ち出すことで、アジアの文化を世界に広めることができるという側面もありますが、逆に偏見やオリエンタリズムを増大させてしまう可能性もありますよね。そのバランスについてはどうお考えでしょう?
T:私の目標は、これらの伝統的なサウンドを、フェティシズムやアジア文化のエキゾチックな感覚ではない方法でシェアすること。この問題にどうやってアプローチするかはとても気をつけているわ。

■いま〈88rising〉が、インドネシアのリッチ・チガや中国のハイヤー・ブラザーズなど、アジアのヒップホップを精力的にプッシュしていますが、そういった動きについてどう見ていますか?
T:彼らがやっていることは大好きよ。私たちがステレオタイプなアジア人のギミックや誇張として見なされない限り、あらゆる音楽分野で世界的に評価されることは素晴らしいわ。
■あなたはTwitterでときおりトランプやホワイトハウスについて発言しています。いまの合衆国の状況についてはどのようにお考えですか?
T:私は現政権に不満を持ち、彼らの選択、コメント、決定に失望している。でも、つねに希望を持っているし、未来を楽しみにしているわ。
■あなたの音楽について、いまでも「女性」という枠で括って捉えようとする人もいるのではないかと察します。そのことにストレスを感じることはありますか?
T:たしかにそれは少し過剰な表現のように感じるわ。でもそれは二面性を持った問題ね。女性プロデューサーの稀少さを強調するために、人びとは、私のような「女性プロデューサー」によってこのトピック全体が転換されていることを理解する必要があると思うわ。それはいつか、これ以上議論する価値がないほど一般的になるでしょう。
■文化的なものには、すでに根付いてしまった社会的な因襲や慣習を変える力が具わっていると思うのですが、あなたが曲を作るときに、そういったことを意識することはありますか? 音楽や言葉や映像、アートやファッションなど、文化が持つ力についてどのようにお考えですか?
T:アーティストとしての私にとって、創造する理由とは、私が創造する必要性を満たすことなの。動機を持ったり、(ポジティヴでもネガティヴでも)政治的な課題のために音楽を作ったことはないわ。 私の目には、芸術ははっきりしていて、とても純粋なマナーの中で存在することができるように見える。でも芸術はその周りに文化を創造し、文化は人類の他の側面(政治や社会的活動など)と相互作用する。そこで私たちは、アート(音楽、ヴィジュアル、書かれたもの、ファッション、すべてのもの)がどのように文化になり、社会に変化をもたらすのかを見ている。私は自分の創造性を伝えるために音楽を作っているけど、その音楽は独自の生命を持って、インパクトを生み出し、変化を促す能力を持っているわ。それはとてもパワフルだと思う。
質問:小林拓音+菅澤捷太郎(2017年11月30日)
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
Profile
菅澤捷太郎/Shotaro Sugasawa1994年、東京都葛飾区生まれ。2013年からヒップホップ・バンド、「ザ・ブルシット」(Tha Bullshit)に加入。現在はバンド「すばらしか」においても、お手伝い担当として参加中。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE

