MOST READ
- 別冊ele-king J-PUNK/NEW WAVE-革命の記憶
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- 『90年代ニューヨーク・ダンスフロア』——NYクラブ・カルチャーを駆け抜けた、時代の寵児「クラブ・キッズ」たちの物語が翻訳刊行
- FESTIVAL FRUEZINHO 2026 ──気軽に行ける音楽フェスが今年も開催、マーク・リーボウ、〈Nyege Nyege〉のアーセナル・ミケベ、岡田拓郎が出演
- 早坂紗知 - Free Fight | Sachi Hayasaka
- 二階堂和美 - 潮汐
- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ
- interview with Flying Lotus フライング・ロータス、最新EPについて語る
- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Yoshinori Sunahara ──74分のライヴDJ公演シリーズ、第二回は砂原良徳
- interview with Acid Mothers Temple アシッド・マザーズ物語 | 河端一、インタヴュー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- KMRU - Kin | カマル
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
Home > Reviews > Album Reviews > Deerhoof- La Isla Bonita
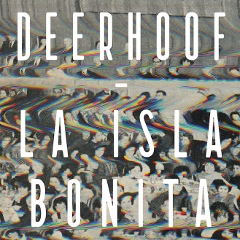
カオスをプレゼントしよう橋元優歩
女子高生が「っょぃ」と小さい文字でツイートしていたりするけれども、近年のサトミ・マツザキとディアフーフに抱くのもちょうどこの「っょぃ」という感じである。通常の表記を意外な方向へと外すこの「小さい文字表現」からは、吃音に似た、発音不可能なことからくるインパクトや、あるいはどこか常軌を逸したような雰囲気が立ち上がってくるけれども、それがちょうど未知にして測りがたい性質をもった存在としての女子高生に重なって、ちょっとした恐れをかきたてる。結成20年、ティーンから遥か遠い年齢のディアフーフを「っょぃ」感じるのは、サトミ・マツザキのヴォーカル・パフォーマンスによるところも大きいけれども、それ以上に彼らがまだスタンスにおいても方法においてもそうした測りがたさを残しているからだ。
前作『ブレイクアップ・ソング』(2012)から2年、〈ポリヴァイナル〉移籍後3作めにして通算で12作めにもなろうか(どう数えていいのか、資料・媒体によって混乱がある)、2000年代のUSインディ・ロックを牽引してきた重要バンドのひとつ、ディアフーフの新作フル・アルバムがリリースされた。グランジを経由したノイズ・ロック/アート・ロックというフォームや、エクスペリメンタルでエキセントリックな雰囲気は変わらず芯となってその音の中に埋もれているけれども、とてもフレッシュな、そしてとても反抗的でやんちゃな印象を残す作品になっている。ぜったいに思いどおりにはなってやらない──それはリスナーや業界が求めるディアフーフ像にはまらないといったケチなレベルの話ではなくて、もっと、世界や、世界の理や、時間、歴史といったものへ逆らうような、とびきり少年くさいやんちゃさだ。「ディアフーフが君にカオスをプレゼントしたい」(“ビッグ・ハウス・ワルツ”)とアルバム中盤においてあらためてなされる宣言には、そうした傲岸さがなんともクールに表れている。
あの曲ではファンキーでダンサブルなリズムが印象的だが、やがてガーンガーンと鳴りつづけるノーウェイヴ・マナーなギターの上で拡声器でわめくようにマツザキの演説がはじまり、グレッグ・ソーニアのドラミングが騒々しく焦燥をあおるように追従していくところに最大の盛り上がりがある。「レディース・アンド・ジェントルメン」からはじまるくだんの宣言はこの部分で不気味になされる。しかしそれでいてどこかしらユーモアがあり、爽快だ。この感覚こそはディアフーフならではのもの。今作も全編にわたって明確に現アメリカ社会への批評が打ち出されているけれども、彼らの側からの社会への応答は、「カオスをプレゼント」することなのだ。そう、「周波数を合わせるのはぼくたちの義務じゃない」(“タイニー・バブルズ”)。まるで音楽と自分たちに何ができて何ができないかということを身体的に知っているかのような回答である。外から飛んできたカオスをそのまま打ち返す、あるいはディアフーフ・オリジナルのカオスをそこに打ってぶつける。それはかつて『ディアフーフ vs. イーヴィル』リリースの際に、「イーヴィルとは何か?」という問いに対して「これはゴジラ対キングギドラのようなものだ」と返答をくれたのと似ているなと思う。あからさまな社会風刺だけれどもふざけてもいる。真面目な事柄に対してふざけるなんてけしからん、批判には行動を伴わなければいけない、というような圧力にもまるで屈しない。彼らの「ふざけ」かたにはエクスキューズがない。そして信念と反抗がある。っょぃ。
そもそもロブ・フィスクの個人プロジェクトとしてスタートしたこのバンドは、彼の早々とした脱退もあり、メンバーの入れ替わりも幾度か経て、初期からその存在意義や性格を大きく変えている。『レヴェリ』(2002)以降に各タイトルに対する注目や評価も跳ね上がり、いまに直結するようなディアフーフの輪郭を見ることができるが、いまはじめて彼らに触れる人からすればそれすら過去のことに過ぎないかもしれない。同様に90年代半ばのベイエリアのパンク・バンドといったイメージや、あるいは〈キル・ロック・スターズ〉の背後に広がる90年代オリンピアのインディ・シーン、ライオット・ガール・ムーヴメントといったものとの関連性もすでに薄く感じられるだろう。
ディアフーフは本当にフレッシュだ。インディ・ロックというフィールドにドラスティックな変化をもたらしたというのとはちがって、つねに「周波数を合わせるのはぼくたちの義務じゃない」の精神で自分たちの遊びをつづけてきた。それが結果としてインディ史にひとつの道標を立てたこともあるだろうけれども、基本的にはスタンスの強靭な自由さがフォームのフレッシュさを生んできた、単独的で異分子的な存在だと思う。『ラ・イスラ・ボニータ』はその意味でも20年を記念し、しかも1曲ごとに別の充実をみせるアルバムではないだろうか。プロデューサーのニック・シルヴェスターは「ピッチフォーク」誌の寄稿者としても知られる〈ゴッドモード・レコーズ〉の主宰者。〈ポリヴァイナル〉移籍後はセルフ・プロデュースにこだわっていたようにも見えるバンドだが、評論気質のプロデューサーを迎えているのもおもしろい。
ALBUM REVIEWS
- 二階堂和美 - 潮汐
- 早坂紗知 - Free Fight
- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- Milledenials - Youth, Romance, Shame
- KMRU - Kin
- Deadletter - Existence is Bliss
- Cardinals - Masquerade
- Jill Scott - To Whom This May Concern
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her
- xiexie - zzz
- Cindytalk - Sunset and Forever
- CoH & Wladimir Schall - COVERS
- KEIHIN - Chaos and Order
- DIIV - Boiled Alive (Live)


 DOMMUNE
DOMMUNE
