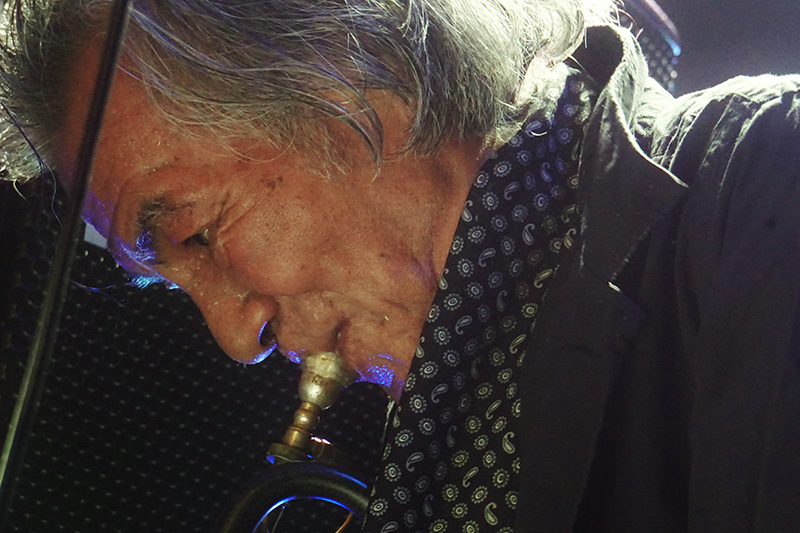80年代後半、Boogie Down Productions らと共にコンシャス・ヒップホップのムーヴメントを作り出し、さらにその革新的な音楽性によって、ヒップホップ史上最も偉大なグループのひとつとして高く評価されている Public Enemy。1987年にリリースされた1stアルバム『Yo! Bum Rush the Show』から代表作である2nd『It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back』(1988年)を経て、4thアルバム『Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black』(1991年)くらいまでが彼らの作品としてのピークであるが、2000年以降も精力的に制作を続けており、今年(2020年)9月に通算15枚目のアルバムとしてリリースされたのが本作『What You Gonna Do When the Grid Goes Down?』である。
80年代の Public Enemy をリアルタイムに知っているようなヒップホップ・ファンであっても、おそらく近年の彼らの作品をチェックしていた人は多くはないだろう。個人的にも90年代後半の時点で、彼らのメッセージや音楽性も含めて全てが時代遅れに感じていて、過去の偉大なアーティストという位置付けであったのは否めない。しかし、コロナ禍かつBLMムーヴメントが盛り上がっていた今年6月にリリースされた、DJ Premier のプロデュースによる先行シングル “State of the Union (STFU)” を初めて耳にした瞬間、あの最も輝いていた頃の Public Enemy を思い起こさずにはいられなかった。(リリース当時)大統領再選を目指していたドナルド・トランプへ向けた、Chuck D と Flava Flav が発するストレートなメッセージと DJ Premier のハードなビートは、いまの時代の空気感にも完全にフィットし、ヒップホップの持つ普遍的な力を改めて証明してくれた。
アルバム・タイトルにある「Grid」はインターネットを意味しており、Cypress Hillと George Clinton をゲストに迎えた “GRID” では、インターネットに依存した現代社会へ警鐘を鳴らしている。正直なところ、このテーマにはあまりピンとこないのだが、2010年代以降、Public Enemy のほぼ全てのアルバムに参加し、本作のメイン・プロデューサーとも言える C-Doc が手がけるロックテイストの強い、90年代前半頃の Public Enemy らしいサウンドに乗った Chuck D のラップには往年の勢いを感じさせ、自然と頭が揺れてくる。
本作の目玉と言えるのが、Public Enemy の代表曲のセルフリミックスである “Public Enemy Number Won” と “Fight The Power: Remix 2020” の2曲だろう。前者はオリジナルの “Public Enemy #1” そのままのトラックの上で、Beastie Boys の Mike D と Ad-Rock が初めて Public Enemy のデモを聞いたときの思い出話をイントロで語り、さらにメインの部分には Run-DMC が参加。残念ながら Run-DMC のラップに最盛期のキレは感じられないものの、Public Enemy、Beastie Boys、Run-DMC という3者の夢の共演には興奮せずにはいられない。BLMムーヴメントに呼応してシングル・リリースされた “Fight The Power: Remix 2020” には Nas、Black Thought、Rapsody、YG などベテランから若手まで幅広くゲストが参加し、原曲のメッセージ性がいまなお色褪せないことを教えてくる。
ちなみに本作は Public Enemy の古巣でもある、いまなおアメリカを代表するヒップホップ・レーベルの〈Def Jam〉からリリースされており、実に26年ぶりのレーベル復帰となる。もちろん、今後も〈Def Jam〉との契約が続く保証もないし、本作によって彼らが第一線に復帰したというわけでもない。しかし、このアルバムによって、Public Enemy があの黄金時代の輝きを一瞬でも取り戻したことは、一ファンとしても実に喜ばしいことである。







 Jam City
Jam City