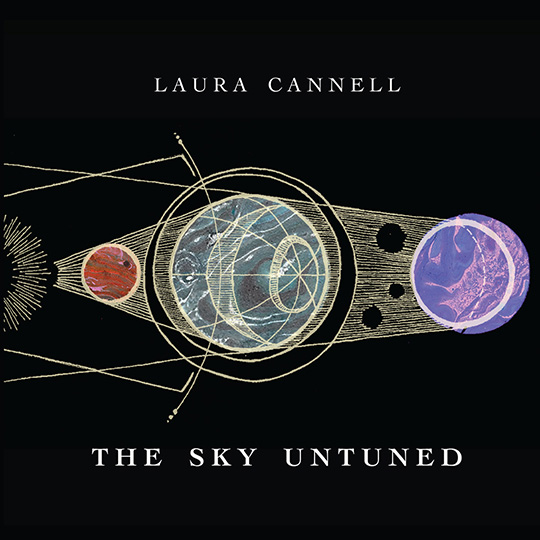MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Laura Cannell- The Earth With Her Crowns
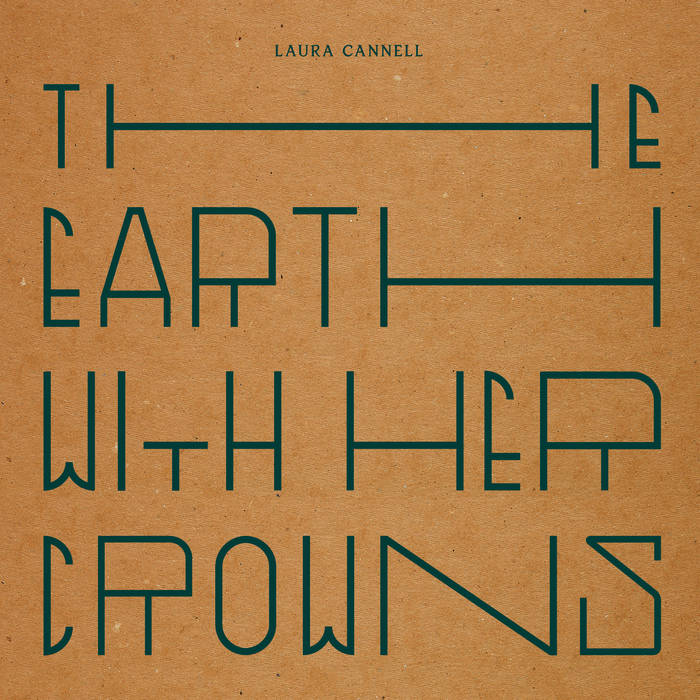
相変わらず美しく、そして深みのある音楽だこと。心が嬉しくなるとはこういう音楽のことだろう。
ローラ・キャネルはイギリスのヴァイオリン奏者であり、インプロヴァイザーである。オリヴァー・コーツの新作のように、キャネルの作品もまずはその音(トーン)によって決定する。それは忘れがたいトーンで、あまりに独自なトーンと響きゆえに、一瞬にしてその場の空気を変えてしまう。あるいはまた、静かで情熱的で、ぎょっとするような強度のある倍音を有している。それはまるで、彼女が自然界と話しているかのような、ある種の言語に思える。
曲のなかには、ヨーロッパ各処の中世の音楽、スティーヴ・ライヒ風のミニマリズム、レデリウス的な室内楽が混ざっている。とくに近代以前の古いもの──国家がとくに誇りとしていないような、中世の旋律や民謡など──を掘り起こすことは、キャネルのおそらく全作品に通底するコンセプトだ(松山晋也氏なら、この曲は地中海のあのエリアで、この曲は東欧のどこそこで、などと言い当てられるかもしれない)。
そして場所。
2014年の実質的なソロ・デビュー作『Quick Sparrows Over The Black Earth』によって注目された彼女は、場所を選んで演奏し、録音している。どこでもいいわけではない。2016年の『Simultaneous Flight Movement』は海沿いの灯台で、2017年の『Hunter Huntress Hawker』と前作『The Sky Untuned』は小さな村の古く荒廃した教会で、今作『The Earth With Her Crowns(彼女の冠をした地球)』は水力発電所で演奏し、録音した。場所もキャネルの作品においては、いわばメタレベルでの楽器である。
クワイエタスはキャネルの音楽を“エイシェント・フューチャリズム(古代・未来主義)”と呼んでいる。以前書いたことの繰り返しになってしまうが、最近は、アイルランド出身のアーニェ・オドワイアー(Áine O'Dwyer)、あるいはアースイーターなんか、エイシェント・フューチャリズム的なアプローチをする人が目につくようになった。自然現象と過去への畏敬の念、そこに未来(それは手法的な未来でもあり、必ずしも楽天的ではない未来である)が絡み合う、強い主張のこもったヴィジョンが空の彼方まで広がる。ちなみに、エイシェント・フューチャリズムの始祖をひとり挙げるとしたら、ぼくはサン・ラーだと思う。
『The Earth With Her Crowns』はリリースされてからすでに数か月が経っているのだが、初夏、真夏、そして秋から冬へと、ぼくは前作同様このアルバムを部屋のなかでなんども聴いている。彼女の高度な演奏技術ゆえに、曲はオーヴァーダブしたかのように聴けてしまうけれど、すべては彼女ひとりによる即興で、驚くべきは、すべては一台のヴァイオリン(そしてリコーダー)によって演奏されている。
ローラ・キャネルの演奏は、そしてきわめて詩的で、記憶を反響させ、閉ざされた思いを解放するかのようだ。そう、だからためしに空を眺めながら聴いて欲しいですね。胸の奥から得も知れない感覚がこみ上げてくるだろう。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE