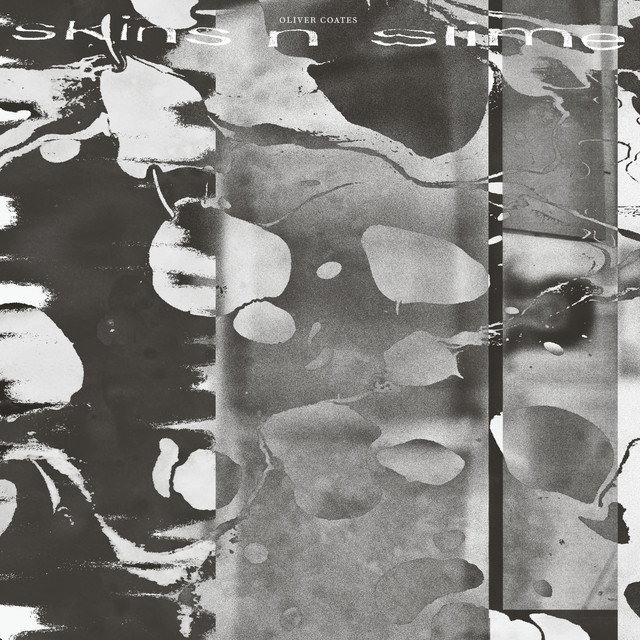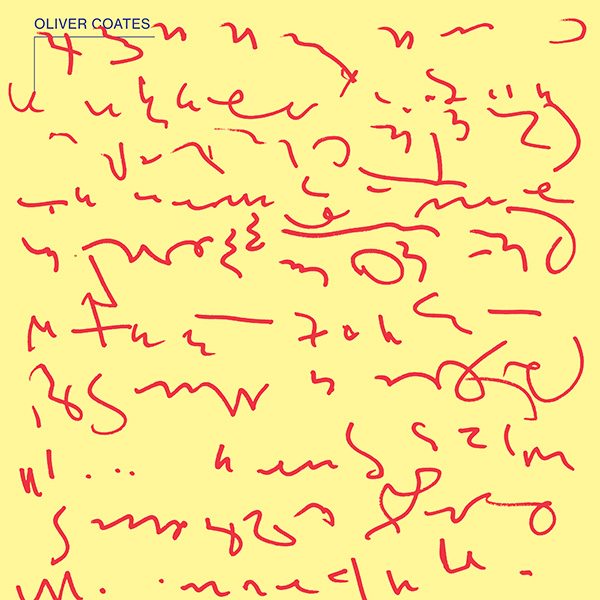MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Oliver Coates- Skins n Slime
スライムといえば日本ではザコキャラの代名詞だけれど、こんなに凶暴でそして、悲しげな顔をしたスライムは見たことがない。
正統なクラシック音楽を修めたエリート中のエリートでありながら、スクエアプッシャーやオウテカを敬愛するチェリスト、相棒の音を躊躇なく加工し、むしろ典型的な弦のイメージから遠ざけることを心がけ、大胆にひずませることもいとわないオリヴァー・コーツは、いま、だれも到達したことのない山頂に立っている。クラシカルとエレクトロニカとの幸福な結合を実現した『Shelley's On Zenn-la』から2年、ジョン・ルーサー・アダムズとの共作を経て届けられた新作『Skins n Slime』が、あまりにも圧倒的かつ独創的なサウンドを誇っているのだ。
タイトルに冠された「スライム」とは、ディストーションとコーラスのエフェクツペダルを用いて彼がつくりあげた、チェロのテクスチャーを指している。さらに「肌」まで付け足すくらいだから、今回コーツは音の触感になみなみならぬ情熱を注いでいるのだろう。まさにスライムこそが本作の鍵を握っているわけだ。
アルバムの前半は、5つのパートからなる組曲 “Caregiver” によって構成されている(「介護者」なる曲名からは一瞬パンデミックを連想してしまったけれど、本作は昨年12月の時点ですでに完成していたそうなので無関係)。ミニマルな弦の反復からはじまる “part 1” は、低音のドローンがしっかりと曲に重量感を与えているところがポイントで、この工夫がビートを持たないアルバム全体にくっきりした輪郭を与えている。
最初のハイライトは “part 2” で訪れる。弦であると同時に電子音でもあるような、器楽曲であると同時に騒音でもあるような、驚くべき未知のディストーション。いったいどうやったらチェロでこんな音を生成できるのだろう? 比較的素朴に弦の響きを聞かせる “part 3” と “part 4” をはさんで、“part 5” でもエフェクトがめざましい活躍を見せている。現界するシューゲイズ的サイケデリア。だが注意しなければならない。これはギターではなく、チェロなのだ。
先行シングルとして公開された7曲目の “Butoh baby” において、かのスライムは悲しみを爆発させている。主旋律の音色もだいぶおかしなことになっているが、地を這う低音の濁り具合はただただ圧巻というほかない。つづく “Reunification 2018” もすさまじい。これまたシューゲイズ的なノイズに覆われているが、繰り返そう。ギターではない。チェロだ。
その後アルバムは高音にフォーカスした “Still Life” やティム・ヘッカー風の寂寥を携えた “Honey” を経て、マリブーを迎えた “Soaring X” で静かに幕を下ろす。こういうクラシカルに寄った曲もいい。しかしやはり本作を他と分かつ最大の特徴は、チェロに施された強烈なエフェクトだろう。
新作のリリースに先がけて公開された『Fact mix』が、序盤はアンビエントで固められているにもかかわらず、途中からマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやザ・ジーザス・アンド・メリー・チェインを招き入れ、おなじ空間系ペダルを採用していると思しきザ・キュアーやコクトー・ツインズ(やディーン・ブラント)の曲をはさみつつ、最後はブラックメタルで〆るという謎の構成をとっていたので、はてこれにはどのような意図が? と頭を抱えていたのだけれど、今回フルでアルバムを聴いてみてわかった。『Skins n Slime』は、かつてエレクトリック・ギターが繰り広げた音響的冒険を、チェロで探究しようと試みたアルバムなのだ。
ただし本作は、夢見心地なムードや浮遊感のたぐいは搭載していない。スライムはどこまでも悲しみと向き合っている。そこがいまの時代とマッチしていて、とても今日的だと思う。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE