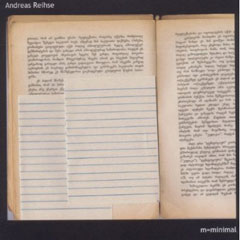MOST READ
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
- Visible Cloaks ──ヴィジブル・クロークスがニュー・アルバムをリリース
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Fumitake Tamura ──「微塵な音」を集めたアルバム『Mijin』を〈Leaving Records〉より発表
- SUGAI KEN ──3月に欧州ツアー、チューリッヒ、プラハ、イスタンブール、ローマ、アントワープの5都市を巡回
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結
- KEIHIN - Chaos and Order
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Geese - Getting Killed | ギース
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- The Master Musicians of Joujouka - Live in Paris
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
Home > Interviews > interview with Mark McGuire - 夏休み特別企画:マーク・マッガイア、ロング・インタヴュー
野田:『リヴィング・ユア・セルフ』以降にもたくさんリリースされていますが、そのなかで大きなものってなると『ゲット・ロスト』かなって思います。抽象的なアルバム・タイトルが多かったなかで、これは「失せろ」って意味じゃないですか。そういう直情的なタイトルにしたのはなぜですか?
マーク:このタイトルもさっきのようにいろんな意味にとれるものだと思うんですけど、英語だと「失せろ」というほかに「迷う」という意味もあるんですね。『リヴィング・ウィズ・ユアセルフ』が家から出ていくものだったとしたら、『ゲット・ロスト』は世界の広さに圧倒されてまよってしまった、そういうものだったんじゃないかって考えられます。世界はとてもクレイジーでいろんなものがうごめいている場所ですからね。でもその「迷う」っていうこと自体いはすごく大事なことだとも思ってます。スリーヴに書いてあるんですけど、「迷う」ことでなにかを発見したり、次につながっていくのはほんとに大事なことです。
野田:それは、クリーヴランドを離れたり、アメリカを離れてツアーをまわったりとか、そういう経験からきた言葉なんですか?
マーク:もちろんそこにはたくさんのできごとがあります。自分を強く持って、ここだって決めて進んでいったとしても、とてもたくさんの筋道ってものがありますよね。そういう、こうしたい、こうしたほうが良かったというたくさんの選択肢のなかで、自分に対して正直にいよう、そうしたことを強く持とうって思ったところからきています。あとは、クリーヴランドからポートランドへ引っ越したっていうのも大きいかな。そんな規模の引っ越しは初めてだったから。ひとりになった気持ち、とてもさびしい気持ちはあらわれているかもしれません。
野田:エメラルズのほかのふたりのメンバーもいっしょに引っ越したんですか?
マーク:彼らはクリーヴランドにいますね。
野田:ポートランドっていうと、いまとてもアーティストが集まる街でもあり、なおかつアメリカでもっとも銃声が鳴り響く街でもあるっていう噂を聞いたんですが。
マーク:銃声? クールですね(笑)。
(一同笑)
マーク:銃については最近考えをあらためて......、まあ、いいや。
野田:ええ、なんです?
マーク:もちろん銃は持たないほうがいいって思ってるんですけど、最近はハンティングのためとか自分を守るためというよりも、政府についてちょっといろいろ、嫌なことがあったものだから、それで銃を持ったほうがいいんじゃないかって思うようになって。
野田:ええ(笑)! それは聞き捨てならないですね!
マーク:いやいやそれは......
野田:ポートランドは治安が悪いっていうのはほんとなんですか?
マーク:僕はいちばんいいとこに住んでるわけじゃないけど、とくに問題ないですよ。住んでる人っていうより、警察のほうが危ない、こわい感じです(笑)。前の警察署長っていうのが、ちょっと獰猛な人だったみたいです。
野田:日本も似ています。
マーク:まあ、でも、これは気にしないでください。なんでもないです。なんでもない(笑)! 僕はいちども銃を撃ったことないですからね。でもそういった人たちや政府に対してアンチを唱える意味で銃を持つのもいいんじゃないかって、最近は思ったりします。
野田:それはすごいなあ。
マーク:でも......、これはほんと、なんでもないから(笑)!
橋元:(笑)『ゲット・ロスト』で声を入れようと思ったのはなぜです?
マーク:歌ってる曲は2007年の曲なんです。いつもは自分の曲に歌が必要だとは思わないんだけど、ときどき音だけじゃ表現できないから言葉で言わなきゃっていうことがあって。この曲はそんなふうにできたものです。シンガー・ソングライターみたいに歌うんじゃなくて、人間の声っていうものはとても面白い楽器にもなるとも思ってるので、もっといろんな可能性を拡張していきたいですけどね。
野田:あなたのライヴを観て、あんなに踊れるっていうか、ダンサブルな演奏に驚きました。いつもあのスタイルでやっているんですか?
マーク:僕はとてもいろいろなことをやっています。だけどあのときのライヴはお客さんとの一体感がほしかったので、音楽とリズムでそれをやろうって思いました。お客さんに身体を動かして観てもらいたかったんです。僕自身もボアダムスのライヴでそんなふうに観ていました。僕自身はドローンとかアンビエントとかもっとメディテーティヴなものとか、いろいろなスタイルでやります。バランスのとりかたに悩むこともありますけど......。
たとえば流行の音楽がありますよね。そういうものも好きで、やりたいなって思ったりもするんですけど、そういうものを取り入れることで自分のスタイルを失ってしまうんじゃないかって思ったりもして、そういうバランスがむずかしいんです。
野田:流行っている音楽っていうのは?
マーク:レトロなインディ・ダンスとかですね。
野田:〈100%シルク〉とか?
マーク:別に悪く言ってるんじゃないんですよ! ローレル・ヘイローやフォード&ロパーティンみたいな人たちのことです。いろんな人がいるってことです。たとえばドラムマシンとギターを使ったような曲もありますけど、そっちの方向に自分が進むべきかっていうとちょっと違うかな、とも思います。
野田:ローレル・ヘイローとは交流があるんですか?
マーク:フォード&ロパーティンとは、特別親しいわけじゃないけど知り合いです。ゾーラ・ジーザスとも知り合いです(笑)。
野田:ちょっと意外ですね! あのー、5~6年前、アメリカのインディ・ミュージック・シーンの若い世代たちがドローンをやってたじゃないですか。あれはなんでなんでしょうね。
マーク:2000年くらいにスケーターとかダブル・レオパード、サンルーフの影響を受けたんですけど、僕はその当時ノイズのコミュニティにいたんです。あの頃は、そんなことをしているのは自分たちだけだと思ってたんだけど、気づいたらほかのノイズの人も同じようなことをやってました。
それが何故か......、たとえばシンセサイズな音楽がダンス・ミュージックになってって、その次の展開ってわからないけど、また90年代にもどるって展開もあるかもしれないですね。ひとつのジャンルにそういうシフトがあるように、それもなにかシフトしていったものなんじゃないでしょうか。僕らにとってはそれはとてもナチュラルでオーガニックな流れなんです。こういうバンドのように、こういうジャンルのようにやりたいって思ってたわけではなくて、自分たちにとって正直に音をつくっていった結果こうなったという感じです。
野田:テリー・ライリーやラ・モンテ・ヤングのような人たちのドローンというのは、現代音楽の発展型で、ある意味論理的で、専門的でマニアックな音楽だったんですけど、それがいまではより感覚的で身近なものになったっていうことでしょうか?
マーク:彼らはニューエイジのドローンの人たちに対して影響があったような作家で、僕らはどうかわからないけど、そういう人たちもいますよね。僕にとってはパンクとハードコアが初めにありました。それはクレイジーなものでしたが、ドローンをはじめたとき、とてもコントロールが効いた音楽だと思いました。とてもミニマルなもので、それが新鮮に思えたんですね。それはとてもリラックスできるものなんだけど、その奥底にパンクやハードコアのようなタフな要素があるんじゃないかって思います。あと、ドラッグなんかをやるときにはパンクみたいにハードなものはやめたほうがいいんじゃないかとも思いますよ(笑)。
橋元:そういう、ドローンとか瞑想的な、アトモスフェリックな音っていうのは、あなたのなかでサーフ・カルチャーと結びついていたりしますか? インナー・チューブ名義での作品はサーフ・カルチャーの影響から生まれたということですが。
マーク:インナー・チューブというのは、スケーターのスペンサー・クラークとのプロジェクトなんですけど、彼ととてもよく遊んでいたことがありました。『ストーム・ライダーズ』というサーフィンについての映画があって、その映画はサーフィンの精神性に関する映画だったんです。そのなかで、「波の力は地球上でいちばん大きな力の源だ」っていうことが語られているんです。
このプロジェクトはシンセサイザーを使ったメディテーション音楽なんですが、とっても楽しかったです。決められたテーマがあったので、むしろいろんなアイディアがふくらんでいきましたね。でもすごいたくさんあるなかで、海のなかにいること、それはサーフィンでも泳ぐことでもいいんだけど、そこに人生のすべての感覚があるんじゃないかって。その海のなかにいる感覚から、世界をどう見るか、人生の経験をそこにどうやってつなげていくかってことをテーマにしました。
野田:レコードにはポスターが入っているんですよね。
マーク:それは映画からきてますね(笑)。
質問:野田努+橋元優歩(2012年8月10日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE