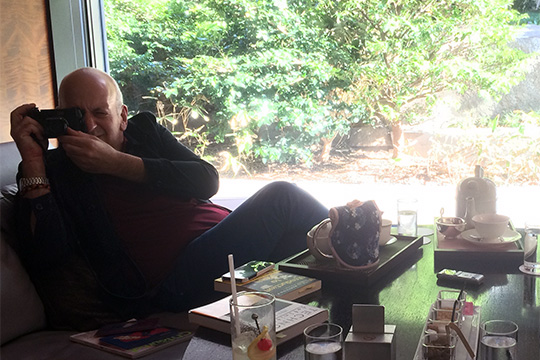MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Daniel Miller - お年玉企画(1)──ダニエル・ミラー
年末年始のお年玉企画の第一弾は、UKの老舗のインディ・レーベル〈ミュート〉の創始者、ダニエル・ミラーのインタヴュー。2014年は、プラスティックマン、アルカ、スワンズなどの話題作をリリースしている。ニュー・オーダーと契約を交わしたこともニュースになったが、2015年の春には待望の新作が控えているらしい。 〈ミュート〉は、80年代のUKポストパンク時代を代表するレーベルのひとつであり、いまだアクチュアルなポップ・センスを失わない数少ないベテラン・レーベルである。相変わらずノイズ/インダストリアルをわんさと出しながら、他方ではポップスにも力を入れて、しっかりビジネスをしているところもすごい。2014年の春、筆者はいかにも仕事ができそうな同レーベルの経営者のひとりにお会いしたのだが、そのときに真顔で、「いまは名前が言えないが、我がレーベルはついにとんでもない大物と契約した。楽しみに」と言われたので、それは誰だ? 誰のことだ? と思っていたら、スワンズだった。たしかにスワンズは「とんでもない大物」である。我々が見習うべきは、このぶれない愛情だろう。
クロックDVAと契約できたらいいね。実はアモン・デュールやノイ!のカタログもリリスしたかったんだけどできなかったんだ。いろいろとややこしくてね。とても出したかったんだけど。
■初めてお会いできて本当に光栄です。
ダニエル・ミラー(以下、DM):ありがとう。こちらこそ光栄だよ。
■先日あなたがニュー・オーダーと契約したニュースにもすごく驚きました。
DM:どうして彼らとの契約に驚いたの?
■当時のポスト・パンクの時代、〈ミュート〉と〈ファクトリー〉はライバル・レーベルという印象を持っていました。〈ミュート〉にはデペッシュ・モードがいて、〈ファクトリー〉にはニュー・オーダーがいましたからね。
DM:いや、むしろ友だちであり同士みたいなものだよ。
■初期の頃、〈ミュート〉はユーモアを大切にしていましたが、それに対して〈ファクトリー〉はもう少しシリアスなレーベルだったので。
DM:〈ファクトリー〉創設者のトニー・ウィルソン自身はかなりユーモアに溢れていた。僕の経験では、ユーモアのあるひとほどダークな音楽をやっている。当時、僕はジョイ・ディヴィジョンやニュー・オーダーと交流があったわけではないから、彼らにユーモアがあったかどうかはわからないけど、〈ミュート〉もダークな音楽は出していたよ。
■現在の〈ミュート〉にはニュー・オーダーやキャバレー・ヴォルテールもいるし、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテンやスロッピング・グリッスルのカタログも持っています。80年代に重要だと思われていたエレクトロニック・ミュージックのほとんどのカタログが〈ミュート〉にはあるのではないでしょうか?
DM:ノイバウテンやスロッピング・グリッスルにしても当時は自主レーベルから出していた。だから〈ミュート〉から出せたことが嬉しいよ。バンドが解散したあとメンバーがもめていたんだけど、そういう困難を乗り越えて〈ミュート〉からのリリースが決まったから自分としても喜ばしかったね。
■80年代に活躍したバンドで、〈ミュート〉が契約したいバンドはいますか? カタログを入手したいバンドでも結構です。
DM:クロックDVAができたらいいね。実は、これらはクラウトロックだけど、アモン・デュールやノイ!のカタログもリリスしたかったんだけどできなかった。いろいろとややこしくてね。とても出したかったんだけど。
■あなたは、クオリティがが高いけど売れそうもない作品を出してしっかりビジネスにするところが、すごいなと思います。ご自身のビジネス・センスを客観的にどう思いますか?
DM:お金にならないものもあるよ(笑)。けれども売れるものあって、そのバランスが大事だと思う。様々なレーベルが世のなかにあるなかで〈ミュート〉が大事にしているのは独自の声と色がある音楽。他でやっていることをやっても意味がないと考えている。その指針となっているのは、ポップから実験的なものまで幅広い僕自身の音楽のテイストで、さっきも言ったバランスがやっぱり大事だよ。異なった音楽の共存が大事であって、それらの相乗効果が〈ミュート〉の生態系を作っている。
■クロックDVAが売れると思いますか?
DM:それなりには売れると思うよ。ちゃんとリマスターをしてパッケージにもこだわってやれば、世界で1,000枚は売れるんじゃないかな。それだけ数字が出せればビジネスは成立する。カタログだとどのくらいの結果が出るのか先が読みやすいけど、難しいのは新人だよ。マーケティングで売り出すためにお金がかかるし、どういうひとが買うのかも考慮しなきゃいけないからね。
■そういう意味ではもうすぐ発売されるアルカは〈ミュート〉らしいアーティストで、しかも、ポップにもアプローチできるアーティストだと思うんです。
DM:いま僕が言った意味でアルカはかなり〈ミュート〉らしい。ずば抜けてユニークだ。まだ非常に若く才能に溢れていて、ヴィジュアル面にもこだわっているしね。ライヴやアートワークにも力を入れているから、こちらとしてもやりがいを持っている。実は彼と契約するのに時間がかかったんだけど、リリースが決まって嬉しいし、ひととしても仕事がしやすいアーティストだよ。
■アルカの音楽は新しい世代のエレクトロニック・ミュージックですが、彼のどこにあなたの世代にはない新しさや若さを感じますか?
DM:言葉で説明するは難しいね。音楽の構築が非常に独自で、いろんなジャンルの要素のミックスが見事だ。各楽曲から出ているムードや雰囲気がこれまでにないものになっている。サウンドそのもの組み立て方もユニークで、そういったものを総合的にみても、いままでにないオリジナリティに溢れた作品になんじゃないかな。
■あなたは音楽シーンに30年以上携わっているわけですが、その間にエレクトロ・ミュージックはとても普及しました。ですが広く普及した反面、クオリティが下がったかもしれません。あなた個人はどうお考えですか?
DM:多くの点で評価しているよ。まず僕のなかで電子機材を自分の音楽で使うミュージシャンと、エレクトニック・ミュージックを作るミュージシャンは大きく違う。僕のエレクトロ・ミュージックの定義は電子機材を使って世界観を作り上げることだけど、いまとなってはコンピュータのなかにソフトがあって、そこからプリセットの音源を使って自分の音楽を作ることが一般化している。
例えば、80年代にデペッシュ・モードとデュラン・デュランはライバル関係にあったけど、前者はエレクトロニック・ミュージックをやっていて、後者は電子音を自分の音楽に取り込んでいたバンドだった。これは音楽を作る上での哲学の違いでもあると思う。
今日の制作現場では多くのひとたちがエレクトロニクスを使っている。なぜなら、それが安くて簡単だからだけど、僕はそれはそれでいいと思う。もちろんクオリティが低いものもあるけど、それはどのジャンルでも同じことだよね?
数多く作り手の一握りから素晴らしい音楽が生まれてくる。エレクトロ・ミュージックの作り方が簡単になって、作り手が増えたことは肯定的に捉えているよ。その何万人のなかからポっと天才が現れるわけなんだけど、それがアルカだと思う。
取材:野田努(2014年12月29日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE