MOST READ
- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス
- valknee - Ordinary | バルニー
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- 『成功したオタク』 -
- Kamasi Washington ──カマシ・ワシントン6年ぶりのニュー・アルバムにアンドレ3000、ジョージ・クリントン、サンダーキャットら
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Zun Zun Egui - きみの“ワイルド”に耳をすませ
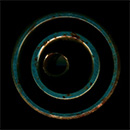 Zun Zun Egui Shackles Gift |
熱い、といったら本人に笑われてしまったけれども、この数年来の「チル」だったり「コールド」だったり「ダーク」だったり「ミニマル」だったりといったムードのなかでは、ズン・ズン・エグイはあきらかに浮いている。個人的に思い出すのは2000年代の中盤のブルックリンだ。ギャング・ギャング・ダンスらの無国籍的エクスペリメンタルからヴァンパイア・ウィークエンドの繊細に濃度調整されたアフロ・ポップまで、あるいはダーティ・プロジェクターズの汎民族的でありつつも色濃い東欧趣味まで、USのど真ん中から放射線状にエネルギーを発していたトライバル志向、その無邪気で鷹揚とした実験主義──
一聴するぶんにはその頃の記憶を呼び覚ます音だけれども、しかしズン・ズン・エグイは実際の多国籍バンドにして中心メンバーのクシャル・ガヤはモーリシャス出身、活動拠点はブリストルとロンドン、また実験ではなくポップが身上である。どこからきてどこへ向かうのか、というコアにあるベクトルが逆向きだ。出自を売りにするどころか、彼が大きく英米の音楽に影響され、またそれを愛してきたことは音にも明らか。そして、そうした志向にミュートされながらも浮かび上がってくる自らのオリジンについては隠すことなく祝福する。以下を読んでいただければよくわかるように、彼には音楽へのとても純真な情熱や、パンクへの精神的な傾注があって、それがまたうらやましいまでに輝かしく、彼らの音の上に表れ出ている。ガヤのバンドではないが、彼がリード・ヴォーカルを務めるメルト・ユアセルフ・ダウンもまたそうしたハイブリッドを体現する存在だといえるだろう。以下で「僕らをブリストルと結びつけないでくれ」というのは、土地やその音楽的な歴史性への違和感ではなく、そのハイブリッド性や多元性を力づよくうべなうものなのだと感じられる。
ともかくも、ファック・ボタンズのアンドリュー・ハングをプロデューサーに迎え、前作に増して注目を集めるセカンド・アルバム『シャックルズ・ギフト』のリリースに際し、ガヤ氏に質問することができた。
■Zun Zun Egui / ズン・ズン・エグイ
ブリストルを拠点に活動する5人組。モーリシャス出身で、メルト・ユアセルフ・ダウン(Melt Yourself Down)のヴォーカルとしても知られるクシャル・ガヤ(Kushal Gaya、G/Vo)、日本人のヨシノ・シギハラ(Key)ら多国籍なメンバー構成を特徴としている。2011年にデビュー・アルバム『カタング』を、本年2月にセカンド・アルバム『シャックルズ・ギフト』を、いずれも〈ベラ・ユニオン〉からリリース。今作ではプロデュースをファック・ボタンズ(Fuck Buttons)のアンドリュー・ハング(Andrew Hung)、ミックスをチエリ・クルーズ(Eli Crews)が手掛ける。
僕は自分自身の中にある、いちばん原始的で、本能的で、すごく人間くさい部分、理性や身体的なものを超えたところにある自分自身のエッセンスとも言えるような何かとのつながりを失いたくないんだよ。
■どの曲にも「You」への強い呼びかけを感じます。この「You」は同じひとつの対象ですか? そして、どのような存在なのですか? もしかしてあなた自身ですか?
クシャル・ガヤ(以下KG):うーん……「You」って言葉を何度も使った理由はたぶん……僕が歌詞を書くときは、自分自身も(その歌詞の中に)含まれたものにしたいんだと思う。たとえばアルバムの中の「I Want You to Know」で「You」って言っているのは、曲を聴いている誰かとダイレクトにつながりたいからだよ。っていうのも、あの曲では、僕らがいまもまだそれぞれのいちばん本能的でワイルドな部分を通してつながることができるっていう事実を、僕自身がとても重要視しているということ──そういう個人的な事実を、みんなに伝えたいって言っているんだ。
個人的に、僕は自分自身の中にある、いちばん原始的で、本能的で、すごく人間くさい部分、理性や身体的なものを超えたところにある自分自身のエッセンスとも言えるような何かとのつながりを失いたくないんだよ。だからあの曲では、「これが僕の感じていることで、これを聴いているみんなにわかってほしい、関わってほしい」っていうことを言っている。だからそれが「You」って言葉を使った理由かな。この答えじゃ何を言っているのかよく伝わらないかもしれないけど……(笑)。
■「You」という言葉によってある種の対話のようなものを生み出したいということでしょうか?
KG:そう、僕は対話のきっかけを作りたいと思っていることが多いんだ。「これが僕の感じていることだけど、君は何を感じる?」っていうふうにさ。
■あなた方と同じブリストルの、ベースミュージック・シーンの重要人物のひとりピンチ(Pinch)は、一昨年〈Cold〉という名のレーベルを発足させました──
KG:ピンチは知っているよ! 個人的には知り合い程度だけど、彼の音楽はよく知っている。
■これはそのまま「冷たい音楽」という意味ではありませんが、音楽の先端的なトレンドが「コールド」という名を掲げる一方で、あなたがたの「熱い」エネルギーは非常に珍しく感じられます。自分たちの音楽が熱いものでありたいという意志や意図はありますか?
KG:ははは、「熱い」か! そうだね、ブリストルってかなりダークなエネルギーがあって、あそこではいろいろなことが起きているけど、そこには間違いなくダークでダウナーな、どこか冷たい感じのエネルギーが感じられるんだ。だからある意味それに対する反応として、僕はそれとはまったくちがった、楽しげでハイテンションな音楽をやるようになった部分はあるのかもしれない。
それに僕はもともと、落ち着くタイプの音楽じゃなく、エネルギッシュな音楽が好きで、音楽には生命感を感じさせたり覚醒させるようなものであってほしいんだ。僕は覚醒だったりとか、目覚めていること、知覚、現在を感じることとかにとても興味があるんだよ。だから、たぶんそのせいかもしれない。
ブリストルには間違いなくダークでダウナーな、どこか冷たい感じのエネルギーが感じられるんだ。だからある意味それに対する反応として、僕はそれとはまったくちがった、楽しげでハイテンションな音楽をやるようになった部分はあるのかもしれない。
■BLK JKS(Black Jacks)というヨハネスブルグ出身のバンドがいますが、彼らもまたプログレッシヴ・ロックなど西洋的な音楽に比較される要素を強く持ちながら、アフリカ音楽のエネルギーを放出する人たちです。あなたの音楽にとって、アフリカというルーツは音楽の制作上どのくらい重要なものなのでしょう。
KG:僕自身アフリカ出身で、人生のうち18年をアフリカで過ごしたから、アフリカ音楽の影響っていうのは自然に出てくるものだと思う。それは僕が意識的に獲得したり、どこかに行って得たものではなくて、自分自身から生じてくるもので、それ自体が僕自身でもあるんだ。たとえばこのアルバムに入っている“Ruby”を例にすると、そこで使われているリズムの多くは、僕の育ったモーリシャスで結婚式や葬式で使うリズムなんだ。そういうリズムを持ってきて、別の何かを作り出しているのさ。そういうふうに、僕にとってそれはすごく自然なもので、作為的なものではないよ。
■では、あなたのなかでのアフリカ音楽と西洋音楽との関係についても教えてください。
KG:えーっと、僕はこの世界は国とかの概念を超えるものだと思っているんだ。国や愛国心みたいな概念は死にゆくものだと思っている。過去には西洋のミュージシャンたちがアフリカ音楽に憧れのようなものを持って、それを彼らなりに解釈したものを作っていたけど、僕はその逆をやっているように感じるんだ。僕は西洋音楽を解釈しなおして、彼らの逆側から歌っている。
それが一点と、もうひとつは、僕は長いこと英国に住んでいるけれど、英国は多文化の合流地点になっていて、人々は「英国的」の定義とは何か、ということについて疑問を持っている。そして「英国的」の定義や、この国の文化のアイデンティティはすっかり変化しつつあるんだ。ロンドンに来れば、それがロンドンのどのエリアであっても、そこにいる人々はそれぞれまったくちがう国から来ている。それってすごく美しいことで、ロンドンという町に多様性を与えているんだ。それこそがここでいろいろな文化が生まれている理由で、人々がここに来たがる理由になっている。そして西洋文化っていうのはここ100年以上の間、世界でいちばん影響力のある文化になっているから、誰もが間違いなくそこから影響を受けていると思う。
僕は長いこと英国に住んでいるけれど、英国は多文化の合流地点になっていて、人々は「英国的」の定義とは何か、ということについて疑問を持っている。
日本でだって、西洋のポップスや音楽は誰が頼まなくても自動的に入ってくるでしょ? だからそういう意味で、西洋音楽には誰もがつながっているんだ。それで、僕は自分のアーティスティックな役割……役割というか、必要に迫られて自然に生まれた反応は、その影響を自分なりのかたちで利用するっていうことだと思っている。なんだか質問にちゃんと答えていない気がするけど……。それに僕は個人的に西洋の音楽はとても好きだし、ヨーロッパの70年代、80年代、あるいは2000年代以降のパンク・ミュージックや80年代のハードコア、ノイズ・ミュージックからも影響を受けている。あとちなみに日本のノイズ・ミュージックからもね! ヨシノと日本の音楽をたくさん聴いたんだ、メルト・バナナやボアダムスとかさ。
■たとえばデーモン・アルバーンはあなたとは逆の立場から西洋とアフリカの融合にアプローチしようとしているように見えますが、彼の音楽に対するシンパシーはありますか?
KG:英国にアフリカのミュージシャンたちを連れてきたりっていう、彼のやっていることの意図自体は良いものだと思うけど、同時に僕にはそこでアフリカの音楽が消毒されすぎているような感覚があるんだ。西洋に持ってこられたアフリカ音楽は、あまりにもきれいに衛生処理されてしまって、元々アフリカで演奏されていたときにはあったはずの生のエネルギーが失われてしまっているような気がする。まるでそれを西洋音楽として新しく、薄まったものにプロデュースし直しているみたいで、生々しくてワイルドなエネルギーや、深みが欠けてしまっている。デーモン・アルバーンのやっていること自体はいいことだし、ポジティヴな動きだと思うけど、その一方でそこで失われてしまっている音楽のエッセンスみたいなものがあるように思えるんだよ。こちらに持ってこられた音楽が、「ほら見て、ここにアフリカのミュージシャンたちと僕がいるよ!」みたいな感じで提示されたりとか……。
西洋に持ってこられたアフリカ音楽は、あまりにもきれいに衛生処理されてしまって、元々アフリカで演奏されていたときにはあったはずの生のエネルギーが失われてしまっているような気がする。
アフリカの音楽を西洋に持ってきて人々に見せたいのなら、それはできるかぎり生の状態、本来の本物の状態に限りなく近いものであるべきだと思うんだ。だって、多くの場合、アフリカの音楽は、売られるためや多数の人に商業的に見せるためのものじゃなくて、儀式のためのものや、日常生活と密接に結び合わさったものであるはずなんだ。結婚式や葬式や、雨の神に雨乞いをしたり、豊穣の神に呼びかけるものだったりさ。もちろんアフリカにもポップ・ミュージックはあるけど、それらふたつの音楽はまったく性質の異なったものだよ。だから、そういう音楽をこっちに持ってきたときに失われてしまうものがあるし、また同時に西洋人のために綺麗に処理されてしまっている部分もあるように感じて、それがもったいないと思うんだ。
■あなたがたはまた、混合的なエスニシティを持ったバンドでもありますね。楽曲制作においてはメンバーはそれぞれ自身のルーツを主張しますか?
KG:いや、あんまり……僕らそれぞれのバックグラウンドはあまり問題ではないよ。だって、僕らはもうそういうことをあまり意識したりしないからさ。僕らはただ人間として気が合うからいっしょにいて、それゆえに音楽をいっしょに作っているってだけだよ。たとえば僕が日本に行って、日本人の友達がたくさんできていっしょに音楽を作りはじめたとしたら、そこで「君は日本人だから、日本の音楽をやろうぜ!」「僕はモーリシャス人だから、モーリシャスの音楽を作るんだ!」とはならないと思うし。だから僕らはべつに……そもそもそういうことについて考えることすらないよ。ときどきそれぞれの出身を冗談の種にすることはあるけどさ。音楽を作ることに関していえば、すべては僕らの心から生まれてくるものなんだ。僕らはただ人間なだけで、国籍とかは関係がないんだよ。
質問作成・文:橋元優歩(2015年3月11日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE




