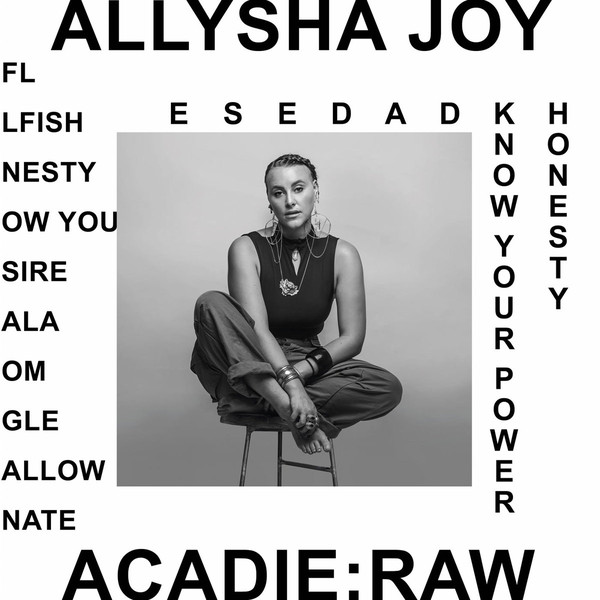MOST READ
- 別冊ele-king J-PUNK/NEW WAVE-革命の記憶
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- 『90年代ニューヨーク・ダンスフロア』——NYクラブ・カルチャーを駆け抜けた、時代の寵児「クラブ・キッズ」たちの物語が翻訳刊行
- Jeff Mills with Hiromi Uehara and LEO ──手塚治虫「火の鳥」から着想を得たジェフ・ミルズの一夜限りの特別公演、ゲストに上原ひろみと箏奏者LEO
- Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs - Teresa Winter, Birthmark, Guest,A Childs | テレサ・ウィンター、バースマーク、ゲスト、エイモス・チャイルズ
- FESTIVAL FRUEZINHO 2026 ──気軽に行ける音楽フェスが今年も開催、マーク・リーボウ、〈Nyege Nyege〉のアーセナル・ミケベ、岡田拓郎が出演
- 早坂紗知 - Free Fight | Sachi Hayasaka
- 大友良英スペシャルビッグバンド - そらとみらいと
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- KMRU - Kin | カマル
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Dual Experience in Ambient/Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング会@野口晴哉記念音楽室、第2回のゲストは岡田拓郎
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
Home > Interviews > interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作
ハープは最近とても重要な楽器になってきていて、ジャズ界にとって興味深い存在だと思います。
■フルートを本格的に始めたのはいつ頃ですか?
CW:フルートとの出会いは、バンドでブラジル音楽を演奏していたときのことです。フルートとサックスはもちろん関係があるし、演奏するときの指の形も似ているから、サックス奏者がフルートやクラリネットを手に取るのは自然なことなんです。演奏技術的にはフルートはサックスのいとこみたいなものですね。私は姉のフルートを借りて学びました。その後、妻が誕生日プレゼントにフルートを買ってくれて、ジョージ・ギャルウェイからレッスンを受けました。有名なフルート奏者のジェイムズ・ギャルウェイの兄で、サックス、クラリネット、フルート、何でも演奏する素晴らしいプロでした。性格はとてもワイルドでしたけどね。
フルートという楽器はサックスよりも演奏するのが技術的にずっと難しい。サックス奏者はしばしばとても下手なフルート奏者になります。その逆は簡単なんですけどね。フルートでいい音を出すのは、サックス奏者には難しいんです。だから、それを修正するために何年も懸命に努力してきたし、好き嫌いをせず複数の楽器を演奏することができるマルチ奏者になるために努力してきました。フルートが大好きなんです。それでハロルド・マクネアやローランド・カーク、ジェイムズ・ムーディといったマルチ奏者の名手たちのレコードを聴くようになりましたね。どちらか一方しか演奏できないのではなく、両方演奏できたから良いキャリアを積むことができたと思っています。アルト・フルートはいつもアルバムで演奏していますね。アルト・フルートは少し大きめで、音に深みがあります。偉大な映画音楽作家のラロ・シフリンは、アルト・フルートとフリューゲルホーンを使っていました。彼の映画のサウンドトラック、とくに70年代の『Bullitt』のようなサウンド、あれはとても特徴的なものですね。
私は美しい音色を奏でるアルト・フルートの大ファンです。でもライヴで演奏するのはとても難しくて、適切な曲を選ばなければならないし、大音量で演奏することもできません。私は “Winter” という曲(『Cloud 10』収録)でアルト・フルートを吹いたのですが、とてもスローで深いスピリチュアルなジャズ・トラックです。アルト・フルートは珍しい楽器で、私はそれを極めていくのが大好きなんです。どちらかというと、サックス奏者としてよりもフルート奏者としての私の方が特徴的だと思います。サックス奏者は何百万人もいるけれど、フルート奏者はもっと少ない。フルートの世界を探求するのはとても楽しいことだといつも感じています。ある意味、あまり開拓されていない領域のようにも思えますね。
■あなたの演奏するジャズはラテンやアフロ・キューバンの要素があり、クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズといった、1950年代から1960年代に土台を築いたモダン・ジャズが軸になっていると思います。クラブ・ジャズにおいてもこうしたジャズは「踊れるジャズ」として一世を風靡し、2000年代にイタリアのニコラ・コンテやレーベルの〈スキーマ〉、フィンランドのファイヴ・コーナーズ・クインテットなどが人気を博した時期もありました。あなたの作品を聴いているとそれらに近い印象を覚えるのですが、あなた自身では自分の音楽はどのように生まれたものだと思いますか?
CW:あのクラブ・ジャズ・シーン全体が好きでしたね。私はファイヴ・コーナーズ・クインテットの大ファンで、ヘルシンキにも行ったことがあります。メンバーのティモ・ラッシーとは親友で、彼の音楽の大ファンですよ。フィンランドのクラブ・ジャズ・シーンは50年代の〈ブルーノート〉のようなクラシカルなサウンドとダンス・ミュージック、そしてモダンな感性との素敵な出会いがあってとても素晴らしいものでした。〈スキーマ〉はどちらかというとボサノヴァ的ですが、あそこのリリースする作品も好きです。それから、ジャザノヴァやキョウト・ジャズ・マッシヴのようなアーティストも大好きで、彼らのようなクラブ・ミュージックとジャズが融合した音楽にたいへん魅力を感じます。
私の音楽に対するアプローチについて話をすると、たとえば古いジャズのドラム・ループやサンプルを取り入れたシネマティック・オーケストラのように、それら素材をもとにダンス・ミュージックを作るというアイデアもあるんです。でも、ファイヴ・コーナーズ・クインテットのように、ジャズが本来的に持つダンス音楽としての要素をもっと直接的に用いる方法もあります。彼らの音楽は一見〈ブルーノート〉の昔のレコードのように聴こえるかもしれないけれど、じつはそれだけではないんです。今回のアルバム(『Cloud 10』)も、まるで50年代のサウンドやそのスタイルを知っている素晴らしいミュージシャンのプレイを聴くことができるような、ちょっとしたスタジオ・ワークの妙技があります。私のアルバムの多くには、そういった要素がたくさん含まれていると思います。『La Sombra』や『Cloud 10』に収録されている “Tubby Chaser” はそんなシーンを彷彿とさせると思います。
クラブ・カルチャーとジャズ・カルチャーは、いまのところある程度まではイギリスではうまく融合していると思いますよ。若い世代が再びクラブ・シーンに溶け込み、ジャズもその一部に組み込まれ、シーン全体に新鮮な空気を吹き込んでいると思います。純粋なジャズ・ファンや、シリアスなダンス・ミュージック・マニアたちの領域を冒さない限り、両者は共存できる。その中間点を見つけるのは難しいと思いますが、それができたときは素晴しいと思います。現在だとほかの国でもミュンヘンのウェブ・ウェブとか、ストリングスがちょっとクラシックなストックホルムのスヴェン・ワンダーも好きですね。もし私の音楽をこれらの人たちと同じカテゴリーに入れてくれてるなら、それはとても光栄なことです。
■〈ラヴモンク〉で3枚のアルバムをリリースした後、2022年にマシュー・ハルソールが主宰する〈ゴンドワナ〉から『Cloud 10』を発表します。マシューが率いるゴンドワナ・オーケストラにも参加しているのですが、どのようにマシューや〈ゴンドワナ〉との関係が始まったのですか? マンチェスターの音楽学校時代から関係があったりするのでしょうか?
CW:私とマシュー・ハルソールの付き合いは〈ゴンドワナ〉ができる前まで遡ります。マンチェスターのシーンで、彼やナット・バーチャルのような連中と一緒に演奏していたんです。それ以来、私たちはずっと友だちです。音楽的なテイストやヴァイブス、意思の面で、出会ってすぐに意気投合しました。私たちはいつも次のことをやりたいと思っているし、アーティストとしてとても好奇心旺盛な性格で、つねに前進していきたいと思っています。私たちは自分たちのやっていることが大好きで、いつも「このアルバムと、あのレコードと、これと、どう?」と話しているんです。話を戻すと、音楽学校を卒業してからはずっと後になりますが、スペインに移住する前の2007年頃、当時私たちはマンチェスター近郊でよく一緒にプレイしていて、私は彼のファースト・アルバム『Sending My Love』に参加しました。私がイギリスを離れてもずっと友だちで、マシューがマドリードに来るときは彼や彼のバンドといつも一緒に演奏していました。
マシューがゴンドワナ・オーケストラを結成したときも、彼は私を招待してくれました。ジョン・スコット、タズ・モディ、アマンダ・ウィッティング、ギャヴィン・バラスといった素晴らしいプレイヤーたちと一緒にね。だからマシューと〈ゴンドワナ〉と私の関係が途切れたことはないんです。〈ラヴモンク〉から最初のアルバムを出したときも、そのデモをマシューに送って感想を聞いたり、雑談したりしたのを覚えています。私はデモをマシューによく送って「これ、どう思う?」とアドバイスをもらっています。『La Sombra』を発表するためのロンドン公演を企画してくれたのも、じつはマシューと彼のマネージャーであるケルステン・マックネスだったんです。当時は彼らのレーベルと契約していたわけではないのに協力してくれた。この関係はとても美しい。いつもそばにいるわけではないのが残念ですが、必要であれば飛んでいきますね。たとえばマシュー・ハルソールの最新作『An Ever Changing View』(2023年)のセッションにも参加しましたし、昨年9月には彼のロイヤル・アルバート・ホールを含む大きなツアーにも参加しました。ロイヤル・アルバート・ホールで3000人もの満員の観客の前で、〈ゴンドワナ〉の15年周年を祝福できたことは本当に意味深いことでした。
私と〈ゴンドワナ〉との契約が始まったときのこと話すと、私とマシューはアーティストとレーベル・マネージャーとしてではなく、まず友人として話をしました。マシューは音楽に関することよりも、私がレーベルと契約することで私たちの友情が失われることを心配したんです。彼は「僕たちは大親友で、仕事という状況に入るのだから、このことについてじっくり考える必要がある」というのです。それはとても優しく、彼の人間性をよく表しています。もちろん〈ゴンドワナ〉とはとてもうまくいっています。ロニー・リストン・スミスをカヴァーしたEP「Astral Traveling」(2022年)も素晴らしいレコードで、本当にいい流れがつくれているし、これからもこの関係が続いてくれることを願っています。

幸運にもロニー・リストン・スミスと3、4回、とても長く話をすることができたんです。彼が「よくやった」と言って連絡をくれたことは、人生の忘れられない瞬間のひとつです。
■『Cloud 10』は作風としては〈ラヴモンク〉時代を継承するものですが、グループ編成を見ると〈ラヴモンク〉での3作目にあたる『Blue To Red』(2020年)よりイギリスのミュージシャンがバンド・メンバーとなっています。録音のベースはイギリスに移ったのですか?
CW:いえ、マドリードにあるエスタジオ・ブラジルでレコーディングして、そこにイギリスからミュージシャンたちがやってきました。素敵なアナログ・スタジオで、そこでの収録は2回目でした。メンバーは当時一緒に仕事をしていた音楽家で、ゴンドワナ・オーケストラのメンバーだったジョン・スコット。それと2作目の『Shamal Wind』(2018年)でピアノを弾いていたフィル・ウィルキンソン。彼もイギリス人ですが、当時彼はスペインに住んでいました。それからサイモン・“スニーキー”・ホートンは、90年代半ばのレイ&クリスチャン時代まで遡る長い付き合いです。トン・リスコはスペインのガリシア地方の出身で、最高に素晴らしいヴァイブ奏者なんです。ほとんどはイギリスのメンバーですよね。でも私にとってアルバム作りは料理みたいなもので、それは材料やキャラクターをまとめることであり、レコーディングした時点でのスナップショットでもあります。だから、そのとき一緒に仕事をしているプレイヤーや周りにいる人たちがその時々のプロジェクトに参加する傾向があって、作品ごとに自然に移り変わっていきます。私は曲を書いてからデモを作ることが多いのですが、そのときの曲について私が求めるフレーヴァーを考えます。そうしたらジョン・スコットが最適なドラマーで、ベースはスニーキーが最高だと思いました。それにマッコイ・タイナーみたいなピアノも必要で……だからフィル・ウィルキンソンにピアノをお願いしました。最終的に正しい結果を得るために、正しい材料を揃えるようなことをするわけです。
アルバムの演奏はライヴ・バンドとはまったく別もので、ライヴ・バンドで使うプレイヤーのリストもあるけれど、アルバムはそのとき必要な要素に基づいています。私にとってはいつも音楽が最優先で……一緒に仕事をした仲間のほとんどは、そんな私のことをよく知っています。私はとても正直で、彼らはそれを理解してくれる。その上でアルバムに参加するなら、参加する。しないなら、しない。ミュージシャンがプロセスにコミットし、自分自身よりも音楽を優先すること、それは私の音楽にとって本当に重要なことなんです。ミュージシャンが私と一緒にスタジオに入るとき、私は彼らがテクニックを見せびらかしたり、楽曲にあれやこれやと注文を入れたりすることを望んでいません。深い意味で、精神的な意味で、献身的な意味で、その瞬間、その楽曲を可能な限り良いものにすることに集中してもらうような……音楽に向き合ってその中に完全に同調してほしいのです。私にとってはそれが全てなんです。私がミュージシャンを集めるときにいつも心がけているのは、スタジオでそのような雰囲気を作り出すこと、つまり何か特別なものを作り出そうというスピリットをみなと共有していくことです。アナログ・スタイルのレコーディングは、その生演奏の瞬間を録音しなければなりません。上手く演奏できなかったらもう一度やり直さなければなりませんが、レコーディングを繰り返すには録音テープに十分なスペースが必要です。アナログ・スタイルのレコーディングにはこういったリスクがある一方、そうした制約下でのエネルギーがもたらすパフォーマンスのレベルはとても特別で、アルバムに美しいものをもたらしてくれると思います。そのプレッシャーに対処し、深く入り込むことができるミュージシャンがいる限り、毎回ずっといいものができる、そう思っています。
■『Blue To Red』からはさらにハープ奏者が加わっています。ハープはゴンドワナ・オーケストラはじめ、マシュー・ハルソールが好んで使う楽器なのですが、そのあたりは影響を受けているのですか?
CW:もちろんです。マシュー・ハルソールはハープにこだわってきました。彼のバンドにはつねにハープがあり、それが彼のユニークなセールスポイントのひとつだと思います。私はマシューのおかげでハープ奏者のアマンダ・ウィッティングと仕事をするようになりました。アマンダがゴンドワナ・オーケストラで演奏していたのが直接のきっかけで、私がベルリンでのライヴに行ったとき、そこで初めてアマンダに会い、彼女の演奏を聴いて、意気投合しました。そして、当時進行中だった『Blue To Red』のセッションに参加してもらいました。土曜日にゴンドワナ・オーケストラで一緒に演奏して、そのまま月曜日に彼女はスタジオにいて、私の次のアルバムのレコーディングに参加してもらったのです。彼女はこれまで私の作品にたくさん参加してくれてますし、私も彼女のアルバム3枚に参加しています。
■マシューの場合はアリス・コルトレーンが好きでハープを重用していると思うのですが、あなたも〈ゴンドワナ〉移籍後はマシューやアリスの影響からか、いわゆるスピリチュアル・ジャズ的な要素も増えているような気がします。いかがですか?
CW:ハープという楽器に関して言うと、アマンダ・ウィッティングはアリス・コルトレーンというよりドロシー・アシュビーに近いタイプの演奏家で、アリスよりはるかにメロディアスだと思います。ドロシー・アシュビーは私がよく聴く偉大な伝説的ハープ奏者です。1970年の『The Rubáiyát Of Dorothy Ashby』はお気に入りのアルバムのひとつ。これまでで最も美しいハープのアルバムだと思っています。私にとってハープはジャズという音楽における重要な一部だし、美しい音色を持ち、フルートとの相性もとてもいい。質感的にもね。ヴィブラフォンやローズ・ピアノなどとも相性はいいですが、とくにフルートと美しく調和する音だと思います。ハープは視覚の面でもステージでとても重要です。とても大きくて、とてもエレガントで、音楽に静けさと落ち着きと真剣さを与えてくれます。ああ、深くてゆっくりとしたスピリチュアルなジャズの曲を演奏しているときに、突然心臓の音が聞こえてきたら、心臓がバクバクしてしまいますね。本当にゴージャスなサウンドです。ハープは最近とても重要な楽器になってきていて、ジャズ界にとって興味深い存在だと思います。アマンダは昨年〈ファースト・ワーズ〉に移籍して、いま新プロジェクトを立ち上げるなど、新しいキャリアをスタートさせています。今後の彼女の動向も目が離せないと思います。
■あなたの音楽はスピリチュアル・ジャズとカテゴライズされる場合もあると思いますが、いわゆるフリー・ジャズやブラック・ジャズ的なそれではなく、あくまでモーダルでクールなものであると思います。たとえばファラオ・サンダースとかマッコイ・タイナーのようなタイプとも少し違い、近い印象ではポール・ホーンやボビー・ハッチャーソンのような音楽を彷彿とさせます。エモーションよりも知性が勝る音楽で、非常に洗練されてスタイリッシュな印象を持つのですが、あなた自身は音楽を作ったり演奏したりする際に意識しているのはどんなところですか?
CW:あなたが名をあげたポール・ホーンやボビー・ハッチャーソンは、実際に参考にするミュージシャンですね。音楽におけるモーダルなエッセンスは、私が好きなクラブ・ミュージックの要素と結びついているから重要です。モーダル・ジャズには深みとクラブっぽさがあると思います。50年代や60年代のハード・バップを演奏するなら、コード・チェンジやウォーキング・ベースがとても特徴的ですが、モーダル・ジャズの世界に一歩足を踏み入れると、ベース・ラインを歩かせる必要はなくなります。モーダル・ジャズの多くには大きなベース・リフがあり、私はそれが大好きです。ベースのフレーズが大好きなので、私の曲はどれもベース・ラインが大きい。どれも美しくメロディアスなベース・ラインです。だから、ハード・バップのようにコード・チェンジを多用するよりも、モーダル・ジャズのウォークしないベース・ラインのほうが自分の音楽にはしっくりくると思っています。もちろん私の曲にはコード・チェンジもあるし、ストレート・アヘッドなジャズへの敬意もあります。スタイル的にモーダルなものはジャザノヴァやザ・ファイヴ・コーナーズ・クインテット、ティモ・ラッシーの世界に共通するもので、彼らの音楽はよりオープンエンドで、テクスチャーが強く、もっとスペースがあるものが多いです。エレクトロニクスを使ったり、ほかのものを使ったりするためにはスペースが必要なんです。ハーモニーが複雑すぎたり、変化しすぎたりすると、サンプルや深みのあるサウンドの効果が少し薄れてしまいますから。
私が参考にしている一例をあげると、ボビー・ハッチャーソンとハロルド・ランドのアルバム『San Francisco』があります。ドナルド・バードがマイゼル兄弟とやった作品もそうですね。それからロニー・リストン・スミス! 私の〈ゴンドワナ〉からの最初のレコード「Astral Travelling」EPに遡りますが、ロニー・リストン・スミスをカヴァーしたこの作品もまたモダンでスピリチュアルなジャズです。モード・ジャズとファラオ・サンダース的なスタイルのクロスオーヴァーのようなものですね。私はじつは、幸運にもロニー・リストン・スミスと3、4回、とても長く話をすることができたんです。彼は私が「Astral Traveling」EPをリリースした後に連絡をくれて、電話でピアノを聴かせてくれました。彼の話に圧倒されて涙が出そうになりましたね。音楽について2、3時間話したのですが、あのレベルに達した人と話して、彼がいま何を考えているのか、どう考えているのか、彼がいま音楽についてどう感じているのか、彼の音楽をリスペクトしながらも新しいものを作ろうとしている私のような人間について、彼がどう考えているのか……彼の脳みその中にあるいろいろなものをかき集める機会を持てたことは、自分の人生が肯定されるような経験でした。
カヴァー・ヴァージョンに関する個人的な見解を述べると、すでにクラシックになっている名曲を新しいものに書き換えてしまうのは最悪の試みだと思っています。私は自分で曲を書くので、カヴァー・ヴァージョンはあまりやりません。だから、あくまでレーベルからの特別企画的な提案だったとはいえ、ロニー・リストン・スミスの曲を3曲やるのはとても難しかったですし、オリジナルとなるべく同じように聴かせたかったから、アレンジもスタイルも深く考えなければなりませんでした。ロニーがトラックをとても気に入ってくれて、本当に理解してくれたのは、私にとっては圧倒的な体験でした。彼が「よくやった」と言って連絡をくれたことは、人生の忘れられない瞬間のひとつです。原曲を書いた人からリスペクトを受けるなんて素晴らしい経験で、一生感謝しつづけたいと思っています。
自分の経験の断片、好みの断片、人生や自分自身の断片を組み合わせることで、アーティストとして、作曲家として、自分の持ち味を発揮することができるようになるのです。私のなかにはマンチェスターの断片があり、ロンドンの断片があり、マドリードの断片がある。中東の断片も持っています。
■『Cloud 10』には先ほど話に出た “Tubby Chaser” という曲があって、これは1960年代に活躍したイギリスの伝説的サックス奏者のタビー・ヘイズへのオマージュかと思います。曲調はそのタビー・ヘイズと同時期に活躍したサックス&フルート奏者のハロルド・マクネアの “Hipster” を彷彿とさせるものです。この “Hipster” はダンス・ジャズ・クラシックでもあるわけですが、こうした1960年代から1970年代初頭のUKジャズの影響はあなたにも大きいのでしょうか?
CW:ああ、素晴らしい影響を受けていると思います。タビー・ヘイズの “Down in the Village” は最高にクールだと思います。ハロルド・マクネアはカリブ海出身ではあるけれど、イギリスに渡って多くの時間を過ごしました。彼の “The Hipster” はまさに私がやってみたいことのひとつですね。スタイルの面で私やファイヴ・コーナーズ、ティモ・ラッシーに通じるサウンドがあります。私たちみんなが聴いてきた音なんですね。タビー・ヘイズやハロルド・マクネアたちはその元祖なんです。タビー・ヘイズはイギリスで言えば、50年代にUKのジャズ・シーンが成長した時期の最初の人物だから、とても愛されています。サックス、フルート、ヴィブラフォンを演奏して、多くの音楽家に影響を与えました。私のような人間ももちろん彼を避けて通ることはできませんよね。50年代にタビーたちはみな船に乗って演奏しながらアメリカに渡った。ニューヨークで3日間音楽を聴き、最新のレコードを買い、それをトランクに入れてまた船で戻ってくる。その頃のロンドンではサックス奏者のロニー・スコットが素晴しいジャズ・クラブをオープンして、タビー・ヘイズは人々がジャズを楽しむそんな素敵なロニー・スコッツ・クラブで演奏し、ニューヨークで聴いてきたものを再現しようとしたんです。古き良き時代のイギリスらしい話ですね。つまり、アメリカ人がやっていることを、私たちイギリス人も真似してやってみようじゃないかと。タビー・ヘイズはニューヨークに行ってアメリカのミュージシャンとレコーディングし、ロニー・スコットはソニー・ロリンズに演奏してもらうためにイギリスに招聘した。彼らはパイオニアであり、道を切り開いてきました。私たちはまだまだ彼らのことについて話をすべきです。彼らが私たち全員に与えた影響はいまでも感じられるわけですから。いま彼らのレコードを聴いても、ほかのどのレコードよりも優れていると感じます。
タビー・ヘイズと同じような時代のハロルド・マクネアも、フルート奏者として私に多大な影響を与えてくれました。息を強く吐きながらフルートを吹くという、いわば歌と演奏を同時にこなす独特なスタイルを持っていました。同じようなスタイルを持つローランド・カークの演奏も聴きましたが、私にとってはハロルド・マクネアの “The Hipster” やそのほかの曲もろもろの方が素晴らしかったです。彼はケン・ローチ監督のドキュメンタリー映画『Kes』(1969年)のサウンドトラックに参加していて……最高に素晴らしい映画なんですが、その音楽を作曲家のジョン・キャメロンが手がけていて、ハロルド・マクネアがフルートを吹いています。初めてそのアルバムを聴いたとき、私は自分が何を聴いているのか信じられなかった。本当にゴージャスで、素晴らしい作品です。けれどもハロルド・マクネアは時代を先取りしていたのに、長生きはできませんでした。彼は3、4枚のアルバムを作って、それで死んでしまったのです。でも、彼が残したものは本当に驚くべきもの。みなさんにはぜひハロルド・マクネアを聴いてみてください、と言いたいですね。
■現在のイギリスは、サウス・ロンドンのシャバカ・ハッチングスたちを中心としたジャズ・ムーヴメントがあり、一方でマンチェスターのマシュー・ハルソールやゴーゴー・ペンギンたちからも発信がおこなわれています。あなたはサウス・ロンドン・シーンとは異なるジャズをやっていて、でもゴーゴー・ペンギンなどともまた異なるジャズであると思います。ブリストルなどほかの都市でもジャズがあるわけですが、あなたは自身の音楽についてどのようなジャズだと思いますか?
CW:私はロンドン南部に近いブライトンで育ちましたから、ロンドンのジャズ・シーンの性質は理解しています。サウス・ロンドンのシーン全体は、アフロセントリックなサウンドですね。とてもディープでエレクトロニックなクラブ・ミュージックの要素もありますね。ロンドンのシーンにはライヴのエネルギーがあります。外に出て、集まって、演奏して、できるだけ多くの人がステージに立つ。現在のロンドンのシーンにはジャズが長い間必要としてきた若々しいスピリットがあります。一方でマンチェスターのマシューはもっと洗練されていると思います。もしマシューがサウス・ロンドンのペッカムを拠点にしていたら、いまごろ彼はイギリスで一番のスターになっていたと思いますよ。マンチェスターにいるということで、彼は少し注目を集めづらい部分があるかもしれません。でもロンドンはロンドンでほかとは違う難しさがあります。私はどちらのシーンも見てきたので、それぞれの苦労がわかるんです。私には世界を旅するトラヴェラーのような要素もあり、幸運にもその土地土地のいろいろなスタイルの音楽を演奏する機会に恵まれてましたから。文字どおりどんなスタイルの音楽もやってきたし、高いレベルで演奏してきました。私が持っている音楽的な幸運です。一緒に演奏するバンドは、多くの異なる味をもたらしてくれますが、それらを何とかうまく調和させることができたと思います。
影響されたものが多すぎるのはときに悪いことで、混沌としてしまうこともあります。でも、音楽に限らず何ごともそうですが、自分の経験の断片、好みの断片、人生や自分自身の断片を組み合わせることで、アーティストとして、作曲家として、自分の持ち味を発揮することができるようになるのです。私のなかにはマンチェスターの断片があり、ロンドンの断片があり、マドリードの断片がある。中東の断片も持っています。私の音楽には、いろんな影響があるんです。住んでいたところからだけじゃなくて、いろんな音楽を聴いていますからね。だから地理的な縛りはあまりありません。いろいろな人に会い、いろいろなミュージシャンと演奏する機会があり、私はその経験を自分のなかに持っている。自分のヴォキャブラリーや作曲、演奏に、そのような断片を少しずつ取り入れることを楽しんでいるんですね。だから私のアルバムにはいろいろなスタイルがあるんだと思います。アフロ・キューバンから得たものも、深いスローなスピリチュアルな曲も、アップテンポのモーダルなものもあります。高速のジャズ・ダンサーからミディアム・テンポのジャズ・ダンサーも、“The Hipster” のような3/4拍のジャズ・ワルツもある。中近東の影響も、パーカッシヴなものもたくさんある。これが作曲の面白いところなんです。願わくは、私がそれらすべてを説得力のある方法でまとめられる実力を持つアーティストでいたいと思っています。ひどいコンピレーションみたいにならないようにね。これが実際に本物の芸術的な取り組みなんです。私はシーンで何が起こっているかということには興味がなく、いい音に興味があるのです。
■『Cloud 10』とEPの「Love & Life」、そして未発表の新曲をまとめた『Cloud 10 – The Complete Sessions』がこの度日本で発売されます。改めて日本のファンに向けて、どんなところを聴いて欲しいかお願いします。
CW:本当に素晴らしい作品だと思っています。なんせ、私たちがおこなったレコーディング・セッションのすべてが収録されていますからね。完全なセッションです。オリジナル・アルバムの『Cloud 10』と、同じセッションで作られたEP「Love & Life」、そしてどちらにも収録されることのなかった“La Bohemia” と “Hang Time” というふたつの未発表曲が収録されています。とくに “La Bohemia” はレコーディングしたときに、ミュージシャンがまるで昔のジャズ・バンドのようにスウィングしている瞬間が最高でした。ベース・ラインは典型的なディープ・リフで、スピリチュアルでモーダルなものですが、奏者たちは突然50年代のスウィング・ジャズのようにベース・ラインをウォークさせ始め、エネルギーが爆発します。“La Bohemia” を聴いて、あのレコーディングのときに私が感じたエネルギーを体験できるかどうか確かめてほしい。本当にこの曲がリリースされたことをとても嬉しく思っています。“La Bohemia” と “Hang Time” をどうぞ楽しんでくださいね。
Chip Wickham
FUJIROCK FESTIVAL'24出演決定!
https://www.fujirockfestival.com/
質問・序文:小川充(2024年4月03日)
| 12 |
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
INTERVIEWS
- interview with Flying Lotus - フライング・ロータス、最新EPについて語る
- interview with Autechre - 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE