みなさんボンジュール、今回は音楽の話題を取り上げたく。2016年世界の音楽市場でストリーミングやダウンロードなどのデジタルの収益が、全体の45%とCDやヴァイナルなどのフィジカルの売り上げを初めて上回った。フランスではまだ音楽市場の59%をフィジカルが占めているが、それでもデジタルは右肩上がりに数字を伸ばしている。このように音楽の聞かれ方が変わりつつある今、主にストリーミング配信が世界の市場で重要な位置を占め、音楽の聞かれ方は変わりつつある。音楽の好みは細分化し、音楽の聞き方も細分化しているようだ。それでも多くの人が共通してあげるツールがYoutubeだ。
そんなYoutubeで楽曲をアップするやいなやあっという間に1千万回を超える再生数を獲得し(現在は5千万回を超えている)彗星のようにフランスの音楽シーンに現れたのがPetit Biscuit(プティ・ビスキュイ)だ。
音楽性から取り巻く雰囲気までEDMを「下世話すぎて、音楽とは言えない」と最初から懐疑的に捉えていたフランスのインテリ層にもこの「Sunset Lover」は受けた。ロマンチックで聴きやすいけれどコード進行もちゃんとあると。この曲を発表した2015年当時、Petit Biscuitことメディ・ベンジョルンはまだ15歳だった。そして2017年11月10日、フランスでの成人年齢となる18歳の誕生日にファースト・アルバム『Presence』をリリース。18歳というのは、フランスではとても意味のある歳で、記念に残るような(裕福な家庭では高価な)プレゼントをする習慣があり、わざわざこの日に当ててリリースしたというほっこりした逸話を持つメディくん。フランスのバカロレアという高校卒業+共通一次試験のような試験で最上級評価「Tres bien(大変よろしい)」を取るような学業にも秀でた若者で、両親の方針で音楽、しかもエレクトロニック・ミュージックのような浮ついた世界でのキャリアより学業優先の姿勢を最初から貫いている。現在は大学に入学したが「あ、その月は期末テストがあるからフランス国外でのライヴはしません」とエージェントが平気でフェスティバルのオファーを蹴るような恐ろしい真似をやってのける。それもこれも2018年のコーチェラ・フェスティバルへのいいスロットでの出演が早々と決まるなど、ヨーロッパのみならず最重要マーケット、アメリカでもブレイクしたゆえの強気さと、アメリカのエージェントだときっと理解できないから、と学業優先を理解し実行するフランスのエージェントをキープする両親の厳格な管理があってからこそ。
そんなPetit Biscuitと「Gravitation」を共作したのがMøME(モーム)。
ニース出身現在28歳のMøME(モーム)ことジェレミー・スイラーは「Aloha」が2016年の”夏のアンセム”となり一躍トロピカル・ハウス・シーンの最前線に躍り出た。
フランスは6月末に学期末を迎え、そこから一気に社会全てがヴァカンス・モードになる。フェスティバルやイビザ型リゾート地でのパーティなどが本格化、素人から大型フェスのDJまでいわゆるパーティ・アンセムが必要だし、スーパーからラジオまでここぞとばかり浮ついた気分を盛り上げようと今年の夏の1曲をヘビーローテーションする。その流れに乗ったMøMEはEDMとは一線を画したいけれど、オーディエンスも盛り上げたいフェスティバルにブッキングされまくった。
そういった意味では、ダヴィッド・ゲッタのバックアップを受けたKungs(クングス)は、時に不当な扱いを受けることがあった。現在21歳のヴァロンタン・ブリュネルは2016年に発表したクッキング・オン・3・バーナーズのリミックス「This Girl」がYouTubeの再生回数で1億回を超え、ダヴィッド・ゲッタのベルシー(2万人キャパシティ)公演の前座に抜擢され、デビュー・アルバム『Layers』がフランスのグラミー賞ことLes Victoires de la Musiqueでエレクトロニック・ミュージック部門を受賞するなど、一気に大きな成功を手にした。
先に挙げた「This Girl」はまだしもその後メジャーのレコード会社と契約し作られたMVは、Petit BiscuitやMøMEとはギリギリ同じトロピカル・ハウスというジャンルに入れられるものの、音楽的にもMVの表現としても明らかにEDMのフェスティバルで何万人ものオーディエンスが盛り上がることを想定したものになっている。そして現に彼はEDM、ロック、両方のフェスティバルでヘッドライナーの1人としてオーディエンスを最高に盛り上げている。だが、こうなるとフランスのスノッブなインテリ層に「下世話な音楽」のレッテルを貼られてしまうのもまた事実なのだ。
そんなインテリ層に逆に愛されているのがパリのレーベル、Roch Musiqueだ。
Roch Musiqueはパリでその名前を冠したイヴェントをオーガナイズするたびに感度の高いオシャレ&音楽好きパリジャンが確実に集結し、カルチャー誌『Les Inrockuptible』では「フレンチタッチを彼らが復興させる!?」などとぶち上げるほどもてはやされている。レーベルとしては2012年にスタートしたもののその歩みは至ってマイペースで、日本でも大変な人気FKJに続いてようやくアルバムを作り上げた2人目のアーティストがDarius(ダリウス)ことテレンス・ンギュエンだ。ルイ・ヴィトンやカルティエなどのCMやM83などのMVを手がけきたLisa Paclet(リザ・パクレ)監督によるアーティスティックなMV「Lost In The Moment」も大好評を得ている。
ベルリン在住のナイジェリア人シンガー、ウェイン・スノウをフィーチャーした浮遊感溢れるメランコリックなこの曲を含む1stアルバム『Utopia』は11月24日にリリースされる。
フランスのエレクトロニック・ミュージック・シーンは、カッパ頭の愉快な実験家Jacques(ジャック)から芸術的だけど社会的視点も含まれた短編映画のようなMVを自ら作るTha Blaze(ザ・ブレイズ。あのハウスの大御所ではなく)までなかなか活気があるけれど、日本まで届くアーティストは稀なのでこれからも定期的に紹介していければ。


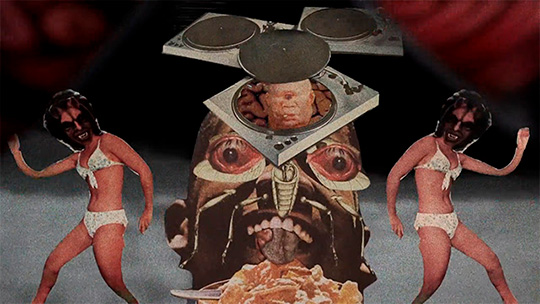


 label: Warp Records / Beat Records
label: Warp Records / Beat Records






