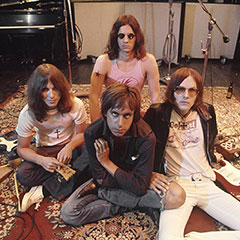MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Reviews > Film Reviews > パターソン
私はパターソンに足を運んだことはないが、ニューヨーク州の隣のニュージャージー州の北部、パサイク郡の郡庁所在地であるかの地は、それがオールロケであってもなくても、画面に映りこんだ街並みから空想するに、都市の喧騒に遠い、いくらかとりのこされた、緑の多い住みよい街のようである。郊外に向かう電車の窓に映る景色がごみごみした都心を抜けた途端にひらけるあの感じ、あるいは金沢とか仙台とか札幌とか、涼しげな土地を連想してしまうのはおそらく、街の情報以上に映像にとらえられた光と空気のせいである。光の差す位置は低く事物の陰影は深い。デジタルでありながら、その色彩感覚はきわめて写真的、ことに70年代のニューカラーを髣髴したのはイメージがエグルストンやショアに似ているからではなく、この世界における映像の階層が変質したなかにあってこの映画の映像の位置関係がニューカラーが写真史にもたらしたそれに近似するからである。フィルムに色を感光する行為はモノクローム基調の写真史の飛躍のひとつだったが、初期のニューカラーの写真には表現と技術の不安定さからくる、色彩を得ることと同時に喪失することのゆらぎがあった。色はあらかじめ褪せることを含意し、イメージはそれが過去のものであるという形式がもたらす事実以上に圧倒的に非在だった――と思わず間章っぽくなってしまうほど、3DやCGやVRやARやMRがはびこるイマージュによる象徴界で、ジム・ジャームッシュの80年の『パーマネント・バケーション』から数えて12作目の劇映画『パターソン』のフレーム内の色彩と陰影と構図は端正であり、つまるところそれは古典的である。
 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
筋書きはいたってシンプル。ジャームッシュはパターソンを舞台に、街とおなじ名前の主人公パターソン(アダム・ドライヴァー)とその妻(ゴルシフテ・ファラハニ)、そこに暮らすひとたちの一週間を淡々ときりとっていく。撮影監督はフレデリック・エルムズ――ジャームッシュ作品では『ナイト・オン・ザ・プラネット』(1991年)をかわきりに、2003年の『コーヒー&シガレッツ』を担当した人物だが、古くはリンチの『イレイザー・ヘッド』(1976年)を撮っていた。彼との直近の仕事は2005年の『ブロークン・フラワーズ』といえば、『パターソン』のトーンをご理解いただけるだろうか。あの作品のビル・マーレーはジャームッシュ作品では比較的クセのないほうだったが『パターソン』でのアダム・ドライヴァーはそれに輪をかけて淡泊である。午前6時には目をさまし朝食をとり仕事にでかけていく。あとにする自宅は、私はアメリカの住宅事情に詳しくないが、おそらく子どものいない若夫婦と犬一匹が暮らすには広すぎず狭すぎない、典型的な物件である。職場までは徒歩でゆく。職場についたパターソンは出発前のバスの運転席でノートになにやら文字を書きつける、そこに同僚がやってきて手は止まる、バスは発車しパターソンの市街を横切っていく、フロントガラスに映る市街地の風景は構図のなかの消失点に吸いこまれるかのよう。古い街なみ。その街にまつわる話を、乗客がする声が運転席のパターソンの耳にとどく。ある日のそれはひとを殺したボクサーの話でありべつの日にはドーナツ屋のいかした女のこともある、パターソンに住んでいたアナキストについて話す学生たちが乗り合わせることもあるだろう。仕事が終わった食後には愛犬マーヴィンの散歩の途中でなじみのバーによることもある。そこで交わす会話は音楽ネタとユーモアをちりばめたいかにもジャームッシュらしいものだが、80~90年代諸作とくらべると、かつて編集がもたらしたオフビートな感覚が役者の演技の間に置き換わっており、いくぶんゆったりと、とてもまろやかである。彼らとの出来事ともいえない出来事がパターソンを触発するともなく触発する、月曜から次の月曜までくりかえす日々にふれられることでパターソンは詩人になる。
 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
うかつな私は書きもらしましたが主人公パターソンはバスの運転手であるとともに詩人でもある。すてきというしかないこの設定が『パターソン』の奥行きである。私は詩については門外漢だが、詩が最初の一行のイメージにはじまりついでイメージをイメージへ橋渡すものなら、『パターソン』の構造そのものが詩である。ところがそれは詩的といったときに、私をふくめ多くのひとが思うような感傷とは無縁であり、作中にコインランドリーのラッパー役でワンシーンだけ登場するメソッド・マンが、詩人としてのパターソンのモデルになったウィリアム・カルロス・ウィリアムズの詩作哲学を借りてつぶやくように、「事物からはじまる観念」なのであり、マッチ箱や靴箱などとわかちがたい、現実に潜ったイメージの群れのようなものを、かつて詩を学んだジャームッシュは映画という、やはりイメージの連なりである形式のなかでたどり直している。むろん映画は詩であるという命題は蕪雑にすぎるが、きりとる視点によっては現実は映画になり文学になり音楽になる、つまりアートになる――などというそっくりかえった言い方をしなくとも、私たちのおくる日々には一日たりともおなじ日はない、とジャームッシュは『パターソン』で種々のイメージをいつくしむようにとらえていく。ときにそれはパターソンの名勝であるグレイトフォールズの水のイメージのもたらす広大無辺さであり、ポール・ローレンス・ダンバーやフランク・オハラやエミリー・ディッキンスン、パターソン生まれのアレン・ギンズバーグやウィリアム・カルロス・ウィリアムズといった米国の詩人の命脈である。それらは符牒となり作品全体に交響していくのだが、そこには桂冠詩人の厳かさや壮麗さに遠い、自由(律)の(オフ)ビート感覚がある。一節ひいてみよう。
「冷蔵庫のスモモを食べた
たぶん君の朝食用だね
許してくれ
おいしかった
甘くて
よく冷えてたよ」
(ウィリアム・カルロス・ウィリアムズ「言っておくよ」)
作中後半でパターソンは妻ローラに彼女が好きだというこの詩を朗読する。うかつな私は詩にうといので詩と散文のちがいも定義できないが、このような唯物詩観は、広津和郎の散文性とはいわぬまでも、たとえば谷川俊太郎の「コカコーラ・レッスン」とか田村隆一の諸作とか、ある種の韻文が散文にひらかれるさいにはらむ質朴な力感と余白を思わせるだけでなく、『ダウン・バイ・ロー』でのホイットマン、『デッドマン』でのウィリアム・ブレイクら、ジャームッシュがこれまでの作品で言及してきた詩人の諸作と響き合い、ことばとイメージがアメリカのみならず世界に波及しやがて覆い尽くすジャームッシュのヴィジョンの根拠にもなっている。むろんブルースマンとロッカーとラッパーの列席も欠かせない。その意味でノーベル財団は40年はおくれている。と書きながらいまふと思ったのだが、上述のW・C・ウィリアムズの詩の一節に出てくるスモモ(plums)は『ミステリー・トレイン』(1989年)で永瀬正敏と工藤夕貴のカップルが持参し、ホテルのフロントにいたスクリーミン・ジェイ・ホーキンスが丸呑みしたスモモの暗喩なのではないか。この詩を読んだ翌日、あることで失意の底に沈んだパターソンはグレーとフォールズの前で日本人の詩人(永瀬)と束の間の出会いをはたす。この「浄化」を思わせる場面、なんなら「癒し」といってもいいこのシーンでしかしジャームッシュは感情を昂ぶらせない、それを押しつけないのはこの映画を彼自身「解毒剤」とみなすからだろう。なんにとっての? スペクタクルとしての映画がはびこる昨今の状況にとっての。むろんこの一文の映画はあらゆる文言と置換可能であり、おそらく現在のアメリカの政治/状況とも無縁ではない。タッチは禁欲的で円熟も感じさせる。ロン・パジェットの手になる作中の三編の詩も見事である。音楽はジャームッシュがその一員であるSQÜRLが担当している。アンビエントを思わせつつもパターソンの思考に同期したようなゆるやかな起伏をもつサウンドトラックは当初「著名なエレクトロニック・ミュージシャンのアーティストのトラックを集めて、映画音楽にする予定だった」というのだが、私はそれがOPNではなかったかと邪推している。というのも―― (以下『ギミー・デンジャー』評につづく)

Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE